ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
スマートハウスはどんな住宅?メリット・デメリットと設備機器を解説

IT技術がどんどんと進んでいる中、私たちが生活する住宅もIT化が進んでいます。
スマートハウスは、そのITを使って快適な生活と普段の生活に必要なエネルギーを管理し、効率的に使える住宅を目指しています。
では、スマートハウスによって私たちの暮らしはどう変わるのでしょうか?
今回の記事ではスマートハウスとはどんな住宅か、スマートハウスの魅力とメリット・デメリットについてご紹介していきます。
スマートハウスとはどんな住宅?
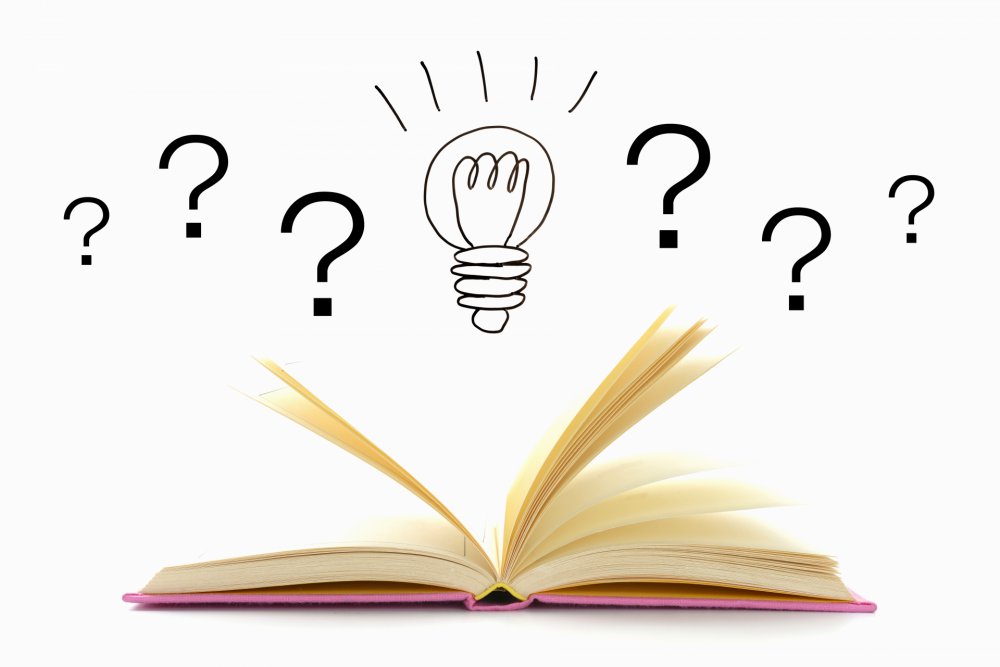
スマートハウスとは、1980年代にアメリカで提唱された住宅の概念で、IT(情報技術)を使って暮らしに必要なエネルギーを最適に制御したり、管理できたりする住宅をいいます。
暮らしに必要なエネルギーとは、例えば電力や水道、ガスなどがあります。
こういったエネルギーをHEMS(ヘムス)や太陽光発電システム、蓄電池などの機器を使って、最適化し、エネルギーマネジメントを行うことができます。
スマートハウスは光熱費を抑え、CO2排出の削減も実現できる省エネ住宅として注目されています。
スマートハウスの重要な3つのエネルギー
スマートハウスの重要となるエネルギーは3つあります。それは、「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」の3つです。
- 創エネ:太陽光発電システムなど使用して自給自足でエネルギーをつくる仕組み
- 蓄エネ:家庭内でつくったエネルギーを貯めるための仕組み
- 省エネ:生活で使用するエネルギーの消費を抑える仕組み
スマートハウスは「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」の3つのエネルギーを軸にコントロールして、使用を最適化するエネルギー全体のマネージメントができる住宅です。
スマートハウスの設備

スマートハウスの重要な設備は下記の3つの設備です。
- HEMS(ヘムス)
- 蓄電池
- 太陽光発電ソーラーパネル
HEMS(ヘムス)
HEMS(ヘムス)は「Home-Energy-Management-System」の略で、使用電力量や水使用量、ガス使用量をモニター画面で確認することができ、履歴として過去の情報を残すことができます。太陽光発電システムでつくられた電力量や蓄電池に蓄えられている電力量、現在使用している電力量などの情報もHEMS(ヘムス)で確認できます。
蓄電池
太陽光発電でつくられた電気は蓄電池に蓄えられ、必要に応じて使用することができます。安価な深夜電力を蓄電池に貯めて日中に使用すれば、光熱費を抑えることも可能です。
また、蓄電池に電気を蓄えておくことで、停電時や災害時の際も非常電源として効果を発揮することができます。
太陽光発電ソーラーパネル
太陽光発電ソーラーパネルは、屋根や屋上に設置して電気をつくることができます。太陽光発電ソーラーパネルでつくられた電気は蓄電池に蓄えられ、家庭内の設備機器や家電に使用することが可能です。
電気を自給自足でつくる仕組みがあることで、毎月かかる光熱費を抑えることが可能です。
スマートハウスに関係するその他の設備
スマートハウスに関係する機器は他にもあり、EV車(電気自動車)やエネファーム(家庭用燃料電池)などがあります。EV車はV2H機器を導入することで、EV車(電気自動車)を家庭用蓄電池の代わりとして利用することができます。
エネファームは家庭内で電気をつくりながらお湯も同時につくり出すことができ、つくられた電気は家電などにも利用できる家庭用燃料電池です。
スマートホーム(Iot住宅)の違い

スマートハウスとスマートホームは、名前が似ていることから混同している方も少なくありません。
スマートホームはインターネットを活用して、スマートフォンやスマートスピーカーを使用し、生活で使う様々な家電をリモートコントロール(遠隔操作)することができます。
スマートホームに対応するスマート家電は、照明器具やエアコンなどがあり、ドアの鍵の施錠・解錠もスマートフォンによって操作することができます。
つまりスマートホームは、IT化によって生活の利便性を高めた住宅のことです。
スマートハウスのメリット

スマートハウスのメリットをポイントとしてあげるのなら下記のことがあります。
- 光熱費の削減
- エネルギーの最適な制限・管理が可能
- 災害時に有効な非常電源として利用できる
- 高断熱・高気密の家で快適な暮らしが可能
スマートハウスはHEMS(ヘムス)を導入することで、エネルギーの見える化により電気の使用量の多い家電の見直しやエネルギーの最適化を行うことが可能です。
太陽光発電してつくられた電気も生活に活用していけば、光熱費の節約に繋がり経済的に貢献することが期待できます。
スマートハウスは電気を使うときに電気会社から電気を供給してもらう他に、電気を貯めておくことができるため、災害時や停電などのトラブルが発生した際に非常電力として効果を発揮します。
また、スマートハウスは省エネ化できる設計の観点から快適な生活空間となるように、高断熱・高気密化した住宅となっているため冬は暖かく、夏は涼しいつくりになっています。
スマートハウスのデメリット

スマートハウスが与えてくれる効果はとても大きいのですが、デメリットも少なからずあります。
スマートハウスのデメリットは下記のことがあげられます。
- 導入費用が高額・定期的なメンテナンスも必要
- HEMSの普及率が低い
スマートハウスにするには、太陽光発電ソーラーパネルや蓄電池、HEMS(ヘムス)など導入しなければいけない設備があります。
そのため、スマートハウスに必要な設備の導入費用が高額になりやすいことがデメリットです。
また、HEMS(ヘムス)の普及率の低さも問題です。
HEMS(ヘムス)の普及率が低いことはどんな意味をするかというと、認知度が低い、信用性に欠ける、ということが問題となっています。
また、普及率が低いためか、HEMS(ヘムス)の通信規格に対応する電化製品の数がまだそこまで多くありません。
これからスマートハウスが一般化されていけば家電などのスマートハウスと連携できる製品も増えてくると思いますが、現状はまだ多くはないのが問題と言えます。
国もすすめるスマートハウスと補助金の交付

家庭でのエネルギー消費を削減しCO2排出を抑制する高い省エネ住宅の普及が求められ、 政府はZ E H住宅などの普及をすすめています。
参考引用元:経済産業省 資源エネルギー庁
スマートハウスに関連する補助金が実施されていますので、新築を建てる計画をされている方はぜひ利用することをおすすめします。
下記はスマートハウスを建てる方も対象となる補助金事業です。
補助金事業は各年度によって実施内容を変更する場合がありますので、利用される方は必ず確認することが大切です。
また、スマートハウスの補助金の交付は各地方自治体も実施していますので、お住まいの地域に補助金があるか確認してみましょう。
まとめ
スマートハウスはこれからの時代のエネルギー効率の高い都市づくりに必要となってくる住宅です。「創エネ」「蓄エネ」「省エネ」を軸に、快適な生活環境とエネルギー全体の管理により光熱費の削減が期待できます。
しかし、スマートハウスのような住宅のIT化というのは中々イメージがしにくいかもしれませんし、専門的な知識が必要です。
これからスマートハウスを取り入れたいと思っている方や興味を持っている方は専門家に相談したり、資料請求をしてみたりすることをおすすめします。
いえとち本舗は省エネ・創エネ住宅のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を標準装備した住宅を提供しています。
家づくりについてもっと知りたいという方は無料で資料を提供していますので、ぜひご利用ください。
資料請求はこちら
関連記事
-

考えておきたいリビング収納【いえとち本舗の新築・山口・宇部・山陽小野田・防府・周南】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^)/ 山口で新築住宅を考える際に、間取りはこれから家づくりで最も重要な点だと言っても過言ではないと思います。建てる前からしっかり考えておかないと、住み始めてから思わぬ苦労をする事になります!住み始めてから「やっぱりこうしておけば良かった」と後悔している中にはいるのではないでしょうか?その中でも1番多かった意見が新築の内装で「リビングの収納」をもっと重要視すればよかったことです。しかし、土地面積が限られていると、広いスペースが確保できないケースもあります。逆に、せっかく広い収納スペースを確保したのに使いにくく、不便を感じてしまうことも……。広くても狭くてもうまくいかないなら、一体どうすればいいのでしょう?そこで今回は、山口の新築住宅の収納スペースでありがちな失敗事例をもとに、リビング収納について解説します。ぜひ、内装の収納計画に役立ててください。 考えておきたいリビング収納のこと 子供が生まれて、家族が増えてくると狭い、収納がない、みんなが片付けをしないなどの理由で散らかりやすいのがリビングです。山口で新築住宅を建てるなら、ぜひリビング収納のことを注力においてほしいです。リビングはなぜ散らかりやすいのか、どうすれば物が溢れないキレイが続くリビングになるかを考えると、リビング収納のコツが見えてきます。これからそのコツを探していきましょう。 リビングが散らかる!収納がなくて困ったこと 家族みんなが集まるリビングは何かと散らかりがちですよね・・・山口で新築住宅を建てられた方に収納がなくて困ったことがないかヒアリングしてみたところ、どの家庭も散らかりやすくて困っている・・・という意見が多いです。その中でもこんな意見が・・・・郵便物や新聞、雑誌など様々な書類があふれてきて、服も増えたので収納スペースが足りない・夏や冬の季節ごとに変えるカーペットや家具をしまうときに、別の部屋の収納スペースに移動しなければならないとこるが面倒・友人や知人が急に訪問ときに、すぐに散らかっているものを入れる収納スペースがないから大変・なるべくリビングに物を置かないように心がけていても、仕事柄で忙しく書斎がないので、夫がリビングで仕事をすることがあり、PCなどの仕事道具や書類が散らかるので、それをきれいにまとめて片付ける場所がない・小学生の子どもがいると、子供部屋を設けているのに学校の勉強道具やゲームや漫画などがリビングに散らばってしまい、1日だけキレイにしていても数日経てばまた散らかってしまう やはりどの家庭でも問題を抱えていることが分かりますね。 散らかりやすいのに収納が少ないリビング 山口で新築住宅を建てる際にもリビングは家族全員が集まる大切な場所なので部屋面積は1番広くなりますが、そのわりには収納が少ないケースが多く見られます。そのため、いろいろな荷物や雑貨、書類などが散乱しやすいのが多いです。散らかる物は家族の年代によっても違います。特に幼い子供ならおもちゃ、小学生なら宿題や文房具、中学生になると雑誌やテストなどの書類がリビングに置きっぱなしになりやすいアイテムです。学校行事や山口の町内会の集まりなどの大事プリントをしまう場所に困るケースもあります。書類とリビングの組み合わせは一見かけ離れていて家を建てるときに忘れがちですが、光熱費などの領収書やスーパーの広告など、意外と紙類は溜まってしまうものです。また、外出先から帰ってきたときに子供のランドセルやカバン、上着やコートをリビングに置きっぱなしにするケースもよく見られます。疲れているときは自分の部屋へ行く前にひと息つきたいものですが、やはり1番最初にたどり着くのはリビングですよね。休憩が長くなってしまうと片付けるのが面倒になってしまう経験がある方も多いはずです。山口で新築住宅を建てたあとのキレイなリビングをキレイに保ち続けるのにも、何らかの対策が必要です。 生活感を出さない理想のリビング収納とは 山口の新築住宅のリビングは家族が集うだけではなく、客間がなければ友人や知人を招く場所でもあります。そのため、生活感を出さないようにリビング収納を作ることがおススメです。備え付け収納棚は扉をつけることで、中身を見られることなく収納できます。もし扉をつけられなかったら、インテリ雑貨店でカーテンなどを購入して隠すように設置してみてください。既製品の家具を買う場合は、リビングと統一感のある収納デザインを選ぶことがポイントです。リビングの雰囲気と収納デザインの統一感を持たせることで、オシャレな空間を演出できます。リビングの片づけ上手であるなら、見せるための収納に挑戦してみるのも良いかもしれません。物が見えていても雑貨屋のようにキレイに整理整頓されていれば、生活感を感じさせません。むしろ、オシャレでこだわりのある理想なリビングになり、友人や知人が訪問しても好印象を与えます。いつも清潔感がありオシャレに整理整頓されていれば、それを保ち続けるために物を置きたくないと感じますので、ぜひ習慣にしてみましょう。 いつもすっきりとしたリビングにするコツ出したものはあった元のあった場所に片付けるのが当たり前です。当たり前のことですが、なぜ簡単なことができないのか、理由を考えてみましょう。まず、物を片付けにくい場所に収納スペースがあると、こまめに片付けなくなってしまいます。リビング収納は、生活動線と紐付けして考えるのがコツです。例えば、新聞や雑誌をしまうラックをリビングに置くのはいかがでしょうか?大体は新聞をリビングに持ってきて読みます。郵便物なども真っ先にリビングにもっていき、リビングに置きっぱなしにしてしまうケースが多いはずです。新聞はいつもどこで読むのか、どこにラックがあればしまいやすいのかを考えることが大切です。片付ける場所の定位置を設けることが部屋をキレイに保つコツです。例えば、テレビのリモコン・領収書などの書類関係、おもちゃ道具・・・これらについても、出したら必ずそこに片付けるようにします。「出す・使う・片付ける」までをルーティン動線を定着されることで、片付ける習慣を身につけることが可能になります。 壁面収納やカウンター収納で片づけできるコツ 山口で新築住宅を建てるなら、ぜひ壁面収納やカウンター収納を検討されてください。 使いやすい壁面収納にするなら、奥行きの狭いパターンがおススメです。棚の奥行きを作ってしまうと奥のほうまで物をしまい、何をどこに片付けたかわからなくなりがちです。壁面収納はインテリ雑貨店などのボックスやかごなどを購入して、見てもスッキリとした印象を与えるものを購入して上手に収納しましょう。ボックスやかごに入れる物はジャンルごとにわけて、何がしまってあるかを書いたシールを貼ることをおススメします。カウンターを設置する場合は書類を片付けるスペースを作り、ちょっとした仕事などの作業スペースとして活用できるのでおススメです。家計簿をつけたり子供の学校行事のプリントに目を通したりなどにカウンター収納があれば便利です。外から帰ってきたときは、とりあえずコートや上着をかけられるようにハンガーラックを設置するのもひとつの方法です。リビングにハンガーラックがあれば来客用としても利用できるので、ちょっとしたおもてなしにもなりますので、どうしたら有効活用できるのか工夫を考えてみましょう。 まとめ せっかくの山口で建てた新築住宅も、物が散らかっているリビングでは台無しです。美しいリビングにするなら、リビングでも効率よく収納できる設計について考えましょう。新築住宅を建てたあとに造成するより、最初から使いやすいように設計するほうが格段に楽なはずです!まずはリビングが散らかる理由を考えてから、ライフスタイルに合わせた収納を作るのが重要です。ぜひキレイなリビングで快適な生活を送れるように、忘れがちなリビング収納について考えて見てくださいね♪ 11月2日(土)~3日(日) 開催イベント↓今だけ50万円相当プレゼントキャンペーン!
-

注文住宅と建売住宅、徹底解剖!!【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^)/ 山口・防府・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅購入をお考えのみなさま、 新築住宅を購入するなら「『注文住宅』か『建売住宅』どっちの方がいいのだろう・・・」と思ったことはありませんか?? ほとんどの方が人生で一番大きなお買い物になり、長く住まれるお家ですので、住宅選びで後悔はしたくないですよね。 そこで今回は、注文住宅と建売住宅のメリットとデメリットを踏まえながら 「注文住宅と建売住宅、徹底解剖!!」についてお伝えしたいと思います(^^)/ 〇注文住宅のメリット ①自由度が高い 注文住宅は、自分好みのデザインを最初から組み立てていくものなので、自由度が高く自分のライフスタイルに合ったお家を作り上げることができます。 理想やこだわりを細部まで表現でき、「世界に一つだけのお家」を作ることができるため、「人とかぶりたくない!」という方にはおススメです(*^-^*) ②予算を調整できる こだわるところにはお金をかけて、こだわらない部分はコストカットできることも注文住宅の魅力です。 お家の作りやデザインを計画していくうえで、予算をオーバーしてしまう可能性はありますが、そういった場合は効率よくコストカットを行うことで予算の調整をすることができます。 〇注文住宅のデメリット ①入居まで時間がかかる 建売住宅等に比べ、相談事項が多い注文住宅は入居までの期間が長いです。土地探しから始めるとなると相当時間がかかると予想しておかなければなりません。契約までの工程がやや複雑なため手間もかかってしまいます。 「早く入居したい!」と考えている方にはあまりオススメできません・・・(*_*) ②完成したお家をイメージしづらい 実際に入居するお家を見て契約できる建売住宅と違い、注文住宅は契約段階では完成品を見ることができません。 完成し、いざ入居してみると「思ってたのと違うかも・・」となってしまう可能性も否めません。 ③価格が比較的高い 建売住宅よりも手間がかかる注文住宅はどうしても割高になってしまいます。 最近は質の高いローコスト住宅も増えてきましたがローコスト住宅は安かろう悪かろうの住宅を購入してしまう可能性もあります。 〇建売住宅のメリット ①価格が比較的安い 建売住宅は、建設する側が土地や部材の節約を考えて建てられていることとデザイン料がかからないケースが多いことから、価格が比較的安いです。価格が「売れ筋の価格帯」に設定されているためあまりに高額なことはほとんどありません。 ②購入手続きが簡単 売り主業者のプランで建てられたお家をその敷地と一緒に購入することになるので、売買契約時に手付金を支払って残りは住宅ローンで一括して借りるなど、資金の流れは単純です。 注文住宅と比べて時間と手間がかからないので、山口の新築住宅に「早く入居したい!」と思われている方にオススメです(^^♪ ③入居したときのイメージがしやすい 建売住宅は完成前から販売しているものや完成した後も販売しているものがあります。完成前でも間取りやデザインは決定しているので完成図をみれば入居後のイメージがしやすいです。 完成している建売住宅はお家の中を見学してから購入をすることができるので、家具の配置や部屋割りなどをイメージしやすいことは大きな魅力です♪ 〇建売住宅のデメリット ①画一的な建物になりがち 建売住宅は画一的な建物になりがちで隣地とそっくりな建物が並ぶ可能性もあります。 建売住宅は万人受けして売りやすいことが優先されるのであまり高級な設備やこだわった内装などは取り入れにくいでしょう(*_*; ②あまり自由が利かない 建売住宅は予め間取りや設備が決められているので、なかなか自分の思い通りにはなりません。一部、間取りの変更やオプションの取付けができるかもしれませんが、全て自由にはできないことがデメリットと思われます( ;∀;) 〇さいごに 注文住宅と建売住宅の違いが分かっていただけたでしょうか(^^)/どちらのメリット・デメリットがあるので山口で新築住宅を建てられるときは吟味しながら進めていきましょう♪ 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓ 【山口市下市町】リビング21.3帖平屋3LDK完成見学会
-

成功例から学ぶ!後悔しない家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・山陽小野田・防府・周南】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^)/ 本日は山口で新築住宅の購入をお考えのみなさまに「成功例から学ぶ!後悔しない家づくり」についてお伝えします♪ 過去に、「失敗例から学ぶ!後悔しない家づくり」についてお伝えしている投稿があります。そちらと少し似た内容になります。そちらもまた参考にされてみてください(^^♪ 一生に一度の大きなお買い物と言われる「家」。一番大きなお買い物なので絶対に失敗はしたくないですよね。山口で新築住宅をお考えのみなさまに、少しでも建てた後の後悔をなくすために、実際に新築を購入された方の成功例をいくつかお伝えします♪ ★成功ポイント①散らからないリビングづくり 一人で住んでいても散らかり気味なリビング。お子様がおられるご家庭は、おもちゃなど散らかってしまうことが多いのではないでしょうか?(*_*; かといって散らかっているものを全部しまえるほどの大きなスペースをリビングには取れない・・・となった時は「動線やしまう物を意識して収納を細かく分ける」ことをオススメします! 例えば、リビングに壁掛けの収納棚を付けるとします。この時に「何かを収納するだろうから」と思って付けるのではなく、「リビングではゲームやおもちゃが散らかり気味だからそれらを収納しよう」という風に実際の生活をイメージしながら具体的にしまうものを決めましょう。 後からしまう物が増える場合もありますが、あらかじめ収納の配置を決めておくことで収納スペースを最大限に生かすことができます。収納を考えながら家づくりをすることで後から「収納スペースが全然足りない・・・」といった後悔を減らすことができます! ★成功ポイント②見えるところにはお金をかけて、見えないところは安く! 山口で新築住宅を建てる際に、あまり目に付かないようなところにまでお金をかけてしまうととても大きな金額になってしまいます。「目に付かない」というのは来客時のゲストだけではなく、そこに住む家族のことも考えなければいけません。 例えば、大勢の人が目にする玄関や長い時間を過ごすリビングにはできるだけ理想を詰め込み妥協しない。その代わり、ゲストからあまり見えず、一日に一回しか利用しないお風呂や寝室は思い切ってコストカットをする、といった方法があります。 コストカットと言われると「品質や見た目が悪くなるのはちょっと・・・」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうなるわけではありません。最近は様々なメーカーさんが多くの商品を売り出しているので、住宅機器の基本的な水準が高いです。なので少々のコストカットをしても性能がすごく悪い、ということはほとんどないでしょう。 お金を抑える部分を決めておくことでお金を掛けたい部分に資金を回すことができるため、事前に取捨選択をしておくことが大切になります。(^^)/ ★成功ポイント③カウンターキッチンを採用し、家事をスムーズに 今や採用されている方が多いカウンターキッチン。カウンターキッチンにはメリットが沢山あります。一番は家事がしやすいことです。出来上がった料理をカウンターにおけば、すぐに食卓に並べることができ、食べ終わったら食器をカウンターに戻しすぐに洗うことができます。このように動線がコンパクトであるのがカウンターキッチンの特徴です。また、リビングの様子をみながら家事ができるのでお子様がおられるご家庭にオススメです(^^)/ カウンターキッチンは高さを選ぶこともできますので、主にキッチンを使われる方の使いやすい高さに設定することで家事がしやすくなりますね♪ ★成功ポイント④おしゃれで節電になるダウンライトを採用 山口での新築住宅の内観を考えるときに大切になってくる照明器具。照明の差でお部屋の印象がガラッと変わります。そこでオススメなのがダウンライト。 LED型ダウンライトを採用しますと、ライトの持ちが長く、年間の電気代も少し安くなります。 また、ダウンライトは真下を照らすので、ピンポイントで明かりが欲しいところを照らすことができます。調光器が付いているタイプなら光の加減を調節することができ、シーンに合わせて使い分けることができます。 ただ、ダウンライトにはデメリットもあります。まず、後から位置を変えたり増やしたりすることができない点です。理由はダウンライトは天井に穴をあけて埋め込むものだからです。そのため、「ダウンライトの下の家具を動かしたらライトが変な所を照らしている・・・」となった時にダウンライトを簡単に移動させることができません。 生活のスタイルが時々変わったり家具の配置をよく変える方は要注意です・・・ しかしこれには対策があります!!それは、照らす方向をある程度変えることができるユニバーサルタイプのダウンライト、ダクトレールなども併用することです。ダクトレールはすっきりとしながらもライフスタイルの変化に対応することができます。 なので、家具を動かすかもしれないと思われる方は前もって上記の対策をオススメします(^^)/ ★成功ポイント⑤よく使う電化製品は生活空間の中心に 生活していてよく使う電化製品である掃除機やアイロン台を、あえてリビングの専用スペースを設けて収納することで、出し入れがしやすく便利です。電化製品を一カ所にまとめて収納するとごちゃごちゃしがちです。使う場所や頻度に分けて収納することで収納スペースを効率的に活用することができます。 リビングにクローゼットを設置する「リビングクローゼット」は最近人気のようです。急な来客時に重宝されそうですね♪ ★成功ポイント⑥土地探しに時間をかける 山口で新築住宅を建てるにあたって初めの一歩の「土地探し」ここに時間をかけることで、希望の区域内で予定よりも安く土地を仕入れることができたというケースもあります。時間をかけて周辺環境を調べたり少しエリアをずらしてみたり・・・土地を多角的に見ることでお得なポイントが見つかったりもします。安く土地を仕入れ、浮いた資金を建物設備に回せると充実した新築住宅で生活を送ることができます。 お仕事をしながら土地探しもして…と忙しくなると思われますが、できるだけたくさんの不動産屋をまわったり自分でリサーチしてみることが、自分にピッタリの土地に出会う近道かもしれません。 多くの不動産屋をまわることで広告に出る前の土地情報をゲットできるケースがあるようです♪ ★成功ポイント⑦自己資金を増やす 山口で新築住宅を購入する際、全て自己資金で払える方はほとんどいません。たいていの方は住宅ローンを組みます。当たり前ですが自己資金が多くある方が月々の返済負担は軽くなります。金融機関にて新築住宅の購入金額全額を借りると月々の返済に利子がつくので実際の購入金額よりも多く払わないといけません。なのでできるだけ、自己資金を集めておいて月々の返済負担を軽減した方がゆとりのある生活ができるかと思います。 まとめ なにか参考になるポイントはありましたでしょうか?新築住宅が完成した後に後悔することは本当にもったいないので、できるだけ時間をかけてプランニングすることが大切になってきます(^^)/山口で新築住宅の購入をお考えの方で、なにか気になること等ありましたら、いつでもご相談下さい♪ 11月2日(土)~11月4日(月)今だけ50万円相当プレゼントキャンペーン!









