ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
キッチンシンクの素材と機能を徹底比較!!【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさん、こんにちは!
いえとち本舗山口中央店です●・ω・)ノ
本日は、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で家づくりを検討されているみなさんに
「キッチンシンクの素材と機能を徹底比較!!」というテーマのもと、様々なキッチンシンクについてご紹介したいと思います。
山口で新築住宅を建てたい!とお考えのみなさん!
新築住宅を建てる際は、キッチンをこだわりたい!という方も多いのではないでしょうか?
やはり毎日使うキッチンは使い勝手が良く、居心地の良いものがいいですよね。
最近では、キッチンもスタイリッシュで使いやすい製品、お手入れのしやすさを工夫したタイプなどが新築住宅はもちろん、アパートにも多くみられるようになってきました。
山口で新築住宅を建てる際にどんなキッチンにしようかなぁと悩まれることはございませんか?
今回はそんなお悩みを解決するためにキッチンシンクの特徴と選ぶ際のポイントを紹介していきます。

キッチンシンク素材の種類
山口で新築住宅を建てる際にこんなキッチンにしたいという理想のキッチンを見つけるためにまずは素材についてご紹介いたします。
現在販売されているキッチンシンクは、ステンレス製、人工大理石製、人造大理石製、ホーロー製の大きく分けて4つに分けることができ、それぞれ異なった特徴を持っています。
これら4種類のキッチンシンクの特徴についてそれぞれ比較して見ていきましょう。

キッチンシンクの特徴
*ステンレス製
昔からキッチンシンクとして使われてきた定番素材で、お手入れがしやすく、耐久性や耐熱性に優れています。柔らかさがあるため、食器などを落としても割れにくいですし、定番のシンク素材なので、価格も比較的安いです。
*人工大理石製
人工大理石製は、大理石のような仕上がりという意味で、実際には石ではなく、熱に強いポリエステル樹脂やアクリル樹脂が使われています。豊富なカラーバリエーションがそろっており、キッチンの扉などとのコーディネートも簡単なことから、最近人気の素材です。
*人造大理石製
人造大理石製は、天然の大理石などの石を砕き、セメントや樹脂で固めた半人工素材のことを言います。見た目は大理石のように美しく高級感がありますが、大理石よりも安価に入手することができるため、最近では選ばれることが多くなってきております。
*ホーロー製
ホーロー製とは鉄やアルミなどの金属を下地にして、その上にガラス質のうわ薬を高温で焼きつけた素材のことを言います。人工大理石製や人造大理石製と比べるとまだ日本ではあまり普及していない素材です。

シンク素材のメリット・デメリット
それぞれのキッチンシンク素材の特徴を踏まえたうえで、次はそれぞれのキッチンシンクのメリット、デメリットに注目してみましょう。
ステンレス製シンクのメリット・デメリット
[メリット]
〇耐熱性・耐久性・耐摩耗性が高い
〇柔らかさがあるため食器類を落としても割れにくい
〇シンク自体が割れにくい
〇価格が比較的安い
[デメリット]
〇鍋や缶などを置いておくと、もらいサビができることがある
〇ステンレス独特の雰囲気を変えられない
〇水垢でステンレスの光沢がなくなりやすい
耐久性や耐熱性、耐摩耗性に優れており、大変使いやすい素材
傷と汚れに関しては人工大理石のほうが優れている
人工大理石製シンクのメリット・デメリット
[メリット]
〇天板からシンクのつなぎ目のないキッチンが作れる
〇色やデザインが豊富
〇細かい傷はメラミンスポンジで落とすことができる
[デメリット]
〇食器類を落としてしまうと多少割れやすい
〇もらいサビがつく
〇強い衝撃が加わるとシンクが割れることがある
手入れがしやすく、デザイン性やカラーも豊富な素材
ステンレスに比べると傷がつきにくいが、食器の保護という点では少し劣る
人造大理石製シンクのメリット・デメリット
[メリット]
〇見た目が大理石のように美しい
〇高級感がある
〇天然の大理石より安価
[デメリット]
〇耐久性があまりない
〇汚れが落ちにくい
大理石のような見た目で、高級感のある素材
ステンレスや人工大理石に比べると汚れが落ちにくい
ホーロー製シンクのメリット・デメリット
[メリット]
〇水や湿気、熱への耐性に優れている
〇スチール製のたわしでこすっても傷つかない耐久性がある
〇比較的値段が安価
[デメリット]
〇食器類を落としてしまうと多少割れやすい
〇表面が欠けたりすると、下地の金属がさびる
耐久性、耐熱性に優れており、掃除もしやすい素材
食器類を落とした時、食器が割れやすい
それぞれの素材の特徴、メリット・デメリットについてご紹介しました。
山口で新築住宅を建てる際、みなさんはどのような素材のキッチンシンクがよろしいでしょうか?
毎日使うキッチンなので、使いやすく、料理が楽しくなるような居心地の良い空間にしたいですよね。
人によって利用しやすいキッチンは異なると思いますので、ここからはキッチンシンクを選ぶ際のポイントをご紹介します。

キッチンシンク選びに気をつけたいポイント
「使いやすいキッチンシンクにしたい!」「居心地の良い空間にしたい!」と考えるのが当然ですが、山口で新築住宅を建てる際に使いやすいキッチンシンクを選ぶときには、どのようなことに気を付けておけばいいのでしょうか。
★色やデザイン
キッチンシンク選びで重要なことは、カウンターやインテリアなどとの部屋の雰囲気に馴染むようなキッチンシンクを選ぶことです。
例えばスタイリッシュな雰囲気の新築住宅のお部屋では、ステンレス製を選ぶと、シャープな印象のキッチンにすることができると思います。
また、ホワイト系のナチュラルな雰囲気の新築住宅のお部屋では、シンクや天板にホワイト系を選ぶと統一感もでると思われます。
新築住宅を建てる際、クロスの色やカウンター、インテリアなども考えると思いますので、その際に雰囲気を崩さないようなキッチンシンクの色、デザインのことも考慮することをオススメいたします。
★シンクのお手入れのしやすさ
せっかくの新築住宅を山口で建てるとなると、やはりキッチンもずっとキレイな状態を保ちたいですよね。
シンクはほとんど毎日使うものなので、どうしても汚れてしまいがちだと思いますが、よりお手入れがしやすいタイプもありますので掃除がしやすいものを選ぶと良いと思われます。
先ほどご紹介しました人工大理石製シンクなどのようにシンクと天板の継ぎ目をなくすことができるタイプのものを選びますと、使用した後も簡単に掃除できるようになります。

★シンクの形や深さ
最近では多くのメーカーで取り扱っているシステムキッチンが広々としたスペースが確保されており、深さにも余裕があるものが増えてきております。深さもあり、広々としたスペースがあると、鍋などの大きなものも洗いやすいですよね。
また、シンクの形も長方形や丸みを帯びた形など形は様々なので、自分はどのような形が一番使いやすいか、一度考えてみるといいでしょう。
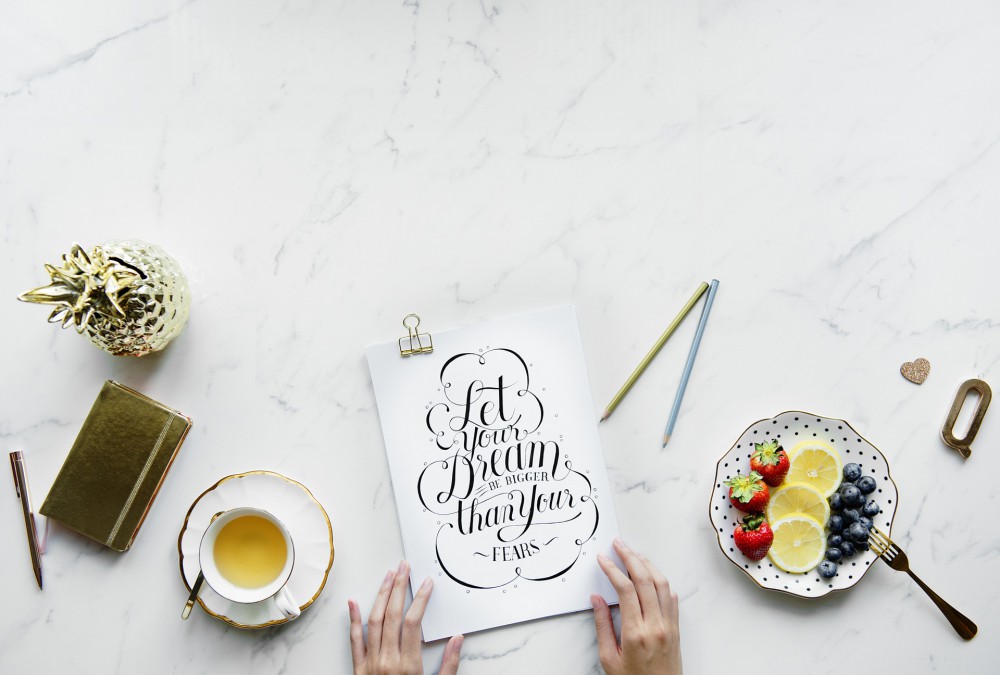
いかがでしたか?
今回、キッチンシンクの素材やその特徴についてご紹介させていただきました。
一言にキッチンシンクとは言ったものの意外と知られていない素材もあったのではないかと思われます。
毎日使うキッチンだからこそ、山口で新築住宅を購入する際も、ステンレス製シンク、人工大理石製シンク、人造大理石製シンク、ホーロー製シンク、それぞれメリット・デメリットがありますので、その人その人に合ったキッチンシンク選びの参考になると嬉しいです。
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は
是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!
家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*)
12月7日(土)~8日(日)開催イベント↓
【山口市下小鯖】驚きの収納力あり!4LDK完成見学会
関連記事
-

こんな物件は注意!買ってはいけない建売住宅の特徴と選び方ポイント
戸建て住宅の購入を検討している方は、注文住宅と建売住宅のどれにするか選択する事になります。比較的に費用が安い建売住宅は、すでに建物が完成している物件もあり、入居までの日数も注文住宅より掛からないメリットがあります。しかし、建売住宅にも買ってはいけない物件というものがあります。今回は、買ってはいけない建売住宅の特徴と家の購入に失敗しない選び方についてご紹介していきます。 こんな建売住宅は買うな!失敗してしまう物件の特徴と成功する選び方点検口がない建売住宅は注意!点検口とは、床下や屋根裏の中を覗く事ができるように設けられたものです。外から見る事ができない配管類や構造体の確認ができるように点検口は設けられており、建物の維持管理をしていくためには重要な箇所となっています。建物の配管や構造体に異常が見られる場合や不具合がないか定期的に点検を行う際は、この点検口を用いて建物の状態を確認します。注意しなければいけないのが、建売住宅の中には点検口が設けられていない物件があるという事です。点検口の有無は、間取り図に記載されていない場合もあり、営業担当者から点検口がない事を説明してくれない可能性もあります。主に点検口を使用するのは業者で、一般の方には縁がありませんから、点検口がない事に気づかないまま契約してしまうなんて事もあるかもしれません。生活するようになり、建物のメンテナンスが必要になった時に初めて点検口がない、という事になりかねませんので、必ず購入する住宅に点検口があるか確認しましょう。 未完成物件や資料不足の建売住宅は注意!標準仕様という曖昧な仕様標準仕様とは、キッチンやシステムバス、床の素材、建物の性能など、住宅会社があらかじめ決めた物件の基準となる仕様のことです。標準仕様は、住宅会社によってそれぞれ内容が異なり、提供する商品のグレードによっても標準仕様は変わります。住宅には仕様書という書類があり、どんな材料で建てられているかを記載している大切な書類があります。建物が完成した後では、柱や梁、基礎など構造体がどうなっているか確認する事ができませんので、図面や仕様書がある事が大切です。どんな建物になっているか書面で確認する事ができない資料不足の物件の購入は、どんな建物か不明のままですから、購入は控えましょう。 高額になる?対応してくれない?追加工事・オプション工事建売住宅の会社によっては、追加工事に対応しない場合もあり、追加を受けても高額な費用を請求してくる会社もあります。また、通常は付いていて当たり前のものまでオプション扱いとなっている建売住宅もあるので注意が必要です。網戸やカーテンレールなど建物の価格を安く見せるために必要なものまでオプション化している事もあります。建物に付いていて当たり前のものが契約するまで知らなかったというのも決して少なくはありません。このように住宅会社の言う標準仕様というのは、各会社によって内容が異なり、建物に付帯しないものも標準仕様と通ってしまうため、必ず建物の仕様を確認するようにしましょう。 アフターサービスが悪い建売住宅の購入後は、何十年とこの家で暮らしていく事になります。その間にも建物は老朽化し、長く保たせるためにも点検やメンテナンスを行わなければいけません。建物の点検やメンテナンスは購入した住宅会社に行ってもらうのが一般的です。しかし物件を販売する時は熱心でも、その後のアフターサービスにはまともに対応してくれない住宅会社も多くあります。物件を販売する事が利益であり、アフターサービスは利益にならない、という考えを持っている住宅会社もありますから、アフターサービスの対応が期待できない会社の建売住宅は購入しない事が望ましいです。アフターサービスが充実している会社は、どのようなスケジュールで販売した物件を維持管理していくか説明があります。住宅保証や点検の周期など、建物の維持管理についてきちんと説明してくれて、その後のアフターサービスに対応してくれる会社の建売住宅を購入する事が大事です。 品質管理ができていない品質管理ができていない建売住宅の購入は避けなければなりません。品質とは言っても外観や内観の目に見える部分が綺麗なら大丈夫かというとそうではありません。重要なのは建物の目に見えない部分である柱や梁、土台、基礎、配管類などの建物の造りがしっかりとしている事です。建売住宅の場合は、すでに完成してしまっている事が多く、構造体などは建物の中に隠れて目に見えない状態です。できる事なら建築中の現場を見学する事がいいのですが、それができない場合は建築中の現場写真が残されているか確認し、写真があるのなら見させてもらうといいでしょう。また、おすすめなのが住宅性能表示のある物件を選ぶ事です。住宅性能表示とは、長期優良住宅やZEH住宅など、ある一定の性能基準をクリアした建物の事で、第三者機関の審査を受けて基準性能を有していると認定されなければ受けられない制度です。販売する住宅会社の間に第三者の審査員が入って建物を見てくれますので、信頼できる住宅を手に入れる事ができます。 周辺物件よりも価格が極端に安い建売住宅は注意土地や建物の価格は、ある程度相場というものがあります。土地につきましても近隣相場から取引価格を算定され、建物も材料費や人件費というものが必ず掛かります。このように必ず掛かる費用のことを考慮すると、周辺の物件よりも極端に安い建売住宅は何らかの理由がある可能性が高い事になります。借地権付きの物件のように土地の購入を必要としない物件は、一般的な建売住宅よりも安くはなりますが、土地と建物の仕入れ価格を見ますと周辺物件の価格よりも大きく下がるとは考えにくいのです。 建築確認済証と検査済証の提示・地盤調査報告書がない建築確認済証と検査済証、地盤調査報告書の書類がない建売住宅は購入しない方がいいでしょう。建築確認済証と検査済証は建築基準法に基づいた建物である事を検査し、証明する公的な書類です。そもそも建築確認済証の交付がなければ建物を建てる事はできません。建築確認済証はあるが、検査済証がないという物件もあるので要注意です。検査済証は、建築確認申請で許可を受けた設計通りに建物が建てられているか第三者機関が検査を行い、認定後に交付される書類です。検査済証がないと、設計図通りに建てられている住宅である事が証明できませんので、注意しましょう。また、住宅瑕疵担保責任保険の加入は地盤調査の実施が必須です。地盤調査の結果を報告書として記載され、軟弱地盤の場合は地盤改良など適切な処置を行う必要があります。建売住宅によっては、この地盤調査報告書がないという事もあり、地盤に不安がある場所に建物を建てると不同沈下の恐れがあります。このように建物がきっちりと建てられているという事が証明できる建築確認済証と検査済証、地盤調査報告書の書類がある建売住宅を選ぶ事が大事です。 セミオーダー住宅も検討してみよう建売住宅のメリットは費用の安さと短期間で入居する事ができる事です。しかし、品質については自分で判断しなければならず、購入者側で色々と情報を集めて自主的に行動しなければいけません。住宅購入の費用をできるだけ抑えたいという方は、注文住宅でも比較的に建築コストを抑える事ができるセミオーダー住宅を検討するのもいいでしょう。セミオーダー住宅とは、基本となるプランから自分の好みに合わせて設計ができるスタイルとなっています。用意されているプランがあるため、期間の短縮と費用を抑えながらも自分の好みに合わせて変更ができる設計ですから、ライフスタイルに合わせた家づくりが可能となっています。費用を安くしたいという方は、セミオーダー住宅も候補の一つとして入れてみるといいでしょう。 いえとち本舗は月々3万円台で叶えられるイエテラスというセミオーダー住宅を提供しています。会員登録する事で施工事例や間取りを無料で見る事ができますので、良ければまずは資料請求をしてみてはいかがでしょうか。https://smarthouse-yamaguchi.jp/member/
-

一戸建ては何年住める?中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説
築40年や築50年の中古一戸建ての購入を検討している方は、あと何年住めるかが気になるのではないでしょうか。住宅の寿命は30年といわれることもあり、築年数が経過した中古一戸建てを購入する際は不安になってきます。 この記事では、中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説します。一戸建ての本当の寿命を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 1.一戸建ての寿命は何年?1-1.建物の寿命は法定耐用年数とは異なる1-2.木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上1-3.長期優良認定住宅は75~90年以上の耐久性がある2.一戸建てに長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠2-1.定期的に住宅の点検を行い劣化や損傷を早期に発見する2-2.メンテナンス・リフォーム・リノベーションを行う3.一戸建ての寿命が近づいたときの対処法3-1.全面リフォーム・リノベーションを行う3-2.建て替えを行う3-3.住宅を売却して住み替える4.中古一戸建てを購入するメリット4-1.新築よりも安い価格で購入できる4-2.実際に物件を確認してから購入できる4-3.立地や間取りなどの選択肢が豊富5.中古一戸建てを購入するデメリット5-1.建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性がある5-2.修繕やリフォームの費用がかかる可能性がある5-3.住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある6.中古一戸建てを購入する際の注意点6-1.建物の現状をしっかりと確認する6-2.契約不適合責任を確認する6-3.予算に余裕を持たせる7.まとめ:メンテナンスやリフォームで住宅の寿命を延ばせます! 1.一戸建ての寿命は何年? 一戸建ての寿命は30年といわれることがありますが、築30年や築35年が経過すると住めなくなるのでしょうか?一戸建ての寿命を知るには、法定耐用年数や期待耐用年数などを理解することが必要です。ここでは、一戸建ては何年住めるかを解説します。 1-1.建物の寿命は法定耐用年数とは異なる 建物の寿命は法定耐用年数とは異なります。木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、築後22年が経過すると寿命がきて住めなくなるわけではありません。法定耐用年数は建物の資産価値がなくなるまでの年数を想定して定められています。 木造住宅の場合、築後22年が経過すると資産価値はなくなりますが、建物の物理的状態に問題がなければ住み続けることはもちろん可能です。ただし、建物の老朽化や設備の劣化が進行している場合はメンテナンスやリフォームが必要になることがあります。 一般的に築30年以上経過している木造の中古一戸建ては建物の資産価値がなくなっており、土地価格だけで購入できる場合があります。しかし、安く購入できてもメンテナンスやリフォームの費用がかかることがあるため注意が必要です。 1-2.木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上 木造住宅の寿命は30年といわれることがありますが、これは日本の住宅の平均利用期間が30年であるためです。 出典:国土交通省「長持ち住宅の手引き」 日本人は新築志向が高く、築30年以上経過すると建物を取り壊して新築住宅を建設、購入する傾向があります。まだ住めるのに建物を解体するケースは多く、諸外国と比べると住宅の平均利用期間が短い原因になっています。 木造住宅の実際の寿命を知るうえで参考になるのは、国土交通省が定める期待耐用年数です。期待耐用年数とは、適切な維持管理を行った場合における建物が使用できる期間を指します。 木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、メンテナンスやリフォームを適切に行うことで、築40年や築50年であっても住み続けられる可能性は十分あります。 出典:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」 1-3.長期優良認定住宅は75~90年以上の耐久性がある 長期優良住宅とは、国が定める耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなどの基準を満たした住宅を指します。長期優良住宅は一般の住宅よりも品質が優れており、期待耐用年数は100年を超えます。 耐震性も優れており、震度6強から7程度の大地震でも倒壊することはありません。断熱性能も高く、冷暖房の効きが良くなることで光熱費の削減にもつながります。 長期間にわたって良好な状態で使用するにはメンテナンスが欠かせませんが、長期優良住宅は維持管理がしやすいように設備が設置されており、メンテナンスも容易です。 また、長期優良住宅の認定を受けると、フラット35の金利が0.25%引き下げられたり、税の特例措置が拡充されたりするなどの優遇が受けられます。 2.一戸建てに長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠 一戸建ては30年以上の寿命がありますが、長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠です。適切なメンテナンスを行うことで、一戸建ての寿命をさらに延ばせます。ここでは、一戸建てのメンテナンスやリフォーム、リノベーションを解説します。 2-1.定期的に住宅の点検を行い劣化や損傷を早期に発見する 一戸建ての寿命を延ばすには、定期的に住宅の点検を行い、建物の劣化や損傷を早期に発見することが大切です。修理や補修を迅速に行うことで、将来における深刻な問題の発生を予防し、住宅の安全性を確保できます。 自主点検で重要な箇所は、浴室や洗面所、トイレ、キッチンなどの水回りです。水回りは劣化しやすいため、日頃からの点検が重要になってきます。 日常の点検は、目視できる範囲で行うようにしましょう。目視できない箇所については、ホームインスペクター(住宅診断士)に点検してもらうと不具合箇所が明確になります。目視できない箇所のホームインスペクションの費用相場は、6~12万円程度です。 なお、ホームインスペクションの費用については、地域や業者によって異なるため、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。 2-2.メンテナンス・リフォーム・リノベーションを行う 点検で不具合箇所が見つかれば、早期にメンテナンス(修繕)を行うことが大切です。住宅を建築した施工業者や修理・修繕業者、工務店、リフォーム会社などに相談すると良いでしょう。 水回りや外壁、屋根などは、劣化が進行しやすいため、築年数に応じて定期的なリフォームが必要です。リフォームとは、劣化した箇所を元の状態に戻すことです。 水回りリフォームは築15~20年、外壁や屋根は築10~20年程度がリフォームの目安です。定期的なリフォームを行うことで、一戸建ての寿命を延ばせます。 間取りを変更するなど、大規模な改装・改修をして建物の価値を高めたい場合はリノベーションを行いましょう。リノベーションをすることで建物の価値が高まり、居住性が大きく向上します。築20年が経過して築30年を迎えた頃がリノベーションを行う目安です。 3.一戸建ての寿命が近づいたときの対処法 一戸建ての寿命が近づいたときは、全面リフォームやリノベーション、建て替え、売却など、いくつかの選択肢があり、最も適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、一戸建ての寿命が近づいたときの対処法を解説します。 3-1.全面リフォーム・リノベーションを行う寿命が近づいた建物を解体せず、改装・改修をしてそのまま住みたい場合は、全面リフォームやリノベーションがおすすめです。ただし、工事箇所が多い場合は、建物を解体して建て替えたほうが費用を抑えられることもあります。 複数の業者と相談して見積もりを取り、全面リフォームやリノベーションと建て替えのどちらにするのかを決めましょう。国土交通省の調査資料によると、全面リフォームの費用は500~2,500万円程度が目安です。リノベーションも同程度の費用がかかります。 ローコスト住宅であれば総額1,000万円台で建て替えができます。そのため、リフォーム費用が予想以上に高額であれば、建て替えを検討するのも一つの選択肢です。 出典:国土交通省「リフォームの内容と価格について」 3-2.建て替えを行う日本人は新築志向が高いため、一戸建ての寿命が近づいたときに建物を解体して、新築住宅に建て替えることはよく行われます。建て替えのメリットは理想とする新築住宅に住めることで、ローンを組みやすいこともメリットです。 一方、デメリットは建物が完成するまでに4~6ヵ月以上かかり、建て替え工事中は一時的に賃貸マンションなどに転居する必要があります。仮住まいの家賃や引っ越し費用なども考慮しなければなりません。 建て替えの費用は新築する建物のグレードによって異なりますが、1,000~4,000万円程度の費用がかかります。長期的な視点で考えて、リフォームをするよりも建て替えのほうがメリットが大きい場合は、建て替えをおすすめします。 3-3.住宅を売却して住み替える一戸建ての寿命が近づいた場合、全面リフォームや建て替えを行わず、売却して住み替えるという選択肢もあります。ただし、古い建物は値段がつかない場合があるため、建物を解体して更地にして売却することも検討しましょう。 建物の状態にもよりますが、建物を解体して更地にしたほうが早く売れる場合があります。建物の解体費用は、建物の構造や延床面積によって異なりますが、30坪の木造住宅だと90~150万円程度が相場です。 なお、住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。今住んでいる一戸建てを売ったお金でローンを完済できなければオーバーローンになるため注意が必要です。 4.中古一戸建てを購入するメリット 一戸建ての実際の寿命は30年以上あるため、メンテナンスやリフォームが適切に行われていれば、中古一戸建てを購入するメリットは大きいです。ここでは、中古一戸建てを購入するメリットを解説します。 4-1.新築よりも安い価格で購入できる新築よりも安い価格で購入できることが、中古一戸建てを購入する最大のメリットです。築30年以上経過していると、土地価格のみで購入できる場合があります。 物件によっては、土地の相場価格以下で購入できることもあり、予算が少なくても住みたかったエリアにマイホームを持てる可能性が高まります。新築では購入が難しい駅チカや都心の物件の取得も可能になることは、中古一戸建ての大きな魅力です。 建物の老朽化が進んでいる場合も、リフォームやリノベーションをすることで、新築住宅と変わらない状態に再生できるため、リフォーム費用を考慮してもお得な場合があります。なお、購入後にリフォームやリノベーションをする場合は、どの程度の費用がかかるかを把握しておくことが大切です。 4-2.実際に物件を確認してから購入できる実際に物件を確認してから購入できることも、中古一戸建てのメリットです。新築住宅は完成しないと物件を確認できません。中古一戸建ては既に物件が存在するため、外観や内観、日当たりなどを自分の目で確認できます。 実際に住んでからのイメージがしやすく、入念に調査をすれば住んでから後悔することは少ないでしょう。修繕やリフォームが必要な箇所も、直接目で見て把握できます。なお、不具合や修繕が必要な箇所がある場合、それを考慮して価格交渉の材料にすることも可能です。 物件を確認する際は、ホームインスペクション(住宅診断)を依頼すると、プロの視点で物件の確認ができます。目視ができない箇所も確認できるため、不動産購入時の安全性が高まります。 4-3.立地や間取りなどの選択肢が豊富中古一戸建ては不動産市場での流通量が多く、立地や間取りなどの選択肢が豊富です。新築住宅は物件数が限定しており、学区や最寄り駅などにこだわりがある場合、なかなか物件が見つからないことはよくあります。その点、中古一戸建ては物件数が多いため、理想の住宅に巡り会える可能性が高いです。 中古一戸建てにはさまざまな間取りがあり、家族のニーズやライフスタイルに合った間取りを選べます。家族構成や将来の計画などに応じて、間取りを柔軟に選択できることは中古一戸建てのメリットです。 また、中古一戸建ては既に建物が完成しているため、即座に入居できる場合が多いです。新築物件よりも迅速な入居が可能であり、急な住み替えや引っ越しにも適しています。 5.中古一戸建てを購入するデメリット 一戸建ての寿命は30年以上ありますが、メンテナンスやリフォームが適切に行われていることが前提です。中古一戸建ては物件によっては劣化が進行しているなどのデメリットがあります。ここでは、中古一戸建てを購入するデメリットを解説します。 5-1.建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性がある物件によっては、建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性があります。一戸建ては適切なメンテナンスやリフォームを行うと寿命を延ばせますが、そのまま放置しておくと老朽化や劣化が進行します。 老朽化や劣化が酷い場合、メンテナンスやリフォーム費用が発生する可能性が高いです。屋根や外壁の補修、配管や電気設備の更新、内部の改装などで100~200万円以上かかる場合もあります。 なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅は耐震性に問題がある可能性があり、注意が必要です。耐震補強工事を行っていない場合、震度5程度の地震には耐えられますが、震度6強~7の地震には耐えられず、倒壊する危険性があります。 5-2.修繕やリフォームの費用がかかる可能性がある購入時には修繕やリフォームが必要なくても、住み始めてから修繕やリフォームの費用がかかる可能性があります。築年数が経過した中古一戸建ては、新築と比べると建物や設備の劣化のスピードが速く、住み始めてすぐに修繕が必要になることもあるでしょう。 購入前に建物の状態を調査し、将来の修繕やリフォームの費用を考慮することが重要です。しかし、将来的なリフォーム費用は予測しにくく、想定以上の費用がかかることもあります。 なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古一戸建てで、耐震補強工事を行っていない場合は、購入後に耐震補強工事が必要です。耐震補強工事の費用相場は100~200万円程度で、工期は1週間〜1ヵ月程度かかります。 5-3.住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある中古一戸建ては新築住宅と比べると、住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があります。これは、建物の資産価値が低下しているため、担保価値が低くなるためです。住宅ローンの種類や建物の状況によっては、審査に落ちることもあるでしょう。 立地条件が悪く、建物だけでなく土地の資産価値も低い中古一戸建ては、審査に落ちる可能性が高まります。 なお、新築住宅は頭金なしのフルローンや諸費用込みローンを利用できる場合がありますが、中古一戸建ては諸費用込みローンの利用は難しいです。建物の状況によってはフルローンの審査も落ちる可能性があります。 住宅ローンを組んで中古一戸建てを購入する際は、事前に仮審査を受けておくことが大切です。 6.中古一戸建てを購入する際の注意点 中古一戸建ては新築よりも安いなどのメリットがある反面、老朽化が進行している可能性があるなどのデメリットがあります。中古一戸建てを購入する際は、デメリットも考慮することが大切です。ここでは、中古一戸建てを購入する際の注意点を解説します。 6-1.建物の現状をしっかりと確認する中古一戸建てを購入する際は、建物の現状をしっかりと確認することが極めて重要です。目視できない箇所まで入念にチェックすることが大切であり、ホームインスペクションの利用をおすすめします。 ホームインスペクションは、建物の構造や設備、電気・配管などの重要な部分を専門家のホームインスペクターが詳細に調査します。これにより、潜在的な問題や隠れた欠陥の発見が可能です。 ホームインスペクションで明らかになった問題は、価格交渉の際に有利な材料となります。修繕が必要な場合、その費用を考慮して値下げを要求できます。 6-2.契約不適合責任を確認する 契約不適合責任とは、2020年の民法改正で定められたもので、旧民法の瑕疵担保責任に類似する売主の責任です。契約不適合責任は、目的物の現状と契約の内容に不一致があれば成立し、売買や賃貸借などの契約に適用されます。 売主は買主の選択によって、目的物の補修、代替物の引き渡し、代金減額、契約解除のいずれかによって責任を履行しなければなりません。例えば、購入した物件がシロアリによる被害を受けていたことが発覚したような場合、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。 なお、売主が個人・不動産会社によって保証期間が異なり、不動産会社は最低2年、個人は売主が自由に決められます。契約内容をしっかりと確認することが大切です。 6-3.予算に余裕を持たせる 中古一戸建てを購入する際は、予算に余裕を持たせることが大切です。土地価格や建物価格だけでなく、仲介手数料や登録免許税、印紙税、司法書士報酬などの諸費用もかかるため、予算に余裕を持たせておかないと資金不足に陥る可能性があります。 修繕費やリフォーム費用がかかる場合もあるため、物件価格だけでなくトータルコストで考えましょう。事前にトータルコストをシミュレーションしておくことをおすすめします。これにより、予想外の支出に対処できる余裕を確保できます。 7.まとめ:メンテナンスやリフォームで住宅の寿命を延ばせます! 木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、30年以上の寿命があります。長期優良住宅の期待耐用年数は100年を超えるため、親子孫の3代にわたって住み続けることが可能です。 一戸建てに何年住めるかは、定期的なメンテナンスやリフォームによって違ってきます。メンテナンスやリフォームを行うことで住宅の寿命を延ばせます。適切な維持管理ができていれば、築30年以上の中古一戸建ては価格が安く大変お得です。 なお、中古一戸建てを購入する際は、ホームインスペクションの利用もおすすめです。目視ができない箇所も専門家に確認してもらうことで、安心して購入できます。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
-

平屋のメリットとデメリットは?二階建てとの違いやリノベーションについて解説
近年、幅広い年代で平屋の人気が高まっています。平屋の購入・新築・リノベーション・賃貸を検討している方は多いでしょう。平屋の購入や新築などを検討している方は、平屋のメリットとデメリットを知っておくことが大切です。この記事では、平屋のメリットとデメリット、二階建てとの違いなどを解説します。平屋で暮らしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 1.平屋の特徴1-1.平屋と二階建ての違い1-2.平屋の人気が上昇している理由2.平屋のメリット2-1.バリアフリーで誰もが利用しやすい2-2.生活動線や家事動線が効率的で移動がスムーズ2-3.家族が自然と集まり会話や交流が活発になる2-4.光熱費やメンテナンス費用が安く抑えられる2-5.耐震性が高く地震や強風などの揺れの影響を受けにくい2-6.構造物が少なく自由な間取りを実現しやすい3.平屋のデメリット3-1.広い敷地が必要3-2.二階建てよりも坪単価が高くなりやすい3-3.日当たりや風通しが悪くなりやすい3-4.プライバシーや防犯面で注意が必要4.平屋と二階建てで迷った場合は?4-1.平屋が向いている人4-2.二階建てが向いている人5.平屋をリノベーションするメリット・デメリット5-1.平屋リノベーションとは5-2.平屋リノベーションのメリット5-3.平屋リノベーションのデメリット6.メリット・デメリットを総合的に検討して平屋にするかを決めましょう! 1.平屋の特徴平屋のメリットとデメリットを把握するには、二階建てとの違いを押さえておく必要があります。ここでは、平屋と二階建ての違いを整理して、平屋が近年人気を集めている理由などを解説します。 1-1.平屋と二階建ての違い平屋と二階建ての大きな違いは階段の有無です。平屋には二階建てには必ず存在する階段がありません。階段の有無は、移動のしやすさや災害時の安全性、費用などの違いを生み出します。 平屋は階段がなくワンフロアで生活できるため、二階建てよりも移動が容易です。また、階段がないため構造的に安定しており、地震や台風などの災害に強いといえます。ただし、床上浸水などの災害時には上階に避難ができず、必ずしも二階建てより安全であるとはいえません。 費用に関しては、延べ床面積が同じであれば、平屋は屋根や基礎の面積が広くなるため、二階建てよりも坪単価が高くなる傾向があります。ただし、どちらが費用面で有利であるかは、建物の規模や間取り、設備などによって異なります。 1-2.平屋の人気が上昇している理由若い世代からシニア世代まで、幅広い年代で平屋が人気を集めている理由として、「コンパクトな暮らしがおしゃれ」や「バリアフリーで暮らしやすい」などが挙げられます。 ミニマリズムなどのライフスタイルの多様化により、コンパクトな暮らしが人気を集めており、ワンフロアで生活できる平屋が魅力的だと感じる方が増えています。また、少子高齢化により、年をとっても安心して暮らせることも平屋の人気が高まっている一因でしょう。 地震や台風などの自然災害に強いことも、平屋の人気が高まっている理由の一つです。平屋は重心が低く安定しており、地震や強風の影響を受けにくい構造になっています。構造上の安定性が高いことで、個性的でおしゃれなデザインにしやすいことも平屋ならではの魅力です。 2.平屋のメリット 平屋ならではの特徴は階段が存在しないことです。平屋は階段がなくワンフロアで生活できるため、二階建てにはないさまざまなメリットが得られます。ここでは、平屋のメリットをいくつかご紹介します。 2-1.バリアフリーで誰もが利用しやすい平屋は階段がないため、小さい子どもから高齢者まで誰もが生活しやすいことがメリットです。階段からの転落事故や段差につまずいて転倒するリスクも少なく、安心して子育てや介護ができます。 家族に車椅子を使用している方がいる場合も、平屋だと室内を安全に移動できることもメリットです。玄関に段差解消スロープを設置すると、車椅子に乗ったままで家に出入りができます。 平屋はワンフロアであるためバリアフリーに対応しやすく、階段に手すりやエレベーターを設置する必要もありません。バリアフリーリフォームをする際も最低限の工事をするだけでよく、二階建てよりも費用を抑えられます。 若い世代も平屋だと年をとってからも住みやすく、将来を見据えて平屋を選ぶ方も存在します。 2-2.生活動線や家事動線が効率的で移動がスムーズ平屋はワンフロアにすべての間取りが収まっており、生活動線や家事動線が効率的でスムーズに移動できます。リビングルームやキッチン、浴室などが同じ階に配置されているため部屋間をスムーズに移動でき、階段による上下移動も必要ありません。 例えば、キッチンからリビングへの移動や、洗濯機の設置場所から洗濯物を干すバルコニーへの移動などは階段を使わなくても済むため、家事の時短や効率化が図れます。また、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、階段の上り下りがないため、日常生活における安全性が向上します。 生活動線や家事動線が効率的になり、家族にとって住みやすい環境になることは、平屋ならではのメリットといえるでしょう。 2-3.家族が自然と集まり会話や交流が活発になる平屋はオープンで広々とした間取りが特徴で、リビング・ダイニング・キッチンが一体化していることが多く、家族が自然と同じ空間に集まりやすいこともメリットです。家族同士の会話や交流が活発になりやすく、家族の絆が深まります。 二階建てだと、学校から帰宅してきた子どもは二階の子ども部屋に直行することがありますが、平屋だといつも家族の気配を感じられます。子どもたちがリビングで遊ぶ様子を見守りながらキッチンで調理をするなど、子育てをするのに適した環境といえるでしょう。 家族間のコミュニケーションが取りやすいことは平屋のメリットであり、家族の団らんを大切にしたい方にとっては、平屋は有効な選択肢になります。 2-4.光熱費やメンテナンス費用が安く抑えられる平屋はワンフロアであるため、光熱費やメンテナンス費用を低く抑えられます。平屋は階段がなく一つの階にすべての部屋が配置されており、空気の循環が効率的です。これにより、冷気や暖気が効率的に行き渡り、電気代の節約につながります。また、平屋は屋根が大きく、太陽光発電を取り入れているケースも多いです。 メンテナンス費用も低層の平屋は低く抑えられます。外壁や屋根をメンテナンスする際は、足場を組まなくてはなりません。建物が高層になるほど足場の料金も高くなるため、低層の平屋は費用面で有利です。簡単な修繕であれば、足場を組まずにできることもあるでしょう。 また、一般的に平屋は二階建てよりも水回りの設備や空調設備が少なく、設備のメンテナンス費用や交換費用も低く抑えられます。 2-5.耐震性が高く地震や強風などの揺れの影響を受けにくい平屋は二階建てと比べて耐震性が高く、地震や強風などの揺れの影響を受けにくいこともメリットです。平屋は構造がシンプルで、建物の上下の重量が均等に分散されています。このシンプルな構造により、地震や強風などに対する耐性が高まります。 平屋は一つの階しかないため、二階建てと比べると基礎を強化しやすいです。適切に設計・施工された基礎は、地震時に発生する揺れに対して建物をしっかりと支える役割を果たします。地震が発生した際も振動が広がりにくく、揺れによる影響は軽減されます。 ただし、基礎や柱、梁などの構造がしっかりとしていないと耐震性は低下するため、地盤調査や設計、施工をきちんと行う信頼できる建設業者を選ぶことが大切です。 2-6.構造物が少なく自由な間取りを実現しやすい平屋は二階がないため構造上の制約が少なく、自由な間取りを実現しやすいこともメリットです。デッドスペースになりやすい階段部分が不要で、限られた空間を有効活用できます。リビング・ダイニング・キッチンを一体化すると壁や廊下のスペースも少なくでき、そのスペースも有効活用できるでしょう。 また、平屋は低層であるため、高さ制限や斜線制限の影響を受けにくく、外観のデザインの自由度も高いです。個性的でおしゃれな外観にしやすく、平屋のデザイン住宅の人気も高まっています。 アメリカンスタイルやログハウス風など、好みやライフスタイルに合った家で暮らしたい方にとって平屋は魅力的であり、これも平屋回帰が進んでいる一因です。 3.平屋のデメリット 平屋はバリアフリーで誰もが利用しやすく、間取りや外観の自由度が高いなどのメリットが得られますが、広い敷地が必要になるなどのデメリットもあります。ここでは、平屋のデメリットを解説します。 3-1.広い敷地が必要平屋は水平方向に伸ばすため、建築するには広い敷地が必要です。平屋は垂直方向に伸ばせず、一階にすべての部屋を配置させなければなりません。建物の延べ床面積が同じであれば、二階建てよりも広い敷地が必要になってきます。 地価の高い都市部では、予算が少ないと広い敷地を確保するのは難しいことがあるでしょう。ただし敷地が狭い場合でも、設計を工夫すると平屋の建築は可能になることがあります。 平屋は階段部分が不要であり、廊下スペースを最低限に抑える間取りにすると、都市部や狭小地でも平屋を建築できます。また、建築基準法や地方公共団体の条例を遵守する必要がありますが、屋根裏を有効活用してロフトを設置することも可能です。 3-2.二階建てよりも坪単価が高くなりやすい建物の延べ床面積が同じだと、平屋は二階建てよりも建築費の坪単価が高くなりやすい傾向があります。坪単価が高くなる理由は、建物の延べ床面積が同じである場合、平屋は二階建てよりも基礎部分や屋根の面積が広くなるためです。基礎工事や屋根工事に費用がかかるため、建築費の坪単価も高くなります。 ただし、坪単価は高くなっても、トータルコストは必ずしも高くなるとは限りません。その理由は、平屋は階段や二階の廊下が不要であり、間取りが同じであれば二階建てよりも延べ床面積を減らせるからです。 「建築費=延べ床面積×坪単価」であるため、坪単価が高くなっても、延べ床面積を減らすことでトータルコストを低く抑えられることがあります。平屋と二階建てを費用面で比較する際は、トータルコストで考えることが大切です。 3-3.日当たりや風通しが悪くなりやすい平屋は周囲の状況や建物の形状、配置によっては、日当たりや風通しが悪くなることがあります。周囲に高い建物や樹木がある場合、それらの障害物によって日光や風が遮られてしまいます。 特に高い建物や樹木が建物の南側にあると、日当たりに影響が出やすいです。また、建物同士が密集している地域では、隣の建物からの影響が大きくなることがあります。 なお、敷地や建物の形状、配置によって日当たりや風通しは大きく変化します。建物の形状を「コの字型」や「くの字型」などにして、敷地の適切な位置に配置すると、採光と通風を確保できる場合があるでしょう。平屋を建築する際は、採光や通風なども考慮して設計することが大切です。 3-4.プライバシーや防犯面で注意が必要平屋は周囲の状況によっては、外から家の中を覗き込まれる可能性があります。これは、平屋が一階建てであり、窓や開口部が低い位置にあるため、外部から内部への視認が容易になるからです。 周囲に遮蔽物がなく、外部から室内を容易に覗き込まれる可能性がある場合、プライバシーの確保や防犯対策をしっかりと検討することが大切です。プライバシーを確保するために、堀や目隠しフェンス、植栽などで外部からの視線を遮りましょう。 設計の段階でプライバシーの確保を考慮して、浴室やトイレ、居室の窓の配置などを工夫することも重要です。必要に応じて、防犯カメラや防犯ガラス、センサーライトなどを設置すると、防犯性能が高まります。 4.平屋と二階建てで迷った場合は? 平屋と二階建てのどちらが向いているかは、個々のライフスタイルや家族構成、好みなどによって異なります。ここでは、平屋が向いている人と二階建てが向いている人を解説します。平屋と二階建てで迷ったときの判断材料にしてください。 4-1.平屋が向いている人平屋はバリアフリーであるため、小さな子どもや高齢者、車椅子で生活している方がいる世帯に向いています。住居内での転落事故や転倒事故を防止でき、安心して子育てや介護ができます。ワンフロアであるため家族を見守りやすく、平屋は子育てや介護をするのに適しているといえるでしょう。 一生同じ家に住みたい場合、今は若くても将来を見据えて、バリアフリーで暮らしやすい平屋を選択する方も存在します。 家族とのコミュニケーションを大事にしたい方にも、平屋がおすすめです。平屋は部屋と部屋の距離が近く、家族同士の会話や交流が活発になりやすい構造になっています。いつも家族の気配を感じられ、温もりのある家庭を築きたい方に最適です。 4-2.二階建てが向いている人平屋を建てるには広い敷地が必要であるため、土地の広さが限られている場合は二階建てが向いています。狭小地でも平屋の建築は可能ですが、二階建てよりも部屋数を多くするのは困難です。 したがって、都市部などで敷地面積が限られていて家族数が多い場合は、平屋よりも二階建てが向いています。4人家族以上で部屋数を多くする必要がある場合、二階建てのほうが間取りプランの自由度は高いです。 同じ屋根の下で家族が一つになりながら、適度な距離を保ってお互いのプライバシーを尊重したい場合も、二階建てが適します。また、将来的に親との同居を考えている方も、二階建てのほうが二世帯住宅にリフォーム・リノベーションがしやすいです。 5.平屋をリノベーションするメリット・デメリット 平屋をリノベーションすることは可能です。リノベーションとは、既存の建物を改修し、新しい要素を追加して機能やデザインを向上させる工事を指します。ここでは、平屋をリノベーションするメリット・デメリットを解説します。 5-1.平屋リノベーションとは平屋リノベーションとは、既存の平屋をライフスタイルや好みに合わせて、間取りや設備、内装などの改装をすることを指します。構造的な問題や法的な問題がなければ、平屋を二階建てに、二階建てを平屋にリノベーションすることも可能です。 例えば、子どもが独立後に夫婦が暮らしやすくするために、二階建てを平屋にリノベーションすることがあります。また、家族構成の変化に対応して、部屋数を増やすためにリノベーションをすることもあるでしょう。 リノベーションの費用は工事内容によって異なるため、一概にはいえませんが、二階建てを平屋にリノベーションするには、500〜2,000万円程度かかるのが一般的です。 5-2.平屋リノベーションのメリット平屋リノベーションのメリットは、ライフスタイルや家族構成に合った理想の住宅にできることです。例えば、大きな屋根裏空間を活用してロフトを作ったり、勾配天井を活かして吹き抜けのあるリビングルームにしたりなど理想の住宅が実現します。 平屋は設計の自由度が高いため、リノベーションをするのに向いているといえるでしょう。また、二階建てを平屋にリノベーションすると、二階建てにはない平屋ならではのメリットを享受できます。 二階建てを平屋にすると階段のないワンフロアになるため、子どもが独立後の老後の生活が暮らしやすくなります。リビングや水回り、物干し場などがワンフロアで完結することは、老後の生活を快適に送るうえで大きなメリットです。 5-3.平屋リノベーションのデメリット二階建てを平屋にリノベーションする場合、災害時の対策や防犯対策などが必要になってきます。洪水や床上浸水などの際は二階やベランダに避難ができず、逃げ場がなくなります。 ハザードマップなどを確認し、洪水や床上浸水などの被害が想定される場合は、万一の災害に備えたリノベーションプランの検討が必要です。特に足腰の弱い高齢者が同居している家庭は、災害時の対策を徹底しておきましょう。 二階建てを平屋にすると防犯性能が低下することもデメリットです。リノベーション業者との打ち合わせでは、平屋にするとどのような防犯上の問題が発生するのかを洗い出し、適切な対策を講じるようにします。 また、土地が広いとリノベーション費用が高額になる傾向があるため、本当に必要な工事だけを行うようにすることも大切です。 6.メリット・デメリットを総合的に検討して平屋にするかを決めましょう! 平屋にするかを決める際は、メリット・デメリットを総合的に検討することが大切です。平屋は「バリアフリー性に優れている」「家族とのコミュニケーションが取りやすい」などのメリットがある反面、「広い敷地が必要」「日当たりや風通しが悪くなりやすい」などのデメリットがあります。 平屋は二階建てよりも設計の自由度が高く、専門家と相談すると、デメリットを解消できる場合があります。 平屋は、家族のライフスタイルや予算に合わせて、自由に設計・カスタマイズできる魅力的な住宅です。メリット・デメリットを総合的に検討して、ご家族にとって最適な住宅を実現しましょう。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。









