ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
考えておきたいリビング収納【いえとち本舗の新築・山口・宇部・山陽小野田・防府・周南】
みなさまこんにちは!
いえとち本舗山口中央店です(^^)/
山口で新築住宅を考える際に、間取りはこれから家づくりで最も重要な点だと言っても過言ではないと思います。
建てる前からしっかり考えておかないと、住み始めてから思わぬ苦労をする事になります!
住み始めてから「やっぱりこうしておけば良かった」と後悔している中にはいるのではないでしょうか?
その中でも1番多かった意見が新築の内装で「リビングの収納」をもっと重要視すればよかったことです。
しかし、土地面積が限られていると、広いスペースが確保できないケースもあります。
逆に、せっかく広い収納スペースを確保したのに使いにくく、不便を感じてしまうことも……。
広くても狭くてもうまくいかないなら、一体どうすればいいのでしょう?
そこで今回は、山口の新築住宅の収納スペースでありがちな失敗事例をもとに、リビング収納について解説します。
ぜひ、内装の収納計画に役立ててください。
考えておきたいリビング収納のこと

子供が生まれて、家族が増えてくると狭い、収納がない、みんなが片付けをしないなどの理由で散らかりやすいのがリビングです。
山口で新築住宅を建てるなら、ぜひリビング収納のことを注力においてほしいです。
リビングはなぜ散らかりやすいのか、どうすれば物が溢れないキレイが続くリビングになるかを考えると、リビング収納のコツが見えてきます。
これからそのコツを探していきましょう。
リビングが散らかる!収納がなくて困ったこと

家族みんなが集まるリビングは何かと散らかりがちですよね・・・
山口で新築住宅を建てられた方に収納がなくて困ったことがないかヒアリングしてみたところ、どの家庭も散らかりやすくて困っている・・・という意見が多いです。
その中でもこんな意見が・・・
・郵便物や新聞、雑誌など様々な書類があふれてきて、服も増えたので収納スペースが足りない
・夏や冬の季節ごとに変えるカーペットや家具をしまうときに、別の部屋の収納スペースに移動しなければならないとこるが面倒
・友人や知人が急に訪問ときに、すぐに散らかっているものを入れる収納スペースがないから大変
・なるべくリビングに物を置かないように心がけていても、仕事柄で忙しく書斎がないので、夫がリビングで仕事をすることがあり、PCなどの仕事道具や書類が散らかるので、それをきれいにまとめて片付ける場所がない
・小学生の子どもがいると、子供部屋を設けているのに学校の勉強道具やゲームや漫画などがリビングに散らばってしまい、1日だけキレイにしていても数日経てばまた散らかってしまう
やはりどの家庭でも問題を抱えていることが分かりますね。
散らかりやすいのに収納が少ないリビング
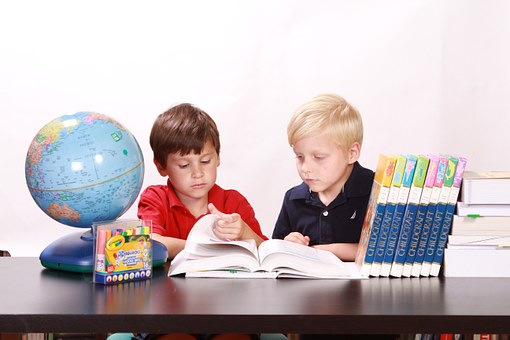
山口で新築住宅を建てる際にもリビングは家族全員が集まる大切な場所なので部屋面積は1番広くなりますが、そのわりには収納が少ないケースが多く見られます。
そのため、いろいろな荷物や雑貨、書類などが散乱しやすいのが多いです。
散らかる物は家族の年代によっても違います。
特に幼い子供ならおもちゃ、小学生なら宿題や文房具、中学生になると雑誌やテストなどの書類がリビングに置きっぱなしになりやすいアイテムです。
学校行事や山口の町内会の集まりなどの大事プリントをしまう場所に困るケースもあります。
書類とリビングの組み合わせは一見かけ離れていて家を建てるときに忘れがちですが、光熱費などの領収書やスーパーの広告など、意外と紙類は溜まってしまうものです。
また、外出先から帰ってきたときに子供のランドセルやカバン、上着やコートをリビングに置きっぱなしにするケースもよく見られます。
疲れているときは自分の部屋へ行く前にひと息つきたいものですが、やはり1番最初にたどり着くのはリビングですよね。
休憩が長くなってしまうと片付けるのが面倒になってしまう経験がある方も多いはずです。
山口で新築住宅を建てたあとのキレイなリビングをキレイに保ち続けるのにも、何らかの対策が必要です。
生活感を出さない理想のリビング収納とは

山口の新築住宅のリビングは家族が集うだけではなく、客間がなければ友人や知人を招く場所でもあります。
そのため、生活感を出さないようにリビング収納を作ることがおススメです
。
備え付け収納棚は扉をつけることで、中身を見られることなく収納できます。もし扉をつけられなかったら、インテリ雑貨店でカーテンなどを購入して隠すように設置してみてください。
既製品の家具を買う場合は、リビングと統一感のある収納デザインを選ぶことがポイントです。
リビングの雰囲気と収納デザインの統一感を持たせることで、オシャレな空間を演出できます。
リビングの片づけ上手であるなら、見せるための収納に挑戦してみるのも良いかもしれません。
物が見えていても雑貨屋のようにキレイに整理整頓されていれば、生活感を感じさせません。
むしろ、オシャレでこだわりのある理想なリビングになり、友人や知人が訪問しても好印象を与えます。
いつも清潔感がありオシャレに整理整頓されていれば、それを保ち続けるために物を置きたくないと感じますので、ぜひ習慣にしてみましょう。
いつもすっきりとしたリビングにするコツ

出したものはあった元のあった場所に片付けるのが当たり前です。
当たり前のことですが、なぜ簡単なことができないのか、理由を考えてみましょう。
まず、物を片付けにくい場所に収納スペースがあると、こまめに片付けなくなってしまいます。
リビング収納は、生活動線と紐付けして考えるのがコツです。
例えば、新聞や雑誌をしまうラックをリビングに置くのはいかがでしょうか?
大体は新聞をリビングに持ってきて読みます。
郵便物なども真っ先にリビングにもっていき、リビングに置きっぱなしにしてしまうケースが多いはずです。
新聞はいつもどこで読むのか、どこにラックがあればしまいやすいのかを考えることが大切です。
片付ける場所の定位置を設けることが部屋をキレイに保つコツです。
例えば、テレビのリモコン・領収書などの書類関係、おもちゃ道具・・・
これらについても、出したら必ずそこに片付けるようにします。
「出す・使う・片付ける」までをルーティン動線を定着されることで、片付ける習慣を身につけることが可能になります。
壁面収納やカウンター収納で片づけできるコツ

山口で新築住宅を建てるなら、ぜひ壁面収納やカウンター収納を検討されてください。
使いやすい壁面収納にするなら、奥行きの狭いパターンがおススメです。
棚の奥行きを作ってしまうと奥のほうまで物をしまい、何をどこに片付けたかわからなくなりがちです。
壁面収納はインテリ雑貨店などのボックスやかごなどを購入して、見てもスッキリとした印象を与えるものを購入して上手に収納しましょう。
ボックスやかごに入れる物はジャンルごとにわけて、何がしまってあるかを書いたシールを貼ることをおススメします。
カウンターを設置する場合は書類を片付けるスペースを作り、ちょっとした仕事などの作業スペースとして活用できるのでおススメです。
家計簿をつけたり子供の学校行事のプリントに目を通したりなどにカウンター収納があれば便利です。
外から帰ってきたときは、とりあえずコートや上着をかけられるようにハンガーラックを設置するのもひとつの方法です。
リビングにハンガーラックがあれば来客用としても利用できるので、ちょっとしたおもてなしにもなりますので、どうしたら有効活用できるのか工夫を考えてみましょう。
まとめ

せっかくの山口で建てた新築住宅も、物が散らかっているリビングでは台無しです。
美しいリビングにするなら、リビングでも効率よく収納できる設計について考えましょう。
新築住宅を建てたあとに造成するより、最初から使いやすいように設計するほうが格段に楽なはずです!
まずはリビングが散らかる理由を考えてから、ライフスタイルに合わせた収納を作るのが重要です。
ぜひキレイなリビングで快適な生活を送れるように、忘れがちなリビング収納について考えて見てくださいね♪
11月2日(土)~3日(日) 開催イベント↓
今だけ50万円相当プレゼントキャンペーン!
関連記事
-

住宅展示場に行く前に必見!展示場見学のチェックポイント
家を購入しようと思い立ったら、まず住宅展示場に行こうと考える方も多いのではないでしょうか。住宅展示場はいろいろなメーカーのモデルハウスをたくさん見学することができますので、家のことを知りたい時はとても便利な場所です。しかし、やみくもに住宅展示場に行ってしまっては時間を無駄にしてしまうことも。この記事は住宅展示場に見学する際にチェックしておきたいポイントについてお伝えします。 住宅展示場のチェックポイント住宅展示場の良いところは実際に生活しているような体験ができることです。ここでは住宅展示場を見学する際にチェックしておきたいポイントをお伝えします。 展示場は家のいろいろな悩みについて相談できる場所 住宅展示場に来る人は家の購入を検討している人がほとんどですが、みんなそれぞれ事情は異なるもの。中古物件を購入してリフォームにするか、そのまま今の家をリフォームするか、いますぐ家を建てたい、いずれ家を建てたい、など家に対する思いも違います。住宅展示場はこういった悩みを相談するのにうってつけの場所です。住宅展示場に行く理由は情報収集ですので、自分が抱えている悩みを住宅展示場のスタッフの方に相談しましょう。また、住宅展示場の見学の際は営業マンとの相性もチェックしておくといいです。家を建てるには担当者とのコミュニケーションが大切になります。できるだけ好感のもてるメーカーを見極めておきましょう。 展示場に行く前に目的を決めて事前準備する 展示場に行くのなら目的を決めて事前準備をしておきましょう。散歩中や突然思い立ってふらりと立ち寄るのもいいですが、時間帯や目的を決めて行った方が効果は高いです。目当てのメーカーがある場合は事前に資料請求をして知識を深めておくことも大切です。見学前に情報収集をしているとモデルハウスの見るポイントや質問したいことなどを絞ることができます。ある程度目的が決まっている場合は予約して住宅展示場に行くことをおすすめします。予約しておけばスタッフからの説明をもらうことができ、ただ見るよりもずっと得られるものがあるでしょう。 住宅展示場の見学の際に持っていくもの 住宅展示場を見学する際はメジャーやペン、メモ帳などを持参しましょう。また、カタログなど持ち帰るためのエコバッグがあると便利です。モデルハウスのメリットは実寸を体験できることなので、廊下の幅、窓のサイズや高さ、キッチンカウンターの高さや間口など、どれくらいの寸法なのか数値で把握しておきましょう。住宅展示場を見学する時は薄手の靴下を履いておくのもおすすめです。足元の感覚はスリッパ越しではわかりづらいですが、薄手の靴下を履いておくことでフローリングの触覚や無垢材と合板の違い、タイルの硬さなども確かめることができます。 1日にモデルハウスを多く見すぎない 住宅展示場はたくさんのメーカーのモデルハウスが建っています。たくさんのモデルハウスを見てまわりたいと思うかもしれませんが、そこはグッと抑えて、見学するのは1日に3棟ほどにしておきましょう。なぜ3棟で抑えるのかというと、それ以上見てしまうと最初に見たものがどんなだったか忘れてしまうからです。どんな印象を受けたか記憶に留めておくためにも1日に多くのモデルハウスを見すぎないことがポイントです。 住宅性能やオリジナル製品をチェック 住宅展示場のモデルハウスを見る際は性能やメーカーのオリジナル製品をチェックしておきましょう。モデルハウスは見栄え良くできていますので、インテリアや内装などに意識が向いてしまうかもしれません。しかし、内装やインテリア、間取りに関しては後からどうとでもなるのが実情です。そしてモデルハウスでしか確認できないのが住宅性能とメーカーのオリジナル製品です。住宅性能は省エネ性や耐震性などあり、ある程度のところは数値で判断することになりますが、断熱性など空間の快適性はモデルハウスで体感することができます。また、透明の壁にして耐震構造を見えるようにしているモデルルームもあります。オリジナル製品についてはメーカー独自のものになるため、モデルルームでしか見られません。住宅展示場を見学する際は、モデルハウスでしか得られない情報を優先してチェックしましょう。 実際に住んだ時のことをイメージして見学する モデルハウスを見学する時は流し見は厳禁です。実際に生活しているイメージを持って見学すると間取り計画の時もその体験が活かせます。特に家事動線は間取り図だけでは実感できないところ。家事動線については間取りの失敗でよく聞くことです。自分が家事した時のことをイメージして見ればどうすれば効率的か実感することができますので、モデルハウスを見る時は実際に生活しているように見学しましょう。メーカーによってはモデルハウスに一泊できる宿泊イベントを催しているところがあります。 より情報を得たい時はしっかりアンケートに答えよう 住宅展示場に行くとアンケートを求められることがあります。アンケートに答えてしまうと営業の人にしつこく訪問されると思って敬遠する人も少なくないですが、より情報を得たいのならアンケートを答えておくことをおすすめします。アンケートは家を購入する本気度を判断する意味合いも持っています。当然のことですが、本気で家を購入しようとしている人にはメーカーも必死に応えてくれます。もし、電話や訪問が嫌なら事前にその旨をお断りしておけば大丈夫です。カタログなどの資料は郵送してもらえばいいことですので、家の情報を深めたい方はアンケートに答えておきましょう。 住宅展示場がすべてではない!他にもチェックしておくこと家の情報収集はなにも住宅展示場の見学だけではありません。モデルハウスは規模が大きく豪華に建てていることが多いので、間取りやインテリアについては実際に建てることを考えるとあまり参考にはなりません。見学会は他にもあり、家の構造を見ることができる現場見学会や、実際に購入した人の家を見ることができる完成見学会などもあります。住宅展示場のモデルハウスを見学する以外にも事前に知識を深めておくことも大切ですので、情報収集はしっかりしておきましょう。 まとめ 家は一生に一度のお買い物です。後悔のないマイホームを手に入れるために、焦らずにじっくりと時間をかけて計画を進めていきましょう。住宅展示場はカタログや図面では得られない体験をすることができます。実物に触れられるのはモデルハウスでしかできないので、住宅展示場に行った際は、今回ご紹介したことを押さえて見学しましょう。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらから さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-

マイホーム購入で失敗&後悔したことベスト10
ずっと夢だったマイホームを購入するとこれから始まる新しい生活にワクワクしますよね。でも、住んでみたらいろいろなことで後悔した、ここが失敗した、という声を多く聞きます。これではせっかくのマイホーム生活もつまらなくさせてしまうでしょう。この記事ではマイホーム購入で失敗&後悔したことベスト10をご紹介します。 マイホーム購入で失敗・後悔したベスト10マイホーム購入の際はどんなことで後悔してしまっているかを知ることが大切です。ここではマイホーム購入で失敗&後悔したことベスト10をお伝えします。 1位:住宅ローンの返済が大変 住宅ローンは返済期間を最長35年間にすることができますが、この長期の間に生活が何も変わらずに進んでいくというのは中々ありません。本来なら年毎に収入が上がっていくはずが会社の業績が悪くなってしまい収入が上がらなくなってしまうことだって考えられます。その他にも「夫婦共働きでお互いの収入で返済計画を立てていたが、妻が退職をしてしまい夫だけの収入で返済することになった。とてもじゃないが返済が大変で生活に困る」という声もあります。 2位:住んでみてわかった間取り・広さに後悔 間取りの失敗は生活にとても影響しますので、できることなら回避したいもの。それでも間取りの失敗・後悔したという声はたくさんあります。多く聞くのが、収納が少ない、コンセントの数や位置、家事動線が悪いなどです。その他には庭を設けたものの雑草が生えてお手入れが大変、吹き抜けにしたけれど断熱性や暖房設備がいまいちで冬は寒い、子供部屋の壁紙を汚れにくいものにしたけどもっと子供部屋らしく可愛いのにすればよかった、など家を建てる人によって間取りの後悔はさまざまあります。 3位:間取りと同じくらい多い!設備に後悔 設備の後悔も間取りと同じくらい多いです。なぜ間取りと同じくらい設備の後悔が多いのかというと、設備は間取りと密接に関わっているからです。設備の後悔で多いのは、コンセントの数や位置、キッチンなどの住宅設備のオプション、棚やカウンターなどの高さなどがあります。現在は電化製品が生活に欠かせないものになっており、家事で使用する際にコンセントがなかったり、数が少なかったりすると日頃行う家事に不満を感じてしまいます。また、キッチンやバスルームなどの住宅設備についても、必要のないオプションをつけてしまった、予算を気にしすぎて妥協してしまった、という声があります。 4位:周辺環境や立地が悪くて住みづらい 周辺環境や立地はマイホームでの新しい生活に大きく関わり、家を建てている間では中々気が付きにくいものです。住んでみると環境が悪いなと感じるところが日常的に見えてくるため、この時に初めて家を建てた土地に失敗したと感じることになります。川が近くにあり虫が大量発生する、川付近だと氾濫が心配、土地の水捌けが悪い、日当たりが良いが砂埃が舞ってくる、子供を抱えるご家庭では家を出ると大きい道路があり交通量があるので心配、という声があります。 5位:家を建ててもらった会社に後悔 家を建てる時は住宅会社選びがとても大事です。ですが、家を建ててもらった会社に後悔してしまっている人もたくさんいるのが実情。会社に任せっきりにしてしまい不満がいっぱいの家になってしまった、施工不良多数、コミュニケーション不足のまま進んでしまい納得できないまま完成してしまった、など家を建ててもらった会社に不満を抱いている方も多いようです。また、家の引き渡し後、担当者の対応が悪いという声もありますので、アフタフォローに後悔している方もいます。 6位:突然の転勤で引っ越しすることに 家を購入したら簡単に引っ越すことはできませんが、マイホームのこういったことが裏目に出て、勤め先から急な転勤を言い渡され引っ越さなければいけなくなることもあります。家族との生活を大切したいがために泣く泣く家を手放してしまう方もいますので、会社に相談もせず購入するのは注意が必要です。独断で家を購入すると転勤を言い渡された時に困ってしまうことになります。 7位:ご近所さんとトラブル マイホーム購入後の新しい生活では近所関係も大切なところ。しかし、ご近所さんとのトラブルで家の購入を後悔してしまっている方もいます。家を建てた場所の雰囲気や住んでいる人の素性を知らないままだと、隣人がクレーマーだったり、お隣の家から毎日喧嘩する声が聞こえてきたりなど、近所関係でマイホームを購入したことを後悔するかもしれません。 8位:出産や同居で家族構成が変化 家族構成の変化で家が住みづらくなってしまうケースもあります。最初は問題なくても出産や両親の介護で同居することになり家族人数が増えることもあるかもしれません。家族が増えるかもしれないなど、今後家に住む人の人数を予想せずマイホームを購入してしまうと、住んでいる家が手狭に感じてしまい購入を後悔する可能性があります。 9位:通勤時間が長くなってしまった 地域の雰囲気や周りの施設などを重視して購入したはずが、住んでみると通気時間が増えていて困ったという声があります。せっかく閑静な住宅で公園や学校なども充実しているのに、通勤時間が長くなってしまっては毎日の生活への負担が大きいです。通勤時間が長ければ長いほど疲れが溜まり体調不良を起こしてしまうこともあります。また、車通勤の場合でも会社までの距離は遠くないのに通勤する時間帯は道路が混んでいて通常よりも2倍の時間がかかったということもあります。 10位:家の予算に修繕費用のことを考えていなかった マイホームは購入して終わりではありません。家を維持していくためには定期的なメンテナンスが必要であり、修繕費用がかかります。ローン返済や固定資産税など毎月の固定費は考えていても、家を維持していく費用のことを考えていないと後々困ってしまうことになります。想定していなかった費用の発生は、さらに生活費を節約しなければいけなくなるため、維持費の問題でマイホーム購入を後悔してしまう方もいます。 マイホームの購入に失敗・後悔しないためのポイントマイホームの購入に失敗しないためのポイントは購入に焦らないことです。マイホームは一生に一度の買い物ですから時間をかけることも大事。焦って購入してしまえば予想もしていなかったことに後悔してしまう可能性が高くなります。購入する費用や購入した後の生活のことをじっくり時間をかけて情報収集し、イメージを膨らませておけば意外と失敗や後悔は回避できるものです。 まとめ マイホームの購入に後悔しないためにはじっくり時間をかけて計画を立てることが大切です。今回ご紹介した失敗・後悔したことについても自分のことのように考えてみることが大切ですので、ぜひ参考にしてください。マイホーム購入のはじめのステップは情報収集です。いえとち本舗は無料で資料を提供していますので、ぜひご利用ください。資料請求はこちらからプレミアムVIP会員になれば間取りや施工事例も見放題。さらに土地情報もご提供していますので、ぜひご興味ある方は会員登録をどうぞ。会員登録はこちらから
-

ビルトインガレージのメリット・デメリットは?後悔しないためのコツ
愛車をいつでも楽しむことができる夢のある住宅。趣味空間として充実しているだけでなく、土地の有効活用ができるということもビルトインガレージの魅力です。人生に楽しみを与え、高い実用性も兼ねているビルトインガレージは、憧れている人も多く人気があります。この記事ではビルトインガレージのメリットやデメリット、後悔しないためのコツなどをお伝えしていきます。1 ビルトインガレージとは2 ビルトインガレージのメリット3 ビルトインガレージのデメリット4 ビルトインガレージに必要なもの5 ビルトインガレージで後悔しないための注意点6 まとめビルトインガレージとは一般的な住宅は建物と駐車スペースを別々に設けますが、狭い土地だと駐車スペースを設けることができなかったり、駐車スペースを設けるために居住する建物部分を削らなければいけなかったりします。こういった事情を解決し、土地を有効活用できる建物がビルトインガレージです。ビルトインガレージは建物の1階部分が駐車スペースとなり、居住スペースと駐車スペースが一体になる構造になっています。ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを設けることができるということだけでなく、車が好きな方やDIY好きな方にも人気が高く暮らしをさらに楽しませてくれる住宅です。 ビルトインガレージのメリット土地が狭くても駐車スペースを設けられる ビルトインガレージは駐車スペースを確保することができない狭い土地にはうってつけといえます。ガレージのように駐車目的のスペースなら容積率の緩和精度があり、建築物の床面積の1/5までなら床面積に算入されません。これなら都心部のような容積率の厳しい土地でも効率よくスペースを活用することができます。 居住空間の良好な環境を取り入れられる 居住スペースは必然的に2階以上に設けることになりますが、上の階に居住スペースがくることで、採光や通風をとりやすい間取りになります。リビングも高所のところにくるため眺望も良くなり、バルコニーとつながるリビングなら空間に奥行きが生まれて開放感を得ることができます。 充実した趣味空間が実現 ガレージと居住空間の仕切りをガラスにすれば、いつでも室内から愛車を眺めることができます。ビルトインガレージはティーラーのショールームのように見せることができるためインテリア性も上がり、趣味空間として充実します。また、屋外のように扱えるため車の整備やDIYも室内で行うことができます。 駐車から居住空間までアクセスが容易 駐車スペースから居住スペースにアクセスできる玄関を設ければ外に出ることなく室内に入ることができます。雨が降っている時や買い物から帰ってきた時は、移動の負担が少なく非常に効率の良い動線になります。 車を室内環境で保管できる 一般的な駐車スペースは屋外にあるため、車は外部の影響を受けやすいことが懸念されます。歩行者のいたずらや風雨にさらされることで、車を痛めてしまう可能性もないとは限りません。その点、ビルトインガレージは室内に車が駐車されるため、外部からの影響を受けず安心して保管することができます。 ビルトインガレージのデメリット 居住空間が2階以上になる 1階に駐車スペースきて居住空間が2階以上になるため、アクセスするには階段の登り下りが必ず必要になります。身体の負担を感じやすい高齢者や障害を抱える方には、この構造はデメリットとなってしまいます。ホームエレベーターを設置する案もありますが、その分エレベーター設置のスペースを確保する必要があるのと、導入コストが高くなります。 建物構造の制約を受けてしまうことも ガレージは車の駐車スペースを確保する必要があるため、居住空間と比べて壁や柱が少なくなり、階数も2階以上ということもあって建物の荷重に耐える構造を有していることが求められます。建物構造には木造や鉄骨造、RC造などがありますが、設計によっては選べる構造が制限されてしまうでしょう。 音や排気の臭いの対策が必要 車のエンジン音や排気の臭いが居住空間にまで届いてきてしまう可能性があるため対策が必要です。遮蔽するシャッターも思っているよりも大きい音が鳴りますので、音の出にくいものを取り付けることが望ましいです。 ビルトインガレージに必要なものガレージの床は水に強く油などで汚れても大丈夫な素材を使うことが望ましいです。一般的にはコンクリートが採用されていて、車のような重量のあるものがのっても割れない強度を有していることが必要です。床材は複合的に使うケースもあり、駐車スペースはコンクリート、車を駐車しない場所は無垢材やタイルで仕上げることもできます。床は水が流れていくように歩行が困難にならないくらいの緩い勾配(傾斜)を設け、洗車などを行う場合は排水口を設けるといいでしょう。コンクリートは水を吸う性質があるため状態を維持していくために撥水性のある塗料や樹脂製塗料を塗ることもおすすめです。駐車スペースとして広さは余裕を持って確保することが大切です。現在所有する車に合わせて設計してしまうと、車の買い替えの時に選べるものが制限されてしまいます。また、介護者の車の乗り降りや車椅子の移動なども1.4m以上の通路幅を確保する必要があります。車の排気ガスの臭いは換気扇を設けて空気の入れ替えができるようにしましょう。シャッターは開閉時に音が響くためできるだけ音の出にくいものを選ぶこと。スライダー式は巻き上げ式のシャッターよりも音が静かです。また、シャッターは間口が長く重量があります。手動だと開く時の負担が大きいため自動開閉型のものがおすすめです。リモコン操作で開閉ができますので、車に乗りながら操作が可能です。 ガレージ内は暗くなりますので照明を設置しておきましょう。ガレージ内で使う道具類や車関係の備品は収納するスペースがあると便利です。また、電気工具が使えるコンセント、湿気や室温対策のためのエアコンもあるといいでしょう。 ビルトインガレージで後悔しないための注意点ビルトインガレージは一般的な住宅と違って求められる構造や条件が異なりますので、ビルトインガレージをご検討されている方は、実績のある会社に依頼することをおすすめします。家づくりは土地を探すところから始まりますが、素人の方がビルトインガレージに適する土地かどうか判断するのは難しいです。傾斜地や高低差のある土地だと、車を駐車することが困難になり実用性が欠けてしまいます。もし、ビルトインガレージを建てたいと思っている方は、土地探しの時に建築士や設計士の方に立ち会ってもらい、その土地が適しているか判断してもらってから購入をしましょう。ビルトインガレージの居住空間はいろいろな工夫を盛り込めることができます。工夫を凝らした間取りにするには、住宅会社の設計力が試され、スキップフロアなど特殊な間取りも設計できる会社を選ぶことが望ましいです。設計力のある会社に依頼することでビルトインガレージのデメリット部分も解消することが可能ですので、希望を叶えてくれる住宅会社を選びましょう。 まとめ ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを確保できる建物です。土地を有効活用することができますので、都心部のような狭小地の多いところに有効です。趣味空間としても楽しませてくれる建物ですので、これから新築を購入しようと考えている方は、ぜひビルトインガレージもご検討してみてはいかがでしょうか。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから









