ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
新築住宅の防犯対策【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
今回は、新築住宅の防犯対策についてお話をします。
山口の空き巣の被害は他県と比較しても被害は少なく、治安は良いですが、日本全体では4日に1件ペースで被害にあっています・・・。
山口で新築住宅を計画する段階でも防犯対策を行っておきたいものです。
警察庁の調査によると、空き巣や泥棒の侵入方法で、最も多いのは「鍵の施錠忘れによる被害」だそうです。
外出の際の締め忘れはもちろん、「少しの間外に出るとき」、「2階に居て1階が施錠されていないとき」などにも狙われています。
まずは、防犯対策の基本中の基本、「施錠」について、常日頃から意識を持つようにしましょう。
窓ガラスの被害対策

次いで多い侵入方法は「ガラス破り」です。
どこも鍵がかかっていた場合の侵入方法で1番でした。
対策として、掃き出しや人が通れるサイズの窓は防犯ガラスにするのが良いでしょう。
イエテラスの窓は全て『複層ガラス』のため、割られにくい窓ガラスです。
侵入を防ぐために

2番目に多いのは、ピッキングなどの「施錠開け」。
ただし、近年はピッキング対策されたドアや錠の製品が増えたこともあり、年々減少しているそうです。
新築時はもちろん、玄関リフォームのときにぜひ検討しましょう。
泥棒が狙いづらい新築住宅は、「見つかりやすい」・「侵入に時間がかかる」といった建物です。
工夫として、
・新築住宅の窓は、大きな窓を一つより、小さな窓を二つにしてみる。
・格子やシャッターを取り付ける。
・補助錠を取り付け、本錠とのツーロックにする。
・人感センサーライトを取り付ける。
などの対策も効果的です。
イエテラスでは玄関ドアの鍵は全て『ダブルロック』でより安全対策をほどこしていますが、このような追加オプションとしてつけることもできますので、お気軽にご相談下さい。
新築住宅の防犯対策

警察庁の調査によると、泥棒の犯行場所の選定理由は、「富豪の家かどうか」より、「犯行がばれるリスクが少ないか」で選ぶことの方が多いようです。
最近では、インターネットの写真付き地図で都合の好さそうな場所を探したり、インスタやツイッターなどのSNSから情報収集を行う泥棒もいるそうです。
また、泥棒というと、「誰も居ない家を狙って侵入する」、いわゆる「空き巣」をイメージする方が多いと思います。
実際、侵入窃盗ではこの空き巣が最も多く、全体の約6割を占めているようですが、
一方、家に人が居る間に侵入する「忍込み」「居あき」のケースも、約3割ほどあるようです。
万が一、家の中で犯人と出くわしてしまった場合、身体的危害を加えられることにもなりかねません。
「忍込み」「居あき」は、食事中や団らんなどで家族が一つの部屋に集まっているとき、
また、主婦が洗濯物を干しているときなどに狙われやすいようです。
在宅中であっても、家人のいない場所は必ず施錠をするようにしましょう。
「留守にしている」と確信を持たれてしまうと、空き巣の標的とされやすくなります。
以下に、「留守にしている」と判断される要因と、その対策を紹介します。
留守を見抜かれるポイント

①インターホンを押しても誰も出てこない
空き巣が留守を確認する方法として多いのが、オーソドックスにインターホンを押してみるという方法。
インターホンを押させない対策として、録画機能付きのインターホンの設置がおススメです。
イエテラスのインターホンは全て、『TVインターホン』で録画機能もついていますので、ご安心下さい。
ボタン付近に「録画中」と書いておけば、空き巣もインターホンを押すのをためらうでしょう。
②大きな荷物をもって出かけた
キャリーバッグをもって出かけた場合、長時間、あるいは長期間留守になる可能性が高いと思われます。
家を出るとき、家にだれもいなくても「いってきます」と声をかけるようにすると、
他に誰かが要るものだと思わせることができます。
可能であれば大きな荷物は事前に目的地に送ってしまうのも良いでしょう。
また、車の有無でも留守を判断されるので、シャッター付きのガレージであれば、
普段から閉めておくようにしましょう。
③電話に誰も出ない
電話番号を事前に入手し、電話をかけることで留守かどうかを判断されることがあります。
携帯電話への自動転送などを活用しましょう。
また、留守番電話機能を活用し、「迷惑電話対策のため、最初にお名前とご用件を伺っています」
というアナウンスにし、誰からかかってきた電話か確認してからとるようにしておけば、
空き巣からの着信だった場合に留守の確信を持たれないうえ、
「声」の証拠を残したくない詐欺電話などの撃退にもつながります。
④郵便受けに配達物が溜まっている
新聞や郵便物が溜まっていると、しばらく留守にしていると思われます。
特にお盆や正月など留守の可能性が高い時期に新聞が溜まっていると非常に危険です。
常日頃郵便受けに郵便物を貯めないようにし、
長期間不在になるときは、配達を止める手続きをしておきましょう。
⑤自宅に不在だということがわかるSNS投稿がある
今現在外出しているという投稿を見て、過去の投稿から住所を特定し空き巣の標的とすることがあるようです。
写真をアップした際に位置情報が表示されてしまうこともあるので、
旅行や山口からお出かけの報告は、帰宅後に行うのが安全です。
普段意識せず行っている行動が、空き巣にとっては良い情報源となってしまっていることがあります。
留守と思わせない行動を実行してみましょう。
空き巣が狙う家の条件

「5分以内に侵入できるかどうか」が判断となっていることが多いそうです。
防犯対策として、侵入に手間がかかりそうだと思わせることがポイントです。
侵入が容易だと思われる特徴
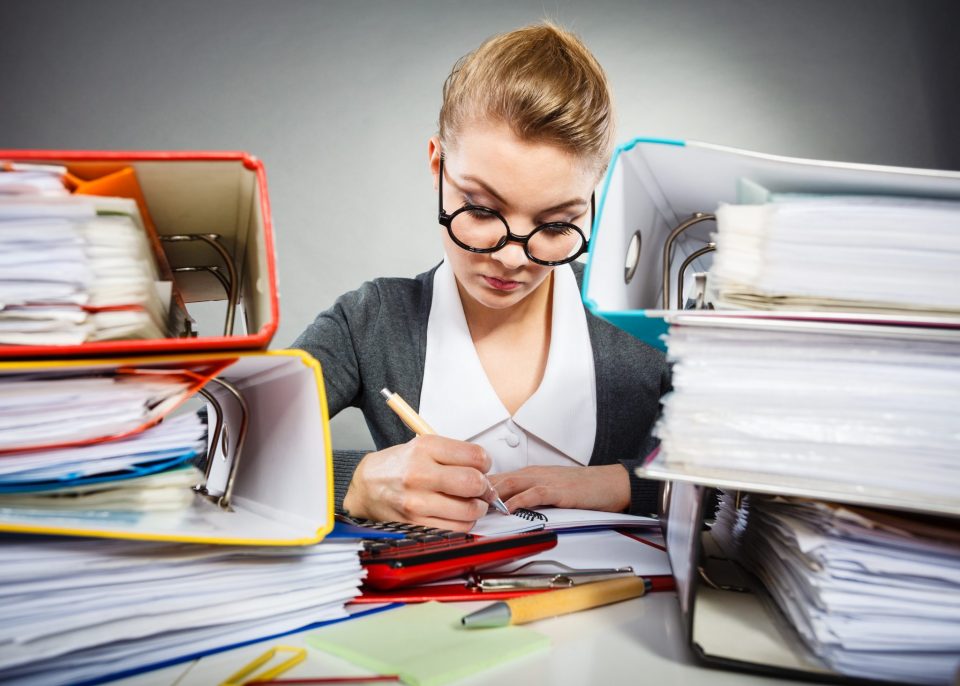
①窓の防犯対策がとられていない
新築住宅を建てた後でも侵入経路となりそうな窓には防犯フィルムを貼ったり、補助錠を取り付けるようにしましょう。
このとき、外から見て一目で「防犯対策が取られている」とわかるようにすると、抑止力につながり防犯により効果的です。
②侵入できそうな場所に足場となる物が放置されている
戸建ての場合、上階の防犯対策が手薄となっている傾向があり、
またベランダに侵入できれば外部からの死角が確保されるため、周囲に気づかれずガラスやぶりを行うことができます。
上階に登れてしまえば侵入が容易とされるため、
新築住宅を計画する段階で2階のベランダと、物置や室外機、電柱などの位置関係を気にするようにしましょう。
また、どうしても移動できない場合は忍び返しを設置するなどの対策をしましょう。
犯行に気づかれにくそうな特徴
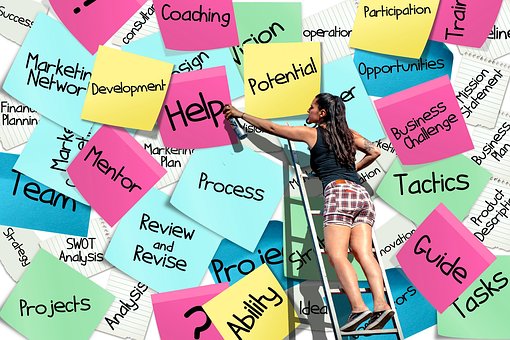
周囲に気づかれそうだと思わせる対策をしましょう。
①侵入箇所が死角になっている
「5分以内に侵入できなければ諦める」と言われていますが、死角であれば周囲の目を気にせずに犯行が行えます。
侵入されそうな場所は、フェンスや植栽で死角とならないよう、できるだけ見通し良くしておきましょう。
②犯行時の音が周囲に聞こえづらい
ガラスを割るなどするときの音で犯行が気づかれるのを恐れるので、
その音をかき消してくれるような場所は狙われやすくなります。
例えば線路や幹線道路の近くなどで新築を計画する場合は、
庭に防犯砂利(踏むと通常の砂利より大きな音が出ます)敷いたり、
窓ガラスに衝撃が加わるとブザーが鳴る装置の取り付けなどが効果的です。
「音が出る」「明かりがつく」装置は、単純でありながら、
目立ちたくない犯人からするとやはり避けたいものです。
見えるところに取り付けてあるだけで犯罪の抑止力となりますので、ぜひ検討してみてください。
山口で新築住宅をご検討する際に、防犯上のお話も新味になってお答えいたします。
ご心配事がございましたら、いえとち本舗までお気軽にご相談下さいませ。
8月24日(土)~8月25日(日)の最新イベント情報↓
関連記事
-

新築住宅はいつからメンテナンスをする?時期と点検・補修ポイント
住宅は年数が経つにつれて劣化していくものです。ここで適切なメンテナンスを怠ると、家の寿命はどんどんと短くなってしまう恐れがあります。では、住宅の適切なメンテナンスや時期とはなにか、疑問に思われるかもしれません。今回は大切なマイホームに長く住んでいけるように、住宅のメンテナンスと時期についてお伝えしていきます。 住宅のメンテナンスは建物と住宅設備に分けられる 住宅は経年劣化するものですから、時期に合わせて適切なメンテナンスを行う必要があります。住宅に必要なメンテナンスの箇所は大きく分けると「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の二つです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために行い、住宅設備のメンテナンスは料理をする、入浴するなど生活に関わることを快適に過ごしていけるために行っていきます。では、「建物のメンテナンス」と「住宅設備のメンテナンス」の項目を具体的にご紹介していきます。 建物のメンテナンス 「メンテナンスはまだ大丈夫だろう」と手入れを放置してしまうと、家の劣化は進み元の状態に戻らない可能性もあります。構造体の腐食や屋根からの雨漏りなどが起きてしまうと、生活に支障をきたし、修復する工事も大規模になりやすいです。建物のメンテナンスは家そのものを保つために重要な要素ですので、必ず適切な時期に行なっておきましょう。 構造体 家の構造体である土台や柱、梁などは壁の中に隠れてしまっているので、建築の専門家でなければ普段見ることはないかもしれません。構造体の補修は必要に応じて補修を行なっていくとしか言えないのですが、地震や台風の直後には異常がないかチェックしておくといいでしょう。防蟻処理は新築を建ててから5年〜10年ごとに行なってください。シロアリは湿気を好み餌に木を食べるため木造住宅にとっては天敵です。シロアリ被害に遭うと修復する規模も大きくメンテナンス費用もかかりますので注意しましょう。また、築20年を超えてくると床がへこんだり、床鳴りを引き起こしたりする症状がでてきます。この時期になりましたら、家の全面的なメンテナンスを検討した方がいいでしょう。 屋根 屋根は太陽の直射日光や風雨に晒されていますので、かなりのダメージを受けています。屋根を良好な状態に保たなければいけない理由は雨漏りです。雨漏りを引き起こしてしまうと、生活に支障をきたすどころか、建物の柱や梁などの木部が雨に濡れて腐食し、さらにシロアリが寄ってきて被害を及ぼす危険性があります。屋根のメンテナンスは、新築を建ててから10年目に一度専門業者に点検してもらいましょう。点検は新築を建ててもらった住宅会社に行ってもらうことをおすすめします。築20年目は、屋根の塗装や葺き替えを検討する時期になります。 外壁 外壁の劣化は外壁のひび割れや防水性の低下が起きます。これらの劣化は、外壁から水が侵入し、柱などを腐食させてしまうリスクがあり、水が侵入した外壁も放置してしまうと劣化が早まってしまいます。建物に水を含んでしまうとシロアリ被害のリスクが高まりますので、しっかりとメンテナンスを行うことが大切です。外壁は新築を建ててから10年目に塗装を行うことをおすすめします。また、外壁が窯業系サイディングの場合は目地シーリングの打ちかえも一緒に行っておきましょう。外壁は10年を目安に定期的にメンテナンスをすることが大切です。 内装 内装のメンテナンスは、壁紙や室内建具、フローリングなどの床材などがあります。壁紙やフローリング、建具などは日常的に使うものですから汚れや傷がつきやすい場所です。内装材の汚れや傷は生活環境によって異なりますので、メンテナンス時期も一概には言えませんが、築5〜10年目あたりから壁紙の汚れやフローリングの傷などが目立ってきます。美観的に気になる場合は、壁紙の貼り替えやフローリング傷のリペアなどを行うといいでしょう。また、内装材の美観を保つには日頃の掃除や手入れが大切です。築20年を超えると家の構造体のメンテナンスも考慮しなければいけない時期ですので、このタイミングに内装を新しくするのもいいかもしれません。 住宅設備のメンテナンス 住宅設備機器は耐用年数というものがあります。耐用年数を超えると住宅設備機器の故障のリスクが高くなります。ベストなタイミングは壊れる前に修理または交換することですので、耐用年数を目安にメンテナンスしましょう。 水回り設備:キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台 【キッチン】キャビネットの蝶番・建て付け調整:約5年目水栓金具の交換:約10年目レンジフードの点検・交換:約10年目コンロの点検・交換:約10年目食洗機の点検・交換:約10年目キッチン全体の取り替え:約20年目【浴室】目地シーリングの打ち替え:約10年目水栓金具の交換:約10年目照明器具・換気乾燥機の点検・交換:約10年目浴室ドアの点検・交換:約10年目浴室全体の交換:約20年目【トイレ】温水洗浄便座の点検・交換:約5〜10年目便器・タンクの点検・交換:約15〜20年目【洗面化粧台】洗面化粧台の点検・交換:約15〜20年目水回り設備の各部材(コンロやレンジフード、換気乾燥機、温水洗浄便座など)を単独で交換することも可能です。メンテナンスの目安は上記の通りですが、水回り設備機器全体(システムキッチンやシステムバス、洗面化粧台、トイレ器具など)の取り替えを行うときは、これまで交換または修理した設備も一緒に交換しなければいけない可能性もありますので注意しましょう。 給湯器 給湯器の交換時期は約10〜15年と言われています。あくまでも目安ですので、普段使っているときに調子がおかしいなと気がついたら、業者を呼んで点検してもらうことをおすすめします。給湯器はメンテナンス時期を間違えてしまうと、修理するまでかなり不便な生活をおくることになる可能性があります。もし、給湯器が壊れて動かなくなってしまうとお湯が出なくなり、お風呂に入るときは水を使うしかなく、冬場では寒くて入浴することが難しくなります。給湯器は壊れてから交換するのではなく、給湯器の耐用年数を目安に壊れる前に交換することをおすすめします。 新築は築10年がメンテナンスのポイント 住宅のメンテナンスは、新築を建ててから10年目を目安に一度点検を行い、必要に応じて補修しましょう。また、新築は瑕疵担保責任保険があり期限が10年までです。10年の期限が過ぎてしまうと保証対象外となるため、10年目に入る前に建物に異常がないか点検することをおすすめします。また、建物を長く保たせるには日頃から建物の状態を点検しておくことが大切です。少しでもおかしいと感じた場所を見つけたら専門業者に相談しましょう。 まとめ 日頃から家の状態を確認して、定期的にメンテンスをすれば家の寿命はさらに伸ばすことができます。住宅のメンテナンスは10年周期で点検し、適切な補修や交換を行うことが大事です。もし、建物に異常を発見したら専門業者に依頼して点検してもらいましょう。家づくりについてもっと知りたいという方は、住宅について情報収集することをおすすめします。いえとち本舗は簡単に家づくりのことがわかる資料を無料で提供しています。もしご興味がありましたら、ぜひご利用ください。資料請求はこちら
-

新築住宅で失敗しない!便利に使えるコンセントの位置や高さの決め方
掃除機や電子レンジ、パソコン、テレビなど、現在の生活に家電は欠かせないものとなっています。これらの家電を使うにはコンセントが必要です。 実は新築住宅のコンセントの数や位置に失敗したという声は多くあります。そこで今回の記事ではコンセントの位置の決め方や配置計画の仕方についてご紹介していきます。 コンセントの位置や数の失敗とは?家を建ててから「コンセントの位置や数に失敗してしまった」とならないように、どんなところに失敗してしまったかを知っておくことが大切です。 コンセントの数が足りない欲しい場所にコンセントがない多めにコンセントを設置したけれど使っていない家具を置く場所にコンセントがあるコンセントの位置が低くて使いづらい 上記の事例は、コンセントを使うことをイメージせずに計画されてしまうことで起きてしまいます。コンセントは、住む人の生活スタイルによって必要な場所が変わります。ですから、計画するときは、ちゃんと自分がどのように生活し、コンセントがどの位置にあれば便利か想像して計画することが大事です。 欲しい場所や位置にコンセントがないのは生活に不便さを感じる コンセントの失敗で多いのが「欲しい場所にコンセントがない」ということです。どんな事例があるかというと下記をご覧ください。 コンセントがなくて掃除機のコードが届かないこの部屋でパソコンを使いたいけれどコンセントがない台所でミキサーを使いたいのに近い場所にコンセントがないエアコンを取り付けたいけれど、その位置にコンセントがないスマートフォンの充電用にコンセントがあると便利なのに…… 使いたい場所にコンセントがないと他の部屋のコンセントを使うしかありませんし、距離が遠ければ遠いほどコードも長くなります。コンセントの位置は、「この部屋でどんなものを使うか」を考えて計画することが大事です。「ここにコンセントがあれば便利だ」ということをポイントにして計画を立てましょう。 火事に注意!コンセントの数が多ければいいというわけではないコンセントを設けたけれど、結局使わずに放置してしまっているということもあります。ここで問題となるのが火災です。放置したコンセントはホコリが溜まりやすくなりますので、ホコリが火種となって火事を起こす可能性があり注意しなければいけません。 また、コンセントが家具に隠れてしまう失敗もあります。家具に隠れてしまっているコンセントは使うことができませんので、結果的に放置してしまうことになります。 コンセントの位置・数の決め方 コンセントの位置や数は、住む人の生活スタイルで変わります。住む人が使いやすい位置にコンセントがあるのがベストですが、そもそもどの位置にコンセントがあれば便利なのか分からない方もいるかと思います。コンセントの位置や数の決め方にも目安というものがありますので、下記でご紹介する目安を参考にしてみましょう。 コンセントの高さは? コンセントの高さは一般的に床から25cm(床からコンセント中心位置までの高さ)の高さです。ただし、エアコンや掃除機など使うものによって高さが異なるので、下記に目安を記します。 一般的なコンセントの高さ:25cm掃除機用の場合:30〜40cm勉強机・書斎机:70〜90cm洗濯機用:105〜110cmエアコン用:180〜200cm ※高さは床からコンセント中心位置までの高さとなります 掃除機用のコンセントが一般的なコンセント高さ25cmよりも高い位置にある理由は、掃除機を使うときにあまり屈まなくてもいいようにするためです。また、トイレの温水便座用のコンセントは、水しぶきが飛ぶことを考慮して、機器から少し離れた位置にコンセントを設けるといいでしょう。このように、コンセントの抜き差しの頻度や使用する機器の特性を考えてコンセントの位置を決めましょう。 コンセントの位置と数は? コンセントの数の目安は下記のようになります。 居室4.5〜6畳:3個居室6〜8畳:4個居室8〜10畳:5個キッチン:6個ダイニング:4個洗面所・廊下・トイレ・玄関:1〜2個 コンセントの位置を決めるときに、掃除機が使えるかどうかを基準にするといいでしょう。掃除機は家の中全体で使うものですから、コンセントがなくて使えない場所があると不便になってしまいます。掃除機のコンセントをどこから取ってどう使うかをイメージすると、必要な位置が見えてきます。 また、部屋のコンセントの数は2畳あたりに一ヶ所が目安です。部屋の対角線上にコンセントを分けて取り付けると、ほとんど延長コードなしで使うことができます。 部屋別にコンセントが必要なものを把握する コンセントを取り付ける位置を計画するときは、どの部屋でどんなものを使うかを把握しておく必要があります。コンセントを使うものを一例ですが下記にまとめましたのでご覧ください。 【リビングで使うもの】 エアコン空気洗浄機テレビDVDレコーダー音響機器スタンドライト電話スマートフォン・タブレット・パソコンインターネット機器・プリンター掃除機アイロンホットカーペット・ストーブ 【キッチンで使うもの】 冷蔵庫電子レンジ電気ポット・電気ケトルオーブントースターミキサー・ハンドミキサーコーヒーメーカー炊飯器 【ダイニングで使うもの】 ホットプレートポット・電気ケトルスタンドライトノートパソコン掃除機 【洗面所で使うもの】 ドライヤー洗濯機電気ヒーターなどの暖房器具掃除機電動歯ブラシの充電 【玄関・廊下で使うもの】 掃除機電話(子機)除湿機・乾燥機 【トイレで使うもの】 温水便座 【外で使うもの】 高圧洗浄機照明器具電動工具 コンセントの計画は取り付ける位置を図面に書くとイメージがしやすい コンセントの配置計画は、図面に書き込むことをおすすめします。頭のだけでイメージしたり、箇所書きのようなメモだけで計画したりすると、どの部屋にコンセントがいくつあるか、どの位置にあるかを把握することが難しくなります。 図面にコンセントの位置を書いておくことで、生活の中でコンセントを使っているイメージもしやすくなります。また、電子レンジやエアコンなど消費電力が多い家電は専用のコンセントが必要になりますので注意しておきましょう。 まとめ コンセントの数が多ければいいというわけではなく、必要な場所に必要な分のコンセントがあるのが理想的な配置となります。そのためには、実際に生活していてコンセントを使っているイメージを持つことが大切です。コンセントの配置計画はテレビのアンテナケーブルやインターネット回線のケーブルなどの配線も一緒に考えなければいけません。自分だけで計画を立てるのは知識や経験も必要になりますので、専門の人に相談して計画を立てるといいでしょう。 いえとち本舗は、簡単に家づくりが分かる資料などを無料で提供しています。その他にも、間取りでお悩みの方は、会員登録をすることで数千種類の中から厳選してまとめた間取りを無料でご覧にいただけます。もし、ご興味がありましたらご利用ください。資料請求はこちら会員登録はこちら
-

これからの住宅取得にコロナウイルスが与える影響とは?
新型コロナという未曾有なことが発生し、働き方などさまざまな場面で社会の変化が起きています。リモートワークやソーシャルディスタンスなど、これまでとは違う生活になりつつある中、住宅も同じように変化し、ハウスメーカーなども安心してお客様が家づくりできるような対策がされています。今回の記事ではこれからの住宅取得にあたり、コロナウイルスが与える影響についてお伝えしていきます。 コロナウイルスで新築住宅事情はどう変わるのかコロナの影響により働き方などさまざまな面で社会が変化しています。住宅会社もコロナの流れが影響して家づくりにも変化があり、今までなかった間取りが採用されています。 コロナウイルスの影響で家の間取りに変化会社勤めの方はコロナウイルスが流行したことにより、リモートワークなど働き方の変化に対応しなければいけなくなりました。コロナの感染を防ぐために通勤を減らし、自宅で仕事ができるリモートワークへと変遷していきましたが、実際のところは問題も多かったようです。リモートワークになることにより通勤する手間は省けますが、現在の住宅では自宅で仕事を行うことが考えられていなく、仕事する環境が整っていませんでした。今回のコロナウイルスの影響により、自宅で仕事をするということに関心が寄せられ、リモートワークに対応できる住宅づくりがでてきています。 コロナウイルスの影響によって関心が寄せられる衛生的な家づくりコロナの流行によって現在はより衛生面に気を配る時代となりました。マスクの着用や手洗い、うがいなど多くの方が心がけています。コロナ感染の心配の一つに家族内感染が囁かれています。現在の家は帰宅後すぐに手洗いやうがいなどをできる間取りにはなっていません。玄関から廊下を通り洗面所へアクセスする動線となっているため、接触感染などのリスクはどうしても拭うことができていません。そこで玄関に手洗器を設けて、帰宅後他の部屋にアクセスすることなく手洗いやうがいができる間取りが注目されています。また、玄関にコートなど外出時に着用した服を収納するスペースを設けることで、さらに衛生面に気を配った間取りづくりが考えられています。 住宅会社はコロナウイルスの感染対策をして安心できる家づくりを実施コロナウイルス感染対策のために、住宅会社はお客様が安心して家づくりができるようにしています。ここでは、住宅会社がとっているサービスや対応についてお伝えします。 オンライン見学会やVR動画内覧会などを実施外出の自粛やソーシャルディスタンスなど人との距離を気にかけなければいけない中で、住宅会社はお客様が不便のない家づくりができるようにいろいろな対策をしています。お客様が自宅にいながらでも物件を内覧できる「オンライン見学会」はスタッフの方が現場に赴き、中継してくれるサービスです。その他にもVR動画によるバーチャル動画をお客様に提供するなど新しい営業活動もされています。 オンラインで打ち合わせや相談に対応家づくりは打ち合わせを積み重ねてようやく完成していきます。大事な家だからこそ手抜きはできません。しかし、コロナウイルスの感染もやはり心配なところ。この時期は家づくりを諦めなければいけないのかと感じるかもしれませんが、住宅会社はこの状況で理想的な家づくりができるようにオンラインで対応するなど対策をしております。対面して行う打ち合わせをオンラインにすることでお客様は自宅にいながらも、これから建てる家の話を進めることができます。また、対面する回数を減らすためオンライン上で契約できるクラウドサインを採用している会社もあります。注文住宅の打ち合わせだけでなく、新規のご相談もオンラインで対応していますので、コロ ナウイルスの感染を心配せずに安心して家づくりの計画を立てることができます。ただし、土地を持っていない方の場合は対面で重要事項説明が必要になりますので、この時は店舗まで来店が必要になります。 三密を避ける・換気・消毒・マスク着用・健康管理の対策住宅展示場はお客様が安心して見学できるようにコロナウイルス感染対策を実施しています。感染予防のために出展メーカー統一のガイドラインを設けていたり、ドアを解放して換気をとったりしています。また、手に触れる場所は随時除菌消毒をし、スタッフの方もマスクを着用して対応するのが基本となっています。ただし、住宅展示場によって対策が異なる場合もありますので、住宅展示場へ見学に行く時はコロナウイルス感染予防対策がちゃんとされているか事前に確認してから行くようにしましょう。 住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置コロナウイルスの感染症およびまん延防止のための特例措置が取られています。コロナウイルスの影響により入居期限(令和2年12月31日)が遅れた場合は要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。【住宅ローン減税の特例措置適用条件】1:一定の期日までに契約が行われていること・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末・分譲住宅・既存住宅を取得する場合:令和2年11月末・増改築等をする場合:令和2年11月末2:新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の影響により入居が遅れたこと住宅ローン減税の特例措置は上記両方の要件満たしていることが必要です。また、契約時期の確認や入居が遅れたことを証明する書類なども必要になりますので、詳しくは国道交通省の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」 住宅ローン減税とは住宅ローン減税とは住宅取得のためのローンの金利負担の軽減を図る制度です。毎年末のローン残高または住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税から控除される仕組みとなっています。(所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除)消費税率10%が適用される住宅を取得した場合は、入居から(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)3年間控除期間が延長されます。 まとめ住宅会社はコロナの影響を考え、家づくりを楽しみにしているお客様が安心して家が建てられるように、いろいろな対策を立てています。本来対面する必要があった打ち合わせや相談もオンラインにすることで改善することができています。また、家の間取りも変化し、 変わっていく生活スタイルに合わせた設計をしています。ステイホームと叫ばれながらも、家づくりでできることはたくさんあります。通常家が建つまで半年から一年はかかります。このタイミングを機に住宅会社の情報を集めたり、資料請求をしてみたりするのはどうでしょうか。いえとち本舗は無料で資料を提供しておりますので、ぜひご利用いただければと思います。資料請求の申し込みはこちらのページになります。









