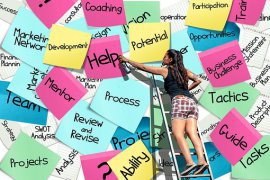ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
和室のある暮らし【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!
現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!
最近では、日本の住宅でも和室のない間取りも増え、新築住宅を建てる上でも「和室は必要?」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。たしかに現代の生活スタイルでは和室がないと困るというような方は少なくなっているのが現状かもしれません。現在では、全室洋室の家を建てる方もいらっしゃいますが、今回は、「和室のある暮らし」というテーマのもと和室の必要性について考えていきたいと思います。

和室の魅力
まず、和室の魅力について見ていきます。
和室があることの一番のメリットとして、”様々な用途に利用することができる”ことが挙げられます。
和室はその時その場面に合わせて、食事スペースにも、寝室にもなり、幅広い用途に利用することができます。

*くつろぎのスペースとして利用
普段生活している中で、「少し横になりたいな」と思うことは誰だってあると思います。
でもそんな時、フローリングだと、かたくて背中が痛くなる!(ー ー;)と思い、少し躊躇してしまう時ってありますよね。
和室があると、すぐに横になることができ、身体への負担も軽減されます。
また、洗濯物をたたむ際や、アイロンかけをする際にも広々と使うことができます。
冬にはコタツを出して、家族みんなでゆったり過ごす というのもいいですよね(・ω・)ノ
*客間として利用
急な来客時でも、柔軟に対応できるのが和室です。
普段は、別の用途で使用していたとしても、来客時に座布団を出すと応接間として利用でき、
さらに布団を敷くと、お客様の寝室として利用する事もできます♪
よく親戚の方や、ご両親が遊びに来る方には和室がとても便利かもしれませんね。
*子供の遊び場として利用
実は子供の遊び場として和室は最適なんです!
畳にはフローリングと比べてクッション性があり、音を吸収する効果があります。
そのため、子供が転んでケガをしてしまうことや、音に関する問題を少し、軽減してくれます。
また、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、赤ちゃんのお昼寝やおむつ替えの際にとても役立ちます♪
このように、和室はとても凡用性が高いです!
一つの部屋でも座布団、座卓を置く事で、応接間やリビングにも、食事スペースにもなり、布団を敷く事で寝室にもなります。
使い方が限られていない和室が一つあれば、どんな目的で部屋が必要になっても困らないという点がとても便利ですよね(*^_^*)
そのため、いざという時のために、客間として和室を確保しておく人が多いのです。

和室は必要?
新築住宅を購入する際、和室は必要ないという方もいらっしゃいます。
ですが、同じスペースで部屋を用意する場合なら、一つは和室にしておいた方が用途の幅が広くなります。
例えば、急な来客で、泊まりたい!となった際にベットの予備があるお家は少ないと思います。
フローリングの床の上に直接布団を敷く場合、床がかたく、寝心地が悪くなってしまうこと。
さらに、洋室だと押入れのように奥行きが広い収納スペースがないお家も多く、お客様用の寝具を用意しておくことも難しいかもしれません。
和室があれば、昼間は寝室以外の用途で使用することができ、使う時間や使う人によって別の用途で使える和室は、限られたスペースを何倍にも有効に使えるという点で優れています。
和室には押入れなどの収納スペースもある分、収納スペースの確保にもつながります。

畳の素材”イグサ”の効果
*リラックス効果
畳の素材である”イグサ”の香りには人をリラックスさせる効果の成分が含まれています。
皆さんも、和室の匂いを嗅ぐと穏やかな気持ちになったことはありませんか?心も落ち着きますよね。
また、イグサには空気を浄化してくれる効果もあります。
イグサの芳香成分の中にフィトンチッドというものが約20%含まれています。
このフィトンチッドというものは、森林の香りの源で、樹木方放散され、殺菌作用をもっています。フィトンチッドは、天然成分として消臭スプレーや空気清浄機にも使われています。
その他にも、α-シペロンというリラクゼーションに役立つ成分や、バニリンというバニラの香りも含まれています。
バニリンという成分は、香水にも多く使われており、リラックス効果の高い芳香成分として、アロマテラピーのお菓子の香料などにも使われています。
これら芳香成分を含んでいることで、和室にいると森林浴と同様のリラックス効果を得ることができます♪
畳を敷いている和室の空気は、人を癒す力がたくさんつまっていて素敵ですね。
畳は、リラックス効果を得ることができますが、さらに生活を快適にしてくれる機能もあるのです。
*部屋の湿度を調節
さらに生活を快適にしてくれる機能、それは、畳には湿度を調節してくれる効果があるということです。
湿度が高くなれば湿気を吸い、低くなれば湿気を放出するので、丁度良い湿度に保ってくれます。
この効果によって、夏は涼しく、冬は暖かく過ごすことができます。また、夏場に畳の上を素足で歩くと気持ちがいいですよね。冬場でも、フローリングのように冷たくないので、過ごしやすいです( ^ ^ )/

和室のデメリット
ここまで、和室のメリットをお話ししてきましたが、一方和室にはデメリットもあります。
和室のデメリットは傷みやすく定期的なメンテナンスの必要な建具が多い点です。
畳もふすまも障子も洋室の壁紙やフローリングと比べると傷みやすく、定期的に張り替えが必要です。
ですが、フローリングの床は簡単に張り替えられませんが、畳の張り替えは比較的簡単に行うことができます。お金がかかることはデメリットと捉えられるかもしれませんが、定期的なメンテナンスが必要なことは、長く美しい状態を保てるという点ではメリットとも言えそうです。(^_^;)

和室がない方へのオススメアイテム
和室についてご紹介しましたが、
「自分の家には和室はないけど、やっぱり和室いいな」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
和室はつくれないけど…という方にオススメのアイテムがあります!
それは”置き畳”です!
置き畳はフローリングの上に置いて使う畳で、洋室を和室に変えたい場合は置き畳を敷き詰めることで和室に変身させることができます!
置き畳は、必要がなくなれば撤去することができ、すぐにフローリングに戻すことができるので、その時その時のライフスタイルに合わせて空間を変化させることができますので、とても便利です!
いかがでしたか?
これから住宅を新築する人にとって、和室は必ずしも要るものではないかもしれませんがどのようにも使える和室は、あると便利であることは間違いありません。
ただし、建てる前に、和室を将来どのように使いたいかというおよその使い道は考えておいたほうがよいかもしれません。
一度検討されてみてはいかがでしょうか( ´ ▽ ` )ノ
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は
是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!
家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。
10月26日(土)~27日(日) 開催イベント↓
年に一度のハロウィン家まつり開催!
関連記事
-

あったら便利!な収納について【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の永井です(^^♪ 本日は周南・山陽小野田・宇部・山口・防府で新築住宅をお考えの方に、「あったら便利!な収納」についてお伝えします。 今から、宇部・山口・山陽小野田・防府・周南で新築住宅を建てようと思うと、様々な不安が出てくるかと思います。 山陽小野田・宇部・防府・山口・周南で新築住宅を建てるのに「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまうことはありませんか? 山口・防府・周南・山陽小野田・宇部で新築住宅を建てることは、ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです(>_
-

ガレージハウスのメリット・デメリットは?税金の有無や施工事例を紹介
新築住宅を建てるとき、「ガレージのあり方」はひとつのポイントとなります。将来的な使用方法も踏まえて、ガレージをどのように設置するか考えている人も多いでしょう。 そしてガレージ(住宅)の一形態として、「ガレージハウス」というものがあります。特に男性から人気が高い構造であり、ある種の「憧れ」を抱いている人も多いでしょう。本記事ではガレージハウスの定義やメリット・デメリットについて、詳しく解説します。ガレージハウスとはガレージハウスのメリット 風雨を避けられる 土地が狭くても建てられる ガレージ以外の用途が考えられるガレージハウスのデメリット 居住空間が狭くなる 通常よりも費用がかかる ガレージハウスを検討する上でのポイントガレージハウスには税金はかかるの?ガレージハウスの施工事例まとめガレージハウスとはガレージハウスとは、「ガレージ(車庫)と建物自体が一体化している住宅・建物」のことを指します。一部ではガレージハウスではなく、「ビルトイン・ガレージ(”内部建築されたガレージの意”)と呼ばれることも。 1階部分はガレージ、2階部分が居住空間となっているわけですね。ガレージハウスは娯楽性や趣味性が高く、先ほども触れたように男性から人気の高い構造です。自動車やバイクを整備する「基地」的な部分に惹かれている人も、多いのではないでしょうか? ガレージハウスのメリットもちろんガレージハウスのメリットは、趣味性や娯楽性が高いことだけではありません。実用面でも、非常にメリットの大きい建築構造だと言えます。ガレージハウスのメリットとしては、以下のような点が挙げられるでしょう。風雨を避けられる第一に、風雨をほとんど完全に避けられるというメリットがあります。 通常、自動車は屋外に駐車されるものです。たいてい、上部の屋根のみの駐車スペースに駐車されているでしょう。もしかしたら何も囲うものがない駐車場かもしれません。 しかしガレージハウスでは、少なくとも前方以外の三方向は住宅そのもので覆われています。よって、風雨の影響をほぼ完全に避けられるわけです。 シャッター付きのガレージハウスであれば、風雨の影響は一切あり得ません。よって、自動車やバイクなどについては、天候の影響が及ばない場所で、安心して保管できるわけです。 また、風雨だけではなく、砂塵や紫外線なども回避できます。外装の劣化や汚染を避ける上では、とても重要なポイントだと言えるでしょう。土地が狭くても建てられる土地利用の観点から考えると、「土地が狭くても住宅を建てられる」のが重要なポイントとなります。 本来、ガレージは住宅とは別な部分に広がる場所です。しかしそれが住宅そのものに組み込まれるため、必要になる土地も小さくなるのは当然のこと。 これにより、土地取得費用などが大きく低減されます。また、購入候補として挙げられる土地の範囲も大きく広がるでしょう。 土地というものは、左右へ広がる限りは取得費用がかさむものです。しかし上下の方向に対しては、少なくとも居宅レベルでは取得費用が余計にかかるわけではありません。ガレージハウスは、経済的に考えても合理性の高い選択肢だと言えるでしょう。ガレージ以外の用途が考えられる「ガレージハウス」という名称があるとはいえ、何も絶対に車庫として使わなければいけないわけでもありません。半ば屋外であることを活かして、さまざまな用途で利用できます。 たとえば自動車やバイクといった、車両以外の物を保管する場所としても活用できるでしょう。あるいはバーベキューの会場、子供の遊び場としても活用できます。変わったところでは、一部分をトレーニング・ルームに改造するようなケースも。ガレージハウスのデメリット一方で、ガレージハウスを作ることにはデメリットもあります。特に以下のようなデメリットは、必ずおさえておきましょう。居住空間が狭くなる最大のデメリットは、居住空間が狭くなること。1階の大部分がガレージになるので、これは当然のことですね。具体的には、最低でも5坪ほどが、ガレージハウスで占有されるでしょう。居住空間を確保するためには、3階建てにするなど、何かしらの大掛かりな工夫を求められます。通常よりも費用がかかるガレージハウスは、そうでない場合と比較して費用がかかります。 ガレージハウスは、その構造上、設計においてあらゆる制限がかかるものです。もちろん設計においても、より幅広い配慮が求められます。 また木造建築において、一般的にはガレージハウスを設置できません。よって、より高額な鉄筋コンクリート造をチョイスする必要があります。 さらには、ガレージハウスは難易度の高い構造です。よって工法も、高度なものが採用されます。 こういった背景があり、ガレージハウスを設置にするには費用がかかるわけです。ガレージハウスを検討する上でのポイントガレージハウスの導入するならば、第一に「ガレージの幅と奥行き」について、長い目線で考えましょう。将来的には、ガレージハウスの利用方法は多様に変化する可能性があります。 たとえば、自動車を2台か3台駐車することになるかもしれません。また、バイクや自転車、その他保管物を置くこともあるでしょう。となると、やはりガレージの幅と奥行きも、それに合わせておく必要があります。 そして、「ガレージの高さ」も重要となります。自動車の種類によっては、ガレージの高さが足りなくなる可能性もあるから。ミニバンなどを購入する予定があれば、それなりの高さは必要になります。 細かいところで言えば、耐震性にも注意したいところ。一階部分にある柱や梁が少なくなるため、ガレージハウスは地震に弱くなりがち。もしガレージハウスを採用するなら、別な部分で耐震性が確保されるように工夫したほうがよいでしょう。ガレージハウスには税金はかかるの?ガレージハウスには、当然ながら固定資産税がかかります。そして、ガレージハウスの場合は固定資産税が高額になるのではないか、と不安に思っている人も多い様子。しかし、ガレージハウスであることが、極端で税制面で不遇なわけではありません。 むしろガレージハウスだからこそ、固定資産税が安くなったりします。具体的には、ガレージ総床面積の1/5以下であった場合、その部分は固定資産税の課税対象から外されるしくみです。つまり固定資産税に懸念があるなら、課税対象から外れるような形でまとめるのがよいわけですね。 ただし、仮にガレージ部分が総床面積の1/5以上であったとしても、通常の部屋と比較して固定資産税が安くなる傾向にあります。これは、多くのガレージハウスは床や天井が簡素な造りであることに由来しています。とはいえ、できることなら固定資産税の課税対象から外れるようにはしておきたいところです。ガレージハウスの施工事例(引用:Instagram)広々としたスペースと、居住空間にも劣らないほど作り込まれたインテリアが魅力的なガレージハウスの施工例。奥には、所有者の自室へ直通している螺旋階段があります。 (引用:Instagram)最大で4台ほどの自動車を格納できる、大きなガレージスペース。通用口を設けることで、動線がきれいに確保されています。まとめガレージハウスは、自動車やバイクの愛好家からしてみれば、非常に魅力的な住宅構造です。ガレージハウスがあれば、日々のカーライフは非常に充実したものとなるでしょう。 もちろん、実用性といった面でも、非常に優れています。本記事で紹介したように風雨が避けられるといった点は、大きなメリットと言えるでしょう。さらに細かいところで言えば、乗り降りの際に雨を避けられるとった利便性もあります。 もちろん居住空間の問題などもありますが、それでもガレージハウスが魅力的であることは間違いありません。ぜひ一度、ガレージハウスを採用する方針で検討してみてください。 いえとち本舗では、今回お話ししたガレージハウス のように、家づくりにおいて少し専門的な内容もわかりやすく解説しています。いえとち本舗の資料とコンテンツなら、ガレージハウスのビジョンがより強く湧いてくるはずです。ぜひ一度、資料請求、および会員登録をしてみてください。 資料請求する 会員登録する
-

30坪の家って広いの?1坪はどれくらい?“坪”を感覚でつかんで損しない家づくり
目次1. そもそも“坪”とは?1-1. 坪の定義と由来1-2. なぜ住宅業界で使われるの?2. 1坪の広さを体感で理解するには2-1. 坪・平米・帖・畳の違いとは?2-2. 1坪はどのくらいの空間か感覚でつかむ3. 30坪の家はどれくらいの広さ?3-1. 一般的な30坪住宅の間取り例3-2. 30坪は広い?狭い?感覚の違いと生活スタイル3-3. 30坪の家に向いている家族構成とは4. 坪単価ってどういう意味?金額だけに惑わされないコツ4-1. 坪単価の基本とよくある誤解4-2. 坪単価が安い=お得とは限らない理由5. 坪数だけでなく「間取り・使い方」も重要5-1. 同じ30坪でも間取り次第で満足度は変わる5-2. 優先すべきは「坪数」より「暮らしやすさ」5-3. 家族構成やライフスタイルを反映した設計を6. まとめ:感覚で“坪”を理解すれば家づくりがスムーズに6-1. 坪数は“目安”。大切なのは「自分に合った広さ」6-2. 「わかる」と「選べる」はセットで身につけよう6-3. 迷ったらプロに相談してみよう1. そもそも“坪”とは?1-1. 坪の定義と由来「坪(つぼ)」とは、日本で古くから使われてきた面積の単位で、主に住宅業界や不動産の分野で使用されています。1坪は約3.31平方メートル(m²)で、畳(たたみ)2枚分に相当します。もともとは、間(けん)という長さの単位から派生しており、「1間(けん)×1間(約1.82m×1.82m)」=1坪という計算になります。このように、坪はもともと日本家屋の構造や生活様式に根ざした単位のため、畳文化とともに自然に使われてきました。1-2. なぜ住宅業界で使われるの?現在ではメートル法が一般的ですが、住宅の広さについてはいまだに「坪」で表示されるのが主流です。その理由は主に以下の3つです:体感に近い:日本人にとって、坪=畳2枚というイメージがあり、メートルよりも生活空間としての広さを直感的に捉えやすい。不動産業界の慣習:不動産の広告や住宅展示場では、「30坪の家」など坪単位の表現が定着しており、業界全体で共通の言語として扱われている。坪単価の算出に便利:建物価格を「1坪あたりいくら」で表現することで、広さとコストのバランスを比較しやすくなる。ただし、「坪」は日本独自の単位であり、国際的には通用しないため、最近では「㎡(平方メートル)」表記も併記されることが増えています。2. 1坪の広さを体感で理解するには2-1. 坪・平米・帖・畳の違いとは?住宅の広さを表す単位には、「坪」「平方メートル(㎡)」「帖(じょう)」「畳(たたみ)」など複数あります。似ているようで微妙に違うため、混乱しがちです。以下に代表的な単位の関係をまとめます。1坪 = 約3.31㎡(平方メートル)1坪 = 畳2枚分(関東間基準:約0.9m × 1.8mの畳)1帖(1畳)= 約1.65㎡(※畳の大きさにより変動)ただし、畳の大きさは地域や建物の種類によって微妙に異なります(例:京間、江戸間、本間など)。そのため「帖」や「畳」はあくまで体感を示す目安として理解するのが良いでしょう。ちなみに、住宅の間取り表示では「6帖の洋室」や「LDK15帖」のように表現されることが多く、これも坪の理解に役立ちます(例:15帖 ≒ 7.5坪)。2-2. 1坪はどのくらいの空間か感覚でつかむ数字ではなかなかイメージしづらい1坪ですが、実際の生活空間に置き換えると想像しやすくなります。1坪 ≒ 押入れ1間分(幅約180cm × 奥行180cm)1坪 ≒ 大人2人が横並びに立ってちょうど収まる広さ0.5坪 ≒ トイレ1室分くらいのスペースまた、「4.5帖の和室」=「約2.25坪」、「8帖のリビング」=「約4坪」など、間取りに変換して考えると、より実感が湧いてくるでしょう。3. 30坪の家はどれくらいの広さ?3-1. 一般的な30坪住宅の間取り例「30坪の家」と聞くと、一見平均的な広さに思えますが、実は標準的な住宅(26〜28坪前後)と比べるとややゆとりのあるサイズです。面積に換算するとおよそ99㎡、これは4人家族がゆったりと暮らせる広さの目安になります。具体的な間取り例としては、LDKが16〜18帖主寝室+子ども部屋×2(計3部屋)納戸やワークスペース付き玄関や洗面所に広めの収納を確保といった、「生活に+αの余裕がある設計」が可能になります。3-2. 30坪は広すぎる?ちょうどいい?感覚の違いと生活スタイル28坪前後を標準とする住宅と比べると、30坪は「少し広め」「余裕を感じられる」という印象です。子どもが2人いる家庭なら、個室+収納がしっかり確保できる夫婦2人暮らしや子育て卒業後の世帯には、やや広めで贅沢に感じる在宅ワークや趣味部屋など、+1の空間を実現しやすい一方で、「部屋数が多くなると、1部屋ごとの面積が狭く感じる」「掃除や空調効率の面ではやや非効率」など、広ければいいという単純な話ではないことも事実です。3-3. 30坪の家に向いている家族構成とは30坪は、以下のような方々におすすめの広さです:収納やワークスペースも重視したい4人家族今はコンパクトで良いが、将来のゆとりも考えたい夫婦世帯平屋を希望しつつ、部屋数や動線にもこだわりたい層反対に、生活動線のコンパクトさや建築コストのバランスを重視するなら28坪前後でも十分満足できる暮らしが可能です。坪数はあくまで目安であり、間取りと使い方次第で快適さは大きく変わります。4. 坪単価ってどういう意味?金額だけに惑わされないコツ4-1. 坪単価の基本とよくある誤解「坪単価◯◯万円」という表現は、家づくりを検討するときによく目にします。坪単価とは、家の本体価格を延床面積(坪数)で割った単価のことです。たとえば、建物本体価格が1,800万円で延床面積が30坪なら、1,800万円 ÷ 30坪 = 坪単価60万円 という計算になります。一見シンプルな計算式に思えますが、この“本体価格”に何が含まれているのかが重要です。ここを見誤ると、他社との比較で大きなズレが生じます。4-2. 坪単価が安い=お得とは限らない理由「坪単価が安い=コスパがいい」と思いがちですが、実はそう単純ではありません。住宅会社によって坪単価に含める内容がバラバラだからです。たとえば:本体工事費のみの会社(照明・カーテン・外構は別途)諸経費込みの会社(給排水工事・付帯工事も含む)標準仕様とオプションの境界が不明確な会社こうした違いにより、見かけの坪単価が安くても、最終的な総額は高くなるケースがあります。また、家の形や間取りが複雑になると、同じ30坪でも坪単価が高くなる傾向があるため注意が必要です。価格だけで判断するのではなく、「何が含まれているか」を確認し、総額・仕様・暮らしやすさをトータルで比較する視点が大切です。 5. 坪数だけでなく「間取り・使い方」も重要5-1. 同じ30坪でも間取り次第で満足度は変わる「30坪の家」と言っても、その中身は間取りによってまったく違います。極端な話、廊下が多ければ居室は狭くなり、収納が少なければモノが溢れやすくなるため、坪数だけでは暮らしやすさは測れません。たとえば同じ30坪でも:回遊動線を取り入れたプラン水まわりを集中させた時短家事設計廊下を極力なくし、有効面積を最大化したプランなど、間取りに工夫があるかどうかで体感的な広さや生活効率が大きく変わります。5-2. 優先すべきは「坪数」より「暮らしやすさ」家づくりでは「広さ=快適」と思いがちですが、大切なのは“自分たちにとってちょうどいい暮らし方”ができるかです。たとえば…朝の支度がラクになる動線使いやすい位置に収納があること生活スタイルに合わせた部屋の配置こうした“体感の快適さ”は、数字では測れません。むしろ、無駄のない間取りの方が坪数以上に広く感じることも多いのです。5-3. 家族構成やライフスタイルを反映した設計を間取りを考える上で、もっとも重要なのが「その家に住む人のライフスタイル」です。子育て真っ最中の家庭共働きで家事時間が限られている夫婦趣味の部屋や書斎が欲しい個人など、それぞれに必要な広さ・部屋数・動線は違います。「平均」や「世間の広さ」にとらわれず、自分たちの生活に合った間取りを軸に考えることが、満足度の高い家づくりにつながります。6. まとめ:感覚で“坪”を理解すれば家づくりがスムーズに6-1. 坪数は“目安”。大切なのは「自分に合った広さ」家づくりにおいて「坪」は確かに基本的な指標ですが、それはあくまで空間の“目安”にすぎません。重要なのは、その広さの中でどれだけ快適に、自分たちらしく暮らせるかということです。たとえば、30坪と聞いて「広そう」と感じるか「ちょっと狭いかも」と感じるかは人それぞれ。家族構成や生活スタイル、将来の見通しによって“ちょうどいい”広さは異なります。6-2. 「わかる」と「選べる」はセットで身につけよう「坪」が何㎡なのか、「30坪の家」がどんな間取りになるのか。このコラムで学んだ内容を通じて、単位の意味や感覚がつかめたなら、次に大切なのは“選べる力”を持つことです。広さの感覚をつかむ坪単価の中身を見抜く数字に惑わされずに、暮らしをイメージするこれらの「判断基準」を持つことで、展示場や住宅相談でもブレずに進められるようになります。6-3. 迷ったらプロに相談してみようとはいえ、数字と間取り、仕様と価格、暮らしと将来設計…家づくりには多くの要素が絡み合います。だからこそ、ひとりで抱え込まず、信頼できるプロに相談することも大切です。「28坪で足りる?」「30坪にした方が快適?」そんな悩みも、ライフスタイルを踏まえて提案してくれる住宅会社と話せば、納得感のある答えが見えてきます。