ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
ハウスメーカーと工務店はどっちがいい?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
現在、山陽小野田・宇部・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!
今回のテーマは、「ハウスメーカーと工務店はどっちがいい?」です。
ハウスメーカーと工務店のどちらにされるかのお悩みを抱えている方にぜひ読んでいただきたいです!
新築住宅を建てたいと考えた時、ほとんどの方は、まず会社選びから始めますよね。
しかし、総務省の統計によると全国には住宅会社は12万社もあり、
どの住宅会社が最適なのか見つけ出すのも大変困難です。
住宅会社を選ぶ中で最初に行き詰まるのが、ハウスメーカーと工務店のどちらにするのか?という選択です。
・どれがハウスメーカーで、どれが工務店?
・どちらに選ぶべきなの?
・新築住宅は絶対に失敗したくない!
ほとんどの方がそう思うはずです。
なんと!ハウスメーカーと工務店にはさまざまな違いがあり、建てたい理想の家によって選ぶ住宅会社は変わってきます。
新築住宅は一生に一度のとても大きな買い物です。
住宅会社を選び間違えて「こんなはずじゃなかった・・・」と後悔する前に、しっかりと情報収集をしてから始めていきましょう!
今回は、ハウスメーカーと工務店の違いについてお伝えをしていきます。
ハウスメーカーとは

ハウスメーカーという言葉に正式な定義はありません。
例として、積水ハウス・セキスイハイム・大和ハウス・パナホーム・ヘーベルハウス・ミサワホーム・住友林業・三井ホームが大手住宅メーカー8社と言われております。
しかし、大手8社の他にも、一条工務店やタマホームなどの住宅メーカーもハウスメーカーと呼ばれることもあり、どの県に行っても住宅会社があるところがハウスメーカーなのです。
つまり・・・
ハウスメーカー=全国展開している住宅会社ということです。
工務店とは

工務店もハウスメーカーと同様に言葉に正式な定義はありません。
主に地元に根付いている建設業者で、伝統的に工務店と呼んでいる場合が多いです。
複数の営業所があっても、建設エリアは県内や市内、近隣の県にとどまるなど、全国規模ではなく地域密着型が工務店です。
工務店は、個人やメーカーから建設を請け負って、様々な分野の専門職人を集めて、工事全体を監督します。
同じ工務店でも、業務体制に違いがあり、その体制は工務店によって多種多様です。
つまり・・・
工務店=地域密着型の地元に特化した住宅会社ということです。
しかし、一条工務店のように、○○工務店という名前で全国展開をしている住宅会社も増えてきており、線引きは難しいところでもあります。ちなみに当社は、山口県内の新築住宅を請け負う地域密着型なので、工務店となります!
業務体制の違い

ハウスメーカーは全国規模で展開しているために、新築住宅は規格住宅が多く、家を商品として売っているので、家を選んで買うと考えるとイメージしやすいです。
反対に工務店は、多少の規格はありますが、間取りや外観などお客様と一緒に決めて、家をつくっていく形態が多いというイメージです。
ここまではハウスメーカーと工務店の違いについてご説明をしてきました。
新築住宅を建てられる方で、ハウスメーカーを選ぶべきか、工務店を選ぶべきか迷われるお客様が大変多いです。
新築住宅を建てるにあたって、どちらにどのようなメリットがあり、そしてデメリットがあるのかをさらに深堀をしてお伝えしていきます。
ハウスメーカーと工務店のメリットとデメリットをまとめてみました!
ご家族の理想の新築住宅を建てるのにぜひ参考にしてみてください。
ハウスメーカーのメリットデメリット

【ハウスメーカーのメリット】
・住宅会社が全国規模なので、大きくブランド力がある。
・モデルハウスなどの展示場やカタログなどで、イメージがしやすい。
・資金計画の相談から、引越し・仮住まい探し(賃貸)などにも対応している。
・アフターメンテナンスなど、サービスが充実している。
・デザイン力が優れている
・品質が安定していて、施工もしっかりしている。
【ハウスメーカーのデメリット】
・商品ラインナップ、仕様などがあまり自由でないことがあり、金額が割高。
・仕様設備にはオプションの追加設定があり、標準設備に追加した方がいいと勧められて、金額が増えることがある。
・住宅会社によっては利益第一で、営業担当は歩合制のため強引な営業をされるケースがある。
・契約はハウスメーカーをしたけれど、実際に家を建てるのは下請けの工務店の場合が多く、技術の差に心配がある。
【どういう人に向いてるか?】
◎経済力に余裕のある方
◎仕事や家事が忙しく、時間をあまりかけたくない方
◎資金計画の相談から入居後のアフターメンテナンスまで、幅広くサービスを受けたい方
ハウスメーカーもたくさん増えてきました。TVCMでもよくみますね。
太陽光発電の設置住宅や、新商品のプランなどにも力を入れているため、最新の商品もあるのも魅力のひとつですね。
長所と短所を比べながら決めていきましょう。
工務店のメリットとデメリット
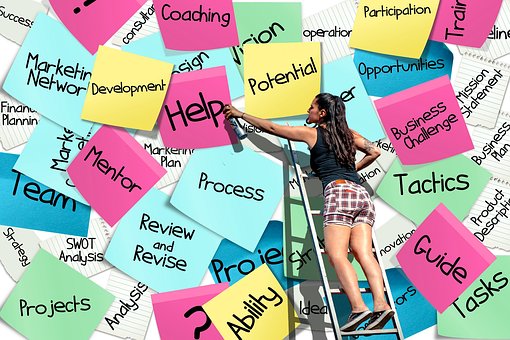
【工務店のメリット】
・信頼関係が大切なので、施工、完成、引渡し後もアフターメンテナンスも地場の業者なので早期対応してもられる。
・ハウスメーカーと比較するとコストを抑えることができる。
・担当者が同一なことが多く信頼関係を築きやすく、コミュニケーションがとりやすい。
・こだわりを細かく聞いてもられて、希望がかないやすい。
・標準設定がないので、後からオプションで追加がかかることが少ない。
・契約時の見積もりがほぼ最終価格になり、金額の交渉もしやすい。
・地元の業者なので安心感がある。
【工務店のデメリット】
・一般的に会社規模が小さく不安に感じることが多い。
・施工図がメインの設計士が多く、デザイン力、内装設備など提案力が弱い。
・モデルハウスを建てていないことが多く、イメージがつかみづらい。
・住宅ローンなど資金計画に対する、支援体制が弱い。
・各建材や水まわりの商品を細かく決めていくので、決めたりするので時間と手間がかかる。
・人数が少ないので、プラン、見積もりに時間がかかる場合がある。
【どういう人に向いてるか?】
◎明確なイメージがあり、積極的に新築住宅作りを楽しめる人方
◎住宅ローンのコストを抑えて、趣味や旅行などを楽しみたい方
◎時間に余裕がある方
◎大きい家ではなく、住みやすいコンパクな家に住みたい方
工務店での新築住宅は決める方も多く、それを楽しみながら決められる人向きかもしれません。
豊かな生活を送るため、納得のいく後悔しないための家づくりができたら良いですね。
地元でずっとやっている工務店さんなどは、安心して新築住宅をまかせられるのではないでしょうか?
自分たちの希望をかなえてくれるかも含めて、新築住宅のお話をすすめていきましょう。

それぞれのメリットとデメリットを比較し、あなたの要望を叶えられる方を選んでください。
例えば、ブランドに価値を感じる方はハウスメーカーがいいと思います。
反対に、ブランドにはまったく興味が無く、
安くて良い家を建てたいと思うのであれば工務店です。
家づくりにおいて、会社選びはとても大切です。
住宅会社選びを間違えると、どんなにあなたに知識があっても、どんなにあなたがしっかりと計画を立てても、家づくりは失敗してしまうでしょう。
この記事を参考にメリットとデメリットをしっかりと把握し、あなたに合った住宅会社を見つけて頂ければ幸いです。
10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓
【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会
関連記事
-

ZEH住宅で健康被害を防ごう!冬の換気不足による体への悪影響【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは! (●ゝω・)ノいえとち本舗山口中央店です! 1月も下旬にはいりましたが、まだまだ寒い日が続いています。そんな寒い日は、みなさん暖房やヒーターなどで室内を暖かくしますよね。 冬はできるだけ冷たい空気を入れたくないものですが、みなさんは換気をされていますか?? (o゜ー゜o) 換気をしなければ、室内の空気はだんだんと汚れてしまい、体へあらゆる悪影響を及ぼしてしまいます。 従来の一般住宅ですと、窓を開けて換気するなど、冷たい空気も取り入れなければいけませんでしたが、ZEH住宅なら、室内を暖かく保ったまま、キレイな空気を室内に取り入れることが可能です。 では、一般住宅での換気不足による体への悪影響には、どのようなものがあるのでしょうか。 実は…外の空気より、室内の空気の方が汚い 室内の空気は、外の空気のように循環しないので、ほとんどの場合は室内の方が外の空気より汚れています。EPA(アメリカ合衆国環境保護庁)によりますと、最悪の場合、室内の空気は、外気よりも100倍も汚れることもあるようです。(゜ロ゜ノ)ノ そんな見えない空気を私たちは24時間吸い続けております。大量の空気を体に取り入れていると考えると、当然、キレイな空気を吸いたいですよね。 部屋の空気がどのように汚れ、その汚れによってどのような健康被害があるのか見てみましょう。 空気の汚れによる健康被害 換気を行わない室内では、あらゆる物質が飛び交っております。空気中に舞っているホコリやダニ、その他有害物質などを吸っていますと ・免疫力が低下する・呼吸器系の病気にかかりやすくなる・アレルギー症状が悪化する・冷暖房設備の効率が悪くなる・生活の質・仕事の質が落ちる などの身体への悪影響があります。 ■空気中を舞うホコリ・ダニ・有害物質 室内の空気には多くの微細なホコリや細菌、ウイルスが含まれています。 空気中のカビやウイルスが粘膜を攻撃することによって、呼吸器系の病気にかかりやすくなります。また、体内に入り込んだ細菌やウイルスを撃退するために免疫が機能した結果、アレルギー症状が悪化することがあります。 ■二酸化炭素の増加 私達が室内で、料理をしたり、作業を行うと、その人間の活動により、二酸化炭素が増加していきます。そして、空気中の酸素の濃度が低下してしまい、集中力や記憶力が低下していくという悪影響が起こります。また、空気が汚染されている室内にずっととどまっていると、免疫力が低下していき、免疫のバランスが崩れて、風邪を引きやすくなったりします。 ZEH住宅は冷たい空気を入れずに換気を行うことができる いかがでしたか?私達が想像していたよりたくさんの身体への被害がありましたよね。 以上のような換気不足による身体への悪影響を防ぐことができるのがZEH住宅です。 ZEHに関わらず、全ての建築物に常時換気ができる設備の設置が義務付けられております。 “室内に冷たい空気を入れたくないけど、クリーンな空気の中で生活したい” そんな理想の暮らしを叶えるのがZEH住宅です。 山口で新たな生活をお考えの方は、ぜひ、ZEH住宅で住居内の空気をキレイにして、健康な生活を送ってみてはいかがでしょうか。 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*) 1月25日(土)~2月2日(日)開催イベント↓【防府市田島】地域最大級!超絶怒涛の3棟同時見比べ見学会
-

カタログを活用して家づくりを失敗しないコツ 【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは!いえとち本舗山口中央店です!●・ω・)ノ新築住宅の購入は、一生に一度の大イベントですよね!しかし「こんなはずじゃなかった・・・」という失敗談をよく聞きます。一生に一度の大きな買い物、家づくりを成功させるにはどうすればいいのでしょうか? 家づくりで失敗する原因 なぜ家づくりで多くの方が失敗してしまうのでしょう? 家づくりで失敗してしまう大きな原因は、会社や担当者の提案力不足です。住宅提案のプロとはいえ、その能力には大きな差があります。 良い住宅会社の良い営業マンに出会うことができれば、高い確率で成功するでしょう。反対に、良い会社の良い営業マンに出会うことができなければ、失敗してしまう確率は高くなってしまいます。 家づくりで成功したと思えるためには、住宅会社や営業マン選びがとても大切です。 カタログの活用が成功のカギ では、家づくりで失敗しないためにはどうすればいいのでしょうか?一番良いのは、多くの住宅会社を訪問することです。できるだけ多くの住宅会社を比べ、営業マンを比べることで、本当に良い担当者が見えてきます。 新築住宅を検討している人は平均9.6社に問い合わせをしているというデータがあります。それくらい、家づくりで成功するのは難しいことなんです。 しかし、約10社もの会社を訪問するのはとても大変です。行く先々で営業を受けるため精神的に疲れてしまいますし、時間や交通費もかかります。 そこでオススメしたいのが、カタログをうまく活用する方法です。カタログを活用するメリットは3つあります♪ ・写真付きイメージを持ちやすい・家のトレンドを知れる ・簡単に住宅会社を比較できる そこでカタログを見て、先に会社だけを比較し、2~3社程度に絞り込んでから訪問することで、営業される心の疲労・時間・交通費の3つを大きく減らすことができます。 カタログにはその会社の考え方や価格が記載されていますので、あなたが共感できる考え方を持ち、予算内で新築住宅が建てられそうな会社をピックアップしてください。 カタログを手に入れる方法 カタログをうまく活用すれば、家づくりに成功する確率はぐっと高まります。カタログを手に入れる方法を3つご紹介します。 ①住宅会社を訪問 しかし、この方法では訪問後の営業も受けるし、時間や交通費もかかります。そのうえ、楽しく会社を比較できるというカタログのメリットは得られません。※あまりオススメできない方法です。 ②ホームページで資料請求 思いつく会社名や、「あなたがお住まいの地域名+新築住宅」などのキーワードで検索をし、出てきた会社にどんどん資料請求の問い合わせをします。 ホームページにはその会社の想いや過去の施工事例、お客様の声などが載っていると思いますので、会社を評価するには有効な手段です。 デメリットとしては、1社ずつ資料請求するのはとても面倒で時間がかかることと、電話番号が必須のところもあり、電話営業をかけられる確率がかなり高いという点です。 ③展示場でまとめて取得 住宅展示場へ行き、そこに出展している会社のカタログをまとめて手に入れる方法もあります。この方法のメリットは、実際に家を見られる点と、1社ずつ訪問しなくてもいいので時間と交通費がかからない点です。 デメリットは、がっつりと営業をされてしまうということと、地場の工務店は展示していない可能性が高いので、比較的規模の大きい会社しか見ることができないところが挙げられます。また、展示場は基本的にある程度の収入があり、予算に余裕がある方を対象としたモデルハウスであることが多く、収入が低いと相手にされないケースもあるようです。ある程度の収入があり、家にかなりお金をかけられる方向けの方法です。 カタログを活用して理想の新築を いかがでしたか?家づくりを成功するためには、カタログをうまく活用する方法がオススメです。通常、カタログを手に入れる方法は3つありますが、営業を受けたり、時間やお金がかかってしまいます。ですが、当社の場合は、無理な押し売りは一切いたしませんので、ご安心くださいませ。1分程度の簡単な入力をするだけで、まとめてカタログを請求することができます。☆★ 資料請求は➜こちら ★☆カタログは完成をイメージしやすく、見ているだけでも楽しいです。ぜひカタログを手にとってこれからの家づくりの参考にされてください。 カタログをうまく活用して最高の家づくりをしましょう! 1月11日(土)~1月17日(金)開催イベント↓【新春限定イベント】この内容を知るまでは家づくりは進めてはいけません!
-

人気の吹き抜けのある玄関って実際どうなの?メリット・デメリットは?
吹き抜けのある玄関は、上からの明るい光が差し込み、開放感を与えてくれます。見た目もおしゃれになる吹き抜けの玄関ですが、採用するにあたりメリットやデメリットもあることは押さえておく必要があります。この記事は吹き抜けのある玄関の魅力やメリット、デメリットをお伝えしていきます。1 玄関に吹き抜けを作る人は多い2 玄関に吹き抜けを作るメリット 3 玄関に吹き抜けを作るデメリット4 デメリットを軽減する工夫5 玄関に吹き抜けを作る際の注意点6 まとめ 玄関に吹き抜けを作る人は多い 吹き抜けのある玄関に憧れる人は多くいます。吹き抜けとは1階から最上階の天井まで空間が抜けていることをいい、天井が高くなる視覚効果により開放性が増し、上からの採光を取り込むことができます。玄関が通常の天井高だと、吹き抜けのような開放感は失われ、窮屈さを感じてしまうこともあります。明かりとりとして窓は設けていても隣家があることであまり光が入ってこないことも。また、玄関は北側や西側に配置されることが多いため、採光の面では不利になります。こういった事情を踏まえた時に玄関が吹き抜けていると彩光がとりやすく、開放性もでるため、明るく広々とした玄関にしたいという方に向いています。 玄関に吹き抜けを作るメリット開放感のある玄関 吹き抜けている玄関は明るさと開放感を持たせることできるのが最大のメリットと言えるでしょう。玄関に開放感があると、家全体が明るい印象になり、生活空間に豊かさを与えてくれます。高い位置に設置した窓は、近隣の建物の影響を受けにくく、1階よりも光を取り入れやすくなりますので玄関も明るくなります。前述したように玄関は北側や西側に配置されることが多く、採光は不利になります。しかし、玄関を吹き抜けにすることで明るさと開放性を確保できますので、北側や西側に玄関がきてしまう場合は吹き抜けが有効です。 おしゃれな玄関こだわりの照明や窓を設置することで魅力的に玄関を演出することができます。窓は一般的な引き違い窓ではなく、縦滑りやFIXの丸窓などを、照明はファン照明やシャンデリアなど、デザイン性の優れるものを選ぶとよりおしゃれな玄関として見せることができます。 広がる縦空間と人の動きを感じることができる 吹き抜けは縦空間が広がるため開放感の他にも、住む人の動きも感じさせてくれる空間となります。生活音が届いてしまうためプライバシーは損なわれてしまいますが、閉鎖的な印象は薄まり、むしろ明るさを感じさせ、コミュニケーションも取りやすくなります。 玄関に吹き抜けを作るデメリット室温の寒暖差には注意 吹き抜けは室温が安定しないデメリットがあります。縦空間が広がるため、温度の流動が大きくなり、適切な室温の維持はしにくくなります。また、部屋間の温度差はヒートショックなどの事故も発生しやすく、体への負担も大きいです。家の中で温度差が生じないようにしっかり断熱対策はしておきましょう。 照明ランプの交換や窓の掃除が大変 吹き抜けにある照明や窓は、高い場所にあり、床もないためお手入れがしにくいです。はしごに登ってランプ交換やお掃除をすることは可能ですが、転落の危険もあるためできることなら避けておきたいもの。お手入れは簡単でも吹き抜け特有の位置に窓や照明があるため業者に頼まなければいけなくなり、余分な費用が発生してしまうこともあります。 居住スペースが削られる 吹き抜けは上の階の床面積を削って設けるため居住スペースが減ります。十分な居住空間が確保できていないのに、無理に吹き抜けを設けてしまっては利便性に欠けてしまいますので、明るさや開放感よりもまず必要な生活スペースを確保することが大切です。また、生活音も届きやすいということも考慮しておきましょう。家族の動きがわかるというのはメリットではありますが、できるだけプライバシーは確保しておきたいという方は、寝室は吹き抜けから離しておくのがいいでしょう。 デメリットを軽減する工夫必要な居住空間は確保しておくこと 吹き抜けは居住スペースを削って設けるため、まず必要な居住スペースは確保しておくことが大切です。2階に必要な生活空間を設けていくのもいいですが、あえて玄関を広くし、収納部屋を配置するのもおすすめです。シューズクロークや雨具など外出時に必要なものをここに収納しすることで動線が効率的になります。収納を併設させた玄関は土間が広くなり、おしゃれ空間としても魅力が増し、吹き抜けも広くなるため、より開放感を与えてくれるでしょう。もう少しスペースに余裕がある場合は台所につながるパントリーを配置するのもおすすめです。買い物してきた食料品を玄関からそのままパントリーにアクセスできる間取りにすれば、買い物後の収納も楽になります。 適切な断熱性能があること 熱が逃げてしまいがちな吹き抜けは断熱性能をしっかり確保することが大切です。玄関にエアコンを設置するのは、あまり現実的とは言えませんので、自然な状態で寒くなりすぎず、暑くなりすぎず、安定した室温になるように計画しましょう。室温を維持していくためには断熱性能が重要になりますので、玄関を吹き抜けするに場合は、熱が逃げていかないように性能の高い断熱材や断熱仕様の玄関、断熱窓などを選んで対策しましょう。 メンテナンスのしやすい照明器具を選ぶ 吹き抜けにある窓や照明のメンテナンスは、キャットウォークを採用することで解消できます。通路を設けることになりますので、その分の吹き抜けはなくなってしまいますが、格子状の床にすれば光も下まで届いてきます。照明はシンプルなブランケットライトやダウンライトにするとお手入れがしやすくなります。照明ランプは交換の手間を減らすために長持ちするLEDを選びましょう。シャンデリアはおしゃれで見栄えがいいのですが、掃除は大変になります。なるべく掃除の手間を減らしたいという方はシャンデリアは避けるのがいいでしょう。 玄関に吹き抜けを作る際の注意点玄関に吹き抜けを作る際は、前述したデメリットを踏まえて以下のことに注意しておきましょう。 必要な居住空間は確保すること生活音は届きやすいので気になる方は玄関から寝室は離すこと掃除やお手入れのことを考えること適切な室温に維持していくために断熱性能を重視すること玄関を明るく開放的にしたいという方は吹き抜けは有効です。しかし、吹き抜けはなにも玄関だけにこだわる必要はありません。リビングの方を優先したいという方は、玄関ではなくリビングを吹き抜けにした方がいいでしょう。リビングは家族が集まる部屋ですから明るさと開放感が重要になります。こういった要素は吹き抜けで解決することができますので、確保できる空間が限られている場合は、どちらを優先するかよく考えて決めましょう。 まとめ 見た目だけでなく実用性も考慮して吹き抜けを設けることが重要ですが、とはいえ、玄関は家のファーストインプレッションとなりますので、こだわりのある玄関に仕上げていくことは妥協できません。理想的な家を建てるためにはいろいろ情報収集し、経験者や専門の人からアドバイスをもらうことが大切ですので、どんな家に住みたいかよくイメージを持って計画を進めていきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから









