ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
失敗したくない!新築住宅の間取りづくりの9つのポイント【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の与倉です!
本日の投稿では、山口県の山口市・防府市・宇部市・周南市・山陽小野田市で新築住宅の購入をお考えのお客様に、
「失敗したくない!新築住宅の間取りづくりの9つのポイント」をお伝えします。
外観、内観、インテリア、設備、、、
新築住宅を購入すると、決めなくてはならないことがたくさんあります。
その中でも、よりお客様の暮らしに影響を与える間取り
実はこの間取り作りを失敗してしまうと、
生活のストレス源になっちゃうんですね。。。
なぜ、間取りがストレス源になるんでしょうか?
実際に家を建て、暮らし始めると
「あぁ、ここはこうしておけばよかった」「玄関からリビングまでの動線が…」
というところが必ず出てきます。
これは、仕方のないことかもしれませんが、
出来るだけ住む前と住んでからのギャップは無くしたいですよね…
そのため、今回は、
このような、既に家を建てた先輩の声をもとに、
「失敗したくない!間取りづくりの9つのポイント」をお伝えします!
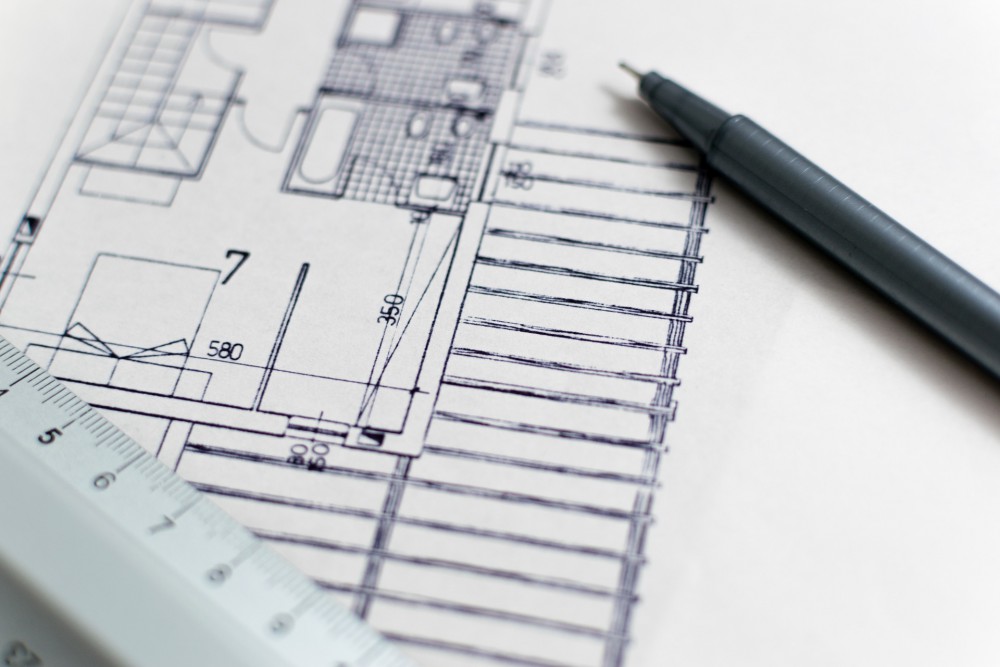
①収納量や収納の内部の作り、収納のつくりで失敗!
1階を広くするために、階に大型収納をつけたけれど…
→階段やはしごをつかって、物の移動が大変
→今はできるけど、老後はとても大変な作業になり、移動できなくなる可能性もある
これは、収納スペースの大きさだけでなく、収納の内部の作りや、収納場所にも問題があります。単に、大きな収納スペースを設けるだけでなく、生活を送る上で、必要な収納位置にもあった方が便利ですよね!
また、大きな収納スペースを設けるメリットとして、1か所にまとめて収納できることができますが、デメリットとしては、1か所であるがゆえに、物を探すのに時間がかかってしまったり、物を移動するのも、大変なんです…
◎日常生活で使うモノ(取り出しやすい位置にあってほしいもの)と必要な収納を、きちんと調べておきましょう!
→収納スペースの坪数や面積だけでなく、幅や奥行きも考えましょう!
②広すぎても狭すぎても困る…部屋の広さで失敗!
来客が一番初めに見る玄関。広々と見せたかったけれど…
→玄関を広くしたことで、玄関収納が激減。
結局収納にはいらない旦那さんのゴルフ用品が、玄関に出しっぱなしになってしまう
マイホームの間取りを決めていく上で、必要なことは収納と部屋のバランス。あまりにも部屋を広くしすぎると、収納が狭くなり、かえって見栄えの悪い空間にしちゃう可能性もあるんですね…
◎収納と部屋のバランスを考えましょう。
→LDKや寝室など、部屋で過ごす人数や動線を考えて、バランスを考えると、より快適で過ごしやすい空間を作ることができます。

③聞きたくない音まで聞こえちゃう…音の伝わり方で失敗!
家の前の道路が予想以上の交通量!夜中までうるさくて…
→寝室が道路に近いため、眠れない
→リビングが道路に近いため、子どもの声も丸聞こえ!
実は、音って生活のストレス源になりやすいもののつなんです!
「賃貸を出て、家を持ちたい」と思ったきっかけが“(周囲の)音に関すること”である方も多いのではないでしょうか?
せっかくの持ち家で、また音に悩まされる…そんな生活は絶対に嫌ですよね!
◎家の周囲の道路の交通状況や地域の様子を知っておきましょう!
→不動産業者は、土地のプロです!そのため、家の周りの道路の交通状況を知っているはずなので、まずは聞いてみましょう!また、意外と見落としやすいのがマンホール。
実は、このマンホール。昼間はそれほど気にならないのですが、夜は、車が通ると「ガタンゴトン」という音が響いてしまい、睡眠の邪魔になる可能性も…
ぜひ、注意して土地を選んでくださいね!
④もっと、欲しかった…コンセントの少なさで失敗!
コンセントを十分に配置したつもりだったけれど…→の四隅にコンセントを配置したら、掃除機をかけるがめんどくさい!
→家事中にテレビを見たいけれど、テレビの配置が悪くて、見えない
「コンセントがここに欲しいのに…」と思って、しぶしぶ延長コードで対応しちゃう…
そうすると、コードで部屋がごちゃごちゃして見える…
そんな経験をしたことがある方って多いのではないでしょうか?
◎家電を多く使用する部屋や寝室には少し多めに、設置しましょう!
→コンセントに関しては、なくて困るより、あって困る方が快適に暮らしやすいです。
また、間取りを決めながら、あらかたの家電の配置を考えることで、コンセントの数を決めやすくなります!
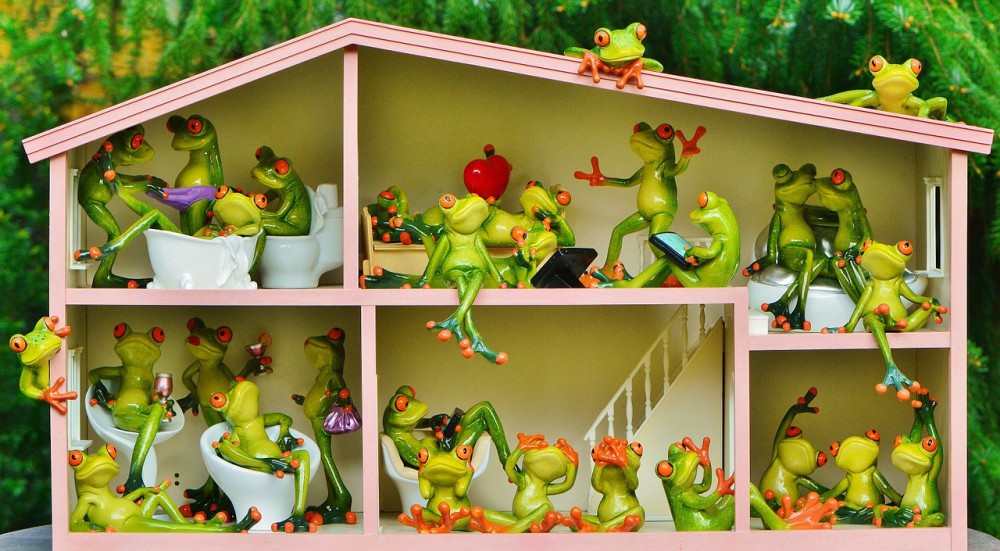
⑤人には見られたくない!プライバシーの空間での失敗!
風通しの良いことばかりに気を取られてしまって…→リビングの窓を大きくしすぎて、外から室内が見えちゃう
→風通しをよくするためにドアを開けると、玄関から奥の洗面室まで丸見え…
他にも、窓やドアを開けた時に、隣のお家の方と向かい合ってしまうことや、来客が通る動線から、汚れた部屋や浴室が見えるのは、複雑な気持ちになりますよね。
そして、なかなか掃除の時間を作るのが難しい方や整理整頓が苦手な方もいらっしゃると思います。この場合、よりよい収納スペースを作ることよりも、部屋の見せ方を工夫するほうが良い場合もあります
◎外からの視線や避けたい視線を把握しましょう!
→家には、道路側と周囲の家からの視線が入ります。間取りを決めていく際には、周囲の家の視線も書き入れておくことで、窓やドアの配置を決めることも大切です。また、玄関を開けてすぐに部屋がある家にしたい場合は、扉をつけることをオススメします。
⑥位置、数、大きさ、窓の失敗!
照明だけが部屋を明るくしてくれるわけじゃなかった…
→トップライトをリビングに付けたのはいいけれど、南向きの部屋だから、日中は必要なかった(別の部屋に付けるべきだった)
→後日、間切りする予定の部屋の南側に照明を付けてしまったせいで、北側が暗い部屋になる可能性が…
せっかくのLDKだから、部屋全体が明るく見えるようにしたい!その思いばかり、走ってしまうと、こんなことが起きてしまうんですね…
しかし、北側にLDKを作ると、暗い部屋になってしまいます…
◎部屋に入る光の量を、間取りに書き込み、自然光を取り入れる部屋を決めましょう!
→いくら、南側に部屋があるからといっても、天候が悪い時期や、光を遮断する建物が周囲にあると、光は入りません。自然光と照明のどちらを使って部屋を明るくするのか、決めておくと、間取りづくりがスムーズになります。

⑦屋内なのに遠く感じる…動線づくりの失敗!
暮らしやすさ=生活動線のスムーズさと言っても、過言じゃない…
→朝の時間は、ドタバタ!廊下や洗面スペースが狭くて困る
→玄関の隣にトイレがあると、来客が来たとき恥ずかしい
生活動線は、快適な生活を送るためには、とても大切。
「慣れれば、大丈夫」なんて、妥協しないでほしい…
◎家族の行動パターンをいくつかで書き出す!
→平日は、仕事や学校のため、朝は親も子供も、みんな忙しい。そのため、忙しい平日の朝や平日の夜、休みの日と分けて、行動パターンを書き出すことで、その家族のライフスタイルに沿った、間取りを作ることができます。
⑧もう少し考えればよかった…屋外スペースの失敗!
家庭菜園や、屋外でやりたいことを考えておかないと…
→土地の中央に家を建てたことで、庭で何をするにも狭い!
→控えめなバルコニーにしたら、中途半端なスペースで不便!
「屋内の間取りに気を取られてしまい、屋外のことは考えてなかった…」という方が稀にいらっしゃいます。
屋外には、物干しざおや室外機を置くスペースも必要だし…
どのくらいのスペースを作るべきなんだろう…
◎屋外でやりたいこととやりたくないことを決めておきましょう!
→もしも、庭で家庭菜園やBBQをしたい!といった要望があれば、ある程度の庭のスペースを設ける必要もあります。
逆に、草抜きが面倒だから、屋外で何かする予定はない方もいらっしゃいますよね。
そのため、屋外のスペースを考えるには、屋外を作る目的と屋外でやりたくないことを明確にしておくことが大切です。

⑨目には見えない、臭いの伝わり方での失敗!
最も、考えにくい臭いの動線。寝室まで、臭いがするのはちょっと…→オープンキッチンにしたら、部屋中に臭いが充満。家で焼き肉はできない…
→キッチンの近くに洗濯物を干すスペースを設けたことで料理や生ごみの臭いが服についちゃった…
昨今、オープンキッチンが主流化しています。このオープンキッチンのデメリットとしてあがるのが、料理の臭いが部屋に充満してしまうこと。
また、階から階への吹き抜けをつくることで、臭いが広がりやすいことも…
◎部屋ごとに、防臭対策をする!
→臭いがつよいキッチンや、オープンキッチンのあるには、風通しのよい空間を作り、他の部屋に繋がらないような風の通り道をつくることが大切。
また、広い空間の場合は、消臭剤などを用いることで、臭いを防ぐこともできます。
以上のポイントを全て叶えた土地や環境に家を作るには、ある程度の金額もかかってきますし、正直、なかなか見つかりません。
そのため、家族内である程度の優先順位をつけながら、間取りを決めていくことで、より快適な暮らしを手に入れることができます。
間取りで、快適な生活を手に入れてみませんか?
10月5日(土)~6日(日) 開催イベント↓
【山口市秋穂】土地90坪の平屋3LDK 完成見学会
関連記事
-

平屋の外観をおしゃれに!和風から洋風までデザインのポイントを解説
最近はマイホームを平屋で建てられる方が多くなり、若いご夫婦にも人気があります。平屋のデザインはスタイリッシュで現代的な外観から落ち着きのある和風な外観と様々ですが、どんな外観にしたいか夢は膨らんでいくけど、どうやって決めていけばいいかわからないと家づくりに悩まれている方も多くいます。そこで、この記事では平屋の外観デザインのポイントをご紹介していきたいと思います。1 平屋の外観デザインのポイント2 おしゃれな平屋の外観【外壁】 3 おしゃれな平屋の外観【屋根】 4 おしゃれな平屋の外観【窓・ドア】 5 おしゃれな平屋の外観【テラス】6 おしゃれな平屋の内観 7 平屋の外観で失敗しやすいパターン8 まとめ平屋の外観デザインのポイント平屋の外観は建物の印象を決める大切なポイントです。見た人の第一印象となりますので、しっかりとこだわっていきたいところです。外観デザインを決めるポイントは外観を構成する屋根と外壁にあります。屋根の形状や色、外壁の模様などが外観を作っていきますので、どんなデザインで装飾していくかが大切です。そして、外観のデザインを考えていく上で最も重要となってくるポイントが統一性です。どんなに優れたデザインを持っていても外壁や屋根のテイストがチグハグでは見栄えは悪くなってしまいます。また、デザインばかり重視しすぎて実用性に欠けてしまうのも問題です。このため統一感のあるデザインと実用性の両方を兼ねて外観をデザインしていくことが大切になります。 おしゃれな平屋の外観【外壁】 外観を決める要素の一つが外壁です。外壁は現在住宅に多く普及するサイディングや昔から日本住宅に採用されているモルタル外壁、タイルなどたくさん種類があります。窯業系サイディングは普及率が高いことからコストが安価にも関わらず、レンガ調や石目調など意匠性に優れた模様が外壁に施されています。サイディングのデザインは豊富にありますので自分の好みに合ったテイストを選ぶことができるメリットがあります。スタイリッシュでモダンな外観にしたい方は金属サイディングがおすすめです。金属のシャープさとシンプルな凹凸ラインが現代的な外観を演出してくれます。塗壁は昔から使われているモルタルの他にも漆喰などがあり、コテで仕上げる美しい模様を外壁に施すことができます。塗壁は和風から洋風と様々な家のスタイルに合わせられます。左官職人によるコテ仕上げは自然の風合いを演出し趣のある仕上がりになります。外壁の種類によって外観の印象が決まりますので、どんな家にしたいかイメージを持って外壁を決めることがポイントです。 おしゃれな平屋の外観【屋根】 屋根の形状は切り妻や寄棟、片流れ、陸屋根などがあり、形状や傾きの角度によって外観のイメージもガラッと変わります。平屋で多く採用されているのは片流れや陸屋根です。片流れは屋根の傾斜が一方向の形状をしており、家を大きく見せる効果があります。傾斜が一方向なためスタイリッシュな印象があり、太陽光パネルの設置も有効です。南向きに太陽光パネルを設置すれば効率的にエネルギーを蓄えることができ光熱費の負担も軽減できます。陸屋根は傾斜がほぼない屋根となっており、建物の外観が箱のようなキューブ型になります。キューブ型の外観はモダンな印象があり、おしゃれな家としても雑誌で掲載されていることが多いです。和風にしたいという方は切り妻屋根がおすすめです。傾斜が二方向にあり屋根と破風板が外観に和を演出してくれます。 おしゃれな平屋の外観【窓・ドア】 開口部は室内の開放性と外観をつくります。窓から漏れる明かりが夜の外観を美しく演出してくれますので、開口部の場所や大きさをよく検討して計画を立てましょう。開口部が大きくなるほど室内の解放性は増しますが、その分外部からの視線が遮断されませんので、計画的なプライバシーと防犯性の確保が必要です。外部から入る視線は生垣やフェンスなどを設けて遮断することができますし、防犯性は人感センサー付きの照明や防犯カメラの設置で対策することができます。照明の光を外観に演出したい方は一階部分の開口は適度にして、二階に開口幅の狭い縦滑り出し窓などを等間隔に複数設置する、若しくはプライバシー空間は仕切り壁を設け、パブリックな空間のところだけ開口を大きくして外部から見えるようにするといった演出も有効です。家の形状をコの字型にして中庭を設けると開放性、プライバシーの確保の両方が実現し、家族との憩いの場として活用することもできます。 おしゃれな平屋の外観【テラス】 テラスは洗濯物を干す実用的なスペースと子供の遊び場として活用する憩いの場、部屋間のアクセスの活用などいろいろな用途を盛り込むことができます。リビングを延長するようにテラスを設ければ内部と外部がつながる奥行きのある空間を作り出すことができます。テラスを外観として取り入れる場合は庭の植栽も大切な要素です。庭のシンボルツリーは育った時のことも想定して計画を立てることが重要になります。育った時に建物やウッドデッキなどに干渉してしまわないように注意しましょう。植栽が多くなると虫害や鳥害を受ける恐れもありますので、防虫剤の散布や鳥よけグッズの設置など対策が必要です。 おしゃれな平屋の内観 おしゃれな内観の特徴はデザインが統一されていることです。壁紙や建具などの内装、住宅設備の他に配置する家具も平屋のテイストに合っていることが大切ですので、イメージしている雰囲気を固めて計画しましょう。平屋は2階建てや3階建てと比べて天井高の制限を受けにくいため開放感のある空間を作ることができます。天井高が低いと圧迫感が出やすいためなるべく天井を高くしておくことをおすすめします。天井をボードで塞がず梁や柱を見せる「あらわし」という仕上げにすると古民家風になって味のある内観になります。また、フラット感が否めない平屋ですが、リビングの床レベル(床の高さ)を下げるダウンフロアは空間に立体感が生まれ、ベンチとしても活用することができますので、家族が集まりやすいリビングにすることができます。 平屋の外観で失敗しやすいパターン これから家づくりをする方は失敗しやすいパターンを知ってすてきな家を計画していきましょう。外観で失敗しやすいパターンは以下のことが挙げられます。 デザインの統一感がない デザインを重視しすぎて実用性に欠けてしまう メンテナンスのことを考えてなく維持するためのコスト負担が大きいプライバシー性と防犯性の確保ができていない家のテイストを統一させるためには、好みのものだからといって安易に取り入れないことです。夫婦でご計画される際はお互いに好きなものを選ぶのではなく、ちゃんとデザインや色が合っているか夫婦同士で確かめるのも重要です。また、住んでみて不便だったということがないように実用性も考えておかなければいけません。住み心地が良くなるように断熱や気密のことは考えて設計しましょう。家は維持していくために定期的にメンテナンスが必要です。最終的にメンテナンスに掛かるトータルコストも想定して計画を立てましょう。 まとめ 平屋の外観を決めていくポイントは屋根と外壁のデザインになります。色やテイストで印象は大きく変わりますので、どんな平屋を建てていきたいかイメージを持っておくことが大切です。統一感のないデザインは外観の見栄えを悪くさせてしまいますので、なるべく採用する色や素材など家のスタイルに合わせて設計しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-

初心者向け! 家づくりの流れについて解説
「新築住宅を建てる段取りって、どんなもの?」「実際に住めるようになるまで、どれくらいかかるの?」 というような疑問は、非常に多く聞かれます。たしかに新築の家を建てる機会は人生で一度あるかないかです。詳しく知っていることのほうが珍しいでしょう。本記事では、新築住宅を建てるまでの流れや期間について、詳しく解説しています。本記事を読めば、実際に住めるようになるまでの流れやスケジュール感が、ほとんど理解できるはずです。 新築住宅を建てようとしている方は、ぜひ参考にしてください。 <どんな暮らしをしたいかを決める>もっとも大切なのは、新築住宅で、どのような暮らしをしたいかはっきりさせることです。理想とする暮らしは、人それぞれの答えがあります。家族と相談して、妥協のない理想像を、まずははっきりさせましょう。注目すべきポイントとしては、以下のようなものが挙げられます。 デザイン費用間取り収納生活導線コンセント配線耐震省エネ性能日当たりソーラーパネルランニングコストetc... というようなところを、つぶさに検討していきましょう。もちろん人によっては、他にも検討すべきポイントは出てくるはずです。気になるところは、徹底して考え抜くことが大切です。 ひとつ注意したいのは、最後に挙げた「ランニングコスト」という点。具体的には水道代やガス代、電気代などですね。家を買うことよりも、ランニングコストとして、決して小さくないお金がかかります。だからこそ、ランニングコストについては、しっかりと考えておくことが重要です。新築住居を建てる費用については、誰しもが深く考えます。しかし建ててから掛かる費用のことを、突き詰めて考える人は、さほど多くありません。「そこは盲点だった!」と、建ててから後悔する人もいます。後悔しないように、じっくり考えましょう。<土地と住宅会社の選定>理想とする新築住宅がはっきりと見えたら、土地を選びます。 周辺の商業施設周辺の公共施設(銀行や病院、市役所など)騒音通勤・通学のしやすさ
-

【2020年6月版】新築住宅の固定資産税とは? 安くおさえる方法はある?
新築住宅を建てた場合、やはり「固定資産税」のことは気になるでしょう。固定資産税がいくらかかるかによって、将来設計も大きく変わってくるはずです。 とはいえ、 「固定資産税はどれくらいかかるのか?」「どうすれば安くできるのか?」 という疑問を抱えている人も、たいへん多いはずです。本記事では固定資産税の概要、および安くおさえる方法について解説します。新築住宅を建てようと考えている、あるいはすでに建てている人は、ぜひ参考としてください。新築住宅の固定資産税の概要固定資産税とは、土地や住宅を持っている人に課せられる税金です。不動産を所有している限りは、支払い続ける必要があります。 支払いは、1月1日時点で新築住宅を持っている人に対して要求されます。実際に支払いを始めるのは、その年の4月から6月あたりです。このタイミングで固定資産税が支出として発生することは、念頭に入れておきましょう。 固定資産税は、どうやって計算される?固定資産税を求める計算式は、【課税標準額×税金率】となっています。 課税標準額と税金率はどのように決まるか、下記で詳しく解説します。課税標準額の算出方法課税標準額は、「家屋調査」によって計算される「評価額」に基づきます。新築住宅に入居してからおおむね3ヶ月後に、自治体が家屋調査を実施します。 家屋調査を拒否することは可能ですが、おすすめはできません。なぜなら家屋調査を拒否すると、正確に評価額が計算できず、課税標準額も高くなってしまうかもしれないから。 基本的に課税標準額は、評価額と同額です。ただし何らかの特例などが適応される場合は、その限りではありません。 ちなみに評価額の見直しは、3年に一度行われます。よほどのことがない限り、評価額が前年より上がるということは起こりません。つまり3年ごとに安くなっていくというわけです。固定資産税がどのように安くなっていくのか、事前に確認しておきましょう。ライフプランも立てやすくなるはずです。 税金率はどうやって決められている?標準税率は、たいていの場合、「1.4%」に定められています。ただし一部の市町村では、これよりも高い割合を設定していることも。心配であれば、市町村に問い合わせるとよいでしょう。新築住宅の固定資産税における減額冒頭でも述べたとおり、固定資産税は減額することが可能です。まず新築住宅を建ててから3年の間、固定資産税は半額になります。減額時の固定資産税は、以下のような式で求められます。 【課税標準額(評価額)×0.14x0.5】 4年目からは、先ほど述べた【課税標準額(評価額)×0.14】という式が適用されます。4年目から固定資産税の支払い総額は高くなるので、家計もそれに合わせておきましょう。固定資産税の減額を受けるための条件 ただし新築住宅にかかる固定資産税の減額を受けるには条件があります。具体的には新築住宅が、以下のようなものでなければいけません。 新築住宅が、令和4年3月31日までに建てられている床面積が50m2から280m2の範囲内である 特に重要なのは、「1」の条件です。新築住宅を建てる場合、令和4年3月31日までに完成されるよう、スケジューリングする必要があります。 土地減税についてちなみに新築住宅のみならず、土地にも減税が存在します。以下の条件を満たしていれば、固定資産税全体の1/6が減税させることさせられます。 面積が200m2以内である令和4年3月31日までに取得した土地である小規模住宅用地に該当する なお、小規模住宅用地以外であれば、全体の1/3が減税されるようになっています。その後に受けられる減税新築住宅を建てたあとも、さまざまな減税措置が存在します。いますぐに受けられるものではありませんが、以下のような減税措置の存在は、頭には入れておきましょう。なお、すべての減税は、令和4年3月31日までが適用期限となっています。 省エネ改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税バリアフリー改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税 他にもさまざまな減税がありますが、少なくとも新築住宅を建ててしばらくは条件が満たせられないでしょう。現実的に関わってくるのは上記ふたつでしょう。固定資産税を安くおさえる、そのほかの方法とは?基本的に固定資産税を安くおさえる方法としては、減税してもらうのが現実的です。しかし、以下のような方法によっても、多少は固定資産税を安くおさえられる可能性があります。家屋調査の実施時、伝えるべきことを伝える 先ほども述べたとおり、評価額(=課税標準額)は、家屋調査にて決定されます。つまり家屋調査にて、査定が不利にならないように、伝えるべきことを伝えることが重要です。 これをやっていたからといって、かならずしも評価額が安くなる、というわけではありません。しかし、いい加減な、あるいは間違った査定を受けることは防がられるはずです。仮に評価額が変動しなかったとしても、その結果には納得できる、という部分もあります。 できれば事前に、評価額の相場や、査定で重要となるポイントなどをおさえておくとよいでしょう。何かを伝えるとき、論理的に主張できるようになります。クレジットカードで支払うまた、クレジットカードで固定資産税を支払うというのも、よい方法です。なぜなら固定資産税をクレジットカードで支払えば、ポイントの還元を受けられるから。 厳密に言えば固定資産税が安くなっているわけではありません。ただしポイントを得られるということは、実質的に安くなっているとも表現できるでしょう。 当然のことながらポイントの還元率は、クレジットカードによって異なります。還元率については、事前の確認が重要です。また、できるだけ還元率の高いクレジットカードを利用するのも、大切なポイントと言えます。 固定資産税は金額が高く、ポイント数も多くなりやすいです。固定資産税は、できる限りクレジットカードで支払いましょう。ただし自治体によっては、クレジットカードでも支払いに対応していないケースがあります。まとめ新築住宅と、およびその土地を有している限り、固定資産税はかならず支払うこととなります。今後の生活においてずっと関わり続ける、たいへん重要な要素です。 できるだけ安くおさえられるように努めましょう。その努力をしているか否かで、新築住宅にまつわる税額は変わってきます。 また、ほぼすべての減税は、令和4年3月31日までと定められています。減税を狙うのであれば、タイムリミットには注意しておきましょう。 いえとち本舗では、快適かつ暮らしやすく住宅を、低価格で提供しています。新築住宅の建築を考えている方は、ぜひ資料をご覧ください。資料請求はこちら また会員サイトでは、住宅と土地に関する重要な情報を発信しています。興味のある方は、ぜひ会員登録してご覧ください。会員登録はこちら









