ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
それぞれのライフスタイルに合った間取り【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の下村です。
現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅を建てたい!とお考えの方、
家づくりをする際、考えることが楽しい反面、間取りのことで悩むことも多いと思われます。
キッチンやリビングを広くしたい、収納を多くしたい、子供部屋を作りたい、などみなさんそれぞれの理想の家づくりの考え方があると思います。
せっかく新築住宅を建てたにも関わらず、建てた後にこの間取りでは生活がしにくい、自分のライフスタイルには間取りが合っていなかったかもしれない…という状況にはなりたくないですよね。
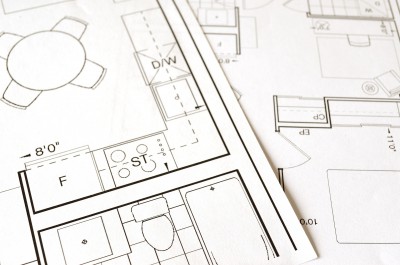
そこで今回は、山口で家づくりをお考えのあなたにとって一番の間取りを見つけるために
「それぞれのライフスタイルに合った間取り」についてお伝えします。
本日は、より良い家づくりのために必要な知識、間取りで失敗しないために押さえておきたいことなどをお伝えできたらと思います。
そもそも間取りとは?
まず、そもそも間取りとは何かについて簡単にご説明させて頂きます。
突然ですがみなさん、1DK、2LDKなどという語句を聞いたことがあると思います。
まずこの頭文字の数字は居室の数に当たります。
例えば2DKだと、居室2つ+DK、1LDKだと居室1つ+LDKのお部屋ということになります。
この後ろに続いているアルファベットは部屋の性質、用途を表しており、
それぞれ
R=ルーム
D=ダイニング
L=リビング
K=キッチン
という意味になっております。
1Rはキッチンと居室が仕切られていない部屋で、1Kはキッチンと居室が分けられている部屋です。
また、L・D・Kの3つは組み合わせて使われることがよくあります。
DK=ダイニング・キッチンとなり、キッチンと食事をするスペースが一緒になっている部屋を表し、これにLが加わるとLDK=リビング・ダイニング・キッチンとなり、ダイニング・キッチンにリビングの機能が加わります。LDKではくつろげる空間が確保してあることが多いです。
簡単に用語について説明させて頂きましたが、ご理解は深まりましたでしょうか?
この用語を頭の片隅に少し入れながら間取り図を見てみると、また考え方が変わってくるかもしれません。
では、用語についてお話をした上で、どのような間取りのお部屋にしたらよろしいでしょうか。様々なライフスタイルに合わせて考えてみましょう。
理想の間取り
「間取り」と一言で言ったとしても、これが一番良いという間取りはありません。
みなさんそれぞれライフスタイルがありますので、誰もが使いやすいという間取りは存在しないのです。
では、どのような間取りがあなたにちょうど良いかを考えていくために、
まず居住人数やライフスタイル別にみてみましょう。

〇1人暮らし
まず、1人暮らしの場合ですが、1人暮らしの場合、料理を作るところ、食事をするところ、寝るところが同じでも問題がない方は、1Rや1Kといった居室が1つである部屋を選択すると良いと思われます。ですが、食事をするところと寝るところはやっぱり分けたいという方は1DK、1LDKがオススメです!〇2人暮らし
2人暮らしの場合、その一緒に住む方との関係性、生活のスタイルによって、間取りの選び方もだいぶ変わってきます。例えば
・お互いの生活習慣を理解しており、1人の時間がなくても大丈夫な方は、広いリビングがくつろぎの空間となる1LDK。
・ダイニングキッチンの他に2つ部屋があることから、自分の生活スタイルを守ったまま2人で生活のできる2DK。
など、寝室が1つでも支障がない場合は、カップルや夫婦でも1DK、1LDKが対象となりますが、お互いの仕事の都合などでライフスタイルが違う場合は、ルームシェアのように、2K以上、DK、LDKで生活空間を分けられる間取りが向いていると思われます。
〇2~4人暮らし(家族)
2~4人暮らしの場合、それぞれの個室が必要か、共有のスペースをどのようにするかで間取りは大きく変わってきます。個室がほしい場合は、人数分の個室を確保し、反対に個室が必要ではなく、家族団らんのスペースを広く取りたい場合は、DK、LDKの間取りを考えてみることもオススメです!
〇4~5人暮らし(家族)
4~5人暮らしの場合は、2~4人暮らしの場合と同様な部分が多いですが、やはり人数が増える分、共有のスペースは大事になってきますので、DKよりもくつろぎ空間を持てるLDKを確保することをオススメします。これまで居住人数別に合った間取りをみてきましたが、
やはり、新しいお子さんの誕生を機会に、またはお子さんと広々と新たな生活をしていきたいということで新築住宅を建てる方も多いと思われますので、奥さんが家事をしやすい間取り、子育てしやすい間取りについても見ていきましょう!

家事をしやすい間取り
実際、家を建てた後に間取りに不満がある方の中で、家事動線を意識できてないという原因が挙げられています。
家事動線とは、文字通り家事をする際に移動する経路のことです。
この家事動線がしっかりと確保できていないと、料理、洗濯、掃除、子育てを同時に
行う際に、何度も同じ経路を往復したり、時間が多くかかってしまう場合もあり、家事をすることが大変になってしまいます。
この家事のための経路をなくす=家事の時間短縮をするために、キッチンと洗面所、ベランダをなるべく近くに設置する。さらには、キッチン、洗面所、リビングを一回りできる動線をつくると、行き止まりもなく、両方向から部屋へ移動ができるので、家事の効率をあげることができると思います。
また、キッチンが広いことに憧れがある方は多いと思われますが、実際にキッチンが広いと、動く距離が多くなるので、意外とコンパクトなキッチンの方が、一連の動作をしやすくなるということもあります。(;^_^A

子育てしやすい間取り
先ほどの家事がしやすい間取りとも関係があるのですが、やはり、家事をしながら子供の様子が見れた方が安心しますよね!特に0~6歳のお子さんがいる方は、いつでもお互いの姿が見えて、一緒に居られる空間が良いと思われます。
例えば、オープンキッチンにして、食事の支度をしながらお子さんを見守ることができ、コミュニケーションをとりながらお手伝いの習慣がつくことも考えられますよね。
お子さんを見守ることとコミュニケーションを自然にとることにオススメな間取りはLDKです!
効率の良い家事動線を確保しながら、子供を見守ることのできる空間を作るというのは難しいことではありますが、このようなことも視野に入れながら、間取りを見ていくことがとても重要です。

あなたにとって一番の間取りを見つけましょう
今回見てきた、家族の人数や、効率の良い家事動線、その他にも収納のことなど、間取りを決める際、考えるポイントは多くありますが、
・これから先どんな暮らしをしたいのか
・どのようなライフスタイルが合っているのか
・何を求めているのか
現在のことだけでなく、未来のことも視野に入れながらあなたのライフスタイルに合った理想の間取りを探してみてください。
いえとち本舗のイエテラスは規格住宅ですが、あなたのライフスタイルに合った間取りが見つかるかもしれません。
山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。
9月21日(土)~9月23日(月)イベント↓
【山口市宮野】女性に大人気のアイランドキッチンを導入した完成見学会
関連記事
-

主寝室は1階?2階?【いえとち本舗の新築・山口・防府・宇部・山陽小野田・周南】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^♪ 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅の購入をお考えのみなさま、 主寝室を1階に設けるか、2階に設けるか考えたことはありませんか?(^^)/ 1日の約3分の1を費やす寝室。場所が違えば暮らし方も変わってきます。 なので今回は「主寝室は1階?2階?」についてメリット・デメリットを踏まえながらお伝えしていきます♪ ★主寝室を1階に設けたら・・・ メリット①人の声にすぐ対応できる 1階は家の中の声はもちろん、外の声にもすぐに反応することができます。外で誰かが呼んでいたりすると、すぐに玄関まで行くことができます。 お子様の喉が渇いて起きてしまったときもすぐに対応できるのは良い点ですね♪ メリット②移動が楽 1階に主寝室を設けると、寝るためにわざわざ階段を上がらずに済むので、移動が楽です(^^)/主寝室に収納スペースがあれば、重い荷物をしまおうと思ったときに階段を上らなくて済むのはとても楽ちんですね♪ メリット③老後を考えると、1階がベスト 人は誰でも歳を重ねるたびに足腰が弱くなってきます。 階段の上り下りは弱った足腰にとって、とてもリスクがあります。少しでも踏み外すと捻挫や骨折の可能性が高まるので、老後のことを考えて新築住宅を購入するなら、1階に主寝室を設けると良いと思います。 デメリット①音が漏れやすい リビングの隣などに主寝室を設けると、テレビや家電の音が寝室まで響くことが予想されます。 メリット①で挙げた外の音が聞こえやすいのも、デメリットになりうりますね。 お子様がおられるご家庭だと、寝たとおもって安心した後にテレビをつけてその音で起きてしまうことも予想できます(;_:) ★主寝室を2階に設けたら・・・ メリット①1階の音が漏れない リビングのテレビの音や玄関ドアを閉める音など、1階に比べて聞こえずらいです。 プライバシーの確保にもなりますし、外の車の音が聞こえづらいこともとても助かりますね♪ メリット②夏場は涼しい 1階に比べ、2階の方が夏場は涼しくなります。防犯上は危険かもしれませんが、少しでも窓を開けると涼しい風が入ってきます。 暑い夏場でも快適な睡眠ができます(^^♪ デメリット①移動が面倒 夜中に喉が渇いたとき、わざわざ1階まで降りなければなりません。何かをリビングに忘れたりしても、主寝室と遠かったら少し面倒になってしまいますよね・・・ 主な収納が2階にあればその持ち運びも億劫になります。 ★まとめ 主寝室を1階に設けるか2階に設けるかは人それぞれのライフスタイルに合わせて設計するのがベストです。 双方のメリットとデメリットを踏まえて老後のことを考えて1階にするか・・・プライバシー面での過ごしやすさを考えて2階にするか・・・ などでお悩みの方の参考になれば幸いです(^^♪ 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓ 【山口市下市町】リビング21.3帖平屋3LDK完成見学会
-

30坪の家って広いの?1坪はどれくらい?“坪”を感覚でつかんで損しない家づくり
目次1. そもそも“坪”とは?1-1. 坪の定義と由来1-2. なぜ住宅業界で使われるの?2. 1坪の広さを体感で理解するには2-1. 坪・平米・帖・畳の違いとは?2-2. 1坪はどのくらいの空間か感覚でつかむ3. 30坪の家はどれくらいの広さ?3-1. 一般的な30坪住宅の間取り例3-2. 30坪は広い?狭い?感覚の違いと生活スタイル3-3. 30坪の家に向いている家族構成とは4. 坪単価ってどういう意味?金額だけに惑わされないコツ4-1. 坪単価の基本とよくある誤解4-2. 坪単価が安い=お得とは限らない理由5. 坪数だけでなく「間取り・使い方」も重要5-1. 同じ30坪でも間取り次第で満足度は変わる5-2. 優先すべきは「坪数」より「暮らしやすさ」5-3. 家族構成やライフスタイルを反映した設計を6. まとめ:感覚で“坪”を理解すれば家づくりがスムーズに6-1. 坪数は“目安”。大切なのは「自分に合った広さ」6-2. 「わかる」と「選べる」はセットで身につけよう6-3. 迷ったらプロに相談してみよう1. そもそも“坪”とは?1-1. 坪の定義と由来「坪(つぼ)」とは、日本で古くから使われてきた面積の単位で、主に住宅業界や不動産の分野で使用されています。1坪は約3.31平方メートル(m²)で、畳(たたみ)2枚分に相当します。もともとは、間(けん)という長さの単位から派生しており、「1間(けん)×1間(約1.82m×1.82m)」=1坪という計算になります。このように、坪はもともと日本家屋の構造や生活様式に根ざした単位のため、畳文化とともに自然に使われてきました。1-2. なぜ住宅業界で使われるの?現在ではメートル法が一般的ですが、住宅の広さについてはいまだに「坪」で表示されるのが主流です。その理由は主に以下の3つです:体感に近い:日本人にとって、坪=畳2枚というイメージがあり、メートルよりも生活空間としての広さを直感的に捉えやすい。不動産業界の慣習:不動産の広告や住宅展示場では、「30坪の家」など坪単位の表現が定着しており、業界全体で共通の言語として扱われている。坪単価の算出に便利:建物価格を「1坪あたりいくら」で表現することで、広さとコストのバランスを比較しやすくなる。ただし、「坪」は日本独自の単位であり、国際的には通用しないため、最近では「㎡(平方メートル)」表記も併記されることが増えています。2. 1坪の広さを体感で理解するには2-1. 坪・平米・帖・畳の違いとは?住宅の広さを表す単位には、「坪」「平方メートル(㎡)」「帖(じょう)」「畳(たたみ)」など複数あります。似ているようで微妙に違うため、混乱しがちです。以下に代表的な単位の関係をまとめます。1坪 = 約3.31㎡(平方メートル)1坪 = 畳2枚分(関東間基準:約0.9m × 1.8mの畳)1帖(1畳)= 約1.65㎡(※畳の大きさにより変動)ただし、畳の大きさは地域や建物の種類によって微妙に異なります(例:京間、江戸間、本間など)。そのため「帖」や「畳」はあくまで体感を示す目安として理解するのが良いでしょう。ちなみに、住宅の間取り表示では「6帖の洋室」や「LDK15帖」のように表現されることが多く、これも坪の理解に役立ちます(例:15帖 ≒ 7.5坪)。2-2. 1坪はどのくらいの空間か感覚でつかむ数字ではなかなかイメージしづらい1坪ですが、実際の生活空間に置き換えると想像しやすくなります。1坪 ≒ 押入れ1間分(幅約180cm × 奥行180cm)1坪 ≒ 大人2人が横並びに立ってちょうど収まる広さ0.5坪 ≒ トイレ1室分くらいのスペースまた、「4.5帖の和室」=「約2.25坪」、「8帖のリビング」=「約4坪」など、間取りに変換して考えると、より実感が湧いてくるでしょう。3. 30坪の家はどれくらいの広さ?3-1. 一般的な30坪住宅の間取り例「30坪の家」と聞くと、一見平均的な広さに思えますが、実は標準的な住宅(26〜28坪前後)と比べるとややゆとりのあるサイズです。面積に換算するとおよそ99㎡、これは4人家族がゆったりと暮らせる広さの目安になります。具体的な間取り例としては、LDKが16〜18帖主寝室+子ども部屋×2(計3部屋)納戸やワークスペース付き玄関や洗面所に広めの収納を確保といった、「生活に+αの余裕がある設計」が可能になります。3-2. 30坪は広すぎる?ちょうどいい?感覚の違いと生活スタイル28坪前後を標準とする住宅と比べると、30坪は「少し広め」「余裕を感じられる」という印象です。子どもが2人いる家庭なら、個室+収納がしっかり確保できる夫婦2人暮らしや子育て卒業後の世帯には、やや広めで贅沢に感じる在宅ワークや趣味部屋など、+1の空間を実現しやすい一方で、「部屋数が多くなると、1部屋ごとの面積が狭く感じる」「掃除や空調効率の面ではやや非効率」など、広ければいいという単純な話ではないことも事実です。3-3. 30坪の家に向いている家族構成とは30坪は、以下のような方々におすすめの広さです:収納やワークスペースも重視したい4人家族今はコンパクトで良いが、将来のゆとりも考えたい夫婦世帯平屋を希望しつつ、部屋数や動線にもこだわりたい層反対に、生活動線のコンパクトさや建築コストのバランスを重視するなら28坪前後でも十分満足できる暮らしが可能です。坪数はあくまで目安であり、間取りと使い方次第で快適さは大きく変わります。4. 坪単価ってどういう意味?金額だけに惑わされないコツ4-1. 坪単価の基本とよくある誤解「坪単価◯◯万円」という表現は、家づくりを検討するときによく目にします。坪単価とは、家の本体価格を延床面積(坪数)で割った単価のことです。たとえば、建物本体価格が1,800万円で延床面積が30坪なら、1,800万円 ÷ 30坪 = 坪単価60万円 という計算になります。一見シンプルな計算式に思えますが、この“本体価格”に何が含まれているのかが重要です。ここを見誤ると、他社との比較で大きなズレが生じます。4-2. 坪単価が安い=お得とは限らない理由「坪単価が安い=コスパがいい」と思いがちですが、実はそう単純ではありません。住宅会社によって坪単価に含める内容がバラバラだからです。たとえば:本体工事費のみの会社(照明・カーテン・外構は別途)諸経費込みの会社(給排水工事・付帯工事も含む)標準仕様とオプションの境界が不明確な会社こうした違いにより、見かけの坪単価が安くても、最終的な総額は高くなるケースがあります。また、家の形や間取りが複雑になると、同じ30坪でも坪単価が高くなる傾向があるため注意が必要です。価格だけで判断するのではなく、「何が含まれているか」を確認し、総額・仕様・暮らしやすさをトータルで比較する視点が大切です。 5. 坪数だけでなく「間取り・使い方」も重要5-1. 同じ30坪でも間取り次第で満足度は変わる「30坪の家」と言っても、その中身は間取りによってまったく違います。極端な話、廊下が多ければ居室は狭くなり、収納が少なければモノが溢れやすくなるため、坪数だけでは暮らしやすさは測れません。たとえば同じ30坪でも:回遊動線を取り入れたプラン水まわりを集中させた時短家事設計廊下を極力なくし、有効面積を最大化したプランなど、間取りに工夫があるかどうかで体感的な広さや生活効率が大きく変わります。5-2. 優先すべきは「坪数」より「暮らしやすさ」家づくりでは「広さ=快適」と思いがちですが、大切なのは“自分たちにとってちょうどいい暮らし方”ができるかです。たとえば…朝の支度がラクになる動線使いやすい位置に収納があること生活スタイルに合わせた部屋の配置こうした“体感の快適さ”は、数字では測れません。むしろ、無駄のない間取りの方が坪数以上に広く感じることも多いのです。5-3. 家族構成やライフスタイルを反映した設計を間取りを考える上で、もっとも重要なのが「その家に住む人のライフスタイル」です。子育て真っ最中の家庭共働きで家事時間が限られている夫婦趣味の部屋や書斎が欲しい個人など、それぞれに必要な広さ・部屋数・動線は違います。「平均」や「世間の広さ」にとらわれず、自分たちの生活に合った間取りを軸に考えることが、満足度の高い家づくりにつながります。6. まとめ:感覚で“坪”を理解すれば家づくりがスムーズに6-1. 坪数は“目安”。大切なのは「自分に合った広さ」家づくりにおいて「坪」は確かに基本的な指標ですが、それはあくまで空間の“目安”にすぎません。重要なのは、その広さの中でどれだけ快適に、自分たちらしく暮らせるかということです。たとえば、30坪と聞いて「広そう」と感じるか「ちょっと狭いかも」と感じるかは人それぞれ。家族構成や生活スタイル、将来の見通しによって“ちょうどいい”広さは異なります。6-2. 「わかる」と「選べる」はセットで身につけよう「坪」が何㎡なのか、「30坪の家」がどんな間取りになるのか。このコラムで学んだ内容を通じて、単位の意味や感覚がつかめたなら、次に大切なのは“選べる力”を持つことです。広さの感覚をつかむ坪単価の中身を見抜く数字に惑わされずに、暮らしをイメージするこれらの「判断基準」を持つことで、展示場や住宅相談でもブレずに進められるようになります。6-3. 迷ったらプロに相談してみようとはいえ、数字と間取り、仕様と価格、暮らしと将来設計…家づくりには多くの要素が絡み合います。だからこそ、ひとりで抱え込まず、信頼できるプロに相談することも大切です。「28坪で足りる?」「30坪にした方が快適?」そんな悩みも、ライフスタイルを踏まえて提案してくれる住宅会社と話せば、納得感のある答えが見えてきます。
-

二世帯住宅の平均価格相場は?タイプ・工法・設備で変わる?
親世帯と子世帯が一緒に住む二世帯住宅。異なる世帯が同じ家に住むことになりますので、メリットはもちろん、お互いの関係を良好に保っていくために気をつけていかなければいけないこともあります。この記事では二世帯住宅の費用相場や間取り対応、注意しておきたいことなどをお伝えしていきます。1 そもそも二世帯住宅とは2 二世帯住宅の種類3 二世帯住宅の費用相場は?4 二世帯住宅のメリット5 二世帯住宅のデメリット6 二世帯住宅を建てる前の注意点 7 まとめそもそも二世帯住宅とは通常の住宅は一世帯だけで住むものですが、親世帯と子世帯が一つ屋根の下で住む住宅を二世帯住宅といいます。二世帯住宅と近いものに近居がありますが、これは両世帯が近い場所に住んでいることを表しているもので、同じ家に住んでいるというわけではありません。二世帯住宅は同じ家に一緒に暮らすという形となり、共有するものやプライバシーの取り方、家の間取り方法など住む人によって仕様も様々です。現在では二世帯住宅を建てた方を対象にした補助金制度もあります。 二世帯住宅の種類二世帯住宅は親世帯と子世帯が一緒に住む住宅ですから、生活スタイルや保っておきたいプライバシー、価値観や考え方などお互いのことを考えて家づくりをしていかなければいけません。間取り方法も住む人に合わせたつくりにしていく必要があり、土台となる間取りの種類があります。二世帯住宅を検討されている方は、どんな間取りがあるのか知り、間取り設計に活かしていきましょう。 完全分離タイプ 二世帯住宅の中では両世帯で最もプライバシーを維持していける間取りになります。名前の通り世帯同士で共有する空間は設けず、完全に生活空間を分けます。居住空間の分け方は、上下階で分ける方法と左右に分ける方法があります。上下階で分ける場合は階段を二箇所設置する必要があります。玄関も各世帯で一箇所ずつ設置することで表札も分けることができるため、苗字の違う世帯が住む場合は都合が良くなります。 一部共用タイプ 玄関やリビング、キッチンなどの水回りなど、部分的に共有する間取りが一部共用タイプです。部分的に共用することで完全分離のように設備類を複数設置することがなくコストを抑えることができます。また、適度に各世帯で距離感を保つことができるため、自由度が高く、プライバシーの確保とコミュニケーションのバランスがとれる間取りです。一部共用タイプは共用部があるため、効率よく空間を使うことができ、そこまで広くない敷地でも二世帯住宅を建てることができます。 同居タイプ 同居タイプは寝室以外の居住空間を共用する同居型の間取りです。昔からある二世帯が住む間取りであり、屋内に入る玄関やキッチン、お風呂、トイレなどを分けず親世帯と子世帯で一緒に使用していきます。プライバシーの確保はとりづらい間取りのため、リラックスできる空間を別に設けておくといいでしょう。また、親世帯と子世帯では生活リズムが異なりますので、この違いが最も影響を受けやすい間取りとも言えます。 二世帯住宅の費用相場は? 二世帯住宅の費用相場は2000〜4000万円になります。ただし、間取りや家の仕様で費用は大きく変わりますのでご注意ください。二世帯住宅の場合は、共用するところが多くなるほど費用を抑えることができます。一部共用タイプや同居タイプをご検討されている方は、費用をかけるところの優先順位を決めて設計することでコストを抑えながらもグレードの高い仕様が実現可能になります。2000〜30000万円台の二世帯住宅は一部共用タイプや同居タイプになり、3000万円以上になると玄関の他は分離できる一部共用タイプと完全分離タイプの二世帯住宅を建てることができます。二世帯住宅は補助金制度もありますので、費用負担を減らすためにも積極的に利用していきましょう。補助金制度には「地域型住宅グリーン化事業」があり、建物の仕様ごとに補助金110〜140万円の給付を受けることができます。また、この仕様の建物で三世代同居住宅にすると特別措置として上限30万円が加算。地域材を過半以上利用することで上限20万円加算することができ、最大50万円の補助金を受けることができます。補助金は年度ごとに要件が変わることがありますので確認しておくことをおすすめします。引用:国土交通省 令和3年度地域型住宅グリーン化事業 グループ募集の開始引用:地域型住宅グリーン化事業(交付) 二世帯住宅のメリット 子育て世帯にとっては二世帯住宅に住むと親世帯から子育てのサポートを受けやすいメリットがあります。子供を病院に連れていかなければいけない場合や保育園の送迎、仕事で子供を見ることができないケースなど、通常なら時間に都合をつけて子供の面倒を見ていかなければいけませんが、同じ家に両親が住んでいますので、子供を見てもらえるように頼みやすい環境にあります。また、生活を共有していくご家庭の場合は、食費や日用品などを共有することで、年間で6〜13万円の生活費を節約することもできます。ただし、いくら家族でもお金のトラブルは多く、双方が納得しているのではないかぎり、どちらか一方に負担が傾いてしまうとストレスの原因になってしまいますので注意しましょう。生活費についてはどのように負担していくか、よく話し合ってルールを決めていくことが大切です。 二世帯住宅のデメリット 同じ家に生活リズムやライフスタイルの異なる世帯が住むことになりますので、お互いの距離感というのが大事になります。二世帯住宅になると完全分離タイプだとしても通常の一世帯の家と比べてプライバシーやコミュニケーションには気を配ることになります。また、お金のトラブルにも注意しておかなければいけません。電気代やガス代などの光熱費、食費や日用品などの生活費については、できるだけ分けておくとトラブルも起きにくくなります。生活リズムが異なると光熱費に差が出ますので、負担の大きい側はストレスになってしまうことも考えられます。手数料や設置費は掛かってしまいますが、ガスメーターや水道メーターは別にしておくことをおすすめします。 二世帯住宅を建てる前の注意点【生活リズムやお金のこと】 生活費について管理方法や分担はお互いによく話し合い、双方納得するようにしておきましょう。お金のトラブルは多いですので、家族だから問題ないと思わずに電気メーターやガスメーターに関しては世帯で分ける方が無難です。また、親世帯と子世帯では生活リズムが異なります。休日はゆっくり眠っていたいのに早朝から生活音が届いてしまうと休むこともままならないです。意外と生活音は届きやすいので、寝室の配置には注意しておきましょう。キッチンやお風呂、トイレなど共有する場合は、使う時間がぶつかってしまうこともあります。部分的に共有していくのなら、お互いに守っておきたい生活ルールはあった方がいいでしょう。【間取りなどの家づくり】親世帯は高齢になっていきますので、介護のことも考えてなるべく階段のない生活ができる間取りにした方がいいでしょう。一階を親世帯の居住空間にすれば、外へのアクセスがしやすくなります。また、トイレや廊下幅を広くとることで車椅子での移動も可能になりますので、将来的に介護が必要な生活になっていくか事前に話し合っておくことが大切です。業者選びでは、二世帯住宅の実績を持つ業者を選ぶことです。異なる生活スタイルの世帯が一緒に住むことになりますので、各世帯が快適に暮らせる家づくりがされていなければいけません。通常の住宅とは、また違ったつくりになってきますので、必ず二世帯住宅の経験を持つ業者に依頼しましょう。 まとめ 家づくりは住み始めた時のイメージを具体的に持っておくことが大切です。失敗や成功したことなど、二世帯住宅を建てた人たちの経験談は参考にしておくと、これから行っていく家づくりに役立ちます。自分では大丈夫だと思っていても意外と見えていないもので、後から不便だなと感じてしまうこともあります。家は一生の買い物ですから後悔のないように妥協なく進めていきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから









