ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
家づくりの流れ【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の下村です。
本日は宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅をお考えの方に、
「家づくりの流れ」についてお伝えします。
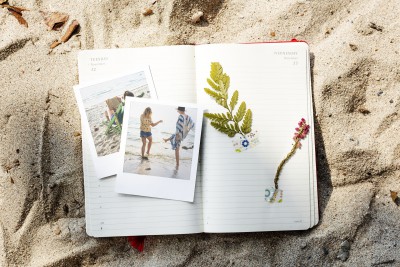
今回は、新築住宅を建てる際の「家づくりの流れ」についてお伝えをしていければと思います。
家づくりの流れを知る
「山口で新築住宅を建てたい!」「マイホームが欲しい!」 とお考えの方、
いざ新築住宅を建てようと思っても、いつ何をして、どうすればいいのか
わからないことだらけですよね。
そこで、まずは新築住宅を建てる際の「家づくりの流れ」を知ることが大切です。
以下より、どのタイミングでどのようなことを行うのかについてお話させていただきます。少しでもみなさんの家づくりの参考になると幸いです。

家づくりに必要な3つのSTEP
家づくりに必要なことについて大きく3つのSTEPに分けてお話させていただきます。
STEP1ヒアリング~土地決め
〇お家づくりヒアリング
営業担当者が、家づくりについてのご説明、ヒアリングをさせていただきます。
みなさんが思い描いている新築住宅、住まいのプランについてのご要望を出来るだけ詳しくお聞きさせていただきます。
まずは、どこに住みたい、どのような暮らしをしたいのかという理想の暮らしについて
家族全員で話し合いましょう。
〇概算資金計画
現在お支払いされている家賃や、年収に応じて、無理なくローン返済が出来る、
住宅・土地の予算の目安をご提案させていただきます。
山口で新築住宅を建てると決めたら、まずは、
家づくりに必要なお金のことを考えましょう!
資金計画で大事なポイント☟
将来をイメージして「いくらまでなら返せるか」という返済計画を立てること。
借りられる金額ギリギリまで借りると、
突然の大きな出費に慌ててしまう可能性があります。
お子さんの誕上や、結婚、進学などこれからの将来のイメージを
ふくらませ、家計状況の変化に対応できるよう、無理のない返済計画を
立てておきましょう。
〇住宅ローン事前審査説明
事前審査の必要性や内容、提出時の持参物などをご説明いたします。
住宅ローンを組むためには、金融機関の審査を通過しなければなりません。
審査で考慮されている項目としては、完済時年齢、健康状態、担保評価、借入時年齢、勤続年数などがあげられます。
住宅ローンの審査の基準は、銀行によって様々違いがあります。
年収や借入金額・返済期間が同じであっても、審査に通る銀行と、
通らない銀行もありますのでご注意ください。
〇住宅ローン事前審査申込
事前審査申し込みで必要なものとしては以下のものがあげられます。
・事前審査申込書
・運転免許証
・健康保険証
・借入残高のわかるもの
・源泉徴収票
・個人経営の方は3期分の決算書一式
〇土地見極め
希望地域で売りに出ている土地をご紹介し、建物を建てるプロとして
アドバイスをさせていただきます。
理想の家づくりには、土地探しが重要となります。
しかし、土地探しには難しい面がたくさんあります。
土地には2つの面積があること、自由に住宅を建てられない土地がある、
土地の契約と建物の契約は別であることなど、様々な法律で定められたルールがあります。
難しい部分は、ぜひ相談できるプロの方に相談し、疑問や不安をなくしていきましょう!
〇住宅ローン事前審査 結果ご連絡
書類提出後1週間後で結果がでます。
結果が出たらご連絡させていただいております。
〇資金計画提示
お客様の要望に応じて間取りプランを提案し、それに合わせ、概算金額、
資金計画も提示させていただきます。
ここで、もう一度、返済計画に無理がないかご確認いただいております。
〇土地 現地確認
土地を絞り込み、現地を確認します。
土地周辺に何があるか、日当たりや風通しはいいのか、また、隣地との境界線もしっかりと確認しておき、後で後悔をしないようにしっかりと敷地選びをしましょう。

STEP2色決め~土地決済
〇内・外装の色決め
思い描かれている、理想の住まいを実現するお時間です。お好みの色を選んであなただけのお家に仕上げます。
〇Panasonicショールームへ
カタログを見ながら考えてもなかなか決められませんよね。スタッフがショールームをご案内しながらお風呂やキッチンを決めていきます。
実際に見て決めることができるのはうれしいですよね。
〇土地契約
土地所有者と不動産屋と日程を合わせ、土地契約をします。土地契約には、手付金と契約印紙代が必要となります。
〇請負契約
請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。
見積書・設計図書に基づきご契約を締結させていただきます。
お支払い条件としては、以下の通りです。
着工時30%
上棟時30%
完了時40%
〇住宅ローン 融資本申込
銀行またはフラットへ融資本申し込みをします。事前審査は銀行などの金融機関が行い、本審査は信用保証会社が行います。
事前審査を無事に通過した場合でも、本審査で落ちてしまう場合もあるので、注意が必要となります。
〇住宅ローン 融資結果ご連絡
1週間~10日程で結果が出ます。結果が出た後、ご連絡させていただいております。
〇内・外装の色決め内容確認
〇見積・資本計画書提示
詳しい打ち合わせ後の資金計画、見積書の確認をし、変更契約をします。〇工務引き継ぎ
現場担当へ引き継ぎをし、図面やプランボードの最終確認をします。〇土地決済(土地代金支払い)
土地の売主と司法書士の立会いにて、代金の授受と所有権の移転を行います。
当日行うこと
・売主から買主に土地の名義を移転するために必要な書類の確認
・売主の住宅ローンなどの抵当権がないかどうかの確認
・買主が利用する住宅ローンの関係の書類確認
・抵当権設定登記申請)
・買主から売主への土地代金の残りの支払い
・各種料金の支払い
土地決済の日に何をするのか、事前に知っておくと、どの書類にどんなサインをしているのかが明確になります。
〇確認申請提出
役所に必要書類を提出し、建築確認を申請します。〇地盤調査
地盤調査をします。結果次第で工程が変わります。
家づくりで難しいことの1つに地盤があげられます。
環境のいい場所を求めた場合でも、
・不同沈下
・液状化
・盛土
に遭遇してしまうと、建物を使用することは難しくなってしまいます。
地盤に関しては専門性が必要とされますので、一級建築士などの頼れる方に相談した方が安心です。
STEP3着工~引渡し
〇地鎮祭
工事中の安全、工事後の家内安全を祈願します。
そもそも地鎮祭とは?
地鎮祭とは、新築住宅工事の前に行う神様へのご挨拶の儀式といえます。
地鎮祭で土地を利用する許可を得ることによって、崇りを防いで工事の安全を祈ります。建築工事を着工する前に大安の日を選んで、地鎮祭は行われます。
ただ神様のために行う行事としてではなく、家づくりを依頼する施主様や施工業者、職人などが一堂に集まる機会ともとらえることができます。
人生に何度もできる経験ではないと思われますので、ぜひ家づくりの記念として
行われるといいでしょう。
〇着工
地盤調査の結果次第で地盤補強工事着工し、
その後、基礎工事着工します。
〇上棟(餅まき)
建物の棟が上がり、上棟の段階になります。
家を建てる際に、骨組みが出来上がり、最後にその上の棟木を上げることを棟上げと言いますが、その棟上げの際に餅まきを行います。
餅まきは、棟上げが行われる上棟式の際に散餅の儀として、厄災を祓うとともに、
地域の方々への感謝と、皆さんに福を分けるという意味があると言われております。
ここでご近所さんとのつながりを築いておくこともできるので、家づくりの思い出にもなり、いい行事であると思います。
〇社内検査
お客様に立ち会っていただく前に社内で入念な検査を行い、
キズや不具合を確認しています。

以上のステップにより新築住宅の家づくりが行われております。
今回は「家づくりの流れ」についてお話いたしましたが、
新築住宅が完成するまでの流れが少しでも理解できましたでしょうか。
宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅をお考えの方、
家づくりに関してお悩み事などございましたら、お気軽にご相談ください。
いえとち本舗ならあなたに丁度いい新築住宅をご提供できます。
是非一度ご来店ください。
9月14日(土)~9月16日(月)イベント↓
アパート脱出大作戦&わくわくイベント同時開催!
関連記事
-

ベタ基礎・布基礎の違いとは?メリット・デメリット を把握して最適なものを選ぼう
家を建てるときはデザインや間取り、住宅設備などに目がいってしまいますよね。しかし、私たちが安全に暮らしていく家にするには建物の構造についてもっとよく知っておかなければいけません。家の土台となる基礎についてはどのくらいご存知でしょうか。家の基礎にも種類があり、それぞれ特徴があります。そこで、今回の記事では基礎の種類と特徴について、基礎の選び方などをご紹介していきたいと思います。 1 住宅の基礎とは?2 基礎の種類 3 基礎の種類を決める前に地盤調査を行うこと 4 結局布基礎とベタ基礎のどちらがいいの?基礎の決め方5 まとめ 住宅の基礎とは? 基礎とは建物の下に見えるコンクリートのところを指します。基礎は地面から少し下がったところから施工がされていて、建築基準法では根入れ深さ(地面から基礎の底盤までの深さ)が基礎の種類ごとに定められています。また、基礎底盤の厚さも建築基準法で定められています。※布基礎根入れ深さ:地面から240mm以上 ベタ基礎根入れ深さ:地面から120mm以上※布基礎底盤厚さ:地面から150mm以上 ベタ基礎底盤厚さ:地面から120mm以上 ただし、建築基準法が定める基準はあくまでも最低限の基準であって、実際には構造計算など様々な検証を行なって建物に適切な基礎をつくっていくことが大切です。 基礎の重要性と役割 基礎の役割は、建物の重さや外からの力(地震や風など)を地面に伝える役割があります。また、基礎があることで地面から上がってくる湿気を防いでいます。もし、基礎が弱く建物に適さないと基礎が沈下してしまったり、建物が傾いてしまったりする危険があります。いくら建物に強度があっても基礎が弱いと、このような危険が起こる可能性があるため、基礎は建物にとって重要な構造体となっています。 基礎の構造 基礎は主に鉄筋とコンクリートで構成がされています。昔の基礎は鉄筋を用いずにコンクリートのみで施工されていましたが、強度の問題で現在では鉄筋を入れた「鉄筋コンクリート造」の構造となっています。鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造の理由は、鉄筋とコンクリートの短所を補い、単体で使うよりも組み合わせることでさらに強度を得られるからです。 【鉄筋の長所と短所】鉄筋の長所:引張力に強い鉄筋の短所:熱に弱く錆びやすい 【コンクリートの長所と短所】コンクリートの長所:熱に強いコンクリートの短所:引張力に弱い コンクリートはアルカリ性ですから、鉄筋をコンクリートに包むことで酸化を防ぐことができます。そして、コンクリートの引張力の弱さを鉄筋が補ってくれる構造になっているのです。 基礎の種類 基礎の種類はいろいろありますが、住宅に用いられる基礎は主に布基礎とベタ基礎です。ここでは、住宅によく採用される基礎の種類と特徴についてお伝えしていきます。 布基礎の特徴 布基礎は住宅によく採用される一般的な基礎です。基礎構造は、基礎立ち上がり部分が連続して繋がるつくりとなっています。布基礎の立ち上がりの部分と基礎底盤(フーチング)で荷重を支えるため点荷重となる構造です。基礎底盤(フーチング)を広くすることで不動沈下を防ぐことができます。基礎内の地面は露出したままにする場合と薄いコンクリートを打設して湿気を防ぐ防湿コンクリートが設けられている場合があります。ベタ基礎よりも施工するボリュームが少なくなり建築コストを抑えられるメリットがあります。布基礎のデメリットとなるところはベタ基礎と比べて耐震性が劣るところです。布基礎は前述したように点荷重となる構造なため、ベタ基礎のように荷重が分散されません。ただし、必ずしも布基礎は地震に弱いといわけではなく基礎底盤(フーチング)を広くしたり、地盤を改良して強固なものにしたりするなど、耐震性を上げる対策はありますので、建物と基礎、地盤と全体的に耐震性を考えていくことが大切です。また、布基礎は地面から上がってくる湿気に弱く床下でこもってしまうデメリットもあります。湿気が多いとシロアリが寄ってくる原因となり被害を受けやすいため防蟻対策を行うことが大切です。 ベタ基礎の特徴 ベタ基礎は、現在の住宅の主流となっている基礎です。基礎構造は、基礎の立ち上がりと地面にコンクリートを打設してつくられている構造となっています。地面に打たれたコンクリートは床スラブとして見るため構造上の重要となる部分になります。基礎立ち上がりと床スラブの構成は、建物の荷重などの力を基礎全体へと分散させる効果があり、不動沈下が起こりにくい構造になっています。地面に打設されているコンクリートは、地面の湿気を防ぐことができ、木造住宅に多い虫害にも強い特徴があります。ただし、施工規模は布基礎よりも大きくなるため、建築コストは布基礎よりも高くなります。注意しておきたいことは、必ずしもベタ基礎だから地震には強いとは言いきれないことです。ベタ基礎が強固であるのはコンクリート内部に鉄筋が組まれているからであり、この鉄筋量で強度が大きく変わってくるからです。もし、鉄筋の量が少ないと思っていたよりも弱いということになってしまうので、家を建てる際は必ず基礎の構造と強度を確認しておくことです。 その他の住宅に用いられる基礎 住宅の主な基礎は上記でお伝えした布基礎とベタ基礎ですが、その他の基礎も住宅に用いられることがあります。下記の深基礎と高基礎は住宅によって採用されることがありますので、特徴をチェックしておきましょう。 【深基礎】高低差のある敷地や傾斜のある敷地など土留めが必要なときに、擁壁を兼ねて対応できるのが深基礎です。通常の基礎よりも深くに基礎をつくる構造となっています。擁壁を設ける必要がある場合や地下室を設ける場合に深基礎を用いることが多いです。建築コストは通常の基礎と比べて高くなります。 【高基礎】高基礎は、通常の基礎よりも立ち上がりを高くしてつくる基礎です。基礎の立ち上がりが高いことで、床と地盤面に空間ができて、通気性が良くなり湿気対策に有効となります。また、床下空間が広くなるため、床下にある配管類などのメンテナンス性も向上します。ただし、基礎の高さが上がるため、通常の基礎よりも地震に対して弱くなるリスクがあります。 基礎の種類を決める前に地盤調査を行うこと 基礎の種類を決めるときは、建物を建てる地盤の強度を調べることが必要になります。地盤の強度を表すのが地耐力です。地耐力は地盤がどのくらいの荷重に耐えられるかを数値で表します。地耐力の数値が基準値に満たない場合は、そのまま施工してしまうと家が重さで傾いてしまったり、倒れてしまったりしまいます。このようなことが起こらないように、地盤の強度がないと判断された場合は地盤改良を行なって地耐力を上げること必要です。基礎は地盤の地耐力に適合した基礎構造を採用することが建築基準法で定められています。 結局布基礎とベタ基礎のどちらがいいの?基礎の決め方 ベタ基礎と布基礎のどちらの基礎が優れているかというと、どの基礎もメリットとデメリットがあるため一概には言えません。そもそも布基礎もベタ基礎も構造自体が違い、荷重に対しての支え方や力の伝達の仕方も異なるため、強度の比較はあまり意味がないでしょう。ただし、ベタ基礎は地面にコンクリートを打設することで、床下空間に湿気が溜まらず乾燥状態を保つことができます。布基礎も防湿コンクリートを打設すれば湿気は防げますが、その分のコストも上がります。現在はベタ基礎が主流になってきて建築コストも以前より下がっている傾向にあります。木造住宅の天敵であるシロアリの対策にもなりますので、日本の気候風土を考慮するとベタ基礎を採用することをおすすめします。 コストはどちらの基礎が有利? ベタ基礎は鉄筋の配筋があり、コンクリートの打設量も多くなるため布基礎よりもコストが高くなります。コストを抑えたいという方には布基礎の方が有利に働くかもしれませんが、現在ではベタ基礎が主流となってきたため施工費用はそこまで大差がなくなりました。工事費用は地域や依頼する業者によって変わりますが、その差額は㎡あたり1,000円ほどで、30坪ほどの施工面積なら10万円ほど布基礎の方が安くなります。しかし、あくまでもこれは基礎のコストのみの比較ですから、地盤改良や建物の強度など全体を合わせた場合のトータルコストが変わらない、または高くつく可能性もあります。基礎の工程と工期の比較 基礎の工期は結論としてほぼ同じと見ていいでしょう。鉄筋の配筋やコンクリートの打設量などを見るとベタ基礎の方が施工手間や工事の日数が長くなると思われるかもしれませんが、そこまで日数の違いはありません。基礎工事の工程は下記のように進んでいきます。 自縄張り・やり方 根切り砕石敷き防湿シート敷設・捨てコンクリート打設鉄筋の配筋型枠設置基礎コンクリート打設 養生型枠ばらし 仕上げ完成「自縄・やり方」とは建物が建つ位置にロープなどを使って印をつける工程です。この工程で建物の外周の印をつけてから、基礎底板までの高さまで地面を掘削する「根切り」を行います。掘削した後は砕石を敷きランマーで転圧をして地耐力を確保します。次に地面からの湿気を防ぐために防湿シートの敷設と捨てコンクリートを打設します。ここから本格的な基礎工事が始まり、まずは鉄筋を組んでいき、床スラブ用の型枠の設置とコンクリートの打設。次に基礎立ち上がりの型枠を設置してコンクリートを打設していきます。コンクリート打設後は強度がでるまで養生してから型枠を外し、最後に基礎のバリ取りや仕上げモルタルを塗って完成となります。耐震性 各基礎の特徴でも挙げましたが、耐震性はベタ基礎の方が優れています。これは布基礎の点荷重と比較して、ベタ基礎は床スラブがあるため荷重が分散され負担が少ないからです。荷重が分散されるというのがどういう仕組みかというと、布基礎とベタ基礎は地盤と基礎との接地面積の大きさに違いがあり、ベタ基礎の方が地盤と接している面積が大きくなります。荷重が分散される理由は、この地盤の接している面積が大きいためで、布基礎は接地面積が小さいため接地圧が大きくなります。反対に接地面積の大きいベタ基礎は接地圧が小さくなりますので、その分、力が分散され地震に強いと言われています。しかし、前述したように布基礎でも耐震性を上げる対策はありますので、地盤と基礎、建物の総合的な強度で判断することが大切です。シロアリ対策となるのはベタ基礎 シロアリは湿気の多いところを好み、木を餌にするため木造住宅にとってシロアリは天敵です。シロアリを寄せ付けないためには水気をなくし、湿気をこもらせない工夫が必要であり、その点で言うとベタ基礎は地面にコンクリートを打っているため、湿気が上がってこず乾燥状態を保ちやすいので、シロアリ被害にあいにくい構造となっています。布基礎は地面が露出しているケースが多く、防湿コンクリートが打たれていても厚みがないため湿気が上がってきてしまうこともあります。多湿な土地というのもありますので、こういったところに家を建てる場合は布基礎よりもベタ基礎の方が適し、また、布基礎を採用するとしても、しっかり防蟻対策をとっていることが重要です。寒冷地の場合は布基礎の方が適している 寒冷地の場合は、地面の凍結による影響を考慮して布基礎の方が適しているとされています。寒冷地のように気温の低い地域は土が凍結し膨張するため、その範囲に基礎があると歪みが生じる恐れがあります。この土が凍結する範囲を凍結震度といい、土の凍結により基礎が膨張しないように寒冷地では基礎底板を凍結深度よりも深くに設けなければいけません。このことより通常の根入れ深さよりも深く掘らなければいけない寒冷地では、ベタ基礎だと掘削量が多くなり残土も増えるため処分費が高くなります。また、ベタ基礎の床スラブが歪んでしなう恐れもあります。凍結深度は建築基準法40条に基づき、地方公共団体が定める条例があるため、寒冷地の建設を計画されている方は役所や検査機関などに確認しましょう。まとめ 住宅で用いられる基礎の種類は、布基礎とベタ基礎が主流です。どちらの基礎が優れているかというと、家を建てる地盤の強度と建物の荷重によって適切な基礎が変わります。基礎の種類を検討するときは地盤の強度を把握しておくことが大切ですから、必ず地盤調査を行っておきましょう。また、木造住宅を建てる方は、虫害の対策をすることも大事です。特に木造住宅にとってシロアリは天敵です。シロアリなどの虫害の要因には湿気がありますので、乾燥状態を保てられるベタ基礎はとても効果的でおすすめの基礎になります。家づくりについてどうしたらいいかわからないという方は、まず情報収集するといいでしょう。いえとち本舗は家づくりについてわかる資料を無料で提供しています。もし、興味がありましたら、ぜひご利用ください。資料請求はこちら
-

注文住宅を建てるのなら覚えておいた方がいい建築用語
住宅を建てるときはたくさんの聞き慣れない建築用語を聞くことになります。少し難しいと感じるかもしれませんが、家を建てる時はどれも大切な用語です。今回は注文住宅に関係する建築用語をまとめましたのでご紹介します。 土地・敷地・建物の法規制建築用語いろいろな面積面積といっても建築には複数の面積が存在します。一つずつ要点のみをお伝えしますのでチェックしておきましょう。 敷地面積文字通り敷地面積は建物を建てる土地の面積のことを言います。建築では㎡(平方メートル)で表すのが一般的ですが、不動産の場合だと坪で表していることもあります。1坪は約3.3㎡で畳2畳分の大きさです。 建築面積建築面積は建物の大きさを表す水平投影面積です。水平投影面積とは建物を上から見下ろした時の大きさのことで、建物の外周の大きさ表します。 延床面積延床面積(のべゆかめんせき)は、建物各階の床面積を合計した面積のことです。建築基準法ではピロティやポーチ、吹き抜け、バルコニー、ロフトなど床面積に含まれないものもあります。 建物の大きさに関する用語建物の大きさは法律により制約があります。注文住宅の設計事によく出てくる言葉ですし、建物の大きさや間取りに関係してくるので覚えておきましょう。 建ぺい率建ぺい率とは敷地面積に対して建ててもいい建物の大きさを指定する割合のことです。敷地には建ぺい率という数値が決められており、敷地面積を建ぺい率で乗じた数値がその敷地で建ててもいい建築面積になります。例えば敷地面積100㎡に対して建ぺい率が50%の制限があると100㎡×50%=50㎡となりその敷地では50㎡までの建築面積を持った建物が建てられるということです。 容積率容積率は建物の延床面積を制限する数値のことです。建ぺい率と同様に敷地には容積率が指定されており、延床面積を敷地面積で割ってパーセントに計算し直した数値が容積率となります。例えば容積率200%、敷地面積100㎡とした場合は下記の計算で延床面積がでます。X㎡(延床面積)÷100㎡(敷地面積)×100=200(容積率)X㎡=200㎡容積率200%、敷地面積100㎡の条件なら延床面積200㎡までの家なら建ててもいいということになります。 住宅を建てる法規制の用語住宅には様々な法規制があり、建物の形や大きさ、サッシや外壁などの仕様にも関係してきます。ここでは代表的な法規制の用語をご紹介します。 二項道路とセットバック二項道路とは敷地に接する道路の幅が4m未満の道路で、特定行政庁に指定される建築基準法上道路とみなした道路のことです。二項道路に接する敷地は、道路中心線から2m以上離した場所に建物を建てなければいけません。2m以上離す(正しくは道路境界線を2m以上後退させる)ことをセットバック(後退)と言います。 用途地域用途地域は地域ごとに建てられる建物の用途や高さを指定する法規です。分類は12種類あり、住宅に関する用途地域は7種類あります。 防火地域・準防火地域防火地域と準防火地域とは火災の危険を防ぐために火災に抵抗できる建物にする制約を定めた地域区分のことです。制約がきつくなるのは防火地域、その後に準防火地域となります。防火地域と準防火地域には延床面積、建物の高さ、不燃材などを使用し、耐火建築物にするなどの制約があります。 建物の構造・工法・性能・設計時の建築用語建物構造に関する用語住宅の建物構造の基本は木造軸組工法と2×4工法、鉄骨造、RC造の4種類あります。ここでは普及率の高い木造住宅の構造と基礎について要点をお伝えします。 木造軸組工法土台、柱、梁で構成される骨組み構造が木造軸組工法です。在来工法とも呼ばれて、日本で最も採用されている工法です。骨組み構造のため間取りの自由度やメンテナンス性に優れ、コストも抑えられる工法です。 2×4工法(木造枠組壁工法)アメリカで生まれた耐力壁と剛床を一体化させて箱型構造で構成するのが2×4(ツーバイフォー)工法です。2×4と呼ばれる所以は主要な部分が2インチ×4インチの規格品の構造部材で構成されるからです。耐力壁と剛床で構成する箱型のため地震の水平力に強く耐震性に優れます。 基礎に関係する用語住宅で採用される基礎の種類は布基礎とベタ基礎です。布基礎は建物の柱や土台、壁がのるところに鉄筋を組んだコンクリートを立ち上がらせてつくる基礎です。ベタ基礎は鉄筋を組んだコンクリートを立ち上がりの部分と水平な床な部分とで一体化させてつくる構造となっています。 建物の性能に関する用語住宅の性能でよくでてくるのが断熱性と気密性、耐震性です。家を建てるのに重視しておきたい性能ですのでどんな意味なのかチェックしておきましょう。 断熱性断熱性は熱の移動のしにくさを表す性能です。断熱性能は熱伝導率(熱の伝わりやすさ)で表すことができ、値が小さいほど断熱性能が高いことを示しています。 気密性気密性は建物の密閉性を表す性能です。建物の隙間を減らし空気の流動を抑えることで省エネルギー性と断熱性の低下を防ぐことができます。 耐震性耐震性は地震による力に対して建物が耐える強度のことを言います。耐震性の高い建物ほど地震に強く、地震大国である日本では不可欠と言ってもいい重要な性能です。 間取り設計に関する用語間取り設計は建築用語を耳にする機会が多くなる場面です。間取りに関わる建築用語をまとめましたので一つずつチェックしておきましょう。 メーターモジュールと尺モジュール建築の幅や長さを表す方法はメーターモジュールと尺モジュールがあります。メーターモジュールはメートルで表すもので1グリッド1mを基準値としています。尺モジュールは、日本で使われる尺貫法であり、1グリッド910mm(3尺)を基本とし、9尺(1,820mm)は1間(けん)と言います。モジュールの違いは廊下幅や部屋の大きさに大きく影響します。 動線動線とは家の中で人が通る経路を線で表したものです。間取りをつくるときは動線を考えることで、家事などの作業を効率よくできる設計ができます。 開口部・間口・外構【開口部】窓や玄関、採光、通風などの目的で壁や天井、床の一部が解放された部分を言います。【間口】対象物の幅や奥行きを表す言葉です。システムキッチンの幅を間口で表記されていることが多いです。【建具】開口部に設けられた扉や窓、引き戸、障子、襖などを言います。【外構】外構とは建物の外にある構造物全体を表す用語で、アプローチ、土間、塀、門扉、フェンス、カーポート、庭木、物置なども含みます。 まとめ建築用語を知っていると家づくりの打ち合わせもスムーズにすすませることができます。今回ご紹介した建築用語以外にもまだまだたくさんありますので、もし知らない建築用語がでてきたら担当者にどんな意味か聞いておきましょう。いえとち本舗は家づくりをサポートする資料を無料で提供しています。家づくりの最初のステップとして役立つ情報を掲載していますので、ぜひご参考ください。資料請求のページはこちらからご覧にいただけます。
-

外壁の色でよくある5つの失敗例とは?成功ポイントもご紹介!
外壁の色は家のイメージを左右する大事なポイントです。失敗せずに見栄えのいい外壁に仕上げるにはどうすれば良いか、家を建てる誰しもが悩むポイントでしょう。この記事では外壁の色選びでありがちな失敗例と原因を解説しています。失敗から学ぶことで立派な家づくりへと近づくことができます。さらに成功するためのポイントや人気の外壁の色も紹介していますので、外壁の色選びでお悩みの方はぜひ参考にしてください。外壁の色選びでよくある5つの失敗とは外壁の色は家のイメージにつながりますので、極力失敗はさけたいものです。しかし、こだわって外壁の色を選ぶあまり失敗してしまう例もいくつかあります。 ここでは外壁の色選びでよくある失敗例とその原因を解説していきます。失敗例から学ぶことで同じ道を歩まないよう、事前に備えておきましょう。 イメージと違う色になってしまった最も多い失敗例がイメージと違う色に仕上がってしまうことです。カタログで見る色と実際に外壁に塗られた色がイメージよりも濃かったり違って見えてしまうのです。 カタログだけで色を決めてしまうのではなく、実物も見て決めるようにしましょう。実際に建っている家の仕上がりを見たり、色見本を太陽光や外壁にあててみたりするなどしてできるだけ現物に近い環境で確認することが肝心です。 汚れが目立つ色を選んでしまった外壁の色の中には汚れが目立ちやすい色があります。外壁は常に雨風やほこりにさらされているので想像しているよりもはるかに汚れが付きやすいのです。 一番いい方法としては汚れが目立つ色を選ばないことですが、どうしても選びたい場合は汚れが目立つ色の面積比を少なくすることで極力汚れを目立たせなくすることができます。 外壁の色によってはこまめな手入れをしないとすぐに汚れてしまうことを念頭において外壁の色選びを行いましょう。 玄関ドアや屋根との色合いが悪い外壁のイメージを決めるのは壁だけではありません。玄関ドアや屋根、窓など総合的に見てイメージが決まります。外壁だけで見れば綺麗な色合いでも全体的にみるとバランスが崩れ、見栄えが悪くなることがあるのです。 玄関ドアや窓のサッシ、特に屋根は面性が広いので外壁とのバランスが重要になります。デザインや質感を考慮してバランスの良い外壁の色を決めていきましょう。 派手な色で近所からクレームがくる赤や青などの原色系の色を多く取り入れると外壁としては目立ちやすい色になりますので、近所の方から目立ちすぎるとクレームが入る可能性があります。 個性を出したい、家を建てるならこの色がいいなどこだわりがあったとしても、クレームによって住み辛くなってしまっては意味がありません。 周りの家の雰囲気を考慮し、目立ちすぎないような色合いにするか原色の使用比率を抑えるなどして対応しましょう。 景観ガイドラインに違反してしまう市区町村によっては街の景観保護のために「景観ガイドライン」が定められている場合があります。歴史的建築物の多い地域などでよく見られ、外壁に使う色が限定されている場合があるのです。 景観ガイドラインを無視して家を建てることはできません。外壁の色を景観ガイドラインに沿って決め直すか、景観ガイドラインが定められていない地域に家を建てるか検討をしましょう。 外壁の色選びで成功する5つのポイント外壁の色選びが成功するポイントを抑えて実践することで、外壁の仕上がりが想像以上になる可能性があります。外壁は家のイメージを左右するといっても過言ではありませんので、できるだけ成功できるように事前に確認していきましょう。 色単体ではなく全体をイメージする外壁のイメージを構成するのは外壁の色もちろん、窓のサッシや屋根、玄関ドアとの色合いも関係してきます。 つい色同士の組み合わせやイメージだけで決めてしまいがちですが、実際に外壁に落とし込んだ時に全体をイメージしていないため、想像と大きく違ってしまうケースがよくみられます。 かならず家全体をイメージして、外壁の色の組み合わせを考えるようにしましょう。 言葉でうまく表現できない時は画像検索をする家のイメージはモダンやエレガント、フォーマルなど多種多様にあります。イメージだけ先に決まっていて肝心の具体的な外壁の色がわからない、という場合は多々あります。 見本色を見てなんとなくで決めてしまうのではなく、インターネットで画像検索をしてサンプルを確認するようにしましょう。実際の画像を見ることでイメージの言語化もしやすくなり、施工業者や塗装業者に具体的にイメージを伝えることができます。 ツヤの加減を考慮する外壁の色のイメージはツヤの具合でも大きく変わります。外壁のツヤの具合は以下の4つから選ぶことになります。 ツヤなし三分五分七分 施工当日に塗装業者が直接ツヤの調節をするのではなく、メーカーが製造する時点で決まっているので注意が必要です。ツヤの加減を確認する場合は晴れた日に日が当たるところで確認しましょう。 汚れにくい色や変色しにくい色を選ぶ日頃のケアが必要なくなるわけではありませんが、汚れが目立ちにくい色や変色しにくい色を選ぶことで、できるだけ劣化を防ぐことができます。 雨風やほこりから外壁を完全に守ることは不可能ですが、グレーや茶色などの色は汚れが目立ちにくくメンテナンスも楽です。個性も大事ですが、管理面も同時に気を配ってみましょう。 色の組み合わせを2~3色にする外壁に使う色は最大でも3色に抑えることでまとまりのある印象を持たせることができます。これ以上多くなるとばらばらとした、落ち着きのない印象になりがちです。 ツートンカラーにする場合は同系色か、同じような薄さの色を採用しましょう。ベースカラーとアソートカラーを決め、6:4か7:3の比率になるように配色するとバランス落ち着きのある雰囲気を持たせることができます。 人気の外壁の色3選外壁の色を選ぶ上で無難な色とはいったい何色でしょうか。ここでは人気の外壁の色を紹介していきますのでぜひ参考にしてください。 人気の理由は汚れが目立ちにくい・雰囲気が落ち着いている・清潔感があるなど外壁が持ち合わせるべき印象・機能を持ち合わせたものばかりです。 グレーグレーは汚れが目立たずシックな印象を持たせられる人気ナンバーワンの色です。周りの家との調和も取りやすく景観を壊すことがほぼありません。 落ち着きのある大人な印象を持たせられるので外壁の色選びに迷ったのであれば、無難にグレーを選ぶことをおすすめします。 茶色茶色もグレーと同じく、汚れが目立ちにくく周りとの調和が取りやすい色です。グレーよりも温かみのある印象を持たせられるのが特徴です。 タイル張りやレンガ調の家にはうってつけの色ですので、外壁をサイディングでタイル張りやレンガ調にしたい方に特におすすめです。 白白は周囲との調和を持たせながら清潔感を感じさせる印象が特徴的です。玄関ドアやサッシとの相性も良く、風水的にも幸せな家庭を築ける効果が見込めるなどメリットばかりです。 しかし、グレーや茶色と違い汚れがかなり目立ちやすいので管理が大変です。外壁の色として採用する場合は管理面の難しさを考慮しましょう。 まとめ外壁の色はなんとなくや好みだけで決めるのではなく、全体のバランスや周りの家との調和を考えて慎重に選択するようにしましょう。 自分で外壁の色を決めるのも楽しみの一つですが、プロの意見を取り入れながら決めていくことで思わぬ失敗を避けることができます。 いえとち本舗の会員なら家づくりのお得情報や限定施工事例が見放題です。無料で会員登録できますので、お家のことでお悩みの方はぜひいえとち本舗に登録してみましょう。









