ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
独自の進化を遂げた山口県のいえとち本舗 ― 池田建設が描く“地域最適”の家づくり
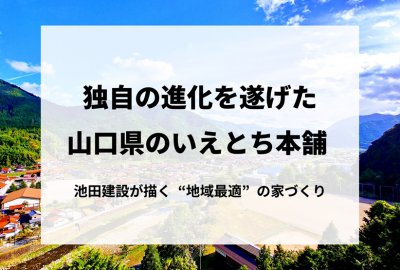
コラム

1. 「いえとち本舗」とは?全国ブランドの理念と強み
いえとち本舗は、「土地と建物をまとめて提案する」という独自の仕組みで全国に広がった住宅ブランドです。家を建てたいと思っても、土地探しと建物計画を別々に進めるのは時間も手間もかかります。いえとち本舗はその課題を解決するため、ワンストップで“理想の土地に、理想の家を”実現できる体制を整えました。
さらに、仕入れ・設計・施工の各工程を効率化することで、“わかりやすい価格設定”と“安定した品質”を両立。全国の加盟企業が共通の基準をもとに運営するため、どの地域でも一定のクオリティを保ちながら、マイホームを手の届く価格で提供できる点が支持されています。
このように、全国ブランドとして培ってきたノウハウは、いえとち本舗の根幹をなす強みとなっています。
1-2. 全国モデルから発展した山口オリジナルの家づくり
全国のいえとち本舗では、どの地域でも安定した品質を提供できるよう、共通仕様のベーシックモデルが展開されています。たとえば「シンプリエ」シリーズのように、コストパフォーマンスを重視した合理的な住宅がその代表です。
一方、株式会社池田建設が展開する山口のいえとち本舗は、そうした全国モデルの仕組みを土台としながらも、地域の気候・土地事情・平屋志向に合わせて独自に発展したスタイルを確立しています。 全国共通の設計をそのまま採用するのではなく、山口の暮らしに最適化したオリジナルモデル(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を自社で開発。
これにより、「同じいえとち本舗でありながら、より地域に根ざした家づくり」を実現しています。これは単に商品を変えたというよりも、「山口の暮らしに最適な住宅を自社で設計し、責任を持って提供する」という考え方の表れです。つまり、同じ“いえとち本舗”であっても、池田建設では地域性を軸にした独自の発展を遂げているのです。
2. 山口で深化した「池田建設のいえとち本舗」
2-1. 地域の暮らしを知る池田建設のものづくり
山口県はいえとち本舗の中でも、新築住宅の需要が非常に高い地域です。一方で、理想の住まいを建てたくても「土地が見つからない」「希望のエリアに空きがない」という悩みを抱える人も少なくありません。そうした背景から、土地探しと家づくりを一体で考える提案力が、山口での家づくりには欠かせない要素となっています。
また、山口県では全国的に見ても平屋住宅の人気が際立っており、若い世代からシニア層まで“ワンフロアで完結する暮らし”を求める声が多くあります。株式会社池田建設が展開する山口のいえとち本舗は、この地域特性を的確に捉え、限られた土地を最大限に活かす平屋設計のノウハウを磨いてきました。
創業以来70年以上にわたり地元の土地・気候・生活習慣を熟知してきた同社だからこそ、「土地の選び方」「建物の配置」「光と風の通し方」まで、“暮らしやすさ”を中心に据えた提案ができます。単に家を建てるのではなく、“土地から暮らしをデザインする”――それが、株式会社池田建設が手がける山口のいえとち本舗の家づくりです。
2-2. 全棟G2仕様という高性能化へのこだわり
池田建設のいえとち本舗が評価される最大の理由のひとつが、「全棟G2仕様+耐震等級3」という確かな性能です。
G2仕様とは、国の省エネ基準を大きく上回る断熱性能(断熱等級6相当)を意味し、冬でも室内の温度差が少なく、年間を通じて快適に暮らせる水準です。
冷暖房効率が高く、光熱費を抑えながら快適さを維持できるため、実際の生活コストにも直結します。
さらに、すべての建物で許容応力度計算による耐震等級3を標準採用。これは建築基準法で定める耐震性能の最高ランクであり、災害時でも家族の安全を守るための基準です。多くの住宅会社が“等級3相当”と表現する中で、池田建設は全棟で構造計算を実施し、確実に等級3を取得している点が大きな違いです。
また、Kダンパー(制震ダンパー)を採用することで、地震の揺れを吸収・分散し、建物へのダメージを軽減。繰り返しの揺れにも強く、長期にわたって構造体の耐久性を維持します。断熱には現場発泡ウレタン吹付断熱を採用し、細部まで気密性を高めることで、G2仕様の性能を最大限に発揮。これにより、「高断熱×高気密×高耐震+制震」という4要素がすべて標準で備わる仕様となっています。
“性能はオプションではなく標準であるべき”――。この考えを貫く姿勢こそが、池田建設のいえとち本舗が多くの施主から信頼される理由といえるでしょう。
2-3. 独自ブランド「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」
池田建設のいえとち本舗では、山口の暮らしに合わせて開発した3つのオリジナルブランドを展開しています。すべてのシリーズでG2仕様(断熱等級6)を標準採用し、性能の高さを前提に“暮らし方の違い”に合わせた提案を行っているのが特徴です。
まず「イエスタ」は、間取りを考える手間を省きたい方や、設計をプロに任せて効率よく家づくりを進めたい方におすすめのシリーズです。設計士が生活動線や収納、採光バランスを考え抜いた完成度の高いプランで、コストを抑えて建てられるため、初めての家づくりをする若い世帯や、予算を重視する方にも適しています。特に平屋需要の高い山口では、シンプルかつ洗練されたプランが幅広い層に支持されています。
次に「イエミライ」は、太陽光発電+蓄電池+HEMS(エネルギー管理システム)を標準搭載したスマート住宅。G2仕様の断熱性能を活かしながら、創る・蓄える・賢く使うエネルギーの自給循環を実現。停電時にも安心して暮らせる、次世代型の省エネ住宅として高く評価されています。「エネルギーを自給自足したい」「将来の電気代上昇や災害に備えたい」と考える未来志向の顧客層に支持されています。
そして「イエテラス」は、G2仕様を基盤としながらも、デザイン性と価格のバランスを重視する方に最適なシリーズ。屋内外をつなぐテラス空間や、自然光を取り込み、性能とデザインの両立を楽しむ設計が特徴です。「性能にもこだわりたいけれど、デザインも妥協したくない」というバランス志向の層から選ばれています。
これらの3シリーズはすべて、池田建設が自社で開発・管理する地域専用ブランドとしてそれぞれ明確なコンセプトとターゲットを持ち、どんな世代・ライフスタイルにも応えられる構成となっています。全国モデルの“量産”ではなく、山口の土地・気候・ライフスタイルに最適化された“質の提案”として展開されています。
3. 全国モデルとの違いが生む“地域最適化”の価値
3-1. 性能の底上げと暮らしの最適化
全国のいえとち本舗が“コストパフォーマンスの高さ”を軸に展開しているのに対し、池田建設のいえとち本舗はコストパフォーマンスに加えて「性能を起点にした家づくり」を徹底しています。全棟でG2仕様・耐震等級3を標準採用することで、単に“建てやすい価格”ではなく、“住み心地の質”を標準化した家づくりを実現しています。
これにより、冬場の室温ムラや夏場の熱こもりが少なく、日々の冷暖房費を抑えながら快適に暮らせる住宅が当たり前になります。また、山口特有の“平屋志向”や“限られた土地条件”にも柔軟に対応。断熱・耐震・換気といった基本性能の底上げを前提に、敷地条件や家族構成に合わせた最適な間取りを提案できる点は、全国モデルにはない大きな強みです。
性能値を高めるだけでなく、その性能を地域の暮らしにどう活かすかまで設計に落とし込む――この姿勢こそが、池田建設が選ばれる理由です。
3-2. 「取り扱う商品を選ぶ」という品質思想
Point.
池田建設はいえとち本舗の理念を共有しながらも、すべての商品を扱うわけではありません。例えば全国的に展開されている「シンプリエ」シリーズは、コスト面で魅力がある一方で、山口の気候や居住ニーズとは異なる設計思想を持つため、同社ではあえて採用していません。
これは“取り扱わない”のではなく、“地域に最も適した品質だけを提供する”という判断です。
代わりに、独自開発のG2仕様シリーズ(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を中心に展開。「選択と集中」によって、性能・コスト・デザインのバランスを地域基準で最適化しています。全国統一ではなく、山口基準での“ベストクオリティ”を追求する姿勢が、同社の品質哲学として根付いています。
3-3. デザイン・価格・サポートの三位一体提案
池田建設のいえとち本舗は、デザイン性・価格・サポートを三位一体で提案する体制を整えています。デザイン面では、間取りや外観だけでなく、採光計画や通風シミュレーションまでを考慮した「体感的な快適さ」を重視。価格面では、性能を高めつつも月々3万円台から実現できるよう、施工効率とエネルギーコスト削減の両面でコストバランスを追求しています。
さらに、過度なメディア露出や外注に依存せず、資料・チラシ・Webなど多くの広告物を自社で企画・制作。その分のコストを住宅の性能・設備・アフターサポートに再投資することで、価格を抑えながら品質を維持しています。
「見せ方より中身を磨く」――この地に足のついたブランド戦略が、長期の満足度につながっています。
また、地域密着の強みを活かし、建てた後の暮らしを支えるサポート体制も充実。定期点検やメンテナンス、蓄電池の追加・改修提案など、住まいを“長く良い状態に保つ”ための伴走を行います。建てる前も、建てた後も、安心して任せられる――総合的な安心感が“地域最適化ブランド”としての価値を高めています。
4. 山口のいえとち本舗が選ばれる理由
4-1. 気候・地形・習慣に合わせた住宅設計
山口県は、瀬戸内海と日本海の両側に面し、エリアごとに日射・風向・湿度の条件が大きく異なる地域です。沿岸部は潮風や湿気、内陸部では冬の冷え込みが強く、地域によって理想的な家の形が違います。池田建設のいえとち本舗では、こうした地域特性を丁寧に読み取り、地形・方角・風の通り方を考慮した設計を一邸ごとに行っています。
また、山口では昔から「家族が集まる広いリビング」「来客を気にせず過ごせる平屋」へのニーズが高く、同社はその生活文化を反映した現代的な平屋デザインを数多く手がけています。性能値やデザインを“全国共通の基準”で押し付けるのではなく、山口で暮らすための最適解を導き出す設計力――それが、池田建設のいえとち本舗が信頼される理由です。
4-2. 県内全域をカバーする店舗ネットワーク
池田建設のいえとち本舗は、山口県内6拠点(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)を中心に展開しています。それぞれの店舗が地域密着で運営され、土地情報・施工事例・お客様の声を常に共有。「家を建てたいけれど、どのエリアが暮らしやすいか分からない」といった初期段階の相談から、建築・アフターまでをワンストップで支援できる体制が整っています。
また、各店舗には経験豊富なスタッフが常駐しており、家づくりが初めての方にも分かりやすく丁寧な対応を徹底。こうした“地域の顔が見える運営”が、全国モデルにはない安心感を生み出しています。
4-3. 建てた後も寄り添う地域密着サポート
池田建設のいえとち本舗が特に重視しているのが、「建てた後の安心」です。完成引き渡し後も、定期点検やアフターメンテナンスを自社で実施し、施工からアフターまでを一貫して責任を持つ体制を維持しています。時代の変化に合わせて太陽光や蓄電池の増設、断熱性能の見直しなど、“住まいのアップデート”を提案できる地域パートナーとしても機能しています。
地元企業だからこそ、住まいの状態や家族のライフステージの変化を継続的に見守ることができる――。この“地域で完結する家づくり”の安心感が、多くのOB施主から高い信頼を得ている理由です。
5. まとめ ― 全国ブランドの枠を超えた、山口発の住宅ブランドへ
5-1. 全国ブランドの枠を超える“地域版アップグレード”
いえとち本舗は、全国で“土地と建物をセットで提案する”という画期的な仕組みを築き上げ、多くの人に「マイホームをより身近にする」きっかけを与えてきました。その理念を受け継ぎながら、池田建設のいえとち本舗は独自の進化を遂げています。
土地不足が課題となる山口県で、最適な土地を提案し、平屋を中心に暮らしやすさを追求した設計とG2仕様・耐震等級3を標準化。さらに、地域の気候・文化・生活リズムに合った自社開発ブランド(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を展開することで、全国モデルにはない“山口版アップグレード”を実現しています。
全国ブランドの安心感と、地域企業の柔軟な対応力を両立させた存在――それが池田建設のいえとち本舗です。
5-2. 山口の暮らしに寄り添う、これからの家づくりへ
家づくりは、単に建物をつくることではなく、その土地でどう暮らしていくかをデザインする行為です。池田建設のいえとち本舗は、山口という地域で暮らす人々の価値観や生活スタイルを丁寧に汲み取り、性能・価格・デザインのすべてを“ちょうどいい”バランスで提案してきました。
全国のいえとち本舗が築いてきた信頼を背景にしながらも、地域に合わせて進化し続ける――その姿勢こそが、池田建設の強みです。これからも同社は、山口の人々が“無理なく、永く、快適に”暮らせる住まいを提供し続けていくでしょう。
「山口で建てるなら、山口を知る会社へ。」その言葉を体現する存在として、池田建設のいえとち本舗はこれからも地域の未来をつくり続けます。
6. FAQ
Q1. 山口県のいえとち本舗と全国の違いは?
全国のいえとち本舗は共通仕様の商品ラインを展開していますが、株式会社池田建設が運営する山口のいえとち本舗では、それらの本部商品は取り扱っていません。
代わりに、山口の気候・土地事情・平屋需要に合わせて独自に開発した「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」という3ブランドを展開。全棟G2仕様・耐震等級3を標準化し、地域に最適化された“山口版のいえとち本舗”として進化しています。
Q2. 高性能なのに価格を抑えられる理由は?
広告や外注を最小限にし、資料やチラシ、Web制作まで自社で行うことでコストを削減。その分を性能やアフター体制に還元しています。過度な宣伝よりも、品質とお客様満足に投資する方針です。
Q3. G2仕様とはどのような性能ですか?
G2仕様は、国の省エネ基準を上回る断熱等級6相当の性能です。冷暖房効率が高く、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちます。池田建設のいえとち本舗では全シリーズで標準採用しています。
Q4. 平屋を希望していますが、対応できますか?
はい。山口県は平屋人気が特に高く、池田建設では限られた土地を有効活用できる平屋設計を多数ご用意しています。間取り・採光・収納計画までワンフロアで完結する快適な住まいをご提案します。
Q5. 見学や相談はどこでできますか?
山口県内の6店舗(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)で随時ご相談を承っています。
ご予約は公式サイト(https://smarthouse-yamaguchi.jp/)からお気軽にお申し込みください。
関連記事
-

リビングを広く見せる工夫【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です。 本日の投稿では、山口県の山口市・防府市・宇部市・周南市・山陽小野田市で新築住宅の購入をお考えのお客様に、「リビングを広く見せる工夫」についてお伝えします。 ~リビングを広く見せて、リラックスできる空間へ~ リビングを見て、「最初はもっと広かったはずなのに…!」と感じたことはありませんか?リビングの面積自体はそれほど狭くない場合も、なんだかんだ家族みんなが集まるリビングが狭く感じてしまうこともありますよね。同じ坪数のお家でも間取りやインテリアの配置によって、広いと感じるお家、または窮屈だと感じるお家があると思われます。 そこで、「広いリビングにしたい!」「居心地の良い空間を作りたい!」とお考えの方に空間を広く見せる工夫をご紹介していきます。ヾ(○・ω・)ノ☆ ■本当に必要な家具を選ぶ インテリアの配置を考える前に、まずは、リビングに必要なモノを考えてみましょう。インテリアを選ぶ際、リビングにはソファを、ダイニングにはダイニングテーブルを選ぶ方も多いと思われます。ですが、これをどちらか一方だけにするという考え方も大事です。ここで一旦、あなた自身のライフスタイルを思い返してみて下さい。ダイニングテーブルはあるけど、食事はローテーブルで食べているということはないでしょうか?実は、私の家でもそうでした(;^_^Aお恥ずかしながら基本、ダイニングテーブルは物置になっていた記憶があります。 その他にも、ソファ、テーブル、ラグ、棚 など無駄だと感じたら一度リビングから取り除いてみることも良いかもしれません。そして、一度リビングが広くなってから、徐々に必要なモノを増やしていくと良いと思われます。 ■インテリアの配置 インテリアの配置換えは意外と簡単にできるものですよね。模様替えをすると気分もリフレッシュできると思います♪ 1か所にまとめて広い床面をつくる歩く途中に、ソファの肘置きや棚などがあると、狭く感じると思います。ドアへ続く通路、ソファからテレビに移動するまでの通路など余白を多く取って、動きやすくすることも大事です。 動線に家具を置かないソファや棚を壁際に寄せるなどして動線に家具を置かないこともリビングを広く見せるためのコツの1つです。ソファの背もたれ、収納の使わない部分を壁際に持っていくだけで、無駄なスペースも減り、自然と空間が生まれると思われます。 ロータイプで広々空間をつくる壁にモノを飾る場合や、飾り棚のスペースをとる場合、通常の目線の高さよりも少し低めのインテリアを取り入れると良いと思われます。背の高いインテリアは、圧迫感があり、少し重たい空気を生み出してしまいます。視界の邪魔にならずスッキリとした印象を持たせるグッズとして、例えば・ローテーブル・ローソファ・座椅子・ビーズクッションなどがあります。 絵や壁の飾り棚も、少し大きくスペースを取りたい場合、通常の目線の高さよりも少しずらすと、壁の色が遮られず、狭くなったと感じられないようになります。下にはすでにテレビなどの物があるので、そこから少し離して、今度は首を上に向けないと見えない場所に壁の棚を設置すると、すっきり見えます。■色や光の効果実は、リビングが広く見えるか、窮屈に見えるかということは、色や光にも関係してきます。 例えば、暑く感じる部屋を青色の心理効果で涼しく見せるなど、色で感じ方が変わりますよね。このように色の特性をいかして狭い部屋を広く見せることができます。 白やパステルカラーは「膨張色」と言い、空間を広く感じさせてくれますが、反対に黒やこげ茶などのダークカラーは、全体的に引き締まって見え、インテリアに多く利用すると、圧迫感があり、部屋が狭く見えることがあります。なので、黒などのダークカラーはポイントとして使い、白の割合を多くすると部屋が広く感じられます。 ■色づかいで工夫するまずは、部屋の中で面積の大きい床・壁・天井の色についてです。横に広く見えるだけでなく、高さもあるとより開放感を得ることができます。とは言ったものの、今住んでいる家の床・壁・天井を替えることは容易くないですよね。ここで使えるのが、色の効果です。できれば、同系色で色の「明るさ」を床・壁・天井の順に、下から上に上げていくと天井が高く広く見えるように感じます。 そして、ソファ・ラグ・カーテンも大きな面積をとるので、部屋の雰囲気を左右させるアイテムですので、やはり明るい色を選んだ部屋が広々としています。例えばカーテンですが、カーテンをしめている時でも部屋をすっきりと見せたい時は薄めの色のカーテンを、あまり広く感じても寂しいかもしれないというときには濃い目の色のカーテンを選ぶようにしたらいいかもしれません。 また、窓からの光も大切です。リビングに大きい窓があるお家は多いと思われます。その大きな窓から入ってくる光を遮らないように、窓の前には極力、物を置かない方が良いでしょう。少しでも窓との空間をあけることで明るい光が入り込み、部屋を広く見せることができます。インテリアの配置でも家具を端に寄せることをオススメいたしましたが、どうしても窓の前にものを置きたい場合も、窓の真ん中は避けて、端のほうに置くようにすると良いでしょう。 ■いつも整理整頓を心がける!ここまで家具選び、インテリアの配置、色の効果についてお話しさせていただきましたが、やはり、たくさんの物があふれていてごちゃごちゃしていると面積的には広いリビングも、なんだか狭くなり清潔感もなくなってしまいますよね。 リビングで勉強して、ノートや教科書をそのまま置いてしまっていたり…読みかけの雑誌、漫画をテーブルに置きっぱなしにする…なんてことはないですか?(;´-`) 新築住宅にする場合、マガジンラックや収納つきテーブルなどもともと収納できるスペースを作っておくと、整理整頓もしやすく、お部屋もスッキリした空間にできると思います。 いかがでしたか?現在、住まわれているお家でも、新築住宅を建てる際でも使えるポイントはいくつかあったのではないかと思います。本当に必要なモノだけを考えてみたり、普段よりロータイプの家具を選んでみたり、色の使い方を考えてみたりなど、いろいろと試してみて、ぜひ、リビングを広く見せて、リラックスできる空間を作ってみてください♪山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。 10月26日(土)~27日(日) 開催イベント↓年に一度のハロウィン家まつり開催!
-

失敗例から学ぶ!後悔しない家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の下村です!現在、宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!せっかく新築住宅を購入するなら絶対に失敗はしたくないものですよね。そこで今回は、「失敗例から学ぶ!後悔しない家づくり」というテーマのもと、後悔しない家づくりをするためのポイントについてご紹介していきたいと思います。( ^ ^ )/ すでに出来上がっている建売、ハウスメーカーのモデルハウス通りに建てる、中古物件をリフォームする。これらは自分たちの生活が、その今ある建物に合うか合わないかで判断できれば後悔することも少ないかと思われます。ですが、自分たちの家を自分たちでつくる場合は、予算内でどこまで希望を叶えられるか、どんな家にしていくか、時間をかけて一から考えなければなりません。ここで後悔しない理想のお家づくりを実現していくにはどのようにしたらよいでしょうか。 ■今の住まいに対する不満を考えてみる 何もない状態から新しいお家のことを考えることは誰でも難しいことです。やはり、「今の暮らし方」から「これからはこう暮らしたい」という理想が生まれてくると思いますので、「今の住まい」と比較していく必要があります。 例えば「キッチンが使いにくい」という現実があったとします。それを解決するために問題点を明確にします。 ・単純に狭い・作業の流れと合っておらずキッチンの構成が使いにくい・調理器具や食器をしまっておく収納スペースが足りない・キッチンと食卓への距離があり、無駄な動きが多くなってしまうまた「玄関に不満がある」のであれば、 ・靴を収納するスペースがない・脱ぎ履きをするスペースが狭い・段差が高い/低いなどの弱点が浮かび上がるかもしれません。どの問題点も、今の自分の暮らし方に合っていないからこそ解決したいと思うはずです。これらの問題点をしっかりと把握しておくことで、新築を建てる際に快適に暮らせるように前もって解決策を考えることができると思います。■さらなるメリットを付け足す 後悔しない家づくりをするためには、先ほどのように問題点を挙げた上で、問題点はもちろん解決し、さらに満足度を上げる仕組みをつけた方がいいです!例えばキッチンの問題点で壁面に向いてシンクやガス台が付いているキッチンが使いにくいとすると、 ☆家族との空間をつくるため対面式、またはアイランドキッチンにする ☆料理を運ぶ際の手間を極力省くためにダイニングルームとの一体感を強化する ☆収納スペースが増えるカウンター式を兼ね備えたコの字型キッチンにする などの解消法が見えてくると思います。料理だけができればいいという一般的なキッチンとは大きく異なり、リビングルームと一体的でありとても便利です。 まずは自分自身が思い描く暮らし方、最低限ここはクリアしたい!という問題点と、それ以上に欲しい快適さをどの部分に求めているか、考えてみてください。(=゜ω゜)ノここからは、家づくりにおいてよくある失敗例についてご紹介します! ■暮らしの快適さを左右する”間取り” 間取りは実際に住む前に考えますので、住んだ時のイメージをしにくく、念入りに考えていた間取りであったとしても、実際に住んでみると少し不便だったということも少なくはありません。では、間取りの中でもどのような部分で失敗と感じる人が多いのでしょうか。 □冷暖房の効率が悪い広いリビング家族みんなが快適に過ごせるような広いリビングを作ろうとリビングの面積を広くしたところ、クーラーの効きが悪くなったり、暖房が床まで温かくなりにくかったりと、空調の効率が悪くなり後悔してしまうということもあります。快適に過ごそうと思って考えた間取りであっても、デメリットをつくってしまう恐れもあるのです。そこで、広いスペースでリビングをとりたい場合は、移動できる仕切りをつけることをオススメします!必要に応じて仕切りを作ることで、無駄な部分を冷やそうとせず冷房の効きも効率的になると思われます。 □こんな場所に配線!?間取りの失敗で多いのが配線の問題です。生活をする上で、家電を多く利用する場合は、コンセントを多くしておいたほうが安全です。必要な場所にコンセントが設けられていないと、家電を使う場所が制限されてしまいます。ここで大事なことは、「どこでどのような家電を使うことが多いか」をイメージしておきましょう!間取りを考える場合は、その間取りで本当にデメリットは出ないか、または、デメリットがあるとしても解決できるかを一つ一つ確認していくことがとても大事になってくると思います!そのためにも普段の自分の暮らしを振り返り、新しいお家での生活をたくさんイメージしましょう! ■昼と夜の違いが多い”土地選び”での失敗 多くの方が、昼の時間帯を中心に土地選びをすると思われますが、昼と夜では当然印象が変わってきます。□夜になると暗い! 昼と夜で大きく印象が変わってくるのが、照明です。昼間に見た時は明るいと感じていた場所でも、夜はとても暗かった!なんてこともあります。土地を探す際は、昼間の様子を中心にチェックしてしまいがちですが、安全面などを考慮し、夜間の土地周辺のチェックもしっかりとしておきましょう! □交通量が多い! 平日と休日では交通量が変わってくる地域もあります。土地を見に来るのがいつも休日であったりすると平日の交通量などがよくわかりませんよね。もしかすると、平日の通勤時間はとても混んでいたり、なんてことも考えられます。道路の交通状況は平日、休日、そして朝、昼、夜でも差があるため、周辺の交通状況はどの時間帯でもチェックしておきましょう! ■”資金面”での失敗 家づくりにはさまざまな費用がかかるので、予算がオーバーしないように事前に把握しておく必要があります。□家具の費用を考えていなかった! 家はあくまで建物であり、快適に暮らしていくためには、当然ながら家具やインテリアが必要となります。じっくりと考えて家づくりをしたものの、新しい家にあったインテリアを購入する予算を確保していなかったという事例も少なくはありません。せっかく理想の家を建てても、満足のいく家具をそろえることができなかったと後悔しないように、建てた後の費用のことも事前に考えておきましょう! ■失敗例から家づくりのイメージを描いてみる ズバリ、家づくりの失敗は、住むまでのイメージと実際の住み心地とのギャップが原因だと思われます。間取り決めや土地選びの段階からのイメージ作りをたくさんしていたとしても、やはり、住んでみると理想通りにはいかないことも多いです。家づくりをすると考えた当初からできるだけ具体的なシチュエーションを行うことや、実際に土地へ足を運び、暮らしていくイメージを鮮明に描いてみることから始めてみましょう!そこから失敗しない・後悔しない家づくりがスタートします!d(^^*)山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。 10月26日(土)~27日(日) 開催イベント↓年に一度のハロウィン家まつり開催!
-

室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性①【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは! (*´_●`)ノいえとち本舗山口中央店です! みなさん、街中を歩いている際に「おしゃれだな」と感じる建物、空間はありませんか?おしゃれな雰囲気のお店、カフェ、レストランなどあらゆる空間で感じることがあると思います。 それぞれの空間で、それぞれの個性が出ていますよね。そういったおしゃれな空間はどのようにして生み出されているのでしょうか。 おしゃれな空間を生み出す大きな要素の一つとして“室内照明”があります。 従来の住宅では、だいたいの部屋は天井に1つだけシーリングライトがついており、そのシーリングライトが部屋の全体を照らしている というのが一般的ですよね。 しかし、室内照明はその空間の雰囲気を大きく変えてしまいます。ただ一つシーリングライトが天井についていても、なかなかおしゃれな個性のあるお部屋は作れないですよね。(lll-ω-) せっかく新築住宅を建てるのであれば、雰囲気の良い空間をつくり、誰もが理想とするようなお家づくりをしたいですよね。 新築住宅購入を考えているみなさんが理想の空間を作り上げるために“室内照明”についてみていきましょう。 直接照明と間接照明 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、”室内照明”には大きく分けて ★直接照明★間接照明 の2種類があります。 直接照明直接照明は、人や床を直接照らし、手元や足元まで明るくしてくれる “直接照明”は言葉の通り、光源が直接室内を照らす直接光を当てる照明です。室内全体を照らすことを目的としているので、「全体照明」や「主照明」と呼ばれることもあります。 この直接照明は、学校やオフィスなどでよく見かけますよね。直接照明は太陽の光を再現しており、とても活動的な明かりとなっております。なので、学校やオフィスなどで “人を活発的にさせる”という目的もかねて取り付けられております。 間接照明間接照明は、天井や壁を照らした反射で空間全体をゆったりとした雰囲気にしてくれる “間接照明”は、天井や室内の壁面、物などを照らす照明です。直接照明とは対照的に、空間の一部を照らすことを目的としているので、「部分照明」や「補助照明」と呼ばれることもあります。 直接照明と比較すると、少し暗い印象ですが、間接照明は人に直接光が当たらないので、リラックスさせる効果を与えます。 多くの方はシーリングライトの下で生活することに慣れていると思われますが、寝室のようなくつろぎを目的とした部屋や、映画を見る空間などは、間接照明が適していると考えられます。 室内空間をつくる 現在、間接照明を取り付けていらっしゃる方はあまり多くないかもしれませんが、間接照明と直接照明を上手く組み合わせることで、おしゃれな空間をつくり出すことができます。(・o・)/ 今回は直接照明と間接照明についてご紹介させていただきました。空間の作り方には光源の照らし方や色も大きく関係してくるので、 引き続きに次回のコラムでは室内照明の照らし方についてお伝えします。 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*) 1月25日(土)~2月2日(日)開催イベント↓【防府市田島】地域最大級!超絶怒涛の3棟同時見比べ見学会









