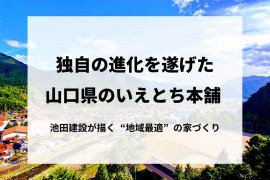ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
ツーバイフォー工法とは?メリット・デメリットを初心者にもわかりやすく解説!

家を建てることを検討している方は、「ツーバイフォー」という言葉を耳にすることがあると思います。しかし、ツーバイフォー工法とは何かがわからない方も多いでしょう。家を建てる際は、ツーバイフォー工法に関する理解を深めておくことが大切です。
この記事では、ツーバイフォー工法の特徴やメリット・デメリットなどを初心者にもわかりやすく解説します。ツーバイフォー工法とは何かがわかるようになるでしょう。
目次
1.ツーバイフォー工法とは
1-1.ツーバイフォー工法の特徴
1-2.ツーバイフォー工法の歴史
1-3.ツーバイフォー工法と在来工法の違い
1-4.ツーバイフォー工法とツーバイシックス工法の違い
2.ツーバイフォー工法のメリット
2-1.耐震性・耐風性・断熱性・耐火性に優れている
2-2.品質が安定しており強度と耐久性が期待できる
2-3.工期が短く迅速な建設が可能
2-4.施工費用が比較的安価で総工費を抑えられる
3.ツーバイフォー工法のデメリット
3-1.間取りの自由度が一部制限されることがある
3-2.大きな開口部を設けることが難しい
3-3.外観デザインの自由度が低い
3-4.建物内部の音が響きやすい
4.ツーバイフォー工法で家を建てる際のポイント
4-1.ツーバイフォー工法の施工実績が豊富な工務店を選ぶ
4-2.契約書や仕様書をしっかり確認しておく
4-3.建ててからも定期的に点検やメンテナンスを行う
5.ツーバイフォー工法に関するよくある質問
5-1.広いリビングやダイニングを実現できますか?
5-2.ツーバイフォー住宅の寿命は何年ですか?
5-3.工事中に雨に濡れても問題はないのですか?
6.ツーバイフォー工法のメリット・デメリットを理解した上で信頼できる業者を選びましょう
1.ツーバイフォー工法とは

ツーバイフォー工法は、戸建住宅や木造賃貸住宅など、住宅建築において広く用いられている工法です。近年では、高気密高断熱の家や耐震性の高い住宅へのニーズの高まりとともに、日本でも普及が進んでいます。
はじめに、ツーバイフォー工法とは何かについて解説します。
1-1.ツーバイフォー工法の特徴
ツーバイフォー工法とは、北米発祥の木造建築工法の一つです。建築において、2インチ×4インチ(約38mm×89mm)の規格角材を使用することから「ツーバイフォー(2×4)」と呼ばれます。
正式名称は「枠組壁工法」といい、木材の枠組みに合板を張り付け、床・壁・屋根などの面で建物を支えるのが特徴です。垂直方向と水平方向の強度が向上することで、優れた耐震性・耐風性を発揮します。
また、壁内に断熱材を充填し隙間をなくすことで断熱性・気密性にも優れており、快適な室内環境の実現が可能です。さらに、面で炎を跳ね返す耐火構造により防火性能も高く、在来工法(木造軸組工法)とは異なる特徴があります。
1-2.ツーバイフォー工法の歴史
1830年代、アメリカのシカゴで誕生した「バルーンフレーム工法」がツーバイフォー工法のルーツといわれています。バルーンフレームは軽量で強度が高く、簡便に住宅を建設できることで、開拓者たちの住宅建設に広く用いられました。
その後、二度にわたるシカゴ大火 (1871年・1874年) をきっかけに、耐火性の高い建築工法へのニーズが高まり、バルーンフレームを改良したツーバイフォー工法が開発されました。
日本では高度成長期に急激に増加した住宅需要に対応するため、1974年に建築基準法に基づく住宅工法として認定を受けたのがツーバイフォー工法の始まりです。現在では技術開発や研究が進み、より高性能なツーバイフォー住宅が開発されています。
1-3.ツーバイフォー工法と在来工法の違い
ツーバイフォー工法と在来工法は、住宅の建築方法が根本的に異なります。在来工法は「木造軸組工法」とも呼ばれ、柱や梁などの軸組みで建物を支える工法で、軸組みを現場で組み立てるため、職人の技量によって品質が左右されます。
ツーバイフォー工法は工場で部材を製造し現場で組み立てる工法であるため、作業する職人の技量によって品質にばらつきが出にくいことが特徴です。
住宅の建築方法の違いにより、ツーバイフォー工法と在来工法は構造や耐震性・耐風性、断熱性・気密性、工期、建築費用などが異なります。ツーバイフォー工法には耐震性や断熱性などが優れている反面、間取り変更が難しいなどのデメリットも存在します。
どちらが優れているというわけではなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の希望に合った工法を選ぶことが大切です。
1-4.ツーバイフォー工法とツーバイシックス工法の違い
ツーバイフォー工法とツーバイシックス(2×6)工法では、建築で使用する木材の規格が異なります。ツーバイフォー工法は柱や梁の木材の規格が「2×4」インチ(約38mm×89mm)であるのに対し、ツーバイシックス工法は「2×6」インチ(約38mm×140mm)と幅が約5cm大きくなっていることが大きな違いです。
ツーバイシックス工法は壁の厚みが約1.6倍になるため、断熱材や気密材をより多く充填でき、断熱性能や気密性能が向上します。ただし、「価格が高くなる」「間取りの自由度が低くなる」というデメリットがあります。
ツーバイフォー工法とツーバイシックス工法は、それぞれ異なる特徴を持つ工法です。どちらが優れているかというのはケースバイケースであり、建築の目的や条件、予算、好みなどを考慮して選択する必要があります。
2.ツーバイフォー工法のメリット

ツーバイフォー工法と在来工法は、それぞれ異なる特性を持つ工法です。住宅建築を検討する際は、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の希望に合った工法を選ぶことが重要です。ここでは、ツーバイフォー工法のメリットを解説します。
2-1.耐震性・耐風性・断熱性・耐火性に優れている
耐震性・耐風性・断熱性・耐火性に優れていることが、ツーバイフォー工法の大きなメリットです。ツーバイフォー住宅は「面」で構成されており、地震や強風などの外力に対して面全体で力を分散することで、耐震性や強風耐性を高められます。
在来工法でも耐震性や強風耐性を高めることは可能ですが、特別な耐震設計や耐風設計が必要になる場合があります。高度な施工技術も要求され、施工費が高くなることもあるでしょう。ツーバイフォー工法は特別な設計をしなくても、耐震性・耐風性が高い構造になっています。
また、柱と梁の木材の間に断熱材を充填することで気密性・断熱性が高く、石膏ボードで火災の拡大を防げることもメリットです。
2-2.品質が安定しており強度と耐久性が期待できる
ツーバイフォー住宅は、規格化・システム化により品質向上が図られているため、品質が安定しやすいことがメリットです。ツーバイフォー工法においては、建築で使用する木材やその他の建材は工場であらかじめ規格化・システム化して製造されます。
建材の寸法や強度などは工場での生産プロセスにおいて厳密に管理されており、品質のばらつきは少ないです。安定した品質の建材の使用で建物全体の構造的な信頼性が向上し、強度と耐久性も期待できます。
ただし、良質な建材を使用しても、施工技術が低いと強度と耐久性のある住宅は建築できません。ハウスメーカーや工務店の技術力は重要であり、施工実績などを確認し信頼できる業者を選ぶことが大切です。
2-3.工期が短く迅速な建設が可能
ツーバイフォー工法では、建材が工場で準備されているため、現場での組み立て作業を効率的に行えます。これにより、ツーバイフォー工法は在来工法と比べて施工期間が短くなる傾向があります。住宅が早く完成することで仮住居費を削減でき、早めに新生活を始められるでしょう。
施工期間は3~4ヵ月程度で、在来工法と比べると短めです。在来工法では建材の加工や組み立て作業が現場で行われるため、ツーバイフォー工法と比べて施工期間が長くなることがあります。一般的に在来工法だと完成までに約半年間かかります。
ただし、建物の規模や形状、施工業者によって施工期間は大きく異なるため、具体的な工期は個別に確認が必要です。
2-4.施工費用が比較的安価で総工費を抑えられる
ツーバイフォー工法のメリットとして、工期短縮による人件費削減と建材の規格化による材料費削減が挙げられます。ツーバイフォー工法は工期が短いため、職人の人件費を抑えられる可能性があります。また、建材の規格化によって大量生産が可能であり、材料費を抑えられる可能性もあるでしょう。
人件費と材料費の削減によって、施工費用が比較的安価になり、総工費を抑えられます。しかし、これらのメリットは必ずしもすべてのケースで当てはまるわけではありません。
総工費は建築プランの規模や条件、労働市場の状況などによって変動します。住宅建築においては建築プランなどを考慮に入れて、最適な建築手法を選択することが重要です。
3.ツーバイフォー工法のデメリット

ツーバイフォー工法にはさまざまなメリットがありますが、同時にデメリットも存在します。建築手法を選択する際は、デメリットも知っておくことが大切です。ここでは、ツーバイフォー工法のデメリットを解説します。
3-1.間取りの自由度が一部制限されることがある
在来工法と比較すると、ツーバイフォー工法は間取りの自由度が一部制限される場合があります。理想の間取りがあっても、実現できない可能性があることはツーバイフォー工法のデメリットでしょう。
ツーバイフォー住宅の壁は柱と梁でしっかりと固定されており、面全体で一体化しているのが特徴です。そのため、壁を増減したり位置を変えたりすると、壁面全体で力を分散できなくなります。
間取り変更や大規模なリノベーションは難しく、間取りの自由度を確保したい場合は、設計段階からツーバイフォー工法の制限を考慮する必要があります。工務店や建築士と相談しながら、制限の中で希望の間取りを実現できるプランニングをすることが重要です。
3-2.大きな開口部を設けることが難しい
ツーバイフォー工法では大きな開口部を設けることが難しい場合があります。大きな窓がある住宅を望んでも、実現できない可能性があることはツーバイフォー工法のデメリットです。
ツーバイフォー工法は壁が構造部材として機能するため、壁を大きく抜くと構造強度が低下する可能性があります。大きな開口部を設ける際には、構造強度を確保できる方法を検討しなければなりません。
一方、在来工法は壁に頼らずに建物を支えられるため、壁を大きく抜いても構造強度が低下しにくく、さまざまな開口部を設けられます。
ツーバイフォー工法で大きな開口部を設けるためには、特別な設計や補強材の追加などが必要になる場合があります。建築士や構造設計士など専門家の助言を仰ぎ、適切な補強策や設計を行うことが重要です。
3-3.外観デザインの自由度が低い
ツーバイフォー工法は在来工法と比べると、外観デザインの自由度が低い傾向があります。ツーバイフォー工法は工場で製造したパネルを現場で組み立てて家を建てるため、パネルのサイズや形状によって外観デザインに一定の制限が生じます。
パネルは曲げられないため、なめらかな曲線のある家は作りにくく、理想の外観デザインが実現しないこともあるでしょう。一方、在来工法は内外ともにデザインの自由度は高いです。
ツーバイフォー工法でも、設計や施工に高度な技術が必要になりますが、設計段階で工夫したり、特注パネルを使用したりすることで、希望に近いデザインを実現できる可能性はあります。
ただし、デザインによっては構造上の問題が発生する可能性があるため、デザインと構造の両面でバランスを取りながら、最適な解決策を見いだすことが重要です。
3-4.建物内部の音が響きやすい
ツーバイフォー住宅は建物内部の音が響きやすい傾向があります。ツーバイフォー住宅は気密性が高く、外部からの防音性能は優れている反面、建物内部の音は響きやすいです。壁や床に空洞があることも音が反響する原因になります。
また、1階の天井と2階の床が一体構造になっていることも、音が響きやすい原因のひとつです。2階で床を歩いたり物を落としたりした振動音が直接階下に伝わってしまいます。ツーバイフォー工法で施工する際は、階下への振動音を抑える対策を講じなければなりません。
テレビや音楽などの音が響きやすいという声もあり、吸音材を設置するなどの対策が必要になることがあります。特にツーバイフォー工法で木造賃貸住宅を建築する際は、入居者の騒音トラブルを防ぐための防音対策が必要です。
4.ツーバイフォー工法で家を建てる際のポイント

ツーバイフォー工法で家を建てる際は、業者選びやアフターフォローが重要になってきます。後々のトラブルを避け、建物の耐久性や安全性、住環境の快適性を保つためにも、以下のポイントに留意することが大切です。
4-1.ツーバイフォー工法の施工実績が豊富な工務店を選ぶ
建ててから後悔しないよう、ツーバイフォー工法の施工実績が豊富なハウスメーカーや工務店を選ぶことが大切です。ツーバイフォー工法は在来工法と比べ、品質が職人の技量に左右されにくい傾向があります。しかし、最終的な性能はハウスメーカーや工務店の技術によって決まります。
ツーバイフォー工法は在来工法とは構造や施工方法が異なるため、専門的な知識と技術が必要です。施工実績が豊富なハウスメーカーや工務店はツーバイフォー工法のノウハウを熟知しており、高品質な住宅の建設が期待できます。
過去に建てたツーバイフォー住宅の棟数が多いほど、経験豊富といえます。コーポレートサイトなどで施工実績や評判をじっくりと確認し、信頼できるパートナーを選ぶことが大切です。
4-2.契約書や仕様書をしっかり確認しておく
ハウスメーカーや工務店と工事請負契約を締結する際、契約書や仕様書をしっかり確認することは非常に重要です。契約書には工事の内容や価格、支払い方法、保証内容などが記載されており、これらを確認することで、後々トラブルが起きる可能性を減らせます。
仕様書には使用する材料や設備、工事の品質基準などが記載されており、これらを確認することで、どのような建物が建てられるのか、どのような工事が行われるのかを理解できます。
建設中や完成後に問題が発生することを避けるためにも、契約書や仕様書を入念にチェックすることが必要です。契約書や仕様書は専門用語が多く、内容がわかりにくい場合があります。わからない点があれば、必ずハウスメーカーや工務店に説明を求めましょう。
4-3.建ててからも定期的に点検やメンテナンスを行う
建物の耐久性を維持するためには、建ててからも定期的な点検やメンテナンスが不可欠です。定期的な点検を行うことで問題が早期に発見され、適切な修理や補修が行われることで建物の寿命を延ばせます。
住宅設備や内外装は経年劣化によって性能が低下したり見た目が悪くなったりします。住宅設備は築10~15年、内外装は築15~20年を目安に、交換や張り替え・塗り替えなどのメンテナンスが必要です。これにより、住宅の美観や住環境の快適性を保てます。
点検やメンテナンスは、建物の安全性を確保するためにも重要です。特に、屋根や外壁などの構造部分や電気設備、配管などの設備部分は定期的な点検が欠かせません。問題が放置されると、安全上のリスクが高まる可能性があります。
5.ツーバイフォー工法に関するよくある質問

ツーバイフォー工法に関する疑問やわからない点があれば、業者に質問することが重要です。業者に質問することで、正確な情報や適切なアドバイスが得られます。ここでは、ツーバイフォー工法に関するよくある質問に回答します。
5-1.広いリビングやダイニングを実現できますか?
日本のツーバイフォー工法では、最大72㎡(約21.8坪)までの広々とした空間の設計が構造計算なしで可能です。これは、間口6m×奥行12mの広さに相当し、開放感あふれるリビング・ダイニングや、家族みんながゆったり過ごせる多目的な空間など、さまざまな用途に活用できます。
72㎡の空間は、一般的なマンションのLDKを上回る広さです。ハウスメーカーや工務店のホームページでは、ツーバイフォー工法による広いリビングやダイニングの施工事例を紹介しています。
5-2.ツーバイフォー住宅の寿命は何年ですか?
ツーバイフォー住宅の寿命は約80年といわれています。これはあくまでも目安であり、実際の寿命はさまざまな要因によって大きく左右されます。定期的な点検やメンテナンスは特に重要であり、リフォームをすることで100年以上に寿命を延ばすことは可能です。
定期点検で建物の劣化状況を確認し、劣化が見つかった場合は早めに対処しましょう。適切な換気を行って結露を防いだり、防虫・防カビ対策を行って木材の腐食を防いだりすることでも、住宅の寿命を延ばせます。
5-3.工事中に雨に濡れても問題はないのですか?
工事中に雨に濡れても、速やかに乾かせば問題ありません。ツーバイフォー住宅は構造用製材に含水率19%以下の乾燥材を使用するなど、さまざまな方法で湿気対策を行っています。ただし、長時間濡れたままにしておくと木材が腐朽するリスクが高まるため、注意が必要です。
信頼できるハウスメーカーや工務店は、木材を長時間濡れたままにしておくことはありません。ツーバイフォー住宅を建てる際は信頼できるハウスメーカーや工務店を選び、工事中に木材が長時間濡れることがないように注意しましょう。
6.ツーバイフォー工法のメリット・デメリットを理解した上で信頼できる業者を選びましょう

ツーバイフォー工法は、耐震性・耐風性・断熱性・耐火性に優れており、工期が短く迅速な建設が可能です。このようなメリットがある一方で、間取りの自由度が一部制限され、外観デザインの自由度が低いなどのデメリットも存在します。
ツーバイフォー工法と在来工法は、どちらが優れているかというのは一概にいえません。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の希望に合った工法を選ぶことが大切です。
耐久性や安全性、快適性に優れた住宅を建築するには、信頼できるハウスメーカーや工務店の選択が重要になります。ツーバイフォー住宅の施工実績や評判などを確認して、信頼できる業者を選びましょう。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹

不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。
いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。
後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
関連記事
-

3月入居のメリット・デメリットとは?!【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさまこんにちは!(^^)/いえとち本舗山口中央店です! 山口・山陽小野田・宇部・周南・防府で新築住宅の購入をお考えのみなさまは、毎年3月~4月は引っ越しシーズンと呼ばれていることを知っていますか? 特に3月は引越しをする人が集中するようです。 社会人のかたは4月から新年度が始まるため異動や研修に伴う家族の移動があり、学生の方は4月から入学・新学期が始まるため、移動をする方が集中する時期になります。 もしかしたら、この記事を読まれている方も様々な理由で引っ越しシーズンに引っ越しをするかもしれません。 なので今回は「3月入居のメリット・デメリット」についてお伝えしていこうと思います!(^^)/ ★3月入居のメリット ①余裕をもって出社・入学できる お子様がおられるご家庭だとお子様は春休み期間なので学校の行事がなく、効率よく引っ越し作業を進めることができます。 時間に余裕がある分、家具家電をそろえたりする時間が多めに取ることができると思われます。(^^♪ 山口で引っ越しをする際、4月間近になってバタバタ準備するよりも、3月から準備をしておくことで心のゆとりにもつながりますね♪ ②季節的に、暖房器具の設置は後回しにできる 地域によって差は出ますが、3月4月は猛烈に寒いという訳でもなく、暑いわけでもなく・・・といった季節なので暖房器具の設置は後回しにできるかと思います。 特にエアコンは設置が大変になりますので、後回しにできると他のことに使える時間ができます♪ ★3月入居のデメリット ①引っ越し費用が高い 3月や4月は引越し業者の繁忙期ですので、お見積りがかなり高いです。引越し業者に委託せず全て自分で作業すれば問題ないですが、時間と手間がかかりますね(;_:) また、この時期は引越し業者の予約も取りにくくなっているので前もって予約しておくなどの対応が必要ですね。 ②役所が混む この時期に引っ越しをする人が多いということは、転入届や住所変更等を行う人が多いということになります。 なので役所がとても混み、長い時間待つことになります。 ③物件数が少ない 年始を過ぎたあたりから物件数はガクッと少なくなります。 人の移動が増える時期でありますので空き物件の数も増えますが、同時に探している人も多いため、希望に合う物件に出会うことは難しそうです。 家賃相場に関しては極端に高くなるわけではありませんが、敷金・礼金の値引きなど条件交渉は難しい場合があるという認識を持っておいたほうが良いと思われます。 ★まとめ 3月入居はメリットもありますが、デメリットも多いように感じます。 山口で3月に引っ越しをしなければならない方もいらっしゃるとは思いますが、時間に余裕があるうちに引っ越しのメドをたて早めに準備するなどのアクションを起こした方が良いと思います(^^♪ 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓【山口市下市町】リビング21.3帖平屋3LDK完成見学会
-

RC造とは?他の建物構造との違いやメリット・デメリットを紹介
建築構造には種類があり、特徴や優れているところ、欠点となっているところがそれぞれあります。見た目だけではどの構造がいいのか判断することは難しいですから、各構造について知っておきましょう。この記事では建物構造の種類や特徴についてお伝えしていきます。 RC造とその他建物構造について 日本の住宅の場合は木造が一般的ですが、その他にもいろいろな構造があり、造りがまったく異なりますので、家の購入を検討されている方はどんな違いがあるか知っておくことが大切です。それでは以下にて代表的な建物の構造をご紹介していきます。鉄筋コンクリート造(RC造/Reinforced Concrete) 鉄筋コンクリート造はReinforced Concreteを略してRC造とも呼ばれています。この構造は名前の通り鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造となっており、鉄筋の引張り力とコンクリートの圧縮力の両方の強度を有しています。この構造はお互いの優れている点と弱点となる点を補っており、鉄筋の熱に弱く錆びやすいところをコンクリートで覆うことで弱点を克服する構造となっております。また、コンクリートの場合は、圧縮力は優れますが、引っ張られる力には弱いため、その引っ張りに対する力を鉄筋が補っています。これにより圧縮力と引張り力の両方の力に対して強い建物を建てることができます。木造(W造/Wood) 木造は日本古来から用いられている構造であり、住宅の他にも神社仏閣などが木材で建てられています。柱や梁など主要な部材は木材が使われており、在来軸組工法や枠組壁工法(2×4、2×6)など同じ木造でも複数の工法があります。在来軸組工法は柱や梁などを組み上げる骨組み構造となっており、日本に多く採用される工法です。枠組壁工法はアメリカで開発され、2×4、2×6など規格化された部材を使い、主に耐力壁を造って建物を建てる工法です。鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造/Steel Reinforced Concrete) 鉄筋鉄骨コンクリート構造(SRC造)は、鉄筋を組んだ芯部に鉄骨を組み込み、外側にコンクリートを覆った構造で、鉄骨の粘り強さと鉄筋コンクリートの強度を合わせ持った非常に耐久性の高い建物を建てることができます。主に高層ビルやマンションなど高い建物に用いられ、鉄骨造よりも座屈(荷重による変形)に対して強く耐火性も高いです。軽量鉄骨造(S造/Steel) 軽量鉄骨造は厚さ6mm未満の鋼材を用いた構造のことをいいます。鉄骨造は木造のように柱や梁で構成する骨組み構造であり、工業製品のため品質が安定しています。また、引張り力と圧縮力に優れて耐震性も高く、3〜4階建ての住宅やアパート、店舗併用型住宅に採用される構造となっています。ハウスメーカーの中には軽量鉄骨造をメイン構造としているところもあります。重量鉄骨造(S造/Steel) 厚さ6mm以上の鋼材を使用した構造が重量鉄骨造です。軽量鉄骨造よりも高い建物を建てることができ、主に中層の集合住宅や店舗併用住宅、高層ビル、マンションなどに採用されます。重量鉄骨造も鉄骨造と同じラーメン構造(柱と梁で構成される構造体)で建てられるのが一般的で、軽量鉄骨造と比べて柱が太く、構成する鉄骨の本数を少なくすることができます。建物構造の特徴・メリット&デメリット 上記でお伝えした各構造には長所と短所があり、これから家を建てる計画をされている方はどんな構造を採用するか判断するために重要な要素となってきます。それでは以下にて各構造のメリット・デメリットをお伝えしていきます。鉄筋コンクリート造(RC造/Reinforced Concrete)メリットデメリット耐火性に優れる建築コストが高い耐久性・耐震性が高い結露が出やすい気密性に優れる熱伝導率が高いため断熱対策が必要遮音性に優れる気密性が高いため換気設備が必要設計の自由度が高い 木造(W造/Wood)メリットデメリット建築コストを抑えられる耐用年数が短い断熱性に優れるシロアリ・漏水・雨漏りの被害に弱い日本の気候にあっている火災に弱いバランス良く性能を高められる柱や壁の数量が多いメンテナンス性に優れる 鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造/Steel Reinforced Concrete)メリットデメリット耐火性に優れる建築コストがかかる耐震性・耐久性に優れる工期が長期化しやすい遮音性に優れる設計の自由度が高い 軽量鉄骨造(S造/Steel)メリットデメリット大開口が可能で設計の自由度が高い耐火性が低い工期が短い壁が薄いと防音・遮音性は期待できない品質が安定している結露により鉄骨に錆が発生する木造よりも耐久性・耐震性が高い 重量鉄骨造(S造/Steel)メリットデメリット大開口が可能で設計の自由度が高い軽量鉄骨よりも建築コストがかかる防音性が高い高層建築が可能耐久性・遮音性に優れる強固な地盤や基礎が必要品質が安定している 構造による防音性や耐火性、耐震性の比較 建築構造耐震性防音性・遮音性耐火性建築コストRC造○○○×木造△△△◎SRC造◎○◎×S造○△△○上記の表はあくまでも各構造の目安ですが、性能が期待できない部分については設計次第で基準よりも高めることができるという点は着目するべきところです。以下にはどんな構造についてどんな人におすすめなのかお伝えしていきます。建築コストを抑えたい方は木造がおすすめ 建築コストを重視するのなら断然に木造がおすすめです。木造は普及率も高く材料も他の構造よりも安価なため、費用を抑えつつ、備えたい性能はバランス良く設計することが可能です。定期的にメンテナンスを行えば建物も長く維持していくことができますので、費用を抑えて建物を建てたい方は木造がいいでしょう。耐震性・耐火性を求めるならRC造・SRC造がおすすめ 建物の強度を求めるのならRC造とSRC造がおすすめです。鉄筋コンクリートと鉄骨の強度はとても信頼が高く、安心して住み続けられる建物といえます。以前ではマンションのような高層建築の場合は揺れの心配がありましたが、技術の進歩により地震の揺れを吸収する免震構造が取り入れる建物も増えております。間口の広い設計にしたいならS造がおすすめ 柱や壁を少なくし、間口の広い設計にしたい場合はS造がおすすめです。主に壁は間仕切り壁となりますので、自由に壁を配置したり、廃したりすることができます。このため大開口を設けることができ、開放的な空間を作ることが可能となっています。自由な設計は他にもRC造やSRC造でも可能ですが、建築コストが高いという点はデメリットとなります。その点、軽量鉄骨造の場合は住宅メーカーも採用する構造となっており、リーズナブルな価格で取り入れることが可能となっています。ただし、間仕切り壁で仕切るため、壁厚がない場合は防音性や遮音性の対策が必要です。まとめ ここまで建物の構造についてご紹介してきました。構造はいくつか種類があり、どれも一長一短ありますので、自分が求める建物構造を選び、欠点を補っていける設計を行うのが重要です。これから家を建てる計画をされている方は今回お伝えした建物の構造のポイントを押さえて、自分に適した構造を選びましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-

独自の進化を遂げた山口県のいえとち本舗 ― 池田建設が描く“地域最適”の家づくり
コラム目次1. 「いえとち本舗」とは?全国ブランドの理念と強み1-1. 全国ブランドとして培ってきた“土地×建物×価格”の仕組み1-2. 全国モデルから発展した山口オリジナルの家づくり2. 山口で深化した「池田建設のいえとち本舗」2-1. 地域の暮らしを知る池田建設のものづくり2-2. 全棟G2仕様という高性能化へのこだわり2-3. 独自ブランド「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」3. 全国モデルとの違いが生む“地域最適化”の価値3-1. 性能の底上げと暮らしの最適化3-2. 「取り扱う商品を選ぶ」という品質思想3-3. デザイン・価格・サポートの三位一体提案4. 山口のいえとち本舗が選ばれる理由4-1. 気候・地形・習慣に合わせた住宅設計4-2. 県内全域をカバーする店舗ネットワーク4-3. 建てた後も寄り添う地域密着サポート5. まとめ ― 全国ブランドの枠を超えた、山口発の住宅ブランドへ5-1. 全国ブランドの枠を超える“地域版アップグレード”5-2. 山口の暮らしに寄り添う、これからの家づくりへ6. FAQQ1. 山口県のいえとち本舗と全国の違いQ2. 高性能でも価格を抑えられる理由Q3. G2仕様とは?Q4. 平屋への対応Q5. 見学・相談の場所1. 「いえとち本舗」とは?全国ブランドの理念と強み1-1. 全国ブランドとして培ってきた“土地×建物×価格”の仕組みいえとち本舗は、「土地と建物をまとめて提案する」という独自の仕組みで全国に広がった住宅ブランドです。家を建てたいと思っても、土地探しと建物計画を別々に進めるのは時間も手間もかかります。いえとち本舗はその課題を解決するため、ワンストップで“理想の土地に、理想の家を”実現できる体制を整えました。さらに、仕入れ・設計・施工の各工程を効率化することで、“わかりやすい価格設定”と“安定した品質”を両立。全国の加盟企業が共通の基準をもとに運営するため、どの地域でも一定のクオリティを保ちながら、マイホームを手の届く価格で提供できる点が支持されています。このように、全国ブランドとして培ってきたノウハウは、いえとち本舗の根幹をなす強みとなっています。1-2. 全国モデルから発展した山口オリジナルの家づくり全国のいえとち本舗では、どの地域でも安定した品質を提供できるよう、共通仕様のベーシックモデルが展開されています。たとえば「シンプリエ」シリーズのように、コストパフォーマンスを重視した合理的な住宅がその代表です。一方、株式会社池田建設が展開する山口のいえとち本舗は、そうした全国モデルの仕組みを土台としながらも、地域の気候・土地事情・平屋志向に合わせて独自に発展したスタイルを確立しています。 全国共通の設計をそのまま採用するのではなく、山口の暮らしに最適化したオリジナルモデル(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を自社で開発。これにより、「同じいえとち本舗でありながら、より地域に根ざした家づくり」を実現しています。これは単に商品を変えたというよりも、「山口の暮らしに最適な住宅を自社で設計し、責任を持って提供する」という考え方の表れです。つまり、同じ“いえとち本舗”であっても、池田建設では地域性を軸にした独自の発展を遂げているのです。 2. 山口で深化した「池田建設のいえとち本舗」2-1. 地域の暮らしを知る池田建設のものづくり山口県はいえとち本舗の中でも、新築住宅の需要が非常に高い地域です。一方で、理想の住まいを建てたくても「土地が見つからない」「希望のエリアに空きがない」という悩みを抱える人も少なくありません。そうした背景から、土地探しと家づくりを一体で考える提案力が、山口での家づくりには欠かせない要素となっています。また、山口県では全国的に見ても平屋住宅の人気が際立っており、若い世代からシニア層まで“ワンフロアで完結する暮らし”を求める声が多くあります。株式会社池田建設が展開する山口のいえとち本舗は、この地域特性を的確に捉え、限られた土地を最大限に活かす平屋設計のノウハウを磨いてきました。創業以来70年以上にわたり地元の土地・気候・生活習慣を熟知してきた同社だからこそ、「土地の選び方」「建物の配置」「光と風の通し方」まで、“暮らしやすさ”を中心に据えた提案ができます。単に家を建てるのではなく、“土地から暮らしをデザインする”――それが、株式会社池田建設が手がける山口のいえとち本舗の家づくりです。2-2. 全棟G2仕様という高性能化へのこだわり池田建設のいえとち本舗が評価される最大の理由のひとつが、「全棟G2仕様+耐震等級3」という確かな性能です。G2仕様とは、国の省エネ基準を大きく上回る断熱性能(断熱等級6相当)を意味し、冬でも室内の温度差が少なく、年間を通じて快適に暮らせる水準です。冷暖房効率が高く、光熱費を抑えながら快適さを維持できるため、実際の生活コストにも直結します。さらに、すべての建物で許容応力度計算による耐震等級3を標準採用。これは建築基準法で定める耐震性能の最高ランクであり、災害時でも家族の安全を守るための基準です。多くの住宅会社が“等級3相当”と表現する中で、池田建設は全棟で構造計算を実施し、確実に等級3を取得している点が大きな違いです。また、Kダンパー(制震ダンパー)を採用することで、地震の揺れを吸収・分散し、建物へのダメージを軽減。繰り返しの揺れにも強く、長期にわたって構造体の耐久性を維持します。断熱には現場発泡ウレタン吹付断熱を採用し、細部まで気密性を高めることで、G2仕様の性能を最大限に発揮。これにより、「高断熱×高気密×高耐震+制震」という4要素がすべて標準で備わる仕様となっています。“性能はオプションではなく標準であるべき”――。この考えを貫く姿勢こそが、池田建設のいえとち本舗が多くの施主から信頼される理由といえるでしょう。2-3. 独自ブランド「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」池田建設のいえとち本舗では、山口の暮らしに合わせて開発した3つのオリジナルブランドを展開しています。すべてのシリーズでG2仕様(断熱等級6)を標準採用し、性能の高さを前提に“暮らし方の違い”に合わせた提案を行っているのが特徴です。まず「イエスタ」は、間取りを考える手間を省きたい方や、設計をプロに任せて効率よく家づくりを進めたい方におすすめのシリーズです。設計士が生活動線や収納、採光バランスを考え抜いた完成度の高いプランで、コストを抑えて建てられるため、初めての家づくりをする若い世帯や、予算を重視する方にも適しています。特に平屋需要の高い山口では、シンプルかつ洗練されたプランが幅広い層に支持されています。次に「イエミライ」は、太陽光発電+蓄電池+HEMS(エネルギー管理システム)を標準搭載したスマート住宅。G2仕様の断熱性能を活かしながら、創る・蓄える・賢く使うエネルギーの自給循環を実現。停電時にも安心して暮らせる、次世代型の省エネ住宅として高く評価されています。「エネルギーを自給自足したい」「将来の電気代上昇や災害に備えたい」と考える未来志向の顧客層に支持されています。そして「イエテラス」は、G2仕様を基盤としながらも、デザイン性と価格のバランスを重視する方に最適なシリーズ。屋内外をつなぐテラス空間や、自然光を取り込み、性能とデザインの両立を楽しむ設計が特徴です。「性能にもこだわりたいけれど、デザインも妥協したくない」というバランス志向の層から選ばれています。これらの3シリーズはすべて、池田建設が自社で開発・管理する地域専用ブランドとしてそれぞれ明確なコンセプトとターゲットを持ち、どんな世代・ライフスタイルにも応えられる構成となっています。全国モデルの“量産”ではなく、山口の土地・気候・ライフスタイルに最適化された“質の提案”として展開されています。3. 全国モデルとの違いが生む“地域最適化”の価値3-1. 性能の底上げと暮らしの最適化全国のいえとち本舗が“コストパフォーマンスの高さ”を軸に展開しているのに対し、池田建設のいえとち本舗はコストパフォーマンスに加えて「性能を起点にした家づくり」を徹底しています。全棟でG2仕様・耐震等級3を標準採用することで、単に“建てやすい価格”ではなく、“住み心地の質”を標準化した家づくりを実現しています。これにより、冬場の室温ムラや夏場の熱こもりが少なく、日々の冷暖房費を抑えながら快適に暮らせる住宅が当たり前になります。また、山口特有の“平屋志向”や“限られた土地条件”にも柔軟に対応。断熱・耐震・換気といった基本性能の底上げを前提に、敷地条件や家族構成に合わせた最適な間取りを提案できる点は、全国モデルにはない大きな強みです。性能値を高めるだけでなく、その性能を地域の暮らしにどう活かすかまで設計に落とし込む――この姿勢こそが、池田建設が選ばれる理由です。3-2. 「取り扱う商品を選ぶ」という品質思想Point.池田建設はいえとち本舗の理念を共有しながらも、すべての商品を扱うわけではありません。例えば全国的に展開されている「シンプリエ」シリーズは、コスト面で魅力がある一方で、山口の気候や居住ニーズとは異なる設計思想を持つため、同社ではあえて採用していません。これは“取り扱わない”のではなく、“地域に最も適した品質だけを提供する”という判断です。代わりに、独自開発のG2仕様シリーズ(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を中心に展開。「選択と集中」によって、性能・コスト・デザインのバランスを地域基準で最適化しています。全国統一ではなく、山口基準での“ベストクオリティ”を追求する姿勢が、同社の品質哲学として根付いています。3-3. デザイン・価格・サポートの三位一体提案池田建設のいえとち本舗は、デザイン性・価格・サポートを三位一体で提案する体制を整えています。デザイン面では、間取りや外観だけでなく、採光計画や通風シミュレーションまでを考慮した「体感的な快適さ」を重視。価格面では、性能を高めつつも月々3万円台から実現できるよう、施工効率とエネルギーコスト削減の両面でコストバランスを追求しています。さらに、過度なメディア露出や外注に依存せず、資料・チラシ・Webなど多くの広告物を自社で企画・制作。その分のコストを住宅の性能・設備・アフターサポートに再投資することで、価格を抑えながら品質を維持しています。「見せ方より中身を磨く」――この地に足のついたブランド戦略が、長期の満足度につながっています。また、地域密着の強みを活かし、建てた後の暮らしを支えるサポート体制も充実。定期点検やメンテナンス、蓄電池の追加・改修提案など、住まいを“長く良い状態に保つ”ための伴走を行います。建てる前も、建てた後も、安心して任せられる――総合的な安心感が“地域最適化ブランド”としての価値を高めています。4. 山口のいえとち本舗が選ばれる理由4-1. 気候・地形・習慣に合わせた住宅設計山口県は、瀬戸内海と日本海の両側に面し、エリアごとに日射・風向・湿度の条件が大きく異なる地域です。沿岸部は潮風や湿気、内陸部では冬の冷え込みが強く、地域によって理想的な家の形が違います。池田建設のいえとち本舗では、こうした地域特性を丁寧に読み取り、地形・方角・風の通り方を考慮した設計を一邸ごとに行っています。また、山口では昔から「家族が集まる広いリビング」「来客を気にせず過ごせる平屋」へのニーズが高く、同社はその生活文化を反映した現代的な平屋デザインを数多く手がけています。性能値やデザインを“全国共通の基準”で押し付けるのではなく、山口で暮らすための最適解を導き出す設計力――それが、池田建設のいえとち本舗が信頼される理由です。4-2. 県内全域をカバーする店舗ネットワーク池田建設のいえとち本舗は、山口県内6拠点(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)を中心に展開しています。それぞれの店舗が地域密着で運営され、土地情報・施工事例・お客様の声を常に共有。「家を建てたいけれど、どのエリアが暮らしやすいか分からない」といった初期段階の相談から、建築・アフターまでをワンストップで支援できる体制が整っています。また、各店舗には経験豊富なスタッフが常駐しており、家づくりが初めての方にも分かりやすく丁寧な対応を徹底。こうした“地域の顔が見える運営”が、全国モデルにはない安心感を生み出しています。4-3. 建てた後も寄り添う地域密着サポート池田建設のいえとち本舗が特に重視しているのが、「建てた後の安心」です。完成引き渡し後も、定期点検やアフターメンテナンスを自社で実施し、施工からアフターまでを一貫して責任を持つ体制を維持しています。時代の変化に合わせて太陽光や蓄電池の増設、断熱性能の見直しなど、“住まいのアップデート”を提案できる地域パートナーとしても機能しています。地元企業だからこそ、住まいの状態や家族のライフステージの変化を継続的に見守ることができる――。この“地域で完結する家づくり”の安心感が、多くのOB施主から高い信頼を得ている理由です。5. まとめ ― 全国ブランドの枠を超えた、山口発の住宅ブランドへ5-1. 全国ブランドの枠を超える“地域版アップグレード”いえとち本舗は、全国で“土地と建物をセットで提案する”という画期的な仕組みを築き上げ、多くの人に「マイホームをより身近にする」きっかけを与えてきました。その理念を受け継ぎながら、池田建設のいえとち本舗は独自の進化を遂げています。土地不足が課題となる山口県で、最適な土地を提案し、平屋を中心に暮らしやすさを追求した設計とG2仕様・耐震等級3を標準化。さらに、地域の気候・文化・生活リズムに合った自社開発ブランド(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を展開することで、全国モデルにはない“山口版アップグレード”を実現しています。全国ブランドの安心感と、地域企業の柔軟な対応力を両立させた存在――それが池田建設のいえとち本舗です。5-2. 山口の暮らしに寄り添う、これからの家づくりへ家づくりは、単に建物をつくることではなく、その土地でどう暮らしていくかをデザインする行為です。池田建設のいえとち本舗は、山口という地域で暮らす人々の価値観や生活スタイルを丁寧に汲み取り、性能・価格・デザインのすべてを“ちょうどいい”バランスで提案してきました。全国のいえとち本舗が築いてきた信頼を背景にしながらも、地域に合わせて進化し続ける――その姿勢こそが、池田建設の強みです。これからも同社は、山口の人々が“無理なく、永く、快適に”暮らせる住まいを提供し続けていくでしょう。「山口で建てるなら、山口を知る会社へ。」その言葉を体現する存在として、池田建設のいえとち本舗はこれからも地域の未来をつくり続けます。6. FAQ Q1. 山口県のいえとち本舗と全国の違いは? 全国のいえとち本舗は共通仕様の商品ラインを展開していますが、株式会社池田建設が運営する山口のいえとち本舗では、それらの本部商品は取り扱っていません。代わりに、山口の気候・土地事情・平屋需要に合わせて独自に開発した「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」という3ブランドを展開。全棟G2仕様・耐震等級3を標準化し、地域に最適化された“山口版のいえとち本舗”として進化しています。 Q2. 高性能なのに価格を抑えられる理由は? 広告や外注を最小限にし、資料やチラシ、Web制作まで自社で行うことでコストを削減。その分を性能やアフター体制に還元しています。過度な宣伝よりも、品質とお客様満足に投資する方針です。 Q3. G2仕様とはどのような性能ですか? G2仕様は、国の省エネ基準を上回る断熱等級6相当の性能です。冷暖房効率が高く、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちます。池田建設のいえとち本舗では全シリーズで標準採用しています。 Q4. 平屋を希望していますが、対応できますか? はい。山口県は平屋人気が特に高く、池田建設では限られた土地を有効活用できる平屋設計を多数ご用意しています。間取り・採光・収納計画までワンフロアで完結する快適な住まいをご提案します。 Q5. 見学や相談はどこでできますか? 山口県内の6店舗(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)で随時ご相談を承っています。ご予約は公式サイト(https://smarthouse-yamaguchi.jp/)からお気軽にお申し込みください。 (function() { var id = location.hash ? location.hash.slice(1) : ""; if (!id) return; var el = document.getElementById(id); if (el && el.tagName.toLowerCase() === "details") { el.setAttribute("open",""); } })();{ "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "LocalBusiness", "@id": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/#localbusiness", "name": "いえとち本舗 山口(株式会社池田建設)", "image": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/assets/img/logo.png", "url": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/", "telephone": "083-941-5963", "priceRange": "¥¥¥", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "山口県山口市大内千坊6丁目9-1", "addressLocality": "山口市", "addressRegion": "山口県", "postalCode": "753-0221", "addressCountry": "JP" }, "geo": { "@type": "GeoCoordinates", "latitude": 34.1623, "longitude": 131.4737 }, "openingHours": "Mo-Su 10:00-18:00", "sameAs": [ "https://www.instagram.com/ietochi_yamaguchi/", "https://www.facebook.com/smarthouseyamaguchi/" ] }, { "@type": "FAQPage", "@id": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/#faq", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "山口県のいえとち本舗と全国の違いは?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "全国のいえとち本舗は共通仕様の商品ラインを展開していますが、株式会社池田建設が運営する山口のいえとち本舗ではそれらの本部商品を取り扱っていません。代わりに、山口の気候・土地事情・平屋需要に合わせて独自に開発した「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」という3ブランドを展開。全棟G2仕様・耐震等級3を標準化し、地域に最適化された“山口版のいえとち本舗”として進化しています。" } }, { "@type": "Question", "name": "高性能なのに価格を抑えられる理由は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "広告や外注を最小限にし、資料やチラシ、Web制作まで自社で行うことでコストを削減。その分を性能やアフター体制に還元しています。過度な宣伝よりも、品質とお客様満足に投資する方針です。" } }, { "@type": "Question", "name": "G2仕様とはどのような性能ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "G2仕様は国の省エネ基準を上回る断熱等級6相当の性能で、冷暖房効率が高く、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちます。池田建設のいえとち本舗では全シリーズで標準採用しています。" } }, { "@type": "Question", "name": "平屋を希望していますが、対応できますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "はい。山口県は平屋人気が特に高く、池田建設では限られた土地を有効活用できる平屋設計を多数ご用意しています。間取り・採光・収納計画までワンフロアで完結する快適な住まいをご提案します。" } }, { "@type": "Question", "name": "見学や相談はどこでできますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "山口県内の6店舗(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)で随時ご相談を承っています。ご予約は公式サイト(https://smarthouse-yamaguchi.jp/)からお気軽にお申し込みください。" } } ] } ]}