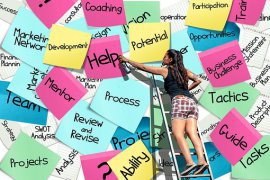ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
一戸建ては何年住める?中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説

築40年や築50年の中古一戸建ての購入を検討している方は、あと何年住めるかが気になるのではないでしょうか。住宅の寿命は30年といわれることもあり、築年数が経過した中古一戸建てを購入する際は不安になってきます。
この記事では、中古住宅の寿命と長く住み続けるためのポイントを解説します。一戸建ての本当の寿命を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1.一戸建ての寿命は何年?

一戸建ての寿命は30年といわれることがありますが、築30年や築35年が経過すると住めなくなるのでしょうか?一戸建ての寿命を知るには、法定耐用年数や期待耐用年数などを理解することが必要です。ここでは、一戸建ては何年住めるかを解説します。
1-1.建物の寿命は法定耐用年数とは異なる
建物の寿命は法定耐用年数とは異なります。木造住宅の法定耐用年数は22年ですが、築後22年が経過すると寿命がきて住めなくなるわけではありません。法定耐用年数は建物の資産価値がなくなるまでの年数を想定して定められています。
木造住宅の場合、築後22年が経過すると資産価値はなくなりますが、建物の物理的状態に問題がなければ住み続けることはもちろん可能です。ただし、建物の老朽化や設備の劣化が進行している場合はメンテナンスやリフォームが必要になることがあります。
一般的に築30年以上経過している木造の中古一戸建ては建物の資産価値がなくなっており、土地価格だけで購入できる場合があります。しかし、安く購入できてもメンテナンスやリフォームの費用がかかることがあるため注意が必要です。
1-2.木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上
木造住宅の寿命は30年といわれることがありますが、これは日本の住宅の平均利用期間が30年であるためです。
日本人は新築志向が高く、築30年以上経過すると建物を取り壊して新築住宅を建設、購入する傾向があります。まだ住めるのに建物を解体するケースは多く、諸外国と比べると住宅の平均利用期間が短い原因になっています。
木造住宅の実際の寿命を知るうえで参考になるのは、国土交通省が定める期待耐用年数です。期待耐用年数とは、適切な維持管理を行った場合における建物が使用できる期間を指します。
木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、メンテナンスやリフォームを適切に行うことで、築40年や築50年であっても住み続けられる可能性は十分あります。
出典:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」
1-3.長期優良認定住宅は75~90年以上の耐久性がある
長期優良住宅とは、国が定める耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなどの基準を満たした住宅を指します。長期優良住宅は一般の住宅よりも品質が優れており、期待耐用年数は100年を超えます。
耐震性も優れており、震度6強から7程度の大地震でも倒壊することはありません。断熱性能も高く、冷暖房の効きが良くなることで光熱費の削減にもつながります。
長期間にわたって良好な状態で使用するにはメンテナンスが欠かせませんが、長期優良住宅は維持管理がしやすいように設備が設置されており、メンテナンスも容易です。
また、長期優良住宅の認定を受けると、フラット35の金利が0.25%引き下げられたり、税の特例措置が拡充されたりするなどの優遇が受けられます。
2.一戸建てに長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠

一戸建ては30年以上の寿命がありますが、長く住み続けるためにはメンテナンスが不可欠です。適切なメンテナンスを行うことで、一戸建ての寿命をさらに延ばせます。ここでは、一戸建てのメンテナンスやリフォーム、リノベーションを解説します。
2-1.定期的に住宅の点検を行い劣化や損傷を早期に発見する
一戸建ての寿命を延ばすには、定期的に住宅の点検を行い、建物の劣化や損傷を早期に発見することが大切です。修理や補修を迅速に行うことで、将来における深刻な問題の発生を予防し、住宅の安全性を確保できます。
自主点検で重要な箇所は、浴室や洗面所、トイレ、キッチンなどの水回りです。水回りは劣化しやすいため、日頃からの点検が重要になってきます。
日常の点検は、目視できる範囲で行うようにしましょう。目視できない箇所については、ホームインスペクター(住宅診断士)に点検してもらうと不具合箇所が明確になります。目視できない箇所のホームインスペクションの費用相場は、6~12万円程度です。
なお、ホームインスペクションの費用については、地域や業者によって異なるため、事前に複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。
2-2.メンテナンス・リフォーム・リノベーションを行う
点検で不具合箇所が見つかれば、早期にメンテナンス(修繕)を行うことが大切です。住宅を建築した施工業者や修理・修繕業者、工務店、リフォーム会社などに相談すると良いでしょう。
水回りや外壁、屋根などは、劣化が進行しやすいため、築年数に応じて定期的なリフォームが必要です。リフォームとは、劣化した箇所を元の状態に戻すことです。
水回りリフォームは築15~20年、外壁や屋根は築10~20年程度がリフォームの目安です。定期的なリフォームを行うことで、一戸建ての寿命を延ばせます。
間取りを変更するなど、大規模な改装・改修をして建物の価値を高めたい場合はリノベーションを行いましょう。リノベーションをすることで建物の価値が高まり、居住性が大きく向上します。築20年が経過して築30年を迎えた頃がリノベーションを行う目安です。
3.一戸建ての寿命が近づいたときの対処法

一戸建ての寿命が近づいたときは、全面リフォームやリノベーション、建て替え、売却など、いくつかの選択肢があり、最も適切な方法を選ぶことが大切です。ここでは、一戸建ての寿命が近づいたときの対処法を解説します。
3-1.全面リフォーム・リノベーションを行う
寿命が近づいた建物を解体せず、改装・改修をしてそのまま住みたい場合は、全面リフォームやリノベーションがおすすめです。ただし、工事箇所が多い場合は、建物を解体して建て替えたほうが費用を抑えられることもあります。
複数の業者と相談して見積もりを取り、全面リフォームやリノベーションと建て替えのどちらにするのかを決めましょう。国土交通省の調査資料によると、全面リフォームの費用は500~2,500万円程度が目安です。リノベーションも同程度の費用がかかります。
ローコスト住宅であれば総額1,000万円台で建て替えができます。そのため、リフォーム費用が予想以上に高額であれば、建て替えを検討するのも一つの選択肢です。
3-2.建て替えを行う
日本人は新築志向が高いため、一戸建ての寿命が近づいたときに建物を解体して、新築住宅に建て替えることはよく行われます。建て替えのメリットは理想とする新築住宅に住めることで、ローンを組みやすいこともメリットです。
一方、デメリットは建物が完成するまでに4~6ヵ月以上かかり、建て替え工事中は一時的に賃貸マンションなどに転居する必要があります。仮住まいの家賃や引っ越し費用なども考慮しなければなりません。
建て替えの費用は新築する建物のグレードによって異なりますが、1,000~4,000万円程度の費用がかかります。長期的な視点で考えて、リフォームをするよりも建て替えのほうがメリットが大きい場合は、建て替えをおすすめします。
3-3.住宅を売却して住み替える
一戸建ての寿命が近づいた場合、全面リフォームや建て替えを行わず、売却して住み替えるという選択肢もあります。ただし、古い建物は値段がつかない場合があるため、建物を解体して更地にして売却することも検討しましょう。
建物の状態にもよりますが、建物を解体して更地にしたほうが早く売れる場合があります。建物の解体費用は、建物の構造や延床面積によって異なりますが、30坪の木造住宅だと90~150万円程度が相場です。
なお、住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、ローンを完済して抵当権を抹消しなければなりません。今住んでいる一戸建てを売ったお金でローンを完済できなければオーバーローンになるため注意が必要です。
4.中古一戸建てを購入するメリット

一戸建ての実際の寿命は30年以上あるため、メンテナンスやリフォームが適切に行われていれば、中古一戸建てを購入するメリットは大きいです。ここでは、中古一戸建てを購入するメリットを解説します。
4-1.新築よりも安い価格で購入できる
新築よりも安い価格で購入できることが、中古一戸建てを購入する最大のメリットです。築30年以上経過していると、土地価格のみで購入できる場合があります。
物件によっては、土地の相場価格以下で購入できることもあり、予算が少なくても住みたかったエリアにマイホームを持てる可能性が高まります。新築では購入が難しい駅チカや都心の物件の取得も可能になることは、中古一戸建ての大きな魅力です。
建物の老朽化が進んでいる場合も、リフォームやリノベーションをすることで、新築住宅と変わらない状態に再生できるため、リフォーム費用を考慮してもお得な場合があります。なお、購入後にリフォームやリノベーションをする場合は、どの程度の費用がかかるかを把握しておくことが大切です。
4-2.実際に物件を確認してから購入できる
実際に物件を確認してから購入できることも、中古一戸建てのメリットです。新築住宅は完成しないと物件を確認できません。中古一戸建ては既に物件が存在するため、外観や内観、日当たりなどを自分の目で確認できます。
実際に住んでからのイメージがしやすく、入念に調査をすれば住んでから後悔することは少ないでしょう。修繕やリフォームが必要な箇所も、直接目で見て把握できます。なお、不具合や修繕が必要な箇所がある場合、それを考慮して価格交渉の材料にすることも可能です。
物件を確認する際は、ホームインスペクション(住宅診断)を依頼すると、プロの視点で物件の確認ができます。目視ができない箇所も確認できるため、不動産購入時の安全性が高まります。
4-3.立地や間取りなどの選択肢が豊富
中古一戸建ては不動産市場での流通量が多く、立地や間取りなどの選択肢が豊富です。新築住宅は物件数が限定しており、学区や最寄り駅などにこだわりがある場合、なかなか物件が見つからないことはよくあります。その点、中古一戸建ては物件数が多いため、理想の住宅に巡り会える可能性が高いです。
中古一戸建てにはさまざまな間取りがあり、家族のニーズやライフスタイルに合った間取りを選べます。家族構成や将来の計画などに応じて、間取りを柔軟に選択できることは中古一戸建てのメリットです。
また、中古一戸建ては既に建物が完成しているため、即座に入居できる場合が多いです。新築物件よりも迅速な入居が可能であり、急な住み替えや引っ越しにも適しています。
5.中古一戸建てを購入するデメリット

一戸建ての寿命は30年以上ありますが、メンテナンスやリフォームが適切に行われていることが前提です。中古一戸建ては物件によっては劣化が進行しているなどのデメリットがあります。ここでは、中古一戸建てを購入するデメリットを解説します。
5-1.建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性がある
物件によっては、建物の老朽化や設備の劣化が進行している可能性があります。一戸建ては適切なメンテナンスやリフォームを行うと寿命を延ばせますが、そのまま放置しておくと老朽化や劣化が進行します。
老朽化や劣化が酷い場合、メンテナンスやリフォーム費用が発生する可能性が高いです。屋根や外壁の補修、配管や電気設備の更新、内部の改装などで100~200万円以上かかる場合もあります。
なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古住宅は耐震性に問題がある可能性があり、注意が必要です。耐震補強工事を行っていない場合、震度5程度の地震には耐えられますが、震度6強~7の地震には耐えられず、倒壊する危険性があります。
5-2.修繕やリフォームの費用がかかる可能性がある
購入時には修繕やリフォームが必要なくても、住み始めてから修繕やリフォームの費用がかかる可能性があります。築年数が経過した中古一戸建ては、新築と比べると建物や設備の劣化のスピードが速く、住み始めてすぐに修繕が必要になることもあるでしょう。
購入前に建物の状態を調査し、将来の修繕やリフォームの費用を考慮することが重要です。しかし、将来的なリフォーム費用は予測しにくく、想定以上の費用がかかることもあります。
なお、1981年(昭和56年)以前に建築された中古一戸建てで、耐震補強工事を行っていない場合は、購入後に耐震補強工事が必要です。耐震補強工事の費用相場は100~200万円程度で、工期は1週間〜1ヵ月程度かかります。
5-3.住宅ローンの審査が厳しくなる可能性がある
中古一戸建ては新築住宅と比べると、住宅ローンの審査が厳しくなる可能性があります。これは、建物の資産価値が低下しているため、担保価値が低くなるためです。住宅ローンの種類や建物の状況によっては、審査に落ちることもあるでしょう。
立地条件が悪く、建物だけでなく土地の資産価値も低い中古一戸建ては、審査に落ちる可能性が高まります。
なお、新築住宅は頭金なしのフルローンや諸費用込みローンを利用できる場合がありますが、中古一戸建ては諸費用込みローンの利用は難しいです。建物の状況によってはフルローンの審査も落ちる可能性があります。
住宅ローンを組んで中古一戸建てを購入する際は、事前に仮審査を受けておくことが大切です。
6.中古一戸建てを購入する際の注意点

中古一戸建ては新築よりも安いなどのメリットがある反面、老朽化が進行している可能性があるなどのデメリットがあります。中古一戸建てを購入する際は、デメリットも考慮することが大切です。ここでは、中古一戸建てを購入する際の注意点を解説します。
6-1.建物の現状をしっかりと確認する
中古一戸建てを購入する際は、建物の現状をしっかりと確認することが極めて重要です。目視できない箇所まで入念にチェックすることが大切であり、ホームインスペクションの利用をおすすめします。
ホームインスペクションは、建物の構造や設備、電気・配管などの重要な部分を専門家のホームインスペクターが詳細に調査します。これにより、潜在的な問題や隠れた欠陥の発見が可能です。
ホームインスペクションで明らかになった問題は、価格交渉の際に有利な材料となります。修繕が必要な場合、その費用を考慮して値下げを要求できます。
6-2.契約不適合責任を確認する
契約不適合責任とは、2020年の民法改正で定められたもので、旧民法の瑕疵担保責任に類似する売主の責任です。契約不適合責任は、目的物の現状と契約の内容に不一致があれば成立し、売買や賃貸借などの契約に適用されます。
売主は買主の選択によって、目的物の補修、代替物の引き渡し、代金減額、契約解除のいずれかによって責任を履行しなければなりません。例えば、購入した物件がシロアリによる被害を受けていたことが発覚したような場合、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。
なお、売主が個人・不動産会社によって保証期間が異なり、不動産会社は最低2年、個人は売主が自由に決められます。契約内容をしっかりと確認することが大切です。
6-3.予算に余裕を持たせる
中古一戸建てを購入する際は、予算に余裕を持たせることが大切です。土地価格や建物価格だけでなく、仲介手数料や登録免許税、印紙税、司法書士報酬などの諸費用もかかるため、予算に余裕を持たせておかないと資金不足に陥る可能性があります。
修繕費やリフォーム費用がかかる場合もあるため、物件価格だけでなくトータルコストで考えましょう。事前にトータルコストをシミュレーションしておくことをおすすめします。これにより、予想外の支出に対処できる余裕を確保できます。
7.まとめ:メンテナンスやリフォームで住宅の寿命を延ばせます!

木造住宅の期待耐用年数は30~80年以上であり、30年以上の寿命があります。長期優良住宅の期待耐用年数は100年を超えるため、親子孫の3代にわたって住み続けることが可能です。
一戸建てに何年住めるかは、定期的なメンテナンスやリフォームによって違ってきます。メンテナンスやリフォームを行うことで住宅の寿命を延ばせます。適切な維持管理ができていれば、築30年以上の中古一戸建ては価格が安く大変お得です。
なお、中古一戸建てを購入する際は、ホームインスペクションの利用もおすすめです。目視ができない箇所も専門家に確認してもらうことで、安心して購入できます。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹

不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
関連記事
-

気密性とは?重要性やメリット・デメリットを解説
高断熱・高気密の家というのをよく目にしませんでしょうか。断熱は熱を遮断するためのもので、快適な部屋にするためにとても必要な性能です。それでは、なぜ断熱と一緒に気密性が必要になるのかご存知でしょうか。快適な家にするためには断熱と一緒にこの気密性もとても大切になってきますので、ぜひどういうものか知っておきましょう。この記事は気密性のことについてご紹介します。1 気密性とは何か?2 住宅の気密性が悪いとどうなるの?3 住宅の気密性が必要な理由とは4 気密性が高い住宅に住むメリット5 気密性が高い住宅に住むデメリット6 まとめ気密性とは何か? 気密性とは家の密閉性を表すもので簡単に言ってしまうと、隙間がたくさんあるのか、それとも隙間が少ないか、ということです。隙間のある家は外からの風が入りやすくなるため安定した室温を維持しにくくなります。服に例えますと気密性が高い服というのは風が服の中にまで入ってこないということです。どんなにウールで包まれた暖かい服を着込んでいても風が服の中に入ってきてしまっては全然体は温かくなりません。それに代わって風が服の中に入ってこなければ当然体は温まってきます。家も一緒でどんなに断熱性の高い家でも隙間があると温度は変化してしまい快適な室温にはなりません。古い木造住宅を思い浮かべてください。昔の木造住宅は隙間がたくさんあり隙間風がよく入りました。冬場は隙間風が入って寒いという経験はないでしょうか。このような隙間風が入る家は気密性の低い家ですので快適性は落ちます。快適に生活していくためには外部からの影響を受けにくくするために気密性を高めることがとても重要になります。 住宅の気密性が悪いとどうなるの? 気密性が悪いということは、家に隙間が多くあり、外気が室内に入り込みやすくなります。外気が入ることで室温は安定性を失いますので、夏場や冬場の極端な熱がそのまま部屋にも反映されてしまいますので、夏は暑く、冬は寒い部屋になってしまいます。これは断熱性も関わってきますが、気密性の低さは室内の熱が外に逃げてしまいやすいため、冷暖房の効率も下がってしまいます。冷暖房効率が悪いとその分エアコンのエネルギー負担が大きくなるため電気代が高くついてしまい経済的によくありません。また、温度の変化は内外の温度差を生じ、結露の発生や体への負担も大きくなります。特に注意しておきたいのがヒートショックです。ヒートショックを起こす主な原因は温度差です。暖かい部屋から寒い部屋に移動したり、その逆の移動をしたりすると、血管の伸縮が起こり血圧は変動します。血圧が高くなったり、低くなったりすると、心筋梗塞や脳梗塞、めまい、ふらつきなどを起こす恐れがありますので、温度差は思っているよりも体への負担が大きくなります。高齢者や疾患を持っている方は特に負担が大きいですので、温度変化の少ない室内環境にすることが重要です。 住宅の気密性が必要な理由とは 快適に生活するためには、暮らしやすい室温であることが重要です。快適性は安定した室温を維持していくことですので、気密性はぜひ重視しておいて欲しい性能になります。 【結露を抑え建物の老朽化を防ぐ】 暖かい家というと断熱性を思い浮かべるかもしれませんが、断熱性が高くても気密性が低ければ、十分な性能を発揮しきれません。また、気密性が低いと結露を起こす可能性があります。断熱は室内や屋外からの熱を遮断するものですので、隙間があればそこから熱の移動が起きてしまい、そこが温度差を生じ結露を発生させてしまいます。そのため断熱性を高めた家は同時に気密性も高めることが重要ということです。特に壁内結露は要注意です。壁や窓の表面に結露が発生するのなら目に入り気がつきやすいのですが、壁の中だと結露していることに気がつくことが難しいです。そのまま放置し続けてしまうと表面に出てきたころには腐食していたり、カビで黒ずんでしまっていたりするかもしれません。構造体の腐食は建物の耐久性を低下させ老朽化を早めることになりますので、家を長持ちさせるためには気密性を高めておくことも重要です。【均一な換気ができる】 建物は室内に水蒸気や二酸化炭素、臭いが溜まりますので、ちゃんと換気して新鮮な空気を取り入れることが重要です。気密性にばらつきのある家は新鮮ではない空気が滞りますので、嫌な臭いが部屋に充満してしまい体にもよくありません。気密性が高いことが屋内の空気を流動させるわけではありませんが、全体的に気密化されていることで、均一に換気ができるため臭いが充満しなくなり、新鮮な空気を屋内に取り込むことができます。【安定した室温と省エネで電気代が節約。災害時での生活も有効】 気密性と断熱性を高めることで熱の移動が少なくなり安定した室温を維持しやすくなります。外の気温に影響されやすい家ですと、屋内の温度を調節するために冷暖房機器でコントロールしなければいけませんが、このコントロールする幅が大きいほどエネルギーの負荷が大きく省エネから遠ざかってしまいます。他にも断熱性も必要になりますが、二つの性能が組み合わさることで、冷暖房効率が良くなり、エアコンを使う電気代も節約することができます。また、一定の室温に維持しやすいということは災害時にライフラインが止まってしまった時にも有効です。高断熱・高気密の家は自然室温が高い傾向にありますので、エアコンなどの冷暖房機器が使えなくても過ごしやすい環境を確保できます。 気密性が高い住宅に住むメリット 気密性の高い住宅に住むメリットは以下のことが挙げられます。 冷暖房効率が良くなり電気代が安くなる温度差が少なくなり身体に優しい環境となる遮音性が高くなる 冷暖房効率が良くなり電気代が安くなる 気密性が高くなることで室温は安定しますので、エアコンでの室温調整も安定します。気密性が低いと快適な温度にするためにエアコンの温度を高くしたり、低くしたりと調整幅がありエネルギーの負担が大きくなります。それに代わって高気密な家は温度を調節する幅も狭くなるためエネルギー負担も小さくなり電気代が安くなります。温度差が少なくなり身体に優しい環境となる これは断熱性も必要になりますが、高気密にすることで部屋間の温度差が生じにくくなり、健康的な生活を送れる室内環境を手にすることができます。温度差は思っているよりも体への負担が大きく、前述したヒートショックを起こす恐れがありますので注意しましょう。遮音性が高くなる 気密性の高さは家の遮音性にも影響を与えます。家の前に交通量の多い道路があったり、学校の近くや通学路であったりなど、騒音を感じやすい環境の場合は気密性を高めると外からの音を遮り静かな暮らしができます。高気密の家は遮音性も高くなるため、騒音を危惧する方はぜひ検討してもらいたいです。 気密性が高い住宅に住むデメリット 気密性を高めることで生じるデメリットもありますので注意しましょう。気密性が高いということは、より隙間がなく密閉されているということのため、換気をしていないと空気や湿気がこもります。空気の循環がないと建材の化学物質が揮発したり、カビやダニ、埃などのハウスダストが舞ってしまったりするため、シックハウス症候群などの健康障害を起こす可能性があります。そのため現在の住宅は24時間換気を設けることを義務付けています。気密性の高い家は密閉され空気の流動が少なくなりますので、必ず換気されていることが重要です。また、気密性が高いことで夏場は部屋が暑くなりやすいのがデメリットです。エアコンで室温を調整する必要が出てきますので、密閉されていないという意味では通気がされている部屋と比べると冷房の負荷は大きくなります。 まとめ 気密性を高めることは快適に生活できる家を建てるために重要な性能です。気密性を高くすることで一定の室温に維持がしやすく、冷暖房効率も良くなりますので、電気代の節約にもなります。気密性は断熱性と組み合わせることが重要ですので、設計の際は気密性と一緒に断熱性を高めることも計画しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-

電気代・災害・エコに備える!家庭用蓄電池の基礎知識と活用法
1. 蓄電池とは?1-1. 蓄電池の仕組み1-2. 蓄電池の種類2. 蓄電池導入のメリット2-1. 停電時の安心2-2. 電気代の節約2-3. 太陽光発電との相性2-4. 環境への配慮2-5. 災害対策3. ニチコン製蓄電池の特徴3-1. 多様なラインナップ3-2. 高い安全性と耐久性3-3. V2Hとの連携3-4. 国内生産とサポート体制4. 実際に導入したご家庭の事例4-1. オール電化住宅での導入事例(山口市・4人家族)4-2. 築20年の住宅に後付けしたケース(周南市・ご夫婦2人)4-3. 子育て家庭に人気の導入モデル(宇部市・5人家族)5. 予測される電気代の高騰とその対策5-1. 電気代は今後どうなる?5-2. 蓄電池で電気代高騰に備える5-3. 長期的な光熱費の最適化へ6. 蓄電池導入のすすめ7. 「イエミライ」について 1. 蓄電池とは?1-1. 蓄電池の仕組み蓄電池とは、電気を貯めておき、必要なときに使用できる装置です。スマートフォンやノートパソコンに内蔵されているバッテリーと同じような原理で、電気を充電し、後から放電することができます。住宅用の蓄電池に多く使用されているリチウムイオン電池は、軽量で高エネルギー密度を持ち、長寿命であるという特長があります。家庭内に設置された蓄電池は、太陽光発電によって発電された電力を一時的に貯蔵し、夜間や天候不良で発電できない時間帯、あるいは停電などの非常時に備えるために活躍します。また、最近の蓄電池はAI制御やスマートメーターと連携することで、電力使用の最適化を図れるなど、ますます高性能化が進んでいます。これにより、家庭ごとの使用パターンに応じて、蓄電・放電のタイミングを自動で最適化できる機種も登場しています。1-2. 蓄電池の種類家庭用蓄電池には、大きく分けて以下の3種類があります。それぞれの特長を理解し、目的に合った選択をすることが重要です。単機能型蓄電池:既に太陽光発電を導入している家庭におすすめです。太陽光システムとは別のパワーコンディショナーが必要になりますが、既存システムに追加設置しやすく、費用を抑えた導入が可能です。導入コストが比較的安価であることから、コスト重視の方に選ばれています。ハイブリッド型蓄電池:太陽光発電と蓄電池が一体型で制御できるタイプ。パワコンも一体化しており、設置スペースや配線の簡素化が図れます。新築時や太陽光システムの更新と同時に導入するケースに適しています。また、効率的に太陽光エネルギーを活用したい方に適しています。トライブリッド型蓄電池:太陽光発電と蓄電池、さらにV2H(電気自動車との連携)を可能にした最先端モデル。EVを家庭の蓄電源として活用するという新たな電力活用モデルを支える機器です。将来を見据えたスマートライフを実現したい方にぴったりです。 2. 蓄電池導入のメリット2-1. 停電時の安心万が一の停電は、災害時に限らず設備トラブルやメンテナンスなどでも発生します。そんなときに、蓄電池があれば冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など、生活に不可欠な家電の使用が継続できます。特に小さなお子様がいるご家庭や高齢者の方がいるご家庭では、停電が長引くと大きな不安につながります。蓄電池は“見えない保険”として、日々の生活に安心をプラスしてくれます。夜間に停電が発生した場合も、自動的に電力を供給できるシステムもあり、非常に頼もしい存在です。2-2. 電気代の節約電力会社の時間帯別料金を上手に活用することで、蓄電池は電気代の節約にも大きく貢献します。夜間の安い時間に充電し、昼間の高い時間に使用することで、ピークシフトを実現できます。また、電力の自家消費率を上げることで、再エネ賦課金の抑制や電気使用量全体の削減にもつながります。光熱費の見直しを考えている方にとって、蓄電池は非常に有効な選択肢です。電気料金が不安定な今の時代だからこそ、安定した電力供給とコストコントロールが求められています。2-3. 太陽光発電との相性売電価格の下落に伴い、太陽光発電で得た電力は「売る」から「使う」時代へとシフトしています。蓄電池を併用することで、昼間発電した電力を夜間にも使うことができ、再生可能エネルギーの有効活用が可能になります。昼間に発電し余った電力を貯めておけば、外出先から帰ってきた後も電力を自給自足できます。まさに“発電した電気を無駄なく使える”スマートな暮らしが実現するのです。こうしたライフスタイルは、将来的には電力会社への依存を減らし、より持続可能なエネルギー利用を支える基盤となります。2-4. 環境への配慮CO2排出削減や地球温暖化防止の観点からも、家庭用蓄電池は注目されています。太陽光発電と併せて使うことで、火力発電に頼らない電力使用が可能となり、再生可能エネルギーの拡大に貢献します。国や自治体の補助金制度とも相性が良く、導入時のコストを軽減しながらエコな暮らしをスタートできるのも大きな魅力です。次世代にきれいな地球を残すという観点からも、今できることの一つとして蓄電池は有効な選択肢になります。2-5. 災害対策災害時に電力を確保できるかどうかは、生活の質を大きく左右します。蓄電池があれば、ライフラインの1つである“電気”を自宅で備蓄することができ、食料・水と並ぶ災害時の備えとなります。避難所に行かずとも最低限の生活が送れるということは、家族の安心にもつながります。防災意識が高まる中で、電力の「備え」を意識する家庭が増えているのも納得です。蓄電池は、電気を使った暖房や給湯設備を維持する手段にもなり、寒冷地などでは命を守る設備ともなり得ます。 3. ニチコン製蓄電池の特徴3-1. 多様なラインナップニチコンは、単機能型からトライブリッド型まで、幅広いラインナップを揃えています。小規模な2kWhから、大容量の16.6kWhまで、多彩なニーズに応えられる製品が豊富です。家族構成や住まいの規模、ライフスタイルに応じて最適な容量を選べるため、導入後の後悔が少なく、長期的な満足度も高いと評判です。さらに、今後の生活スタイルの変化にも対応しやすい柔軟な設計が施されています。3-2. 高い安全性と耐久性日本の厳しい安全基準をクリアし、長寿命を実現しているニチコン製蓄電池は、10~15年の長期保証が標準で付帯。過酷な気象条件下でも安定して稼働し、日々の生活をしっかり支えます。独自の冷却構造や発熱抑制機構も取り入れられており、万が一の事故リスクを最小限に抑える設計です。また、火災や感電のリスクも極めて低く、安全性に優れた構造を持つことで、家庭でも安心して使用することができます。3-3. V2Hとの連携ニチコンは、電気自動車の電力を家庭に供給する「V2H」システムの分野でも国内トップクラスの実績があります。将来的にEV導入を考えている方にとって、ニチコン製蓄電池は拡張性が高く、大きな安心材料となるでしょう。V2Hにより、EVが非常時の電力供給源にもなることで、家庭全体の電力レジリエンスが飛躍的に向上します。電気自動車と家庭との連携が進むことで、より効率的なエネルギーの使い方が実現します。3-4. 国内生産とサポート体制すべて国内で製造されているため、品質や信頼性が非常に高く、安心して導入できます。また、アフターサポート体制も充実しており、万が一のトラブル時にも迅速な対応が期待できます。メンテナンスのしやすさやサポートの質も、多くの導入ユーザーから高い評価を受けています。特に住宅設備としての導入後の安心感は、国内ブランドならではの魅力です。 4. 実際に導入したご家庭の事例4-1. オール電化住宅での導入事例(山口市・4人家族)山口市にお住まいの4人家族、仮名・佐藤様ご一家では、オール電化住宅と太陽光発電を導入済みでしたが、売電価格の低下により自家消費を意識するようになり、ニチコン製11.1kWhの蓄電池を新たに導入されました。結果として、日々の電気代が以前よりも抑えられている実感があり、日常のエネルギー管理がしやすくなったと感じているそうです。また、災害時の備えとしても非常に安心できるとご満足いただいています。4-2. 築20年の住宅に後付けしたケース(周南市・ご夫婦2人)周南市の仮名・吉田様ご夫婦は、築20年の住宅にお住まいで、これまで太陽光発電は導入していませんでしたが、将来の停電リスクと老後の電気代を見据えて蓄電池8.0kWhを新設。ハイブリッド型パワコンとセットで導入しました。導入後は「電気を買う機会が明らかに減った」「毎月の光熱費が以前よりも分かりやすくなり、支出の管理がしやすくなった」といった声があり、電気代が以前より安定し、負担が軽くなったと実感されています。4-3. 子育て家庭に人気の導入モデル(宇部市・5人家族)宇部市在住の仮名・村上様ご一家は、共働きで3人のお子さまを育てており、日中にせっかく発電した電気が売電に回ってしまうのがもったいないと感じていました。ニチコン製の12kWh蓄電池を導入したことで、発電した電力の有効活用が可能になり、電気代の削減にもつながっています。特にお子さまのいる家庭では、万が一の停電時に冷蔵庫や給湯、Wi-Fi環境などが維持できる安心感は非常に大きく、「家族の暮らしを守る設備」として非常に高い満足度を得られています。 5. 予測される電気代の高騰とその対策5-1. 電気代は今後どうなる?ここ数年、日本国内でも電気代がじわじわと上昇していることを実感されているご家庭も多いのではないでしょうか。その背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。まず第一に、エネルギーの多くを輸入に頼っている日本では、世界的な燃料価格の高騰がダイレクトに家計に影響します。特にロシアによるウクライナ侵攻などの地政学リスクは、天然ガスや石油の価格を不安定にし、結果として電力会社のコスト増に直結します。さらに、電力自由化により競争が激化する一方、燃料費調整制度の影響で、原油価格の高騰がそのまま電気代に転嫁されやすくなっています。また、日本政府が進める「脱炭素社会」への移行もコスト上昇の一因です。再生可能エネルギーへの転換には多額の初期投資が必要であり、その負担は再エネ賦課金などを通じて消費者にも求められています。これらの理由から、今後も電気代は中長期的に上昇する傾向が続くと予測されています。5-2. 蓄電池で電気代高騰に備えるこうした電気代の高騰に対抗する有力な手段の一つが、家庭用蓄電池の導入です。特に太陽光発電とセットで導入すれば、昼間に発電した電力を蓄えておき、夜間や曇天時に使うことで、電力会社から購入する電力量を大幅に削減することができます。さらに、電気料金の安い深夜帯に電力を蓄電池に貯め、日中の高い時間帯にその電力を使用する「ピークシフト」により、電気料金の変動リスクにも柔軟に対応できます。これは、今後ますます重要になるエネルギーの“価格安定性”という視点から見ても、大きな意味を持ちます。蓄電池は、単に非常時のバックアップ電源としてだけではなく、日常的な経済メリットを享受できる「電力のストラテジーアイテム」としての役割が期待されています。5-3. 長期的な光熱費の最適化へ電力コストが今後も不安定な推移を続ける中、光熱費の“固定費化”は家計にとって大きな安心材料になります。蓄電池を導入することで、自宅の電力消費の一部または大部分を自家発電・自家消費でまかなえるようになれば、将来的な値上がりリスクを大幅に軽減できます。また、再生可能エネルギーの活用は地球環境にもやさしく、CO2排出削減への貢献にもつながります。家庭でできるエネルギーシフトの一環として、蓄電池はまさに“未来を見据えた投資”といえるのではないでしょうか。エネルギーの自立、自給、安心のために──電気代高騰が続く今こそ、蓄電池の導入を本気で検討する価値があります。 6. 蓄電池導入のすすめ電気は、日々の暮らしに欠かせないインフラです。これまで「当たり前」に使えていた電力も、災害時や非常時には途絶える可能性があります。そんな時に、家庭用蓄電池があれば、電力の備蓄という安心感を得られます。また、再生可能エネルギーの活用や電気代の節約、環境配慮といった複数の観点からも、蓄電池は私たちの生活をよりスマートで持続可能なものへと進化させてくれます。太陽光発電とセットで導入することで、電力を「つくる・ためる・つかう」自給自足型のライフスタイルが実現します。特に長期的な視点で見ると、エネルギーコストの削減と安心の備えを同時に得られる蓄電池は、まさに未来への投資と言えるでしょう。弊社では、お客様のライフスタイルや電力使用状況を丁寧にヒアリングした上で、最適な蓄電池をご提案しております。導入に関する疑問や不安も、専門のスタッフが丁寧にご案内いたします。ご相談から設置後のサポートまで、安心してお任せいただける体制を整えております。未来の安心と快適な暮らしのために── 今こそ「家庭用蓄電池」の導入を真剣に考えてみてはいかがでしょうか? 7. 「イエミライ」について「イエミライ」は、太陽光発電・蓄電池・HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を標準搭載した、当社オリジナルのスマート住宅商品です。エネルギーの自給自足を目指し、災害時の備えと日々の電力コスト削減を両立。さらに、家全体の省エネ性能や快適な住環境にもこだわって設計されています。新築住宅をご検討の際には、「イエミライ」の導入を通して、これからの時代にふさわしいスマートな暮らしを実現してみてはいかがでしょうか。いえとち本舗の「イエミライ」を見てみる
-

あったら便利!な収納について【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の永井です(^^♪ 本日は周南・山陽小野田・宇部・山口・防府で新築住宅をお考えの方に、「あったら便利!な収納」についてお伝えします。 今から、宇部・山口・山陽小野田・防府・周南で新築住宅を建てようと思うと、様々な不安が出てくるかと思います。 山陽小野田・宇部・防府・山口・周南で新築住宅を建てるのに「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまうことはありませんか? 山口・防府・周南・山陽小野田・宇部で新築住宅を建てることは、ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです(>_