ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
ローコストで二世帯住宅は建てられる?費用や間取りなどについて解説

二世帯住宅はコストがかかるため、予算内で建築できるかが不安になるのではないでしょうか。ローコストの二世帯住宅も選択肢に含めると、予算内で建築できる可能性が高まります。 この記事では、ローコストの二世帯住宅の費用と間取りを解説します。お互いのプライバシーを確保しながら低コストで二世帯住宅を建てたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
二世帯住宅とは?

二世帯住宅とは、親子などの二世帯がひとつ屋根の下で暮らす住宅を指します。一般的な住宅にはないメリットがあり、親子の両世帯が助け合いながら暮らせます。子育てや介護が楽になり、相続税対策になる可能性があることは二世帯住宅ならではの魅力です。 戦前は親子二世帯が同居するライフスタイルが一般的でした。戦後に核家族化が進み、親子二世帯が同居するケースは少なくなっています。二世帯住宅は1970年代に誕生し、新しい住宅のスタイルとして定着しています。 二世帯住宅は住宅メーカーが考案した商品名で、建築基準法での定義はありません。完全同居型・部分共用型・完全分離型の3種類あり、ライフスタイルに合った間取りの二世帯住宅を建築できます。
ローコストで二世帯住宅は建てられる?

ローコストで二世帯住宅を建てることは可能です。予算の関係で二世帯住宅の建築を諦めていた場合でも、建築できる可能性があります。二世帯住宅の価格は坪数や間取り、所在する地域、依頼先などによって異なりますが、3,000~5,000万円程度が相場の目安です。 しかし、ローコスト住宅の建築を得意としているハウスメーカーや工務店に依頼すると、2,000~4,000万円程度で二世帯住宅を建築できます。ローコストメーカーは、建材を一括で大量に仕入れたり、広告宣伝費を削減したりすることで低価格を実現しています。 ただし、ローコストで二世帯住宅を建てる際には、シンプルな形にしたり水回りをまとめたりする工夫が必要です。
二世帯住宅の種類

二世帯住宅は完全同居型・部分共用型・完全分離型の3種類に分けられます。二世帯住宅を建築する際は、3種類のうちどのタイプにするかを決めなければなりません。タイプによってプライバシーの確保や生活利便性が異なるため、慎重な検討が必要です。 ここでは、完全同居型・部分共用型・完全分離型のそれぞれの特徴を解説します。
完全同居型
完全同居型は、一般的な一戸建て住宅に二世帯が同居するタイプの二世帯住宅です。玄関やリビング、キッチン、浴室などは親世帯と子世帯が共有します。一般的には高齢者の階段の上り下りを避けるため、親世帯の居室を1階に設け、子世帯の居室を2階に設けるケースが多いです。 完全同居型は、親世帯と子世帯が一致協力して子育てや介護をしたいファミリーに向いています。ただし、両世帯のプライバシーの確保は難しく、過干渉になったり衝突したりすることがあるため注意が必要です。お互いのプライバシーを尊重して暮らすことが大切になってきます。
部分共用型
部分共用型は、玄関やキッチンだけを共有するなど、一戸建て住宅を部分的に共有するタイプの二世帯住宅です。玄関やキッチンなどは二世帯で共有しますが、居住スペースは分離しており、お互いのプライバシーに配慮しながら同居できます。 完全同居型と完全分離型の中間のタイプで、親子の関係性とプライベート空間のバランスが取れることがメリットです。完全分離型と比べると建築費を低く抑えられることもメリットで、共有部分を多くするほど建築費は割安になります。 ただし、完全分離ではないため、両世帯のプライバシーの確保には限界があります。ルールを設けて共有部分の利用方法などを調整し、生活スタイルの違いによるトラブルを防ぐことが重要です。
完全分離型
完全分離型の二世帯住宅は、親世帯と子世帯が完全に独立した住宅ユニットを持つ住宅形態です。玄関を2ヵ所設置し二世帯が完全に分離して暮らす形態であり、「同居」というより「近居」に近く、お互いのプライバシーを完全に保てます。 左右に完全に独立した住宅ユニットを持つ「完全左右分離型」と、1階と2階に独立した住宅ユニットを持つ「上下完全分離型」があります。いずれのタイプも両世帯のプライバシーを完全に保てますが、建築費が高額になることがデメリットです。 また、両親が亡くなれば片側が空き家になるため、将来の利用方法も考えておく必要があります。完全分離型の二世帯住宅は、プライバシーを重視し、独立性を保つのに適しますが、建設費用や両世帯の距離感についての検討が重要です。
ローコストの二世帯住宅のメリット・デメリット

ローコストの二世帯住宅は、一般的なローコスト住宅と二世帯住宅の特性を併せ持っており、特有のメリット・デメリットがあります。ローコストの二世帯住宅を建築する際は、メリット・デメリットを総合的に検討することが大切です。 ここでは、ローコストの二世帯住宅に特有のメリットとデメリットをご紹介します。
ローコストの二世帯住宅のメリット
ローコストの二世帯住宅は、一般的な二世帯住宅と比べると建設費用を低く抑えられることがメリットです。完全同居型だと1,000万円台で建築できる可能性があり、完全分離型でも工夫を施すと2,000~3,000万円程度で建てられる場合があります。 一般的な二世帯住宅と同様に、お互いのプライバシーを確保しながら、家族間の交流の機会が増えることもメリットです。建築費を低く抑えつつ、二世帯住宅ならではのメリットを享受したいファミリーにとって、ローコストの二世帯住宅は最適な選択肢でしょう。
ローコストの二世帯住宅のデメリット
ローコスト住宅は間取りや設備の自由度が低く、希望する間取りや設備が実現できない場合があります。間取りや設備の変更が可能であっても、オプション追加費がかかります。また、断熱性能が低い建材が使用される可能性もあり、信頼できるローコストメーカーに依頼することが大切です。 一般的な二世帯住宅と同じく、プライバシーの確保などの問題が発生する可能性があることもデメリットになります。完全分離型にするとお互いのプライバシーを確保できますが、建築費が割高になるため注意が必要です。
ローコストの二世帯住宅にかかる費用

一般的なローコスト住宅の相場は坪単価30~50万円程度であり、二世帯住宅の仕様にすると坪単価45~60万円前後が目安です。 完全同居型の二世帯住宅であれば一般的なローコスト住宅と間取りは変わらないため、30~40坪であれば900~2,000万円程度で建築できる可能性があります。 部分共用型は間取りにもよりますが、40~50坪であれば1,800~3,000万円程度が相場の目安になるでしょう。完全分離型は最も建築費が高く、55~65坪であれば2,500~4,000万円程度が相場の目安です。 これはあくまでも相場の目安であり、実際の建築費は要望を伝えたうえで見積もりを取得し、確認すると良いでしょう。
ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際のポイント

ローコストに限らず、二世帯住宅は間取りが最も重要であり、間取りによってプライバシーの確保や生活利便性が変わってきます。「親世帯と子世帯のプライバシーの確保」「動線の効率化」「将来の変化に対応」の3点が、間取りを決める際の重要なポイントです。 ここでは、ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際の3つのポイントを解説します。
親世帯と子世帯のプライバシーの確保
親世帯と子世帯のプライバシーの確保をどうするかによって間取りは決まります。完全同居型は一般的な一戸建て住宅と同じであるため、親世帯と子世帯のプライバシーの確保は難しいです。 部分共用型は親世帯と子世帯の関係性や距離感を保ちながら、お互いのプライバシーを確保できます。ただし、玄関やキッチンなどの共有スペースでは顔を合わせるため、プライバシーの確保には限界があります。 完全分離型であれば、完全なプライバシーの確保が可能です。家計も完全分離ができ、水道光熱費の負担の割合で揉めることもありません。完全同居型と部分共用型はトラブルを防ぐため、水道光熱費の負担の割合を事前に決めておきましょう。
動線の効率化
二世帯住宅の間取りの設計において、動線の効率化は極めて重要なポイントです。室内のスムーズな移動と利便性を確保することで、快適かつ機能的な住環境が実現します。動線の効率化のポイントは、動線を可能な限り短くし、別の動線と交差しないようにすることです。 動線がスムーズであればキッチンから居室などへの移動が楽になり、より快適に暮らせます。また、完全同居型と部分共用型の二世帯住宅は親世帯と子世帯が共有スペースを使うことがあるため、動線を工夫することでお互いのプライバシーを尊重できます。 さらに間取りを決める際は、トイレや浴室など衛生面に関する「衛生動線」と、調理や洗濯など家事に関する「家事動線」が交差しないようにすることも、利便性や快適性、プライバシーの確保において重要です。
将来の変化に対応
間取りを決める際は、子どもの成長や親の介護、死別など、将来の変化も考慮することが大切です。家族構成やニーズは時間とともに変化するため、適切な設計を行うことで、将来の変化に柔軟に対応できます。 子どもが成長するにつれて、個別の勉強部屋や寝室が必要になる場合があります。兄弟姉妹がいる家庭では、子どもの成長を意識して間取りを決めましょう。親の介護が予想される場合は、バリアフリー化や親の居室を1階に配置するなど、アクセスしやすい間取りの設計が重要です。 両親が高齢の場合は、親世帯の死別も考慮する必要があります。特に完全分離型は半分が空き家になるため、賃貸に供するなど将来の利用方法を念頭に間取りを設計しましょう。完全同居型と部分共用型は、部屋の再配置や用途の変更を容易に行えるようにしておくと、将来の変化に柔軟に対応できます。
ローコストの二世帯住宅を建てる際の注意点

ローコストの二世帯住宅を建てる際は、家族同士の話し合いなどが重要になってきます。複数の業者を比較することも大切です。ここでは、ローコストの二世帯住宅を建てる際に、特に注意しておくべき事項を解説します。
親子でしっかりと話し合う
ローコストの二世帯住宅を建てる際は、親子でしっかりと話し合うことが大切です。どのような生活環境を求めるのかや、どのようなプライバシーの確保が必要なのかなど、意見を交換することで理想の二世帯住宅が実現します。 完全同居型と部分共用型の二世帯住宅の設計においては、プライバシーの確保と共有スペースのバランスを考える必要があります。お互いのプライバシーを尊重できるようにするために設計やルールを話し合い、合意を形成しましょう。 二世帯住宅の建築にはコストがかかります。建築費の費用負担の割合を話し合って決めておくことが大切です。完全同居型と部分共用型は、水道光熱費の費用負担の割合も事前に決めておくと、将来のトラブルを防げます。
希望をリストアップし優先順位をつける
親子双方の希望をすべて実現させると予算オーバーになる可能性があります。希望は優先順位づけが必要です。親子双方の希望事項をリストアップし、優先順位をつけることで、どの要素が最も重要かが明確になります。 これにより、設計や予算の決定において焦点を絞りやすくなり、限られた予算を最適に配分できるようになります。コスト効率の向上は希望を可能な限り実現するのに欠かせません。最も重要な要素に予算を割り当て、それに従って設計を調整できます。 希望事項をリストアップし、優先順位をつける際には、家族全員が参加しての話し合いを通じて合意を形成することが成功の鍵となります。間取りの設計プロセスがより円滑に進行し、家族全員が納得できる住環境を実現するのに役立つでしょう。
複数の業者を比較検討する
ローコストの二世帯住宅の施工実績が豊富な業者を3社程度選んで、相見積もりを取ることは重要です。複数の業者から見積もりを取得することで価格競争が生まれ、建築費をより低く抑えられる可能性が高まります。 ただし、価格だけで比較するのは禁物です。価格が安くても品質が悪ければ建ててから後悔するでしょう。各社のこだわりや強みを比較して、予算内で希望を実現可能で信頼できる業者を選ぶようにします。 業者の信頼性と品質を評価するには、過去の施工実績や、実際に利用したことのある人の口コミが参考になります。アフターフォローや保証条件も重要であり、保証期間なども比較検討しましょう。長期保証を採用していれば建ててからも安心です。
ローコストの二世帯住宅の間取りや施工事例
ローコストの二世帯住宅の間取りを決める際は、ハウスメーカーのホームページやブログなどに掲載されている間取り図や施工事例が参考になります。さまざまな間取り図や施工事例を確認することで、理想的な間取りがわかるようになるでしょう。 ここでは、ローコストの二世帯住宅の間取りや施工事例をご紹介します。
完全同居型の間取りの事例
完全同居型の間取りの事例として一般的なのは、1階に共有スペースと親世帯の居室を配置して、2階は子世帯の居室を配置する間取りです。以下のような間取りが参考になります。 1階 ・共有の玄関ホール ・共有のリビングルーム ・共有のキッチン ・共有の洗面室 ・共有の浴室とトイレ ・親世帯の居室や寝室 2階 ・子世帯の居室や寝室 ・子世帯の子どもの勉強部屋 ・子世帯の洗面室 ・子世帯のトイレ ・収納スペース ・バルコニー 予算やスペースに余裕があれば、2階に子世帯専用のミニキッチンを設置することも検討できます。完全同居型の二世帯住宅の間取りは、パブリック空間とプライベート空間のバランスを最適にするのがポイントです。親子でしっかりと話し合って間取りを決めましょう。
部分共用型の間取りの事例
部分共用型は共有スペースを何にするかによって間取りが決まります。玄関とキッチンを共有する場合の間取りの事例は以下のとおりです。 1階 ・共有の玄関ホール ・共有のリビングキッチン ・親世帯の洗面室 ・親世帯の浴室とトイレ ・親世帯の居室や寝室 2階 ・子世帯の居室や寝室 ・子世帯の子どもの勉強部屋 ・子世帯の洗面室 ・子世帯の浴室とトイレ ・バルコニー 部分共用型の二世帯住宅は、双方の日常生活に支障のない間取りにするのがポイントです。また、双方のプライバシーを尊重しながら共同生活を楽しむための設計が求められます。動線の効率化を意識して、各世帯が共有スペースやプライベートなスペースにアクセスしやすいように設計しましょう。
完全分離型の間取りの事例
完全分離型は「完全左右分離型」と「上下完全分離型」がありますが、どちらのタイプも親世帯と子世帯が独立した住宅ユニットを持ちます。間取りの事例は以下のとおりです。 上下完全分離型 1階 ・親世帯の玄関ホール ・親世帯のリビングキッチン ・親世帯の洗面室 ・親世帯の浴室とトイレ ・親世帯の居室や寝室 ・和室や洋室 2階 ・子世帯の玄関ホール ・子世帯のリビングキッチン ・子世帯の洗面室 ・子世帯の浴室とトイレ ・子世帯の居室や寝室 ・子世帯の子どもの勉強部屋 ・バルコニー 完全左右分離型も1階と2階が左右になるだけで、基本的な間取りはほぼ同じです。2階には親世帯・子世帯専用のバルコニーを設置できます。完全分離型は親子の関係性を維持するために、二世帯が交流しやすい間取りにするのがポイントです。
ローコストで二世帯住宅は建てられる!しっかりと話し合って理想の間取りを実現しよう
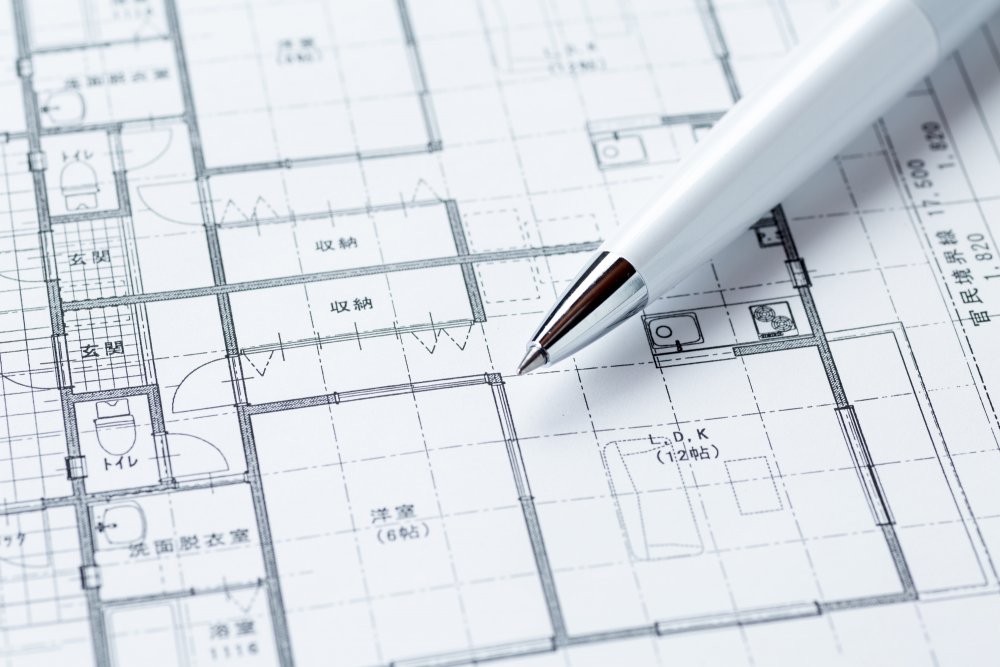
ローコストで二世帯住宅の建築は可能です。ローコストの二世帯住宅の建築を得意としているハウスメーカーや工務店に依頼すると、2,000~4,000万円程度で二世帯住宅を建築できます。間取りを工夫すると、1,000万円程度でも建築できる可能性があります。 二世帯住宅を建築する際は、間取りの決め方が特に重要です。親世帯と子世帯のプライバシーの確保と動線の効率化、将来の変化への対応の3点を念頭に、最適な間取りを検討しましょう。 間取りを決める際は、家族同士でしっかりと話し合うことが大切です。建築費や水道光熱費の負担の割合なども決めておくと、トラブルを未然に防げます。しっかりと話し合って、理想の二世帯住宅を実現させてください。
監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹

不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-stylehouse山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
関連記事
-

家を建てると決めたらまずやることは?家づくりの基本的な流れをわかりやすく解説
家を建てるのが初めての方は、何から始めればよいのかがわからず、戸惑うこともあるでしょう。家を建てる際は、まずやることを知っておくことが大切です。まずやることがわかれば家づくりをスムーズに行えます。 この記事では、家を建てると決めたらまずやることを解説します。家を建てるのが初めての方も、家づくりの基本的な流れがわかるようになるでしょう。 1.家を建てると決めたらまずやること1-1.家づくりの情報を収集する1-2.家族で話し合って建てたい家のイメージを固める1-3.予算を決める1-4.家が建つまでの基本的な流れを把握する2.家を建てる手順と流れ2-1.土地探し・建築会社探し2-2.プランの決定・見積もり2-3.住宅ローンの事前審査2-4.土地の売買契約2-5.工事請負契約・建築確認申請2-6.住宅ローンの本審査2-7.工事の着手2-8.工事完了検査・引き渡し3.家を建てると決めてから家が建つまでの期間の目安3-1.事前準備3-2.土地探し・建築会社探し3-3.プランの決定~契約3-4.工事の着手・工事完了検査・引き渡し4.家を建てるときに気をつけること4-1.間取りは入念に決める4-2.複数の業者を比較する4-3.値引きだけで判断しない4-4.契約書はよく確認する4-5.建て替えの際は法令上の制限などを調べる5.家を建てると決めたらまずやることを把握しましょう! 1.家を建てると決めたらまずやること 家を建てると決めたらまずやることは、以下の4つが重要になります。 家づくりの情報を収集する家族で話し合って建てたい家のイメージを固める予算を決める家が建つまでの基本的な流れを把握する 上記の4つのことをしっかりと行うことで、理想の家づくりが実現できるでしょう。また、時間に余裕を持って計画を進めることも重要です。以下では、家を建てると決めたらまずやることを解説します。 1-1.家づくりの情報を収集する家を建てると決めたらまずやることは、家づくりの情報を収集することです。インターネットや住宅展示場、モデルハウス、住宅情報誌などで情報収集を行い、知識を深めましょう。 建築業者や建築士のホームページやブログなども参考になります。プロの視点で書かれているため、正確な情報を収集するのに役立ちます。掲載されている施工事例の写真を見ると、理想の家のイメージが膨らんでくるでしょう。 実際に家を建てたことがある友人や知人に話を聞いてみるのもおすすめです。実際の経験から得た知識やヒントは、より良い家づくりのための貴重な情報源となります。また、家づくりの過程での注意点や失敗談などは、失敗を防ぐのに役立ちます。 1-2.家族で話し合って建てたい家のイメージを固める家族全員が快適に暮らせる家づくりをするには、家族で話し合い、建てたい家のイメージを固めることが重要です。家族全員で話し合って、家族それぞれの希望を出しましょう。話し合いを続けていると、どのような間取りや設備が欲しいのか、どのような雰囲気の家にしたいのか、といったイメージが湧いてきます。 話し合いの結果、家族全員の希望を実現するのは難しい場合があります。そのため、妥協が必要な場面もあるかもしれません。バランスを考えながら、家族全員が満足できるような選択をしましょう。 なお、家族で話し合う際は、将来のライフスタイルやニーズも考慮する必要があります。子供が成長し独立することや、高齢化に伴う身体的な制約など、将来の変化に備えた計画を立てることが重要です。 1-3.予算を決める家を建てるには予算の制約があります。予算をしっかり立てることで、計画的に家づくりを進められます。年収から大まかな借入金額を決め、予算シミュレーションをしてみましょう。 借入金額を決める際は、返済負担率(年収に占める住宅ローンの年間返済額の割合)が25%以下であれば、返済に問題ないとされています。ただし、これはあくまで目安であり、他の借入金や生活費なども考慮して、無理のない返済負担率の設定が重要です。 なお、予算シミュレーションをする際は、住宅ローン手数料や登記費用、引っ越し費用などの諸費用がかかることも考慮する必要があります。これらの費用は、土地・建物の購入費の10~12%前後が目安とされています。また、家づくりには予期せぬ追加費用が発生する場合があるため、予備費を確保しておくことも大切です。 1-4.家が建つまでの基本的な流れを把握する家を建てるには、土地探しや建築業者選び、設計、施工、工事完了検査など、さまざまな工程があります。基本的な流れを把握しておくと、スムーズに家づくりを進められます。 家を建てることは人生の一大プロジェクトであり、完成するまでにさまざまなプロセスを経るため、工程や流れを理解して計画的に進めることが重要です。家が建つまでの基本的な流れは以下のようになります。 土地探し・建築会社探しプランの決定・見積もり住宅ローンの事前審査土地の売買契約工事請負契約・建築確認申請住宅ローンの本審査工事の着手工事完了検査・引き渡し これはあくまでも基本的な流れであり、順番が前後したり同時に行ったりする場合があります。 2.家を建てる手順と流れ 家を建てる手順と流れは先に説明したように、さまざまなプロセスがあります。ここでは、各プロセスで行うことの詳細を解説します。 2-1.土地探し・建築会社探しまずは、家を建てるための土地と建築会社を探すことから始めます。インターネットで探すのが一般的ですが、実際に建築会社を訪問して話を聞いてみることも大切です。 なお、土地の条件によって建てられる建物の形状や規模が限られることがあるため、土地と建築会社は合わせて探すことをおすすめします。 土地探しをする際は、希望のエリアや条件を明確にしておくと探しやすくなります。建築会社探しは複数の会社から相見積もりを取り、実績や評判を比較検討することが重要です。 2-2.プランの決定・見積もり建築会社が決まれば、建築プランと正式な見積もりを依頼します。家が完成すると簡単には間取りの変更などはできないため、間取りや住宅設備などの要望をしっかり伝えることが大切です。 予算内で実現できるプランにすることも大切であり、予算オーバーにならないよう注意しましょう。予算オーバーする場合は、要望に優先順位をつけておくと予算内におさまる可能性が高まります。予算内で家を建てるには、要望と予算のバランスを考えることがポイントです。 2-3.住宅ローンの事前審査建築会社から見積もりを取得できれば、事前審査(仮審査)を申し込みます。住宅ローンの審査のプロセスは事前審査と本審査の2段階になっており、事前審査に通った場合でも、本審査に通るとは限りません。 事前審査では、申請者の年齢や職業、収入、資産、負債などの情報をもとに、どの程度の金額のローンが組めるかを大まかに把握することが目的です。この結果をもとに、具体的な予算や物件探しの範囲を絞り込めます。事前審査は土地探しのプロセスでも申し込め、結果は2日〜1週間程度で判明します。 2-4.土地の売買契約住宅ローンの事前審査に通れば、土地の売買契約を締結します。売買契約の際には土地価格の5~10%程度の手付金が必要になるため、提示された金額を準備しておきましょう。手付金は現金で支払うのが一般的です。 売買契約を締結する際は、不動産会社の宅地建物取引士から重要事項の説明を受け、重要事項説明書と契約書に署名・捺印をします。不明な点があれば必ず宅地建物取引士に質問し、契約書の内容をよく確認してから署名・捺印しましょう。 2-5.工事請負契約・建築確認申請土地の売買契約を締結すれば、次は建築会社と工事請負契約を締結します。建築会社との工事請負契約では、建物の設計や施工、工事完了までの一連の工程や条件、支払い条件などが取り決められます。 契約を締結する際は、工事請負契約書に記載してある内容をしっかり確認することが重要です。不明な点があれば、建築士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。契約締結後は建築確認申請を行いますが、一般的には建築会社が代行してくれます。 2-6.住宅ローンの本審査土地の売買契約と工事請負契約を締結すれば、住宅ローンの本審査を申し込みます。本審査では完済時年齢や返済負担率などの項目がチェックされ、本審査に通過後、金融機関と金銭消費貸借契約(住宅ローン契約)を締結します。 本審査では事前審査とは異なるさまざまな書類の提出が必要です。書類に不備があると審査が遅れる原因になるため、必要書類は早めに準備しておきましょう。審査の結果は通常1~3週間程度で判明します。 2-7.工事の着手住宅ローン契約を締結してから工事に着手するのが一般的な流れです。施主の希望に応じて地鎮祭などの儀式が執り行われ、その後工事が始まります。工事中は騒音や工事車両の出入りがあるため、工事の着手前に近隣住民に挨拶しておくことをおすすめします。 建物の規模や間取り、工法によって完成するまでの期間は異なりますが、3~6ヵ月程度が工事期間の目安です。ただし、特殊な工法や建物の規模が大きい場合、より長い期間が必要となることもあります。工事中は定期的に現場を訪問して進捗状況を確認しましょう。 2-8.工事完了検査・引き渡し工事が終われば工事完了検査(完了検査)を受け、検査済証が発行されると家の引き渡しが行われます。完成した家の内外の状態を確認し、不備がないかをチェックすることが大切です。 費用はかかりますが、ホームインスペクション(住宅診断)を受けると、プロの目で細かくチェックしてもらえます。なお、引き渡しの際は、今後のアフターフォロー体制なども確認することが重要です。不具合やトラブルが発生した際にスムーズに対応してもらえるよう、事前に確認しておきましょう。 3.家を建てると決めてから家が建つまでの期間の目安 家を建てると決めてから実際に入居するまでは、8~15ヵ月程度かかるのが一般的です。ただし、建物の規模や構造、工法、契約内容、施工業者などによって期間は異なります。ここでは、家を建てる各プロセスにおける期間の目安を解説します。 3-1.事前準備情報収集や予算決めなどの事前準備の期間は、1~3ヵ月程度が目安です。新居に入居したい時期が決まっていれば早めに準備しましょう。 インターネット上には建築会社のWebサイト、家づくりのブログやフォーラム、建築雑誌のオンライン版など、多岐にわたる情報源があります。インターネットを活用すると、情報収集をスムーズに行えます。 予算決めの際は、金融機関が無料で提供している住宅ローンシミュレーションの活用がおすすめです。シミュレーションの結果画面から、事前審査を申し込めるものもあります。 3-2.土地探し・建築会社探し土地探し・建築会社探しの期間の目安は3~6ヵ月程度です。土地を探す際は、エリアや立地、最寄りの交通機関、商業施設などの条件を家族全員で話し合ってみましょう。条件に100%合致する土地は見つけにくいため、どこかで妥協点を設けることが必要です。 土地探しも建築会社に依頼すると、条件に合致する土地を探しやすくなります。すべての建築会社が土地探しをしてくれるとは限りませんが、系列や提携している不動産会社を通じて、理想の建物を建てられる土地を探してくれる場合があります。 3-3.プランの決定~契約プランの決定から契約までのプロセスは、3~6ヵ月程度が目安です。間取りや外観デザインなどの要望を伝えると、建築会社は要望を実現するためのプランニングを進めてくれます。なお、ローコスト住宅だとプランニングの期間の短縮が可能です。 同時に正式な見積もりを出してもらい、プランと予算を固めます。住宅ローンの事前審査に申し込み、審査に通れば土地の売買契約と工事請負契約を締結します。その後、住宅ローンの本審査に通過すれば、家を建てるための準備はほぼ完了です。 3-4.工事の着手・工事完了検査・引き渡し工事の着手から工事完了検査までの期間の目安は3~6ヵ月程度です。ただし、建物の規模や構造、工法などによって期間は異なります。また、天候やその他の要因によって工期が延びることがあります。建物の完成後、引き渡しまでの期間は1ヵ月程度が目安です。 建物の引き渡しと住宅ローンの実行は同時に行われるのが一般的です。住宅ローン実行の1~2週間前に金銭消費貸借契約を締結し、住宅ローンの実行と引渡しを同時に行います。なお、引渡しが土日祝日に行われるときは、住宅ローンの実行を先に行うケースもあります。 4.家を建てるときに気をつけること 家を建てることは、長い時間と労力が必要です。建物が完成してしまうと根本的なやり直しは基本的にはできません。しっかりと準備をして、理想の家づくりを実現しましょう。ここでは、家を建てるときに気をつけることを解説します。 4-1.間取りは入念に決める間取りは家づくりにおいて非常に重要な要素であり、建ててから後悔するケースも少なくありません。間取りは一度決めてしまうと変更が難しいです。後悔のない家づくりをするためにも、慎重な検討が求められます。 間取りは家族構成やライフスタイル、生活動線などを考慮して入念に決めることが重要です。間取りが不適切だと、生活の利便性や快適さに影響を及ぼす可能性があります。 例えば、部屋の配置や広さが合わないために家族の生活が不便になったり、使い勝手の悪い間取りによってストレスが溜まったりすることがあります。 間取りを検討する際には、家族の日常生活や将来のライフスタイルの変化なども考慮し、慎重に決めることが大切です。 4-2.複数の業者を比較する家を建てる際には複数の業者から見積もりを取得し、比較検討することが大切です。見積もりを比較することで、費用や施工品質、アフターサービス、担当者の対応などの違いを把握でき、最適な業者を選べるようになるでしょう。 ただし、5~6社以上の見積もりを取得すると、情報が多すぎてわかりにくくなる可能性があります。そのため、相見積もりは3社程度に留めるのがおすすめです。3社程度だと比較がしやすくなり、適切な業者を見つけやすくなります。 なお、業者の選定にあたっては価格だけでなく、施工品質やアフターサービスなども考慮することが重要です。最終的には、自分のニーズや優先順位に合った業者を選ぶようにします。 4-3.値引きだけで判断しない価格の安さや値引きだけで選ぶのではなく、家づくりにおける重要な要素である施工品質やアフターサービス、プランやデザインに優れた業者を選びましょう。 家は一生に一度の大きな買い物です。価格の安さや値引きだけにこだわらず、長期的な視野で判断することが大切です。質の高い住宅は快適な暮らしを提供してくれるだけでなく、資産価値も高くなります。 質の高い住宅はそれに見合った価格が設定される傾向があります。本当に価値のある住宅は簡単に値引きされません。価格の安さや値引きだけで業者を選ぶと、建ててから後悔する可能性が高いです。施工品質にこだわりがなく、価格の安さだけをことさらアピールする業者には注意しましょう。 4-4.契約書はよく確認する家を建てる際には、契約書をしっかり確認することが非常に重要です。契約書に署名・捺印をすると、契約書に書かれている内容をすべて了承したことになります。 特に「工事請負契約書」と「約款」は、家づくりにおいて最も重要な書類の一つです。これらの契約書には、工事内容や価格、支払い条件、アフターサービスなどの重要な事項が記載されています。 専門用語が多く、わかりにくい部分もあるかもしれませんが、内容をよく理解する必要があります。不明な金額や条件などがあれば、遠慮なく業者に質問しましょう。後からトラブルにならないよう、疑問点は必ず解消しておくことが大切です。 内容が複雑で、自分で判断するのが難しい場合は、弁護士や建築士などに相談することをおすすめします。 4-5.建て替えの際は法令上の制限などを調べる家を解体して建て替える場合は、建築基準法などの法令上の制限を調べることが大切です。法令上の制限によっては、更地にすると家が建てられない場合もあります。法令上の制限の例として、以下が挙げられます。 道路斜線制限北側斜線制限隣地斜線制限日影規制接道義務市街化調整区域 接道義務を例に挙げると、家を建てるには、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接することが必要です。接道義務を満たさない場合は再建築不可物件とされることがあり、原則として家の建て替えはできません。 家を解体して建て替える前に必ず法令上の制限を調べ、建て替えが可能かどうかを確認しましょう。法令上の制限を調べるには、役所の建築指導課や建築士に相談するなどの方法があります。 5.家を建てると決めたらまずやることを把握しましょう! 家を建てると決めたらまずやることは、家づくりの情報を収集し、家族で話し合って建てたい家のイメージを固めることです。予算シミュレーションをして、家が建つまでの基本的な流れを把握することも大切です。 家づくりの基本的な流れは、土地探し・建築会社探しから始め、プランの決定・見積もり、土地の売買契約・工事請負契約の締結、住宅ローンの本審査、着工、引き渡しという流れになります。この流れを理解しておくと、住宅建築をスムーズに行えます。 家を建てることは家族の未来を形作る決断です。この記事を参考に後悔しない住宅建築を目指してください。 監修者:宅地建物取引主任者 浮田 直樹 不動産会社勤務後、株式会社池田建設入社。いえとち本舗山口の店長を経て、セカンドブランドのi-Style HOUSE山口店店長に就任。後悔しない家づくりをモットーにお客様の家づくりの悩みを日々解決している。
-

屋根の種類と特徴を解説!切妻・片流れ・寄棟のどれがおすすめ?
屋根は家の外観を決めるだけでなく、私たちの暮らしにもとても影響してきます。どんなにデザインがいい家でも、屋根から雨漏りしてしまってはせっかくの新しい生活も気持ちよくできませんよね。しかし、屋根の種類もたくさんあってどれが正解かわからないかもしれません。今回はこれから家を建てる方やリフォームを考えている方に屋根の種類と特徴などをお伝えしていきます。 屋根の種類とメリット・デメリット屋根の形状にも複数の種類があります。ここでは一般的に用いられている屋根の種類の特徴についてお伝えします。 切妻屋根切妻屋根は、屋根の面が2面で構成され、屋根の頭頂部は棟があります。切妻屋根は一般的な屋根として用いられることが多く、外観や構成がシンプルで問題の少ない特徴があります。屋根構成がシンプルで材料の調整も少ないため費用を抑えられ、工事期間も比較的に短いです。屋根の施工や劣化状態によって変わりますので雨漏りが起きにくいかというと一概には言えませんが、シンプルな構成ですのでトラブルは起きにくいでしょう。また、棟が大棟のみのため、寄棟屋根と比べて棟板金が飛ばされてしまう被害は少ないかもしれません。 【メリット】工事費用・工事期間を抑えられるリフォーム費用が経済的太陽光パネルの設置面積が確保しやすい棟を換気棟にすることで屋根に溜まる湿気の対策ができる棟板金のトラブルが少ない 【デメリット】ケラバ(正面から見て三角となっている方向)側の外壁と破風板の劣化がある屋根のデザインに個性を感じない 寄棟屋根寄棟屋根も現在の住宅では一般的に採用されている屋根の形です。屋根の面が4面、棟も複数あり頭頂部が大棟、屋根面が互いに接して隅に向かって傾斜する箇所を隅棟といいます。屋根が多面となっているため、屋根に受ける雨や風、雪が分散し耐久性が高いといわれています。また、軒先全体に雨樋を設置しているので雨量が多くてもトラブルは少ないいでしょう。屋根の傾斜が下がったところで、互いの屋根が接している箇所を谷といいます。名前の通り屋根が谷のようになっているため、谷のある寄棟屋根はそこに水が流れていき雨漏りを引き起こす問題があります。 【メリット】軒の出を大きくすれば外壁の劣化を抑えられる屋根面が多いため風・雨・雪を分散させ耐久性が高い和風・洋風のどちらの家にも対応できる外観 【デメリット】棟の部材が多いため強風により飛ばされてしまうリスクがある棟の板金加工や屋根材の加工調整など手間がかかり切妻屋根よりも費用は高い谷があると雨漏りのリスクが高くなる太陽光パネルの設置面積の確保が少ない雨樋の設置量が多い 片流れ屋根片流れ屋根は、屋根面が1面のみでつくられる屋根の形です。片方の傾斜のみで構成されるシンプルでスタイリッシュなデザインとなっています。最近の住宅に採用されることが多く人気の屋根の種類といえるでしょう。片流れは屋根面を1面にすることで、居住空間を最大限広げることが可能です。太陽光パネルの設置の確保がしやすく、コストも安価に抑えやすい特徴があります。 【メリット】コストが安価太陽光パネルの設置の確保がしやすい高い位置に窓を設置できるモダンなデザインで個性的棟のトラブルが少ない 【デメリット】雨樋が受ける雨の量が多いケラバ側の外壁の劣化が早い方角を考慮して設計しないと日照に問題が起きる壁面からの雨漏りのリスクが高い棟換気の設置ができないため換気計画が必要 陸屋根陸屋根は屋根が水平になっていて、バルコニーのように平らな仕上げとなっています。一般的に鉄筋コンクリート造や鉄骨造に採用される屋根の種類で、水を染み込みやすい木造住宅には適しません。水平な屋根面は屋上スペースとしてガーデニングやバーベキューなどの活用ができ、外観もモダンな印象を与えます。屋根面は防水処理がされていて多少勾配をつけていますが、ほぼ水平ですので水の流れは良くありません。定期的なメンテナンスを行わないと劣化して雨漏りするので注意が必要です。 【メリット】モダンなデザインで洗練された印象を与える屋上スペースとして活用できる風の影響が少ない 【デメリット】防水面が劣化し適切なメンテナンスを行わないと雨漏りする落ち葉などが流れていかないため排水口にゴミが溜まりやすい屋根面が水平なため雪が落ちていかない太陽光パネルを設置するときは角度をつけて設置しなければいけない 雨漏りに注意する屋根一番大切にしなければいけないのが雨漏りしない屋根であることです。では、雨漏りしない屋根とは何かということになりますが、どの屋根も一長一短あり、必ず雨漏りしないという屋根はありません。しかし、雨漏りのリスクを避けるために注意する屋根の形はあります。雨漏りのリスクが高くなる屋根の形とは下記のことがあげられます。 軒先の出がない谷がある下屋と外壁の取り合い部(雨押え板金の箇所)の処理が甘い防水シート(ルーフィング)の施工が適切ではないコーキング処理が適切ではない 当然のことですが、水の流れが悪い屋根や水が溜まりやすい屋根は雨漏りのリスクが高くなります。最初は雨漏りがしていなくても、その分雨の影響を受けやすい状態には変わりませんので劣化が他の箇所よりも早くなります。また、屋根から雨漏りしないのは防水シートが敷かれているためで、防水シートの施工が適切でなかったり、防水シートが劣化していたりすると雨漏りが発生しますので注意しましょう。 屋根は片流れがおすすめ片流れ屋根はデザイン性の高さとコストを抑えられることから、新築住宅に人気です。外観だけでなく、片流れ屋根は優れた内観をデザインするのにも適しています。片流れ屋根は1面のみの傾斜で構成されているため、室内は高さを活かした空間をつくることができます。高い位置に窓を設けて光を取り入れたり、ロフトを設けたりすることもでき、さらに天井の高いリビングを計画することも可能です。片流れ屋根は、コストを抑えながらも室内空間をデザインする幅が広くなるのでおすすめの屋根の形です。 まとめ ここまで屋根の種類についてお伝えしてきました。屋根の形も複数あり、メリット・デメリットはそれぞれの屋根にあります。屋根で大切なことは雨漏りしないことです。雨漏りしやすい屋根の特徴は水が流れにくく、雨が溜まりやすい構造になっています。さらに雨漏りは屋根の状態にも影響しますので、メンテナンス性も考慮することをおすすめします。また、外観だけにとらわれずに、屋根の形によって室内空間も影響してくることを押さえておきましょう。ほとんどの方は家を建てるのが初めてという方ではないでしょうか。家づくりでわからないことは専門家に相談したり、資料をもらって情報収集したりすることが大切です。いえとち本舗は簡単に家づくりが分かる資料などを無料で提供しています。また、会員登録することで、数千種類の中から厳選した間取りを閲覧することができます。もし、ご興味がありましたら下記のページをご利用してみてはいかがでしょうか。資料請求はこちら会員登録はこちら
-

セキュリティ面を完璧に!安心安全な家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^♪ 山口・山陽小野田・周南・宇部・防府で新築住宅の購入をお考えのみなさま、お家を建てる際には、危ない人から自分や家族を守るためにも「セキュリティ」って必ず必要ですよね。 なので今回は「セキュリティ面を完璧に!安心安全な家づくり」についてお伝えしていきます(^^♪ 〇セキュリティ面で危ない家って? セキュリティ面で危ない家は「下見がしやすい家」だと言われています。 家の敷地が道路に直接接していたり路地の奥にあったりすると泥棒や放火魔が下見をしやすいため、狙われやすいです。 上記のような敷地に家を建てる場合、庭のお手入れ等で見通しを良くして死角を作らないことの他に、お家自体のセキュリティを強化する必要があります。 ここからは具体的なお家のセキュリティを強化するポイントを述べていきます(^^) ★窓からの侵入を防止 泥棒の侵入経路として約半数が窓のガラスを破って侵入しています。 つまり侵入されない窓を取り入れることでセキュリティ面がグッと強化されます◎ ガラスを破られないように防犯ガラスを取り入れたり、シャッターや面格子をもちいてそもそも入れそうと思わせないようにしましょう。 内側からの対策としては鍵とサブロックを必ず施錠しましょう。 ★玄関からの侵入を防止 玄関には最低でもピッキング対策が必要です。 最近の玄関ドアはほとんどがピッキング強い鍵になっていますが、これに加えてダブルロックにするとなお安心です。 意外と盲点なのが玄関ドアの横についている採光の窓です。 窓のガラスを割り、そこから内側の鍵を解錠して堂々と侵入するケースもあるため、手を差し込めないような格子を付けたりガラスの部分を小さくしたりする工夫も必要です。 ★モニター付きインターホンは防犯性抜群 最近は賃貸物件でも増えてきたモニター付きインターホン。 モニター付きインターホンがあると在宅時は来客を確認したうえで対応を選べるようになりました。 不在時にも来客が画像・映像で記録が残るので不審な人が来てないかどうかのチェックができます。 泥棒は家に入る前にまずインターホンを鳴らして人が不在の時間帯を予測するケースが多いようです。 インターホンがモニター付きだとわかると泥棒も記録が残るのを恐れてインターホンを押すことはほとんどないでしょう。 ★さいごに この家は入れないなと思わせることが一番の防犯です。 玄関ドアや窓の施錠はもちろんですが「見える防犯」も強化することが被害を未然に防ぐポイントです。 泥棒等がいなくなることが一番ですが自分たちができる限りのセキュリティー強化をすることが必要不可欠です。 山口で新築住宅の購入をお考えのみなさまは、セキュリティ面を最大に強化し、安心安全なお家で毎日を過ごせることを考えてお家づくりをしましょう(^^) 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓ 【山口市下市町】リビング21.3帖平屋3LDK完成見学会









