ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
ウォークインクローゼットとは?収納のコツもご紹介

家の中が物で溢れてしまうと生活するスペースが雑然となり、必要以上に狭く感じてしまいます。収納量が増えるウォークインクローゼットは収納の他に生活動線も効率的になりますので、快適に生活していくためにもしっかり収納の計画を立てていきましょう。この記事ではウォークインクローゼットのことや収納のコツをお伝えしていきます。
ウォークインクローゼットとは

一般的なクローゼットの大きさは(幅)1,800mm×(奥行き)900mmほどのサイズになりますが、ウォークインクローゼットは3畳ほどと人が出入り可能な広さを持っているため、たくさん収納することができます。独立した収納部屋ですので、入り口には扉を設置し、室内は棚やハンガーパイプを設置しています。
また、「ウォークスルークローゼット」というものもあり、こちらは出入り口を2つ設けているため、一つの方向にしかアクセスできないクローゼットと比べて動線を効率化させることができます。また、通り抜けができるクローゼットのため一つのクローゼットを共有することも可能です。
ウォークインクローゼットのメリット・デメリットとは
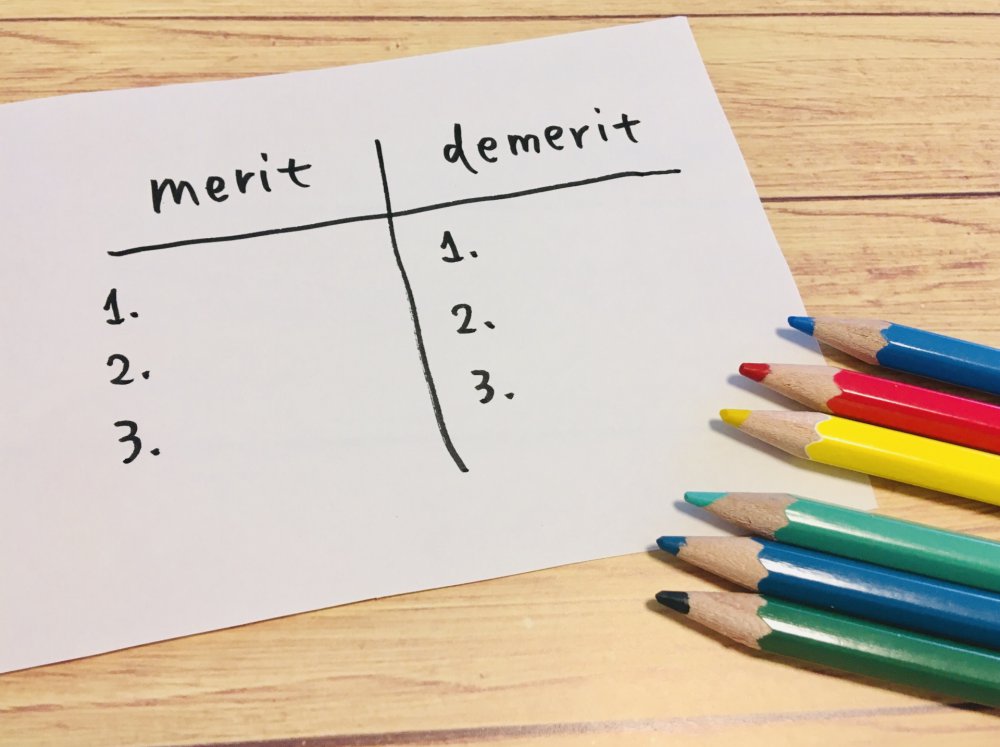
ここではウォークインクローゼットのメリットとデメリットをご紹介していきます。
メリット
- 収納量が増える
- 大きい物を収納できる
- 収納物の管理がしやすい
- 効率的な家事動線にすることができる
ウォークインクローゼットは人の出入りができるほどの余裕のあるスペースがあるため、視認性に優れ、収納物の管理がしやすくなっています。また、衣類の他にキャリーバッグやスキー用品、家具など大型の物も置けるため、物が溢れてしまうといったことも回避できます。
収納する物や量に合わせて棚やハンガーパイプなどで自由にレイアウトすることが可能なため効率的に収納ができ、物干場と隣接する間取りなら洗濯から収納までのアクセスが効率的で家事動線も良くなります。
デメリット
- 居住する部屋を削ることになる
- 配置を間違えると使い勝手が悪くなる
- 定期的な掃除が必要
ウォークインクローゼットを設けるには最低でも2畳ほどの広さが必要です。ある程度のスペースを収納に当てることになりますので、限られた面積をどう配分していくかが重要になります。
また、配置を間違えると使い勝手が悪くなり、使わなくなってしまう恐れもありますので、設計の際は実際に使用するイメージを持って計画することが大切です。また、使っていると埃も溜まりますので、定期的に掃除が必要になります。
ウォークインクローゼットの種類

【パイプハンガータイプ】
衣類をメインに収納したい場合は上部に棚を設置し、棚下にはハンガーパイプを取り付けたパイプハンガータイプがおすすめです。こちらのタイプはコートやジャケットなど丈のある服もたくさん収納ができます。注意するところは下のスペースがあきやすいため、そこのスペースをどう活用するかが重要になります。
【収納棚タイプ】
クローゼット内を収納棚で仕上げたタイプは、服の他にバッグや靴を収納するのに適しています。可動棚にすることで棚の高さを自由に設定でき、効率的な収納が可能になります。棚の設置スペースが必要になりますので、ある程度の広さを持たせることが必要です。
【ユニット棚タイプ】
既製品のキャビネットをクローゼット内に配置し、造作で棚を設けるのが「ユニット棚タイプ」です。家具の設置スペースが必要ですが、収納するものや好みに合わせてキャビネットを用意することができ、収納物の幅も広がります。
ウォークインクローゼットの間取り

【2畳】 2人家族が使うのに適している広さです。2畳は1,800mm×1,800mmの広さがあり、60cm幅で当分することができます。60cm幅の収納スペースを両端に設けることができ、通路も60cm取れるため、収納物の管理もしやすいです。
ハンガーパイプにかけた服の下にはキャリーバッグなど大型の物も置けますが、たくさん置けるというわけではないので注意が必要です。また、2畳だとクローゼットの中で着替えるには少し手狭に感じるため、もう少し広さを確保する必要があります。
【3畳】
3畳は一般的に採用されやすい広さで3〜4人家族に適しています。通路のスペースも大人2人が入っても余裕があり、十分な収納量がありますが、服が多めの方は少し物足りないかもしれません。服をぎゅうぎゅうに詰めてしまうと管理もしにくくなるため、服が多めの方は3.5〜4畳の広さを取るのが無難です。【4畳】
4〜5人家族に適した広さで、衣類や大型の物も余裕を持って収納することができます。この広さなら収納ユニットを配置することも可能なため収納の幅が広がります。また、クローゼット内で着替える場合は鏡やベンチソファを置くと便利でしょう。注意するところは収納の使い方によって無駄なスペースができてしまう可能性がありますので、棚やキャビネットには収納物に合わせられる可変性を持たせるといいでしょう。ウォークインクローゼットの収納レイアウト

【I字型】
片側のみに収納スペースを配置したタイプが「I字型」です。このタイプは奥行きが取れない時に有効で、収納スペースと通路のスペースが等分された配置になります。そのため他のレイアウトと比べて通路のスペースが多くなり、収納としては非効率的です。収納棚とハンガーパイプを設置したレイアウトが一般的で、外壁に面している場合は窓の設置が可能です。【II字型】
クローゼットの中心を通路とし、両側に収納スペースを配置したタイプが「II字型」です。このタイプは収納スペースが両側に配置されているため「片方を衣類のためにハンガーパイプを設置し、もう片方は箱物を置くために収納棚を設置する」といった収納物を分けてレイアウトすることができます。通路の突き当たりの壁は収納スペースではないため窓の設置も可能。「I字型」ほど人が移動するスペースを取らなくてもいいので、収納も効率的です。【L字型】
片側と奥側の壁に収納スペースを配置した一般的に採用されやすいレイアウトです。II字型のレイアウトに似ていますが、コーナー部分はデッドスペースとなりやすいので注意が必要になります。こういったスペースには使用頻度の少ないものを置くなど無駄なスペースとならないように配慮することが大切です。このレイアウトは一面だけ収納スペースとならない壁ができるため窓を設けることができます。【コの字型】
両側と奥の壁に収納スペースを配置したレイアウトが「コの字型」です。このレイアウトもよく採用されやすく、すべての壁が収納スペースとなるため窓を設置することはできませんが、その分収納できる量が増えます。収納物を見渡すことができるため管理がしやすく、出し入れも容易です。パイプハンガーや収納棚の設置、キャビネットの配置などレイアウトできる幅も広がるため収納物に合わせた効率的な収納が可能です。ウォークインクローゼットの設置場所

ウィークインクローゼットの配置はライフスタイルに合わせて計画することをおすすめします。設計の際はどう利用するかが大切ですので、どんなことを求めているか明確にしておきましょう。おすすめの設置場所を以下にまとめましたのでご参考にしてください。
- 起きてすぐに着替えたい場合は寝室横に設置
- 更衣室として使うなら廊下に設置
- バスルームとのアクセスを考えるのなら洗面所と隣接する位置に設置
- 帰宅してすぐに着替えたい場合は玄関横に設置
- 家事動線を考慮するならベランダやバルコニー横に設置
まとめ
収納量が増えるとあちこちに物を置くことがなくなり家の中がきれいになります。収納物や用途によって適切なレイアウトや設置場所がありますので、間取り計画の時はどんな物を収納するのか、どういった使い方がしたいか設計士の方に伝えて使いやすいウィークインクローゼットを計画しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-

いい家は“いい見学”から!モデルハウスで後悔しないための7つの視点
モデルハウスの見学は、家づくりの第一歩。でも「なんとなく見に行っただけ」で終わってしまうと、本当に自分たちに合った住まいは見えてきません。近年では、ネットで事前に情報を集めたうえで、実際に訪れるのは2〜3社程度という人がほとんど。だからこそ、1回の見学の“質”がとても大切なのです。この記事では、モデルハウス見学を「いい家づくり」につなげるための7つの視点を、初心者にもわかりやすくご紹介します。営業トークに惑わされず、自分たちにぴったりの暮らしを見つけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。 1. 見学は“比較”だけじゃない!現代的な家づくりのスタート地点 1-1. いきなり見に行くのは2〜3社だけ。それが今の主流 1-2. ゴールを持って見学すれば、得られる情報が変わる 1-3. モデルハウスは「理想の暮らし」を体感できる絶好の機会2. 豪華さに惑わされない!空間演出の正体を見抜くコツ 2-1. 標準仕様とオプションの違いを見極める 2-2. 家具・照明・天井高による“広く見せる”演出に注意 2-3. 大手ハウスメーカーほど「演出が上手」な点に注意3. 暮らしをイメージする“体感目線”で間取りを見る 3-1. 図面では見えない「生活のしやすさ」に注目する 3-2. 音・視線・空気感にも意識を向けてみる4. 営業トークに飲まれない!費用と提案の見極め方 4-1. 「費用感」は必ず標準仕様ベースで確認する 4-2. ライフプランに合わせた提案ができているか見極める5. 比較してこそ見えてくる!質問リストで判断力をアップ 5-1. 見学は1社で終えない!比較してわかる「違い」 5-2. 質問リストを用意して比較検討を 5-3. モデルハウス見学時に使える質問リスト【例】6. 見たあとの行動が大事!振り返りと家族のすり合わせ 6-1. 見学直後の“メモ”が判断を助けるカギになる 6-2. 家族で見た感想を持ち寄ってすり合わせる7. 最後に:いい見学が、いい家づくりにつながる理由 7-1. 「感動」ではなく「現実目線」で見ることが成功のカギ 7-2. 「自分たちの基準」を持つことが、比較・決断を楽にする1. 見学は“比較”だけじゃない!現代的な家づくりのスタート地点1-1. いきなり見に行くのは2〜3社だけ。それが今の主流現在の住宅購入者の多くは、最初から複数のハウスメーカーを回ることはしません。特に共働きや子育て中の30〜40代夫婦では、限られた時間の中で効率的に情報を得るため、「ネットで徹底的に調べてから、実際に行くのは2〜3社だけ」という動きが一般的です。そのため、モデルハウス見学は“最終候補”の中から実物を確認するフェーズとも言えます。事前にWebサイトやSNS、口コミ、資料請求などを通じて絞り込み、自分たちの希望や価値観に合った会社を選んでから訪問する傾向にあります。このように、今の見学は「とりあえず見てみよう」ではなく、「この会社でいいかを確認する」行動に近いのです。1-2. ゴールを持って見学すれば、得られる情報が変わる限られた2〜3社しか見学しないのであれば、1回の見学で得られる情報の質がとても重要になります。そのためには、あらかじめ「このモデルハウスでは何を確認するか」という目的をはっきりさせておくことが大切です。例えば、「子どもが走り回れる間取りか」「水回りの家事動線はストレスなく使えそうか」「収納は本当に足りそうか」など、実生活をイメージした具体的な視点を持つことで、“見るべきポイント”が明確になります。営業担当者の話にただ耳を傾けるだけでなく、自分たちが知りたいこと・確認したいことを事前に整理しておくことで、限られた見学の機会を無駄にせず、納得感のある家づくりにつなげることができます。1-3. モデルハウスは「理想の暮らし」を体感できる絶好の機会モデルハウス見学は、単なる情報収集にとどまらず、住まいへのイメージを“具体化”するための大切なステップです。図面やカタログでは分からない「空間の広がり」や「自然光の入り方」「床材やドアの質感」「設備の使い勝手」など、五感を通じて体験できるのは、モデルハウスだけの魅力です。また、営業担当者との対話を通じて、自分たちが気づいていなかったこだわりや、思い描いていた暮らしの輪郭がはっきりしてくることもあります。「自分たちの理想はこうだったんだ」と気づけるきっかけにもなり、家づくりの軸が定まる瞬間でもあるのです。つまり、見学は“会社を選ぶため”だけではなく、“自分たちの理想を明確にするため”の機会でもあります。限られた時間だからこそ、その1回1回を前向きに活かしていく姿勢が、満足度の高い家づくりにつながります。 2. 見た目に惑わされないチェックポイント2-1. 標準仕様とオプションの違いを見極めるモデルハウスには、最新設備やおしゃれな内装がふんだんに取り入れられていますが、その多くが「オプション仕様」であることに注意が必要です。キッチンのグレード、造作収納、床材、天井高、外壁など、実際の建築プランにそのまま反映できるわけではないケースが多々あります。例えば、モデルハウスで見たキッチンが気に入っても、標準仕様ではグレードが異なり、希望通りにするには数十万円の追加費用が発生することもあります。見学時には「これは標準ですか?オプションですか?」と積極的に確認する姿勢が大切です。2-2. 家具・照明・天井高による“広く見せる”演出に注意モデルハウスは“魅せる”ために作られています。そのため、実際の居住空間よりも広く、開放的に感じるよう巧みに演出されています。代表的なテクニックとして、以下のようなものがあります。ダイニングテーブルやソファなどの家具サイズを小さく配置天井を高めに設計建具(ドアや窓)をハイタイプに間接照明やスポットライトで空間を美しく見せるこれらは決して悪いことではありませんが、「この広さなら自分たちの生活にちょうどいい」と感じたとしても、それが標準仕様でない場合、実際の建物で再現できない可能性があります。実寸を測る、間取り図と照らし合わせるなど、冷静な視点を持つことが重要です。2-3. 大手ハウスメーカーほど「演出が上手」な点に注意特に大手ハウスメーカーのモデルハウスは、住宅展示場の中でも「とにかく豪華」「非現実的なほど立派」なケースが目立ちます。玄関ホールが吹き抜けになっていたり、収納があらゆる場所に組み込まれていたり、デザイン住宅のような内装が施されていたりするのは珍しくありません。しかし、それらはあくまで“ハウスメーカーのブランド力を見せるためのモデル”であり、現実的な住まいとは少し距離があります。特に「展示場仕様の建物」=「一般的な商品プラン」とは限らないため、「自分たちの予算や敷地に収まるか」「ライフスタイルにフィットするか」という視点を忘れないようにしましょう。 3. 暮らしをイメージする“体感目線”で間取りを見る3-1. 図面では見えない「生活のしやすさ」に注目するモデルハウスを見学するとき、つい「おしゃれかどうか」「豪華かどうか」に目がいきがちですが、実際に住んだときの“生活のしやすさ”こそ、もっとも大切にすべきポイントです。例えば、家族が日常的に使う動線――「玄関からリビングまでの流れ」「洗濯・干す・しまう」の流れなどを自分の行動に当てはめて歩いてみると、思わぬ不便さや工夫に気づけることがあります。さらに、買い物帰りの荷物を運び込む動線、子どもが走り回るスペース、来客時のプライバシー確保など、モデルハウスを“生活の場”として体感することで、図面や間取り図だけではわからない現実的な視点が得られます。3-2. 音・視線・空気感にも意識を向けてみる生活とは視覚だけで完結しません。モデルハウスでは、「音の伝わり方」「視線の抜け感」「採光や通風の心地よさ」といった、空間の“感じ方”もぜひ意識してみてください。たとえば、リビングと子ども部屋の距離感によって、生活音の干渉度は大きく異なりますし、吹き抜け構造があると上下階の音が意外と響くこともあります。また、窓の位置や大きさによって視線の抜け方が変わり、開放感やプライバシー性に直結します。季節によって日の入り方がどう変化するか、風通しがどうか――こうした点は、現地でしか感じ取れない重要な要素です。 4. 営業トークに飲まれない!費用と提案の見極め方4-1. 「費用感」は必ず標準仕様ベースで確認するモデルハウスで営業担当から説明を受けるときに気をつけたいのが、“話されている価格がどこまで含まれているか”という点です。大切なのは、「このモデルハウスをこのまま建てる場合、総額でいくらになるのか?」「自分たちが希望する仕様にしたらいくらになるのか?」を具体的に尋ねることです。モデルハウス見学は、夢を描くだけでなく、現実的な資金計画を立てる第一歩でもあります。4-2. ライフプランに合わせた提案ができているか見極める営業担当者によっては、モデルハウスの魅力を伝えることに終始してしまい、顧客の暮らしや家族構成、将来のライフプランをあまり聞かずに話を進めてしまうことがあります。ですが、良い提案とは「今の理想」だけでなく「10年後、20年後も快適に暮らせる家」を一緒に考えてくれる姿勢から生まれるものです。たとえば、「子どもが巣立ったあとの暮らし方」や「住宅ローン返済を続けながら老後資金をどう確保するか」といった話題に触れてくれる営業担当であれば、信頼できる相手かどうかを見極める材料になります。逆に、予算を無視した高額プランを強く勧めてくる場合は注意が必要です。 5. 比較してこそ見えてくる!質問リストで判断力をアップ5-1. 見学は1社で終えない!比較してわかる「違い」家づくりにおいて、1社だけを見て決めるのはリスクがあります。同じ価格帯でも、間取りの自由度・標準仕様のグレード・営業の対応・アフターサポート体制など、各社ごとに大きな違いがあるからです。たとえ「ここが良さそう」と思ったとしても、他社と比べて初めてその良さが際立つ、もしくは過剰だったと気づけることもあります。また、複数のモデルハウスを見ることで、自分たちの希望や好みがより明確になるメリットもあります。例えば「収納が多い間取りがいい」「やっぱり平屋が暮らしやすそう」といった“気づき”は、比較を通して生まれることが多いのです。5-2. 質問リストを用意して比較検討を見学時は限られた時間しかありません。その中で効率よく情報を引き出すには、事前に「質問リスト」を用意しておくのがおすすめです。営業担当者に任せきりにせず、自分たちから積極的に聞くことで、各社の考え方やサービス姿勢にも違いが見えてきます。同じ質問を各社にぶつけてみることで、「どこまで具体的に答えてくれるか」「提案の幅があるか」「回答が曖昧でないか」などを比較する視点も持てるようになります。5-3. モデルハウス見学時に使える質問リスト【例】 このモデルハウスの仕様は、どこまでが標準でどこからがオプションですか? この家を建てる場合、土地以外でどれくらいの費用がかかりますか?(本体・付帯・諸経費など) 間取りの自由度はどのくらいありますか? 設計のカスタマイズは可能ですか? 断熱性能・耐震性能など、住宅性能について教えてください 太陽光発電や蓄電池などの提案はありますか? 標準のアフターサポートや保証内容はどうなっていますか? 自分たちの年収で、無理なく返済できる資金計画はどのように立てられますか?このような質問を投げかけながら、営業の反応や説明の仕方にも注目することで、「この人なら信頼できる」と感じられる判断材料にもなります。 6. 見たあとの行動が大事!振り返りと家族のすり合わせ6-1. 見学直後の“メモ”が判断を助けるカギになるモデルハウス見学は印象が強いため、「この間取りは良かった」「収納の工夫が参考になった」といった感想がその場では明確に残ります。しかし、時間が経つにつれて複数の見学内容が混ざってしまい、「どこがどの会社だったか分からなくなった」ということはよくあります。そうした混乱を防ぐためには、見学直後に感じたことを“文章でメモしておく習慣”が非常に有効です。気に入った点、不安に感じた点、営業の印象、話に出た費用や仕様の内容など、気づいたことを簡単に書き留めておくだけで、後から比較・検討する際に大きな助けとなります。記録は手書きでもデジタルでも構いませんが、「その場でしか得られない気づき」をできるだけフレッシュなうちに残しておくことが重要です。6-2. 家族で見た感想を持ち寄ってすり合わせる見学後には、家族で「どう感じたか」を共有する時間を設けましょう。どんな家が自分たちに合っているのかという判断は、家族それぞれの価値観によって異なるものです。「キッチンの動線が使いやすそうだった」「リビングの広さはちょうど良かった」「この営業さんは信頼できそう」など、主観的な意見を持ち寄ることで、新たな気づきが生まれます。お互いの感想を聞いたうえで「自分たちが求める暮らしに近いのはどの会社か」「優先すべき条件は何か」を明確にしていくことで、今後の比較検討もより納得のいくものになります。 7. モデルハウス見学まとめ:後悔しないためのポイント整理7-1. 「感動」ではなく「現実目線」で見ることが成功のカギモデルハウスは「理想の住まい」をイメージするために作られているため、見学中はどうしてもテンションが上がりがちです。「この家に住みたい!」「素敵すぎる!」という感動は、家づくりのモチベーションにはなりますが、その感情だけで判断してしまうのは非常に危険です。本当に大切なのは、その家が“自分たちの暮らし”にとって現実的かどうかです。予算に収まるか、土地に適しているか、家族の生活スタイルに合っているか。感情と現実のバランスを取ることが、後悔しない家づくりの第一歩になります。7-2. 「自分たちの基準」を持つことが、比較・決断を楽にする複数のモデルハウスを見学する中で重要なのは、「自分たちの基準」をしっかり持つことです。他人の評価や営業のトークに流されるのではなく、自分たちが重視するポイント――たとえば家事動線・収納の量・家族のプライバシー確保・アフターサービスなど――に沿って判断していく姿勢が大切です。その基準が定まっていれば、たとえ豪華な演出や過剰な設備に惑わされても「自分たちにとっては不要だ」と冷静に見極めることができますし、各社の提案を比較する際にも迷いが少なくなります。モデルハウス見学は、ただ“家を選ぶ場”ではなく、“自分たちの暮らしを見つめ直す場”でもあります。情報を冷静に整理し、家族と価値観を共有しながら、納得のいく家づくりを進めていきましょう。
-

成功例から学ぶ!後悔しない家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・山陽小野田・防府・周南】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です(^^)/ 本日は山口で新築住宅の購入をお考えのみなさまに「成功例から学ぶ!後悔しない家づくり」についてお伝えします♪ 過去に、「失敗例から学ぶ!後悔しない家づくり」についてお伝えしている投稿があります。そちらと少し似た内容になります。そちらもまた参考にされてみてください(^^♪ 一生に一度の大きなお買い物と言われる「家」。一番大きなお買い物なので絶対に失敗はしたくないですよね。山口で新築住宅をお考えのみなさまに、少しでも建てた後の後悔をなくすために、実際に新築を購入された方の成功例をいくつかお伝えします♪ ★成功ポイント①散らからないリビングづくり 一人で住んでいても散らかり気味なリビング。お子様がおられるご家庭は、おもちゃなど散らかってしまうことが多いのではないでしょうか?(*_*; かといって散らかっているものを全部しまえるほどの大きなスペースをリビングには取れない・・・となった時は「動線やしまう物を意識して収納を細かく分ける」ことをオススメします! 例えば、リビングに壁掛けの収納棚を付けるとします。この時に「何かを収納するだろうから」と思って付けるのではなく、「リビングではゲームやおもちゃが散らかり気味だからそれらを収納しよう」という風に実際の生活をイメージしながら具体的にしまうものを決めましょう。 後からしまう物が増える場合もありますが、あらかじめ収納の配置を決めておくことで収納スペースを最大限に生かすことができます。収納を考えながら家づくりをすることで後から「収納スペースが全然足りない・・・」といった後悔を減らすことができます! ★成功ポイント②見えるところにはお金をかけて、見えないところは安く! 山口で新築住宅を建てる際に、あまり目に付かないようなところにまでお金をかけてしまうととても大きな金額になってしまいます。「目に付かない」というのは来客時のゲストだけではなく、そこに住む家族のことも考えなければいけません。 例えば、大勢の人が目にする玄関や長い時間を過ごすリビングにはできるだけ理想を詰め込み妥協しない。その代わり、ゲストからあまり見えず、一日に一回しか利用しないお風呂や寝室は思い切ってコストカットをする、といった方法があります。 コストカットと言われると「品質や見た目が悪くなるのはちょっと・・・」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうなるわけではありません。最近は様々なメーカーさんが多くの商品を売り出しているので、住宅機器の基本的な水準が高いです。なので少々のコストカットをしても性能がすごく悪い、ということはほとんどないでしょう。 お金を抑える部分を決めておくことでお金を掛けたい部分に資金を回すことができるため、事前に取捨選択をしておくことが大切になります。(^^)/ ★成功ポイント③カウンターキッチンを採用し、家事をスムーズに 今や採用されている方が多いカウンターキッチン。カウンターキッチンにはメリットが沢山あります。一番は家事がしやすいことです。出来上がった料理をカウンターにおけば、すぐに食卓に並べることができ、食べ終わったら食器をカウンターに戻しすぐに洗うことができます。このように動線がコンパクトであるのがカウンターキッチンの特徴です。また、リビングの様子をみながら家事ができるのでお子様がおられるご家庭にオススメです(^^)/ カウンターキッチンは高さを選ぶこともできますので、主にキッチンを使われる方の使いやすい高さに設定することで家事がしやすくなりますね♪ ★成功ポイント④おしゃれで節電になるダウンライトを採用 山口での新築住宅の内観を考えるときに大切になってくる照明器具。照明の差でお部屋の印象がガラッと変わります。そこでオススメなのがダウンライト。 LED型ダウンライトを採用しますと、ライトの持ちが長く、年間の電気代も少し安くなります。 また、ダウンライトは真下を照らすので、ピンポイントで明かりが欲しいところを照らすことができます。調光器が付いているタイプなら光の加減を調節することができ、シーンに合わせて使い分けることができます。 ただ、ダウンライトにはデメリットもあります。まず、後から位置を変えたり増やしたりすることができない点です。理由はダウンライトは天井に穴をあけて埋め込むものだからです。そのため、「ダウンライトの下の家具を動かしたらライトが変な所を照らしている・・・」となった時にダウンライトを簡単に移動させることができません。 生活のスタイルが時々変わったり家具の配置をよく変える方は要注意です・・・ しかしこれには対策があります!!それは、照らす方向をある程度変えることができるユニバーサルタイプのダウンライト、ダクトレールなども併用することです。ダクトレールはすっきりとしながらもライフスタイルの変化に対応することができます。 なので、家具を動かすかもしれないと思われる方は前もって上記の対策をオススメします(^^)/ ★成功ポイント⑤よく使う電化製品は生活空間の中心に 生活していてよく使う電化製品である掃除機やアイロン台を、あえてリビングの専用スペースを設けて収納することで、出し入れがしやすく便利です。電化製品を一カ所にまとめて収納するとごちゃごちゃしがちです。使う場所や頻度に分けて収納することで収納スペースを効率的に活用することができます。 リビングにクローゼットを設置する「リビングクローゼット」は最近人気のようです。急な来客時に重宝されそうですね♪ ★成功ポイント⑥土地探しに時間をかける 山口で新築住宅を建てるにあたって初めの一歩の「土地探し」ここに時間をかけることで、希望の区域内で予定よりも安く土地を仕入れることができたというケースもあります。時間をかけて周辺環境を調べたり少しエリアをずらしてみたり・・・土地を多角的に見ることでお得なポイントが見つかったりもします。安く土地を仕入れ、浮いた資金を建物設備に回せると充実した新築住宅で生活を送ることができます。 お仕事をしながら土地探しもして…と忙しくなると思われますが、できるだけたくさんの不動産屋をまわったり自分でリサーチしてみることが、自分にピッタリの土地に出会う近道かもしれません。 多くの不動産屋をまわることで広告に出る前の土地情報をゲットできるケースがあるようです♪ ★成功ポイント⑦自己資金を増やす 山口で新築住宅を購入する際、全て自己資金で払える方はほとんどいません。たいていの方は住宅ローンを組みます。当たり前ですが自己資金が多くある方が月々の返済負担は軽くなります。金融機関にて新築住宅の購入金額全額を借りると月々の返済に利子がつくので実際の購入金額よりも多く払わないといけません。なのでできるだけ、自己資金を集めておいて月々の返済負担を軽減した方がゆとりのある生活ができるかと思います。 まとめ なにか参考になるポイントはありましたでしょうか?新築住宅が完成した後に後悔することは本当にもったいないので、できるだけ時間をかけてプランニングすることが大切になってきます(^^)/山口で新築住宅の購入をお考えの方で、なにか気になること等ありましたら、いつでもご相談下さい♪ 11月2日(土)~11月4日(月)今だけ50万円相当プレゼントキャンペーン!
-

老後の暮らしを豊かにするマイホームの建て方・間取り計画を解説
わたしたちの生活は歳を重ねるごとに変化していきます。子供が成長し家を出て独立する、定年になり職場を退職するなど、いままでの生活が変わると、これまで住んできた家のことを再検討する方も多くいます。老後のマイホームは、若いときの生活スタイルとは違ってきますので、老後に合わせた家づくりをしていくことが大切です。そこで、今回の記事は老後のマイホームについて押さえておきたいポイントやおすすめの間取りにいついてご紹介していきます。 ライフスタイルの変化老後にマイホームを建てるときは、ライフスタイルの変化に気づくことが大事です。ライフスタイルは若い年齢のときと老後のときで違います。過去に建てた家と同じようにしてしまうと、老後の生活では不便を感じるかもしれないので、まず老後になったときにどうライフスタイルが変化したか気づいていきましょう。 定年退職という変化 老後になってライフスタイルが変わるものの一つに定年退職があります。現役時代とは違い仕事に出かけることもなくなるため、家の中にいる時間も増えます。いままで空けていた家に長い時間過ごすことになると、いろいろと不便だなと感じることがあるかもしれません。 子供が出て行って部屋が広すぎると感じる 老後になると子供も成長し、独立して家を出て行っているかもしれません。生活する人数も減りますから、これまでよりも家が広く感じる可能性もあります。また、子供が使っていた部屋も空いてしまうため、使わない部屋ができてしまうでしょう。しかし、使わない部屋だとしても放置していると埃が溜まりますので掃除は欠かせません。部屋が余ると余計な家事も増えてしまうということになります。 加齢による足腰の低下 歳をとると若いときよりも足腰が弱くなってきます。身体能力の低下は、そのまま生活の仕方に関係してきますので、体の負担を減らす家づくりが大事になります。2階建ての家の場合、掃除や物を出すときなどに階段の上り下りがあると、体への負担が大きく、次第に二階への用事はしなくなってしまうことが考えられます。また、家の中だけでなく、買い物などの利便性も老後の生活には大きく影響してきます。なるべく移動距離が少ないことが望ましいと考えますので、利便性を求めて都市部に住みたいと思うかもしれません。 老後のマイホームの重要ポイント老後にマイホームを建てるときはライフスタイルの変化に気づくことが大切と上記でお伝えしました。では、老後のマイホームに重要としていくポイントとは具体的に何かというと下記のことが考えられます。立地条件価格建物の安全性上記のポイントがどういったものか具体的に下記にてお伝えしていきます。 立地条件 食品や日用品の買い物は生活する上でどうしても必要なことです。坂が多い地域や高台の上に家がある、スーパーが近くにないなど、買い物を歩いて利用する人はこのような環境では足腰の負担が大きく、生活に不便を感じてしまいます。また、スーパーの他に病院や銀行なども近くにあることが望ましいでしょう。生活に必要な施設が徒歩10分以内にある場所に家を建てることがおすすめです。 価格 老後に建てるマイホームの価格も重要です。住宅ローンを利用して家を建てる場合は、ローン返済をしながら生活していきます。ローンの返済が負担となって生活を苦しくさせてしまうのは避けなければいけません。生活に負担をかけない予算で家を建てることが大事です。また、老後に建てるマイホームを将来どうするかによっても家の予算は変わります。子供に引き継いでもらうのか、売却するのかなど、自分が亡くなった後の家の対応についても考えて計画を立てましょう。 建物の安全性 建物の安全性とは、家の構造のことだけではありません。家の中で生活する安全性や外部から守る防犯性も確保していくことが大切です。下記は考えられる建物の安全性ですので、よくチェックしておきましょう。 地震などの災害から守る家の中で安全に暮らせる(バリアフリー)不審者から守る防犯性の確保安心して生活するには上記の安全性が確保されている建物を建てることが大事です。 老後の暮らしに合う間取り老後のマイホームは、生活スタイルの変化や加齢による体の動作の変化を考慮しなければいけません。老後の家づくりはバリアフリーが考えられている間取りにすることをおすすめします。ここでは、老後の暮らしに合う間取りについて解説していきたいと思います。 バリアフリー 老後の暮らしに合う間取りとは、どういう間取りか下記にまとめましたのでご覧ください。 床の段差をなくす手すりを設置する滑りにくい床材を使う住宅用エレベーターを設置する自動開閉できるシャッターを使う階段や廊下をなくす家の広さを最低限にする生活動線・家事動線を考える老後になると加齢で足腰が弱くなり体の動作も鈍くなるため、無意識に足を引きずって歩行していることがあります。床にほんの数センチでも段差があると、足をつまずかせて転倒してしまう恐れがありますので、床はフラットにして段差をなくしておくことが望ましいです。階段の上り下りも同様で、加齢になるとこの動作が負担になり階段を使わなくなる可能性があります。老後のマイホームは二階のない平屋を採用するのも一つの方法でしょう。また、二階建ての家にする場合は、上下階の往復が楽になるようにホームエレベーターを設置してあげると体への負担を軽減することができます。 手すりの位置 老後の暮らしに関わらず、現在の住宅に手すりは欠かせない建材です。手すりがあると便利な場所をまとめましたので下記をご覧ください。【玄関】 上がり框から玄関扉までに横手すりの設置靴脱ぎ場(上がり框のところ)と廊下の段差の直線状に縦手すりの設置【廊下】 廊下の歩行用に横手すりの設置【階段】 階段を上り下りするための補助用に設置階段の上がり始めと上がり切った場所に縦手すりの設置【トイレ】 便器横(便座の座り・立ち動作を補助する用)にL型手すりの設置【浴室】 浴室入り口に縦手すりの設置洗い場方向に横手すりの設置浴槽手前に縦手すりの設置浴槽横に横手すりの設置洗面所入り口に縦手すりの設置あくまでも手すりの高さや長さは目安で、人によって使用感覚は違います。 手すりを設置するときは、専門業者の方と現地で打ち合わせを行い決めていきましょう。手すりを取り付ける位置に当てがい調整して決めていくことをおすすめします。 ヒートショック・健康を意識した家づくり高齢者の方に問題となっているのがヒートショックです。ヒートショックとは温度差が原因して血圧の変化や脈拍の変動が起こり、脳梗塞や脳溢血、心筋梗塞などの疾患を引き起こすことです。ヒートショックが起こりやすい場所とは、浴室や脱衣所、トイレがあげられます。入浴時の暖かい場所から寒い脱衣場への移動など温度の変化は体への負担が大きくなります。また、トイレの場合は、便座から立ち上がるときなど力をかける動作は血圧が上がります。ヒートショックの危険から守るためには、家の断熱性能をあげることが重要になります。ZEH住宅や長期優良住宅など高断熱・高気密の家にするといいでしょう。 まとめ ここまで老後のマイホームにおすすめの建て方についてお伝えしてきました。老後の家は若いときとは違って、ライフスタイルや体への負担が変わります。いままでおくっていた生活との違いに気づき、老後の暮らしに合う家づくりを行いましょう。いえとち本舗は会員登録すると厳選した間取りをまとめた資料を無料でご覧にいただけます。もし、家の間取りに悩んでいると感じていましたら、ぜひご参考にください。会員登録はこちら









