ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
騒音対策で快適なお家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の永井と申します(^^)/
本日は防府・山口・山陽小野田・宇部・周南で新築住宅の購入をお考えの皆様に「騒音対策で快適なお家づくり」についてお話します!
突然ですが皆様、今住まわれているお家で他人の音について困ったことはありませんか?
例えばアパートなどでは、上の階の人の足音がうるさいだとか話し声が響いてくるとか、、、
一軒家でも、隣のお家との間隔が狭かったら生活音はかなり聞こえてきますよね。

新築を建てるときに大切にしたいポイントとして、「静か」であることが挙げられます。
日中は気にならない程度の音も、深夜や早朝では聞こえ方が変わってきます。
騒音が気になってしまうお家では気が休まらず、知らないうちにストレスが溜まってしまうことも、、、( ;∀;)
それが原因でご近所トラブルになってしまったニュースもありました。
反対に、自分から発せられる生活音が近隣住民のストレスになっていないかの配慮も必要です。
静かな家は落ち着きがあり、趣味や仕事に没頭できる空間であると同時に大切な家族とのコミュニケーションの場です。
そこで山口・周南・防府・宇部・山陽小野田で新築住宅の購入をお考えの皆様に、
静かなお家を実現させるために知っておきたい騒音対策についてのポイントと具体的な対策方法をご紹介していきます。
★騒音対策のポイント
〇騒音の特性をまず理解する
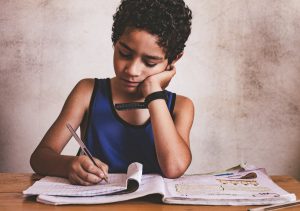
音には様々な種類がありますが、騒音対策として知っておきたいのが
・空気伝搬音
・個体伝搬音
です。
空気伝搬音とは、空気を媒体として伝わる音のことで、電車や車の音がこれにあたります。
個体伝搬音とは、壁や床などの物体を媒体として伝わる音のことで、2階の足音や床に物を落とした時の音がこれにあたります。
このように、同じような騒音でも伝わり方で特徴がことなるので、対策も異なってきます。
家を建てる前に土地の立地や騒音の特性をよく検証し、それに合わせて必要な対策を練ることが大切になってきます。
〇防音性能を高める方法
①主な生活スペースは音源から距離を置く

外からの騒音対策として、家族と過ごす時間が長い寝室やリビングは、道路や川などの音源からできるだけ離れたところに作るプランニングが必要です。
プランニングの時に部屋の開口部をできるだけ小さくすることをお忘れなく。防音効果が高まります(^_-)-☆
音源から離すことが難しい場合は窓に防音カーテンを取り付けることで窓から入ってくる音を減衰させましょう。防音カーテンは防音だけでなく断熱や遮光の効果もあります。
防音カーテンは厚手の記事を複重層に折り重ねた構造になっており、布の間には遮音材が挟み込まれています。
一般のカーテンだと上部や最下部にすき間ができやすいですが、防音カーテンは密閉性を確保するためにカーテンの上部と底部はカーテンレールや窓に密着するような構造になっています。
最近の防音カーテンは複数カラーが用意されていることが多いので部屋の雰囲気に合わせて好きな色を選ぶことができます♪
通常では、防音カーテンは重い方が効果を発揮するので、大幅な騒音カット効果を実感したいのなら、重量のある物を選びましょう。(^^♪
また、道路側の壁を防音壁や防音パネルを使用するなどの対策もあります。
防音壁は割と価格が安価で屋外のどんな過酷な環境でも使用できることからパーキングの付近の壁などに多く使われています。
防音パネルはお家の外側の壁だけでなく内側にも取り付けることができる上に簡単で設置に時間がかかりません。
②遮音効果の高い窓やサッシを使用する

なるべく気密性の高い窓やサッシは外の騒音を大幅に軽減させることができます。
気密性の高い窓やサッシは音の遮断の他にも、室外の空気の流入を防ぐのでエアコンなどの冷暖房費を抑えることができるので省エネにもなります♪
気密性の高い窓やサッシが付けられない場合は窓と窓枠のすき間にシールテープを貼ることにより外気の風や音を遮断します!

気密性が高いと、外からの騒音だけでなく自分のお家からでる生活音を軽減させることができますので、
ピアノや楽器を室内で使用する方はできるだけ気密性の高いお家に住まれた方がトラブルを未然に防ぐことができます。
③小さな工夫で遮音・吸音性能を高める

音は平らで固いものにぶつかると反射しやすく、デコボコして柔らかいものにぶつかると吸収されやすくなります。
この特性を利用し、お家の壁紙を凹凸のあるものにしたり、床をフローリングではなくカーペット素材にすることで遮音・吸音効果を高めることができます。
具体的な対策としては、まず壁に遮音シートを貼ることが挙げられます。
遮音シートは壁に貼るだけで壁から伝わってくる音を減衰させることができ、簡単に取り外しができる優れものです。
シートはできるだけ質量のある物を選んだ方が壁の防振効果が高く、防音に優れているので、ピアノや楽器を室内で使用される方は質量のあるものを選ぶ方がよさそうです(^^)/
床材は防音マットを敷くことが適していますが、お子様が小さい場合は柔らかいコルクマットの方がよいでしょう。
万が一お子様が転んだ時も緩衝材となるためタンコブやアザができたりといった怪我をする可能性が低くなります。
また、コルクマットは夏は涼しく、冬は暖かく過ごす事ができるためとても快適です。
保温効果もあるのでエアコンの冷暖房代を削減する効果も期待できます!
コルクマットを購入するときはそのコルクの粒の大きさも確認するようにしましょう。
大粒タイプのコルクは通気性や弾力性に優れています。一方、小粒タイプのコルクは遮音性に優れています。
防音マットやコルクマットの上に防音カーペットを敷くとさらに遮音効果が高まります。また、カーペットは肌触りが良いので生活空間を快適にします♪
防音カーペットにも種類があり、「タイル式」、「ラグ式」、「オーダーメイド」、「不織布」があります。
タイル式は、汚れたり傷ついた部分を簡単に交換できるのでメンテナンスに優れています。
ラグ式はデザイン性に優れているものが多いです。
不織布はフエルト素材でできており、安価といった特徴があります。
家族それぞれのライフスタイルに合わせてカーペットを選べるので適応しやすいですね (^^)/
家具家電の振動や騒音を防ぐための防振ゴムというものもあります。
防振ゴムは一般的にはゴムもしくはジェルでできています。
エアコンや冷蔵庫、プリンターなど振動して音を発生させている機械の下に防振ゴムを置き、振動をゴムの弾性により吸収します。
また、スベリ止め効果もあるので机やテーブルに設置した機械が地震などで落ちてくるのを防止する効果も期待できます。
ゴム製品は一般的に時間経過とともに劣化をします。(*_*)
ですので新築を建てたときの購入当時より硬くなったりヒビが入ってしまっているものは買い替えをする必要があります。
防振ゴムの他に家具家電に取り付けられる騒音対策として防音材というものもあります。
防音材は発砲素材で作られていることが多く、ハサミなどで簡単に思ったカタチに加工することができます!
素材が柔らかいので、曲面やパソコンの角への貼り付けも簡単にできます。
防音材は耳障りな高周波音を遮断してくれるので、パソコンの静音対策やドアのすき間から入ってくる外部の音を防ぐのに適しています。
また、防音材は音にこだわる人のスピーカーやピアノ用吸音材としても効果があり、反射音を吸収することで音がクリアになる効果もあります♪
★最後に
上記の騒音対策を実施することで、騒音によるストレスが軽減するのではないでしょうか。
「静か」なお家づくりには家を建てる前のプランニングがとても大切になってきます。
壁材や床材に加えて小さな工夫を施すことで快適な住まいづくりができると思います。
防府・山口・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅を建てられる際は、静かで快適で居心地の良い空間を実現するために参考にしてみてください。
気になることがあれば、イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店までお問い合わせ下さい(^^)/
10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓
【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会
関連記事
-

擁壁とは?種類や費用、注意点を徹底解説
1 擁壁とは?2 擁壁工事の種類は? 3 擁壁工事の費用や工期は?4 擁壁トラブルやリスクを回避するための注意点5 まとめ 高低差のある土地には斜面が崩れてしまわないように擁壁を設けています。これから新しく家を建てる方の中には新しく擁壁を設けなければいけないケースや、土地や中古住宅を探している方は擁壁付きの物件と出会うかもしれません。この時に擁壁のことを知らないまま購入してしまうと、後々トラブルに発展する可能性がありますので、ちゃんと擁壁のことについて知っておきましょう。擁壁とは? 擁壁とは高低差のある土地にできる斜面が崩れないように設ける壁のことをいいます。高く積まれた土壌は重力により土砂崩れなどを起こす可能性があり、土壌の安息角を超える大きな高低差を設ける際は、土壌の横圧に耐えられるように擁壁を設けて斜面の崩壊を防ぐ必要があります。安息角とは土地や粉粒体を積み上げた時に自発的に崩れず安定を保った時の斜面と水平面の角度のことです。この安息角を超える斜面は土壌が崩れる恐れがあるため擁壁を設けて崩落を防ぐ対応が必要となります。擁壁を設ける際は、土壌の横圧の他に水圧も考慮する必要があり、排水の仕組みがうまく働かないと静水圧が擁壁に影響を与えます。擁壁は土留と呼ばれることもありますが、土留は一時的な構造、擁壁は長期的な構造と区別されているのが一般的です。擁壁が造られるケースは、崖地の崩落を防ぐために造られたり、土地の造成時にできた高低差のために造られてたりします。高低差のある土地に建物を建てる際は、土壌がしっかりと安定した形のまま保たれていなければ、いずれ建物ごと崩れてしまいますので、このような崩落を防ぐために擁壁は造られます。擁壁工事の種類は? 擁壁は大きく区別すると鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック、石があります。それでは以下にてどんな擁壁か一つずつお伝えしていきます。コンクリート造擁壁コンクリート擁壁は無筋コンクリートと鉄筋コンクリートに分けられます。二つの違いは名前を見てもわかるとおりコンクリートの中に鉄筋が組まれているか、組まれていないかになり、鉄筋が組まれている方が強度はあります。一般的に用いられるのは鉄筋コンクリート造の擁壁で、構造計算が容易で崖に対して垂直に建てやすい特徴があります。コンクリート造の擁壁の底版には「逆T字型」「L型」「逆L型」「重量式」「もたれ式」などがあり、立地条件に合わせて適切な構造を使い分けていきます。間知ブロック擁壁間知ブロックを用いた擁壁のことを間知ブロック擁壁といい、大きさの揃ったブロックを積んで造られます。間知ブロック擁壁は練積みという工法が用いられ、ブロック裏側をコンクリートで固めたり、割石などを詰めたりします。また、積み方にも水平方向に積む布積みや斜めに積む矢羽積みなどがあります。石積みの擁壁石積みの擁壁には大谷石で作られた「大谷石積み擁壁」と石やコンクリートブロックを積んで造る「空石積み擁壁」があります。コンクリート造や間知ブロックは建築基準法により基準が定められていますが、大谷石積みの場合は現在の基準よりも低いため、もし「大谷石積み擁壁」が残る擁壁の場合は損傷がないか確認する必要があります。「空石積み擁壁」は簡素な造りとなっており、高低差の少ないところに造られます。こちらも現行基準に満たされていないため1.5m以上の高低差に設ける場合は強度の懸念があるため対策が必要です。擁壁のメンテナンスの必要性擁壁の耐用年数は20~50年ほど。鉄筋コンクリート擁壁やコンクリートブロック積み擁壁などコンクリートで作られる擁壁の寿命は50年ほどです。このため経年劣化でそうそう壊れることはありませんが、劣化は進みますので、いずれメンテナンスは必要になります。劣化症状には排水の具合や土や草の詰まり、コケの発生、ひび割れ、膨れ、変形などがあります。擁壁は水が溜まらないように水抜き穴が設けられていますが、この排水の状態は気にかけておくことです。擁壁の表面が湿っていたり、水が染み込んでいたりする場合は、排水がうまくできていない可能性があります。また、水の抜け具合にばらつきがある場合も気をつけましょう。こういった劣化は年数が経つにつれて症状が出てくるため定期的に点検しておくことです。一般の方が劣化しているか判断するのは難易度が高いため、擁壁に変化が見られる場合は専門業者に相談しましょう。また、石積み擁壁は現在のがけ条例の基準を満たしていない可能性があります。もし基準を満たしていない場合は、現在の基準を満たす工事が必要です。工事をするのに申請は必要か高低差2m以上ある土地は自治体が定める条例で擁壁を設けるように義務付けされている傾向にあり、もし自治体が擁壁を設けるように条例で義務付けしている場合は、工事を行うのに申請が必要になります。また、がけ条例の該当要件の範囲については自治体によって詳細は異なるため各自治体に確認を取る必要があります。東京都のがけ条例の場合は、崖から「がけの高さに2をかけた距離」離して家を建てること、崖は擁壁にすることになっています。一般的に申請してから許可が下りるまで一ヶ月前後かかりますので、入居するスケジュールを決めている場合は早めに行動しておく必要があるでしょう。 高さが2mを超える切土の崖を生ずる工事高さが1mを超える盛り土の崖を生ずる工事盛土と切土を同時に行う場合、盛土は1m以下で切土と合わせて2mを超える崖を生ずる工事宅地造成面積500㎡を超える工事(切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく)高さ2mを超える擁壁や排水施設の除去を行う宅地造成工事規制区域で上記の工事を行う場合は、各自治体に申請して工事の許可を取る必要があります。また、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されている土地に住宅を建てる場合は申請をして許可を取る必要があります。5m以上の崖高さがあるところは「急傾斜地崩壊危険区域」として各都道府県によって指定されています。「急傾斜地崩壊危険区域」に指定される土地での住宅の建築は、一般的に施主が擁壁工事を行うのではなく、都道府県が崩落防止のために擁壁工事を行います。擁壁工事の費用や工期は? 擁壁の中では鉄筋コンクリート造が高く、無筋コンクリート、ブロック造の順で安くなっていきます。工事費用は立地条件や土地の状態によって変動しますので、一概にいくらと決めることはできませんが、相場としては5〜10万円/㎡が目安となっています。擁壁工事の内容別に費用の目安を以下に記載しましたのでご参考にしてください。 新規擁壁工事:数百万円~数千万円擁壁のやり直し:3~13万円/㎡擁壁の一部修復:1~2万円/㎡擁壁工事の価格変動の要因は施工する土地の地盤が安定しているか、というのが影響します。地盤の緩い土地に擁壁を設ける場合は、より強固に造る必要があり、自然災害の多い地域ではリスクも高いため、強度が一層に求められます。このようなケースだと工事の単価も上がるため、一般的な費用相場では擁壁を作ることができない可能性があります。擁壁工事の費用は立地条件も左右され、工事車両や重機が入れない道路環境の場合は、車両の規模を小さくするか人材を増やす対応が必要となります。車両の規模を小さくするということは、その分搬出・搬入の往復が多くなるため、こちらも費用がかさむ要因となります。また、施工時に出る残土の処分費も土の状態によって価格が変わります。もし汚染されている土の場合は浄化する必要が出てくるため、費用も通常の価格から加算されます。 擁壁工事は補助金や助成金を出している自治体もあります。補助金の対象要件は各自治体によって異なりますので、もし利用する場合は実施されているか確認を取りましょう。要件を満たしているかなどの判断は一般の方で行うのは難易度が高いため専門業者に依頼することをおすすめします。擁壁工事の工期は規模により違いはありますが、規模が小さければ約15日、中規模で約一ヶ月、大規模になりますと約三ヶ月かかります。工期についてはほとんどの業者は工程表を渡してくれると思いますので、工事前に必ず確認をしましょう。擁壁工事の助成金 擁壁工事は高額となりやすい工事なためお金の負担が大きいですが、条件に該当する工事を行う場合は地方自治体が実施する助成金制度を利用することができます。対象要件は各地方自治体に確認する必要がありますが、東京都港区の場合は工事費用1/2(500万円を上限とする)まで助成金を受けることができます。基本的に助成金の利用は施主本人が申請する必要がありますが、委任状を交わせば業者に申請手続きの代行をしてくれることもあります。申請に慣れていない方は戸惑うところも出てくると思いますので、助成金の利用を検討している方は、申請手続きをサポートしてくれるか業者に相談することをおすすめします。擁壁トラブルやリスクを回避するための注意点 擁壁を新しく造る場合や擁壁付きの土地または中古住宅を購入する場合など、擁壁についていくつか注意する点がありますので以下にお伝えするポイントをチェックしておきましょう。擁壁や地盤の状態を確認 擁壁の耐用年数は約20〜50年です。築年数の浅い擁壁なら問題ですが、年数の経っている擁壁の場合は経年劣化を起こしている可能性があるため、クラックがないか、変形がないか、など確認しておくことが重要です。懸念される状態はその他にも、隙間がある、排水気候が設けられていない、水抜き穴の詰まり、擁壁が湿っているなどです。このような状態にある場合、強度の低下や水圧により変形が起きている可能性があります。また、擁壁は地盤の状態により適した強度であるかが判断されます。軟弱な地盤の場合は不動沈下を起こす恐れもありますので、費用はかかりますが地盤調査をしておくとより安心です。擁壁付きの物件は状態によって造り直しが必要になることもあり、トラブルとなってしまう可能性があります。そのため擁壁付きの土地や中古住宅を購入する際は擁壁の状態や年数、地盤の強度を確認しましょう。擁壁と境界のトラブル 隣家との境界に擁壁がある場合もトラブルに発展しやすいため注意が必要です。境界に擁壁がある場合、もし不適格な擁壁だったとすると、この工事費用や責任はどちらが負担するのかが問題となってきます。このようなトラブルは必ずしも擁壁を所有している側が負うのではなく、例えば上側の土に問題があって崩落の危険があるといった場合、上側も負担を負わなければいけない可能性があります。双方に責任が及ぶ場合、修復する費用の割合をどうするかで非常にもつれますので、擁壁が不適格か適合しているか事前に確認しておくことが大切です。まとめ ここまで擁壁とはなにか、修理費用やトラブルなどの注意点についてお伝えしてきました。擁壁は高低差のある土地の斜面の崩落を防ぐために設ける壁状の構造物です。もし、擁壁を新しく造る計画をされている方や擁壁付きの土地または中古住宅の購入を検討されている方は、擁壁の状態や隣家との境界などに注意して工事を進めていくことが大切です。擁壁は専門的な知識と経験が必要ですから、本格的に計画が進む際は専門家に相談することをおすすめします。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-

掃き出し窓とは?腰窓の違いやメリットを徹底解説
採光や通風、開放性などを取り入れるには欠かせない掃き出し窓ですが、掃き出し窓とはどんな窓なのか詳しくは知らないという方もいるのではないでしょうか。掃き出し窓は大きな開口を設けられるため開放的な空間を作り出すことができますが、取り入れる際にはいくつか注意しなければいけないところもあります。この記事はこれから家を建てる方に向けて掃き出し窓や腰窓の違いなどをお伝えしていきます。 掃き出し窓とはどんな窓? 掃き出し窓とは床にまで下ろされている窓のことであり、引き違い窓のようにレールの上を滑って左右に開閉する構造を持っています。人が出入りするところに設けられることが多く、窓のサイズも大きいことから開放的で採光を取ることができる特徴があります。腰窓との違いは、床にまで下ろされているか、壁上で納まっているかのサイズの違いになります。腰窓は高さが掃き出し窓よりも低く、主に採光や風を取り入れるために設け、高さは90〜120cmほどが標準です。また、窓には開閉できる窓とFIXという開閉できない窓があります。FIXははめ殺し窓、ピクチャーウィンドウとも呼ばれて、明かり取りや眺望を目的として設けられることの多い窓となっています。掃き出し窓と腰窓の違いを大まかに言いますと、採光や通風を取り入れながら人の出入りもできるのが掃き出し窓、人の出入りを目的とはしていないけど、採光や通風を取り入れるために設けるのが腰窓となります。掃き出し窓の設置面について 掃き出し窓は人の出入りできる窓のため床にまで下ろした180cm以上の高さのある窓ですが、ベランダに接する掃き出し窓は防水のため立ち上がり(床よりも少し高めに設置するために作る壁のこと)を設けます。なぜ床よりも高い位置に窓を設けるかというと、掃き出し窓が床と同じ高さにあると、もし大雨でベランダに水が溜まってしまった場合、窓から水が入ってきてしまう恐れがあるからです。大雨でも窓から水が入ってこないようにするために、現在の住宅では床よりも少し高い位置に掃き出し窓を設けることになっておりますので、必ずしも掃き出し窓が床に接しているとは限らないことを押さえておきましょう。掃き出し窓のメリットは? 掃き出し窓のメリットは以下のことが挙げられます。 採光をとることができる開放的な空間を作ることができる人の出入りができる眺望に優れる通風を取り入れやすい掃き出し窓はサイズも大きいことから、開放感や眺望性に優れている窓と言えます。また、中庭やウッドデッキ、サンルームなどにアクセスできる掃き出し窓の場合は、室内とつながる空間となるため、間取り以上の広さを感じることができ、開放感のある空間にすることができます。2階リビングに掃き出し窓を設ければ眺望性も期待できますのでおすすめです。掃き出し窓は開口が大きくなるため風を取り入れること、光を取り入れることに優れ、湿気やカビ対策にもなります。日光は生活リズムを整える効果もありますので掃き出し窓は健康管理にも役立ってくれます。掃き出し窓のデメリットは? 掃き出し窓のデメリットは以下のことが挙げられます。 断熱性が下がる遮音性・防音性が下がる耐震性が下がる防犯の懸念プライバシーの確保が必要窓の開閉が重くなる窓が大きくなる分、デメリットとなるところはいくつかあり、まず耐震性が低下します。間口が広いほど耐震性が下がりますので、その分建物の強度を上げる対策が必要です。また、建物の熱の出入りは窓からが最も割合が高く、しっかりと断熱性を確保しなければ冬は寒く、夏は暑い家になってしまいます。なるべく窓から熱の流出がないように二重サッシやLow-E、樹脂サッシなど断熱性の高い窓を取り入れることが大切です。掃き出し窓の開放性は、見方によっては防犯性やプライバシーの確保が必要ということです。窓が大きいほど人の視線は入りやすく、人が侵入しやすいということですので、窓を取り付ける位置に気を付けたり、防犯ガラスにしたりするなどの対策をしましょう。また、構造上仕方ないことですが、窓が大きくなるとその分重量が増しますので、窓の開閉時に重たいと感じやすいのもデメリットとなります。掃き出し窓のデメリットをカバーするには? 掃き出し窓のプライバシーや防犯性を改善していくためには、窓の設置位置や外側から視線が入らない工夫をしていくことが大切です。窓の位置については「近隣の家の窓と近接しないこと」「近隣の窓から家の中を覗ける位置に窓を設けないこと」が大事になります。また、外側の視線に対しては「目隠しフェンスを設ける」「生垣を設ける」「目隠しカーテンを取り付ける」など視線を遮るものがあると家の中でも外側からの視線を気にすることなく生活を送ることができます。防犯性については補助錠といった防犯グッズを活用することで、より安全性を高めることができます。掃き出し窓の懸念される要素として断熱性や耐震性の住宅性能が落ちることですが、こちらは掃き出し窓を設ける際に耐震性や断熱性などの住宅性能が全体的に適切であるかを見定めることが重要です。掃き出し窓を取り付けたいけれど断熱性能が不安な場合「樹脂サッシにグレードアップする」「Low-Eガラスなど断熱性の高いガラスにグレードアップする」などできるだけ住宅性能を下げない対策をするといいでしょう。また、耐震性については家全体のバランスや強度となりますので、設計士の方と打ち合わせをしながら適切なサイズの掃き出し窓を選定、配置していくことが大切です。「掃き出し窓」を選択したかたの実例紹介 これから家を建てようとご検討されている方はどのように掃き出し窓を活用すればいいか気になるところかと思います。実際にどんな風に掃き出し窓が取り入れられているか事例を知っておくと今後の家を設計する際にイメージがつかみやすくなりますので、ここでは掃き出し窓の実例をご紹介していきます。インナーバルコニーのある2階リビング 2階リビングを採用したお家は、リビングからバルコニーまで床がフラットにつながる開放的な空間。掃き出し窓は折れ戸を採用し、間口の幅いっぱいまで窓を開くことができます。バルコニーはコの字型にすることで外からの視線を避けプライバシーを確保する設計がされ、風通しがよく、陽の光も入る空間を実現しています。引用:suumo TAKUMITO/ヘルシーホーム:インナーバルコニーのある2階リビング。風が通り、陽の光があふれる窓辺で猫と暮らす住まい吹抜け大空間のデザイナーズ住宅 吹き抜けのあるリビングに中庭につながる掃き出し窓は、光と風をたっぷりと取り込む設計がされた開放的な空間となっています。窓の間口を広くしたり、吹き抜けを設けたりすると耐震性が懸念されることですが、こちらのお家は高い耐震性を誇る構造を取り入れることで地震にも強い明るく開放的なお家を実現しています。どうしても開口が大きくなる掃き出し窓も建物の構造を地震に強いものにすることで弱点を補うことができますので、窓を大きくして開放的な空間にしたいという方は地震に強い建物構造を取り入れてみましょう。引用:suumo 新栄建設 パナソニックビルダーズグループ:強靭な耐震で地震から家族を守る。吹抜け大空間のデザイナーズ住宅 まとめ 掃き出し窓は床にまで下ろされた人の出入りができる窓のことです。光や通風を取り入れることに優れ、明るく開放的な空間にしてくれます。開口が大きくなる分、プライバシーの確保や耐震性などを考慮する必要はありますが、窓の位置を変える、建物構造を地震に強いものにする、など設計の工夫次第で欠点を補うことも可能ですので、これから家を建てる方は設計士の方に相談してみましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから
-

ビルトインガレージのメリット・デメリットは?後悔しないためのコツ
愛車をいつでも楽しむことができる夢のある住宅。趣味空間として充実しているだけでなく、土地の有効活用ができるということもビルトインガレージの魅力です。人生に楽しみを与え、高い実用性も兼ねているビルトインガレージは、憧れている人も多く人気があります。この記事ではビルトインガレージのメリットやデメリット、後悔しないためのコツなどをお伝えしていきます。1 ビルトインガレージとは2 ビルトインガレージのメリット3 ビルトインガレージのデメリット4 ビルトインガレージに必要なもの5 ビルトインガレージで後悔しないための注意点6 まとめビルトインガレージとは一般的な住宅は建物と駐車スペースを別々に設けますが、狭い土地だと駐車スペースを設けることができなかったり、駐車スペースを設けるために居住する建物部分を削らなければいけなかったりします。こういった事情を解決し、土地を有効活用できる建物がビルトインガレージです。ビルトインガレージは建物の1階部分が駐車スペースとなり、居住スペースと駐車スペースが一体になる構造になっています。ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを設けることができるということだけでなく、車が好きな方やDIY好きな方にも人気が高く暮らしをさらに楽しませてくれる住宅です。 ビルトインガレージのメリット土地が狭くても駐車スペースを設けられる ビルトインガレージは駐車スペースを確保することができない狭い土地にはうってつけといえます。ガレージのように駐車目的のスペースなら容積率の緩和精度があり、建築物の床面積の1/5までなら床面積に算入されません。これなら都心部のような容積率の厳しい土地でも効率よくスペースを活用することができます。 居住空間の良好な環境を取り入れられる 居住スペースは必然的に2階以上に設けることになりますが、上の階に居住スペースがくることで、採光や通風をとりやすい間取りになります。リビングも高所のところにくるため眺望も良くなり、バルコニーとつながるリビングなら空間に奥行きが生まれて開放感を得ることができます。 充実した趣味空間が実現 ガレージと居住空間の仕切りをガラスにすれば、いつでも室内から愛車を眺めることができます。ビルトインガレージはティーラーのショールームのように見せることができるためインテリア性も上がり、趣味空間として充実します。また、屋外のように扱えるため車の整備やDIYも室内で行うことができます。 駐車から居住空間までアクセスが容易 駐車スペースから居住スペースにアクセスできる玄関を設ければ外に出ることなく室内に入ることができます。雨が降っている時や買い物から帰ってきた時は、移動の負担が少なく非常に効率の良い動線になります。 車を室内環境で保管できる 一般的な駐車スペースは屋外にあるため、車は外部の影響を受けやすいことが懸念されます。歩行者のいたずらや風雨にさらされることで、車を痛めてしまう可能性もないとは限りません。その点、ビルトインガレージは室内に車が駐車されるため、外部からの影響を受けず安心して保管することができます。 ビルトインガレージのデメリット 居住空間が2階以上になる 1階に駐車スペースきて居住空間が2階以上になるため、アクセスするには階段の登り下りが必ず必要になります。身体の負担を感じやすい高齢者や障害を抱える方には、この構造はデメリットとなってしまいます。ホームエレベーターを設置する案もありますが、その分エレベーター設置のスペースを確保する必要があるのと、導入コストが高くなります。 建物構造の制約を受けてしまうことも ガレージは車の駐車スペースを確保する必要があるため、居住空間と比べて壁や柱が少なくなり、階数も2階以上ということもあって建物の荷重に耐える構造を有していることが求められます。建物構造には木造や鉄骨造、RC造などがありますが、設計によっては選べる構造が制限されてしまうでしょう。 音や排気の臭いの対策が必要 車のエンジン音や排気の臭いが居住空間にまで届いてきてしまう可能性があるため対策が必要です。遮蔽するシャッターも思っているよりも大きい音が鳴りますので、音の出にくいものを取り付けることが望ましいです。 ビルトインガレージに必要なものガレージの床は水に強く油などで汚れても大丈夫な素材を使うことが望ましいです。一般的にはコンクリートが採用されていて、車のような重量のあるものがのっても割れない強度を有していることが必要です。床材は複合的に使うケースもあり、駐車スペースはコンクリート、車を駐車しない場所は無垢材やタイルで仕上げることもできます。床は水が流れていくように歩行が困難にならないくらいの緩い勾配(傾斜)を設け、洗車などを行う場合は排水口を設けるといいでしょう。コンクリートは水を吸う性質があるため状態を維持していくために撥水性のある塗料や樹脂製塗料を塗ることもおすすめです。駐車スペースとして広さは余裕を持って確保することが大切です。現在所有する車に合わせて設計してしまうと、車の買い替えの時に選べるものが制限されてしまいます。また、介護者の車の乗り降りや車椅子の移動なども1.4m以上の通路幅を確保する必要があります。車の排気ガスの臭いは換気扇を設けて空気の入れ替えができるようにしましょう。シャッターは開閉時に音が響くためできるだけ音の出にくいものを選ぶこと。スライダー式は巻き上げ式のシャッターよりも音が静かです。また、シャッターは間口が長く重量があります。手動だと開く時の負担が大きいため自動開閉型のものがおすすめです。リモコン操作で開閉ができますので、車に乗りながら操作が可能です。 ガレージ内は暗くなりますので照明を設置しておきましょう。ガレージ内で使う道具類や車関係の備品は収納するスペースがあると便利です。また、電気工具が使えるコンセント、湿気や室温対策のためのエアコンもあるといいでしょう。 ビルトインガレージで後悔しないための注意点ビルトインガレージは一般的な住宅と違って求められる構造や条件が異なりますので、ビルトインガレージをご検討されている方は、実績のある会社に依頼することをおすすめします。家づくりは土地を探すところから始まりますが、素人の方がビルトインガレージに適する土地かどうか判断するのは難しいです。傾斜地や高低差のある土地だと、車を駐車することが困難になり実用性が欠けてしまいます。もし、ビルトインガレージを建てたいと思っている方は、土地探しの時に建築士や設計士の方に立ち会ってもらい、その土地が適しているか判断してもらってから購入をしましょう。ビルトインガレージの居住空間はいろいろな工夫を盛り込めることができます。工夫を凝らした間取りにするには、住宅会社の設計力が試され、スキップフロアなど特殊な間取りも設計できる会社を選ぶことが望ましいです。設計力のある会社に依頼することでビルトインガレージのデメリット部分も解消することが可能ですので、希望を叶えてくれる住宅会社を選びましょう。 まとめ ビルトインガレージは狭い土地でも駐車スペースを確保できる建物です。土地を有効活用することができますので、都心部のような狭小地の多いところに有効です。趣味空間としても楽しませてくれる建物ですので、これから新築を購入しようと考えている方は、ぜひビルトインガレージもご検討してみてはいかがでしょうか。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから









