ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
オープンキッチンのメリットやデメリット対策を解説!実例あり

壁で仕切らないオープンキッチンは開放感のある空間をつくりだすことができる魅力があります。一体感のある空間は広々として、家族とのコミュニケーションもとりやすく明るい空間を実現することができ、多くの方がオープンキッチンを取り入れています。この記事ではオープンキッチンの優れているところや不便なところ、問題への対策などをご紹介していきます。
オープンキッチンとは?

オープンキッチンとは壁で仕切られていないキッチンのことで開放感のあるLDK(リビング・ダイニング・キッチン)の間取りに採用されることが多いです。キッチンが壁で仕切られていないため空間に一体感が生まれ開放感を生み出すことができます。また、キッチンを囲んで友人や家族と一緒に料理を楽しむことができたり、調理中でもリビングを見渡すことができたりもしますので、コミュニケーションもとりやすいのが特徴です。
オープンキッチンには腰壁や垂れ壁を設ける場合とキッチン本体のみ設置するタイプがあり、壁を設けずに設置するキッチンをフルフラットキッチンと呼びます。腰壁を設ける場合は壁がキッチンよりも少し高くなりますが、フルフラットキッチンはキッチンカウンターが伸びる形状をしていますので、高さを変えずフラットに仕上げることができます。
オープンキッチンには「腰壁など仕切り壁を設けるタイプ」と「キッチン本体のみを設置するフルフラットキッチン」があることを押さえておきましょう。
オープンキッチンの種類
オープンキッチンの設置方法にはアイランド型とペニンシュラ型があります。以下にアイランド型とペニンシュラ型の違いをまとめましたので見てみましょう。【アイランド型】
アイランド型は壁に接しないでキッチンを設置する方法です。壁に接していないためキッチンを囲んで料理を楽しむことができ、360°アクセスが可能です。しかし、キッチンを設置するスペースが通常のキッチンよりも必要なため、ある程度の広さが確保できないと圧迫感が出てしまいます。
また、吊り戸棚を設けないことが多いため収納スペースも減ります。しかし、キッチンが独立した形となりますので、空間に一体感が生まれ広々とした印象を演出するには最適なキッチンと言えます。
【ペニンシュラ型】
ペニンシュラ型とは半島を意味し、キッチンの片面だけ壁に接して設置するタイプのキッチンです。ペニンシュラ型はアイランド型のようにある程度の広さがない場合でもオープンキッチンにすることができるメリットがあり、アイランド型のようにキッチンを囲んで料理をすることはできませんが、収納スペースの確保や対面式の開放さとコミュニケーションのとりやすさをバランス良く合わせもたせています。
オープンキッチンのメリット・デメリットとは?
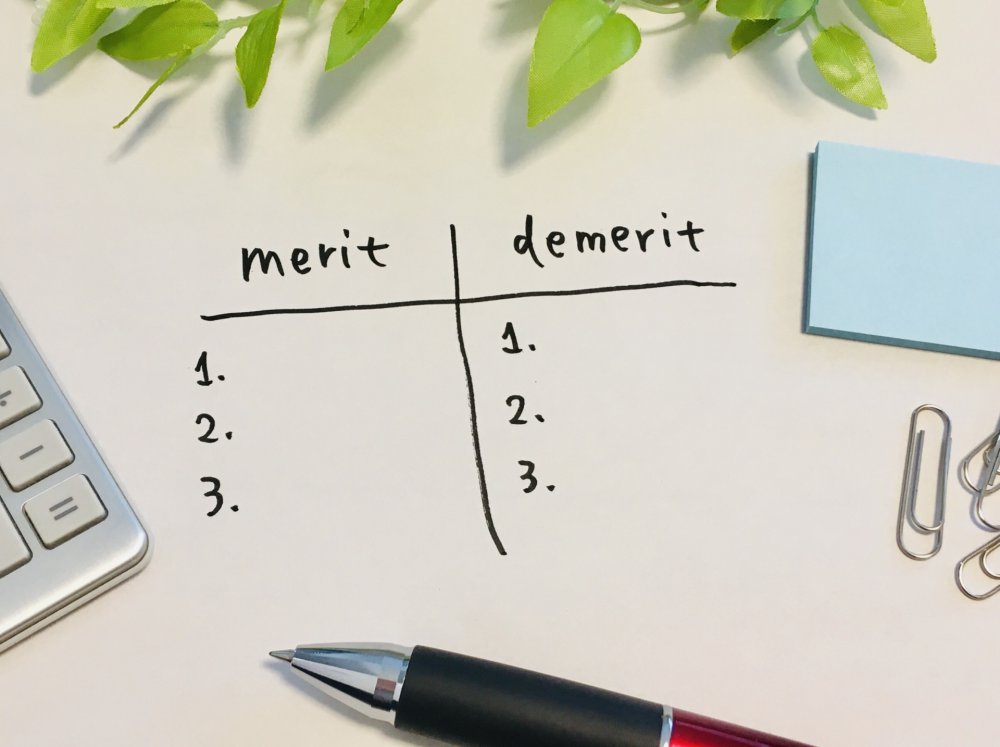
どのキッチンもそうですが、キッチンを使っていて便利な面と不便な面というものがあります。オープンキッチンを考えている方はメリット・デメリットをしっかりと押さえて採用するか検討しましょう。
オープンキッチンのメリット
オープンキッチンのメリットは以下のことが挙げられます。- 開放感のある空間を作ることができる
- コミュニケーションがとりやすい
- 配膳がしやすい
オープンキッチンは壁で仕切らないため、空間に開放感を持たせたい方にはぴったりなキッチンとなっています。料理中でもリビングの様子を眺めることができるため小さい子供のいるご家庭にもおすすめできます。
また、LDKの間取りならリビングとつながる空間となりますので、キッチンが分断されず会話もとりやすいでしょう。また、キッチン正面にカウンターがあれば出来上がった料理をそこに置くことができるため、配膳もしやすいメリットがあります。
オープンキッチンのデメリット
オープンキッチンのデメリットは以下のことが挙げられます。- ある程度の広さが必要
- 収納スペースの確保が必要
- 音や匂いがリビングに届く
- 水ハネや油ハネがする
- 通常のキッチンよりもコストがかかる
- キッチン周りが見えてしまう
- 動線が悪いと使いづらくなる
オープンキッチンを取り入れる場合はある程度の広さが必要です。余裕を持った広さがないとリビングが狭くなってしまうので注意しなければいけません。また、吊り戸棚を設けない場合は食器棚や食品棚を別に設ける必要がありますので、さらに収納スペースの確保が必要になります。
壁で仕切らないことで開放感は出ますが、かえってキッチン周りが見えてしまったり、匂いや音がリビングまで届いてしまったりするなどのデメリットもありますので、こまめな掃除と適切な換気設備の設置が必要です。また、配膳や片付けの際に動線が直線上になく複雑になるという声もあるため、動線によっては使い勝手が悪くなるのも注意が必要です。
オープンキッチンのデメリット対策とは?

上記でお伝えしたようにオープンキッチンのデメリットはありますが、問題を解消する対策もあります。以下にオープンキッチンのデメリットの対策をお伝えしていきます。
【収納スペースが少ない】
開放的になるかわりに収納スペースが少なくなってしまうオープンキッチンですが、背面に食器棚を設けることで収納スペースを確保することができます。また、間取りにキッチンと隣接するパントリーを設けることで空間を分断せず収納スペースを作ることができます。
玄関からパントリー、キッチンへとアクセスできる間取りだと買ってきた物を玄関からそのままパントリーに収納でき、料理の時はキッチンからパントリーにしまってある物を簡単に持ってくることができるため効率的な動線になります。
【音・匂い・水ハネ・油ハネ】
音についてはシンクを静音タイプにする、コンロ正面側のみ壁を設けるなどの対策ができます。また、調理中の匂いに関しては換気量の多い換気扇を設置することでリビングまで匂いが届きにくくなります。換気扇は料理を始める際に回しておくと効果が高くなりますので、ぜひお試しください。
油ハネや水ハネは油ハネガードや腰壁を設置することで防ぐことができます。また、食洗機やタッチレス水栓を取り入れることでシンク内の水ハネ対策になりますのでおすすめです。
【キッチン周りが見えてしまう】
生活感が見えてしまいキッチン周りが気になるという場合は、キッチンよりも少し高さのある腰壁を設けてリビング側からは見えないようにしたり、食洗機を設けてなるべくシンク内に洗い物を置かないことが対策となります。収納が少なく調味料や食品などで散らかってしまう場合はパントリーや食器棚を設けるなど収納計画をすることで問題を解消することができます。
オープンキッチンの実例を紹介

オープンキッチンとはいってもさまざまなレイアウトがありますので、オープンキッチンをご検討されている方はいろいろな施工事例を見て参考にすることをおすすめします。以下にはオープンキッチンの実例をご紹介しておりますのでご参考にしてください。
家族との会話がはずむキッチン
キッチン奥にパントリーを設置して収納を確保したオープンキッチン。コンロ正面側には壁を設け、シンク側は仕切りのない開放的なつくりとなっていますので、リビングとの一体感を生み出し家族とのコミュニケーションもとることができるレイアウトとなっています。引用:LIXIL キッチンのリフォーム実例集
広々としたアイランド型キッチン
キッチン背面には間口2.7mの引き戸付きの収納を配置。収納の引き戸は壁と同じ色なため一体感があり、雑然としやすいキッチンをすっきりまとめあげ、急な来客の時も安心です。キッチンカウンターが伸びた形状のフルフラット型だから凹凸がなくスタイリッシュな空間を演出しています。引用:LIXIL キッチンのリフォーム実例集
まとめ
オープンキッチンは空間に開放感を持たせ、家族とのコミュニケーションもバッチリとれる魅力的なキッチンです。LDKの間取りは空間が一体となる間取りのため、リビングとつながることができるオープンキッチンは壁で仕切るキッチンよりも最適と言えます。オープンキッチンにもいろいろなレイアウトがありますので、オープンキッチンをご検討している方はいろいろな実例を参考にし、自分の好みに合ったキッチンを採用しましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-

子供が安心できる家②【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の杉田です。本日は防府・山口・山陽小野田・周南・宇部で新築住宅をお考えの方に、「子どもが安心できる家」についてお伝えします。今から、宇部・防府・周南・山陽小野田・山口で新築住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。宇部・周南・山口・山陽小野田・防府で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。山陽小野田・防府・宇部・山口・周南で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。子供と安心して過ごせる家とは新築は子供の成長を見据えて、選ぶ決め手の1つになると思います。しかし、子育てをしながら住宅ローンの支払いで持ち家をもつことをご心配されている方も多いですよね。今回は、新築注文住宅を持つことのメリットについて少しばかりではございますが、お伝えをしていければと思います。新築住宅を持つメリットとしてあげられるのが、賃貸アパートに比べて、子供がつい走ってしまう物音や子供の泣き声を気にしなくても良いと言う点です。賃貸アパートでしたら、お隣の方に気を遣いながら子育てをしなければならないので、子供ののびのびとした健やかな成長を無意識のうちに妨げてしまうことも多くなるはずです。持ち家をもつことで、子供には元気いっぱいに家の中で過ごしていただければ、より明るい家庭を作ることができます。また、賃貸アパートと違って、壁紙に消えない落書きをしてしまったなどの子供のいたづらで困り事も寛容になれるのではないでしょうか。更に、庭で夏には簡易プールを設置したり、バーベキューをして楽しんだり、冬には雪合戦など家族と家で過ごした思い出をつくることができ、コミュニケーションも格段に広げることができます。子供の安全を守るための最高等級の建物耐震等級3相当!日本は地震大国ではあり、他県の地震災害のニュースを目にしますが、山口県はあまり大きな地震がおきていません。しかし、油断は禁物です。最近は新築住宅を建てる際に耐震を気にされる方が非常に増えてきています。耐震等級1は、まれに発生する大地震(震度でいうと6強から7程度)に対して倒壊、崩壊してはいけないレベルとなっています。つまり法律では最低限、耐震等級1を満たし震度6から7で最低倒壊しない新築住宅を建築しなさい、と定められています。ですが、当社の建物は地震に強い、最高等級の建物耐震等級3相当で、地震対策を施しています。こちらは、阪神・淡路大震災相当の1.5倍の力の地震でも倒壊しない程度です。(警察署や、消防署など大震災でも倒壊しない建物と同じ基準です。)今後、どんな自然災害が起こるかわかりませんので、万が一に備えて対策は必要です。耐震等級が高ければ高いほど安心の建物ということになりますので、子どもが安心できる家をご提供しています。 省令準耐火構造で、火災保険料も安くなるワケ住宅ローンを組む際に、万一、火事で自宅が燃えてしまって、ローンだけが残ってしまうようなことを避けるためにも、建物に関しては火災保険に加入するのが一般的です。「私の家はオール電化だし、たばこも吸わないから大丈夫」と思っている人も、隣りの家からのもらい火で自宅が燃えてしまった場合はどうでしょう。“自分の家は自分の火災保険で守る”必要があるのです。その中でも当社は省令準耐住宅にすることをおすすめしております。省令準耐住宅にすることで、鉄筋コンクリート住宅などと同じ保険料率にすることができ、火災保険料を安くすることができるのです。省令準耐火構造の3つのポイントをお伝えします。①隣家などから火をもらわない。②部屋から火を出さない。③部屋から火が出た場合にも広げない。火災保険料を安くすることで家計にも優しく、火災が発生しても通常の木造住宅と比較しても、火災を最小限にくいとめることができます。 子供の安眠を取るためにも欠かせない窓日々の疲れを改善するためには、質の良い睡眠は欠かせません。子供の成長のためにも質の良い睡眠をとることは大切です。せっかく建てた新築住宅なのに、あまり眠れない、寝起きが悪くなってしまった・・・そうなってしまうよりも質の良い睡眠を取れるのが理想で、毎日快適に過ごしたいですよね。よりよい睡眠を取りやすくなる子どもが安心できる家には、部屋の広さや温度・湿度・遮光・防音・色彩などが挙げられますが、さらにその環境を整えるのに必要なのが、『ペアガラス(複層ガラス)』です。一流ホテルでも外の騒音を遮断するために窓が2重サッシが増えてきています。遮光カーテンも活用することで部屋を暗い環境にすることで睡眠の質が上がりますが、断熱性が高く、結露しにくいのが特徴の『遮熱Low‐Eガラス』を当社は使用しています。夏は室内に入る太陽の熱線を約60%カットして、冬は室内熱を外へ逃がしにくくするため、普通のペアガラスよりさらに冷暖房の効率も高めることができます。エアコンの省エネにもつながりますし、質の良い睡眠を取りやすい住宅環境につながります。ののどもが安心できる家の新築住宅を建てる際には毎日の睡眠の事も考えてみてくださいませ。 1年中快適な新築住宅昔の建物は左程、断熱性能が重視されていませんでしたが、現在の新築住宅は更に快適性を大切にするため断熱性能をしっかりと確保しています。先ほどご紹介しましたペアガラス(複層ガラス)に加えて、更に壁や屋根の断熱性能にをグッと上げる方法がございます。当社は人にも環境にも優しい安心の『高性能グラスウール』を使用しています。こちらは、短いガラス繊維でできた綿状の素材で、放火性にも優れてにもおりまして、従来のグラスウール繊維をより細く均一にすることでより高い断熱性能を現実化しています。今の夏の暑い時期にエアコンをつけてもなかなか快適な温度にならない、冬は暖房をつけてもなかなか温まらず、朝の布団から出たくないなど、せっかく建設した新築住宅なのに不快感があればとても残念ですよね。このような問題を改善したいというのは当然あると思います。夏は外からの熱を最小限に抑えたい、冬は室内の熱を外に逃がしたくない。つまり子どもが安心できる家には断熱性能は必須です。そこで当社では『遮熱Low‐Eガラス』仕様の窓+『高性能グラスウール』仕様の壁や屋根をおすすめしています。壁や屋根のなかの断熱材も様々なものがあるので皆様も調べてみると面白いですよ。子供が生まれたご家庭やこれから生まれる予定のご家庭では意識するポイントも違ってくるかと思いますが、子育てはとても大変なことで、またとても大切なことです。子どもが安心できる家の重要ポイントを押さえて、カバーができる新築住宅を探すお手伝いができれば幸いです。当社では以上のようなちょっとした工夫の点も踏まえながら、お客様のご要望に沿って、お打合せをさせていただきます。これからの幸せな家庭の為に理想的なお住まいとなるようにご提案をさせていただきます。ちょっとしたご不明な点もございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。7月13日~16日、19日は夏祭!家祭り開催!【山口・防府・宇部・山陽小野田・周南】で【月3万円から高性能なスマートハウス イエテラスの新築】
-

室内の空間を作り出す"室内照明"の重要性①【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは! (*´_●`)ノいえとち本舗山口中央店です! みなさん、街中を歩いている際に「おしゃれだな」と感じる建物、空間はありませんか?おしゃれな雰囲気のお店、カフェ、レストランなどあらゆる空間で感じることがあると思います。 それぞれの空間で、それぞれの個性が出ていますよね。そういったおしゃれな空間はどのようにして生み出されているのでしょうか。 おしゃれな空間を生み出す大きな要素の一つとして“室内照明”があります。 従来の住宅では、だいたいの部屋は天井に1つだけシーリングライトがついており、そのシーリングライトが部屋の全体を照らしている というのが一般的ですよね。 しかし、室内照明はその空間の雰囲気を大きく変えてしまいます。ただ一つシーリングライトが天井についていても、なかなかおしゃれな個性のあるお部屋は作れないですよね。(lll-ω-) せっかく新築住宅を建てるのであれば、雰囲気の良い空間をつくり、誰もが理想とするようなお家づくりをしたいですよね。 新築住宅購入を考えているみなさんが理想の空間を作り上げるために“室内照明”についてみていきましょう。 直接照明と間接照明 ご存知の方もいらっしゃると思いますが、”室内照明”には大きく分けて ★直接照明★間接照明 の2種類があります。 直接照明直接照明は、人や床を直接照らし、手元や足元まで明るくしてくれる “直接照明”は言葉の通り、光源が直接室内を照らす直接光を当てる照明です。室内全体を照らすことを目的としているので、「全体照明」や「主照明」と呼ばれることもあります。 この直接照明は、学校やオフィスなどでよく見かけますよね。直接照明は太陽の光を再現しており、とても活動的な明かりとなっております。なので、学校やオフィスなどで “人を活発的にさせる”という目的もかねて取り付けられております。 間接照明間接照明は、天井や壁を照らした反射で空間全体をゆったりとした雰囲気にしてくれる “間接照明”は、天井や室内の壁面、物などを照らす照明です。直接照明とは対照的に、空間の一部を照らすことを目的としているので、「部分照明」や「補助照明」と呼ばれることもあります。 直接照明と比較すると、少し暗い印象ですが、間接照明は人に直接光が当たらないので、リラックスさせる効果を与えます。 多くの方はシーリングライトの下で生活することに慣れていると思われますが、寝室のようなくつろぎを目的とした部屋や、映画を見る空間などは、間接照明が適していると考えられます。 室内空間をつくる 現在、間接照明を取り付けていらっしゃる方はあまり多くないかもしれませんが、間接照明と直接照明を上手く組み合わせることで、おしゃれな空間をつくり出すことができます。(・o・)/ 今回は直接照明と間接照明についてご紹介させていただきました。空間の作り方には光源の照らし方や色も大きく関係してくるので、 引き続きに次回のコラムでは室内照明の照らし方についてお伝えします。 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*) 1月25日(土)~2月2日(日)開催イベント↓【防府市田島】地域最大級!超絶怒涛の3棟同時見比べ見学会
-

ハウスメーカーと工務店はどっちがいい?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
現在、山陽小野田・宇部・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!今回のテーマは、「ハウスメーカーと工務店はどっちがいい?」です。ハウスメーカーと工務店のどちらにされるかのお悩みを抱えている方にぜひ読んでいただきたいです!新築住宅を建てたいと考えた時、ほとんどの方は、まず会社選びから始めますよね。しかし、総務省の統計によると全国には住宅会社は12万社もあり、どの住宅会社が最適なのか見つけ出すのも大変困難です。住宅会社を選ぶ中で最初に行き詰まるのが、ハウスメーカーと工務店のどちらにするのか?という選択です。・どれがハウスメーカーで、どれが工務店?・どちらに選ぶべきなの?・新築住宅は絶対に失敗したくない!ほとんどの方がそう思うはずです。なんと!ハウスメーカーと工務店にはさまざまな違いがあり、建てたい理想の家によって選ぶ住宅会社は変わってきます。新築住宅は一生に一度のとても大きな買い物です。住宅会社を選び間違えて「こんなはずじゃなかった・・・」と後悔する前に、しっかりと情報収集をしてから始めていきましょう!今回は、ハウスメーカーと工務店の違いについてお伝えをしていきます。 ハウスメーカーとはハウスメーカーという言葉に正式な定義はありません。例として、積水ハウス・セキスイハイム・大和ハウス・パナホーム・ヘーベルハウス・ミサワホーム・住友林業・三井ホームが大手住宅メーカー8社と言われております。しかし、大手8社の他にも、一条工務店やタマホームなどの住宅メーカーもハウスメーカーと呼ばれることもあり、どの県に行っても住宅会社があるところがハウスメーカーなのです。つまり・・・ ハウスメーカー=全国展開している住宅会社ということです。 工務店とは工務店もハウスメーカーと同様に言葉に正式な定義はありません。主に地元に根付いている建設業者で、伝統的に工務店と呼んでいる場合が多いです。複数の営業所があっても、建設エリアは県内や市内、近隣の県にとどまるなど、全国規模ではなく地域密着型が工務店です。工務店は、個人やメーカーから建設を請け負って、様々な分野の専門職人を集めて、工事全体を監督します。同じ工務店でも、業務体制に違いがあり、その体制は工務店によって多種多様です。つまり・・・ 工務店=地域密着型の地元に特化した住宅会社ということです。 しかし、一条工務店のように、○○工務店という名前で全国展開をしている住宅会社も増えてきており、線引きは難しいところでもあります。ちなみに当社は、山口県内の新築住宅を請け負う地域密着型なので、工務店となります! 業務体制の違いハウスメーカーは全国規模で展開しているために、新築住宅は規格住宅が多く、家を商品として売っているので、家を選んで買うと考えるとイメージしやすいです。反対に工務店は、多少の規格はありますが、間取りや外観などお客様と一緒に決めて、家をつくっていく形態が多いというイメージです。ここまではハウスメーカーと工務店の違いについてご説明をしてきました。新築住宅を建てられる方で、ハウスメーカーを選ぶべきか、工務店を選ぶべきか迷われるお客様が大変多いです。新築住宅を建てるにあたって、どちらにどのようなメリットがあり、そしてデメリットがあるのかをさらに深堀をしてお伝えしていきます。ハウスメーカーと工務店のメリットとデメリットをまとめてみました!ご家族の理想の新築住宅を建てるのにぜひ参考にしてみてください。 ハウスメーカーのメリットデメリット 【ハウスメーカーのメリット】・住宅会社が全国規模なので、大きくブランド力がある。・モデルハウスなどの展示場やカタログなどで、イメージがしやすい。・資金計画の相談から、引越し・仮住まい探し(賃貸)などにも対応している。・アフターメンテナンスなど、サービスが充実している。・デザイン力が優れている・品質が安定していて、施工もしっかりしている。 【ハウスメーカーのデメリット】・商品ラインナップ、仕様などがあまり自由でないことがあり、金額が割高。・仕様設備にはオプションの追加設定があり、標準設備に追加した方がいいと勧められて、金額が増えることがある。・住宅会社によっては利益第一で、営業担当は歩合制のため強引な営業をされるケースがある。・契約はハウスメーカーをしたけれど、実際に家を建てるのは下請けの工務店の場合が多く、技術の差に心配がある。 【どういう人に向いてるか?】◎経済力に余裕のある方◎仕事や家事が忙しく、時間をあまりかけたくない方◎資金計画の相談から入居後のアフターメンテナンスまで、幅広くサービスを受けたい方 ハウスメーカーもたくさん増えてきました。TVCMでもよくみますね。太陽光発電の設置住宅や、新商品のプランなどにも力を入れているため、最新の商品もあるのも魅力のひとつですね。長所と短所を比べながら決めていきましょう。 工務店のメリットとデメリット 【工務店のメリット】・信頼関係が大切なので、施工、完成、引渡し後もアフターメンテナンスも地場の業者なので早期対応してもられる。・ハウスメーカーと比較するとコストを抑えることができる。・担当者が同一なことが多く信頼関係を築きやすく、コミュニケーションがとりやすい。・こだわりを細かく聞いてもられて、希望がかないやすい。・標準設定がないので、後からオプションで追加がかかることが少ない。・契約時の見積もりがほぼ最終価格になり、金額の交渉もしやすい。・地元の業者なので安心感がある。 【工務店のデメリット】・一般的に会社規模が小さく不安に感じることが多い。・施工図がメインの設計士が多く、デザイン力、内装設備など提案力が弱い。・モデルハウスを建てていないことが多く、イメージがつかみづらい。・住宅ローンなど資金計画に対する、支援体制が弱い。・各建材や水まわりの商品を細かく決めていくので、決めたりするので時間と手間がかかる。・人数が少ないので、プラン、見積もりに時間がかかる場合がある。 【どういう人に向いてるか?】◎明確なイメージがあり、積極的に新築住宅作りを楽しめる人方◎住宅ローンのコストを抑えて、趣味や旅行などを楽しみたい方◎時間に余裕がある方◎大きい家ではなく、住みやすいコンパクな家に住みたい方 工務店での新築住宅は決める方も多く、それを楽しみながら決められる人向きかもしれません。豊かな生活を送るため、納得のいく後悔しないための家づくりができたら良いですね。地元でずっとやっている工務店さんなどは、安心して新築住宅をまかせられるのではないでしょうか? 自分たちの希望をかなえてくれるかも含めて、新築住宅のお話をすすめていきましょう。 それぞれのメリットとデメリットを比較し、あなたの要望を叶えられる方を選んでください。例えば、ブランドに価値を感じる方はハウスメーカーがいいと思います。反対に、ブランドにはまったく興味が無く、安くて良い家を建てたいと思うのであれば工務店です。 家づくりにおいて、会社選びはとても大切です。住宅会社選びを間違えると、どんなにあなたに知識があっても、どんなにあなたがしっかりと計画を立てても、家づくりは失敗してしまうでしょう。この記事を参考にメリットとデメリットをしっかりと把握し、あなたに合った住宅会社を見つけて頂ければ幸いです。 10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会









