ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
二階建てと平屋の違いとは?メリットや費用面の違いを解説

近年は平屋も人気が出ており、新築を建てる上で選択肢の一つとなっています。一般的なのは二階建てですが、具体的に平屋とどう違うのか知っておくことで、家選びの幅も広くなります。この記事では二階建てと平屋の違いやメリット、費用面の違いについてご紹介していきます。
二階建てと平屋のメリット

二階建てと平屋、構造的に違う二つの建物はそれぞれメリットも異なります。それでは二階建てと平屋のメリットについてご紹介していきますので確認していきましょう。
二階建てのメリット
二階建てのメリットは下記のことが挙げられます。- 階層があるため敷地が限られていても空間の確保ができる
- 採光やプライバシーの確保がしやすい
- 二世帯住宅に適している
二階建ては階層があるため平家と比べて延床面積を増やすことができます。平屋の場合は延床面積を増やすには建築面積を広げる必要があり、その分広い敷地が必要になります。また、建物に囲まれていても2階部分で採光をとることができ、空間も仕切られるため家族間や外部からもプライバシーを確保することができます。二階建ては階層に分けて二世帯にする住宅もあり、二世帯住宅としても適しています。
平屋のメリット
平屋のメリットは下記のことが挙げられます。- バリアフリーで高齢者や子供が暮らしやすい
- 動線が効率的で家事がしやすい
- 廊下が不要で無駄のない間取りができる
- コミュニケーションがとりやすい
平屋は階段が不要なため階段の転落や登り下りの動作負担がなく高齢者や子供も暮らしやすい家となっています。また、すべてが一階に集約されるため洗濯や掃除、料理など家事のしやすい間取りを作ることができます。廊下も設ける必要がありませんので、効率的に空間を確保ができ、開放的な間取りにすれば家族とのコミュニケーションもとりやすいメリットがあります。
二階建てと平屋のデメリット
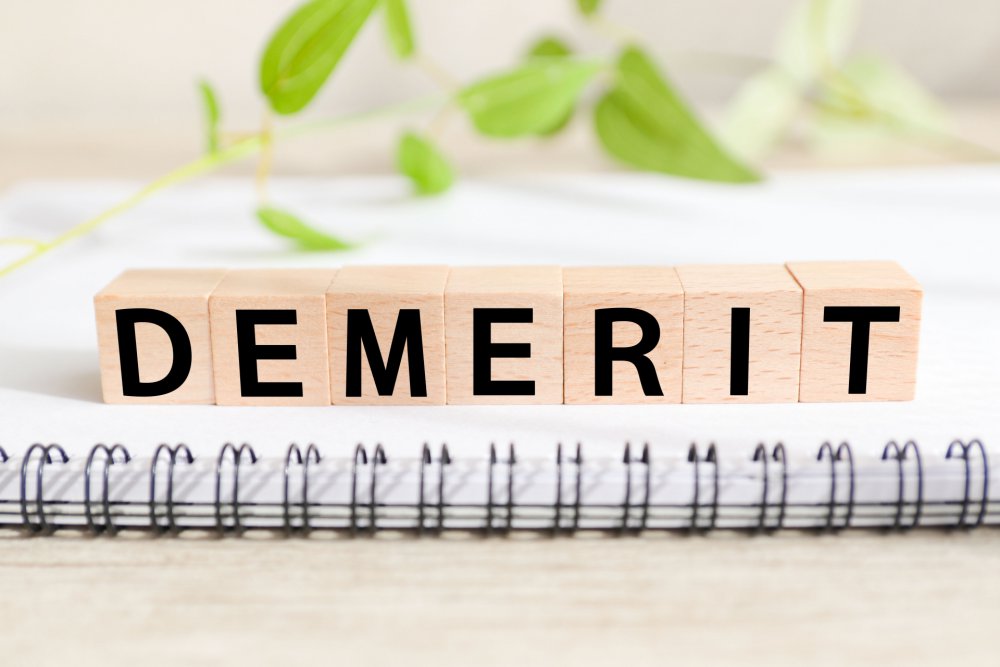
続いて二階建てと平屋のデメリットを見ていきましょう。それぞれ生活のしやすさや間取り設計、建築費用に関わってきますので、これから家を建てようと計画されている方はしっかりとポイントを押さえておくことが大切です。
二階建てのデメリット
二階建てのデメリットは下記になります。- 階段の登り下りにより動作の負担がある
- 効率的な家事動線を考える必要がある
- 耐震性の確保が必要
- 将来的なメンテナンス費を考慮しておく必要がある
二階建ては階段の登り下りがあるため体への負担を感じやすい作りとなっています。高齢の方の場合は足腰の負担により次第に二階の部屋を使わなくなってしまうということもありますので、二階部分が無駄になってしまうということも。
また、洗濯機が一階にあり、物干場は二階になる場合は、階段の登り下りが必須なため平屋と比べると家事動線は複雑になります。建物の構造上、階層があるため耐震性を考慮することも重要です。メンテナンスの際は外壁や屋根塗装の時に足場を設置しなければいけませんので、将来的に掛かるメンテナンス費用も考えておく必要があるでしょう。
平屋のデメリット
平屋のデメリットは下記になります。- 建築コストが割高になる傾向にある
- 広い敷地が必要
- 床上浸水の心配
- 採光・プライバシーの確保が難しい
平屋は二階建てと比べて建築コストが割高になる傾向にあります。その理由は外壁や屋根、基礎の施工面積が広くなるからです。平屋はある程度の空間を確保したい場合、広い敷地が必要になります。建築面積がほぼ延床面積になりますので、二階建てと同じ建築面積で平屋を建てた場合、延床面積は二階建ての方が広くなります。
平屋で気をつけたいことは水害です。床上浸水してしまうと一階部分が水浸しになり、逃げ場がなくなりますので過去に水害が発生していないか家を建てる前に確認しておくことが大切です。また、高さのない平屋は周辺の建物により採光がとれなくなる場合があります。生活が一階で納まってしまうので外部からの視線も遮る必要があり、プライバシーの確保にも配慮する必要があります。
二階建てと平屋の費用面の違いとは
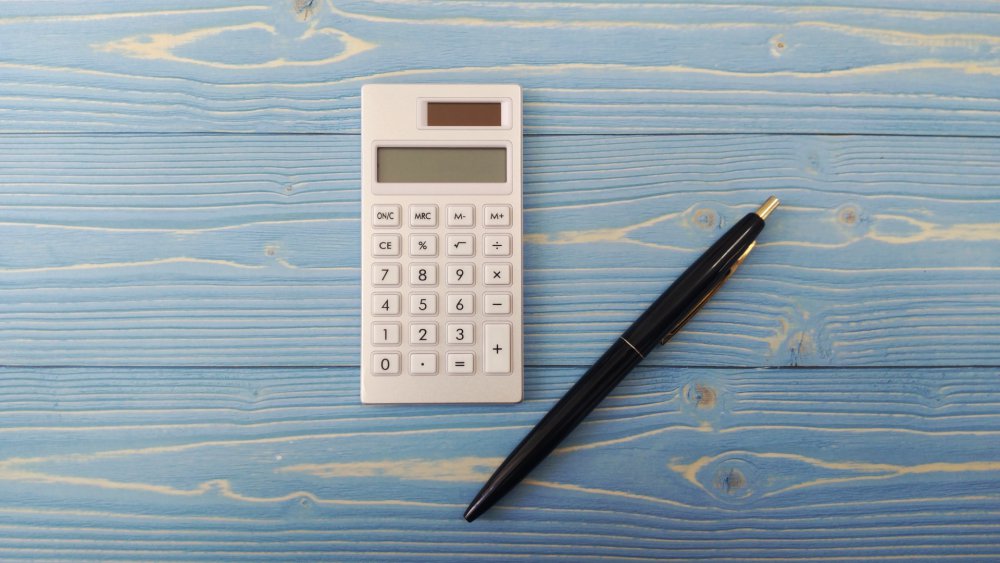
二階建てと平屋は建築コストから将来的なメンテナンス費、固定資産税などの負担する費用に違いがあります。以下にてそれぞれの費用面の違いをお伝えしていきますのでポイントを押さえておきましょう。
平屋と二階建ての建築コストの違い
平屋のデメリットでも前述しましたが、それぞれの建物の建築コストには違いがあり、一般的に平屋の方がコストは掛かる傾向にあります。坪単価で計算すると同じ延床面積で建てた場合、二階建ての方が外壁の面積数は大きくなりますが、基礎や屋根の面積は平屋の方が大きくなり坪単価が上がります。後述しますが、後々掛かってくるメンテナンス費も考慮すると一概に平屋の方が高く、二階建ての方が安いとは言い切れませんので、トータル費として検討し、どちらで建てた方が費用の負担が少ないか資金計画を立てることが大切です。
外装のメンテナンスは二階建ての方が高くなる
二階建ての場合、外壁の塗装や屋根の葺き替えの際に足場の設置が必須になり設置面積も増えるため足場代は平屋よりも掛かります。また、外壁の面積数も二階建ての方が大きくなりますので施工費用も平屋よりは高くなるでしょう。二階建ては高所作業となりますので、点検時も長い梯子をかける必要があり手間もかかるため、メンテナンスのしやすさについては平屋の方が負担は少ないです。税金面では平屋の方が不利になることも
家を建てると固定資産税が掛かり、平屋だと税金面で不利になることがあります。固定資産税は土地と建物に掛かり、負担する額は敷地の広さや建物の資産価値などで決まります。資産価値は建物の価格が目安の一つになりますので、価格が高くなる平屋は二階建てよりも評価額が高くなり、税金も高くなる可能性があります。二階建てと平屋を決める時のポイント

二階建てと平屋はそれぞれ良さがありますし、不便だなと感じるところもあります。どちらの建物を選んだ方がいいか判断に迷われるかと思いますが、どちらの建物が合っているか決め手となる以下のポイントをチェックして計画を立てましょう。
- 家族構成やライフスタイルがどちらに適しているか
- 建物と比較して予算が適切か
- どれくらいの広さの土地を確保できるか
家ですので生活のしやすさはとても重要になります。また生活していく上で資金も大切ですから建物と費用が見合っているかも配慮する必要があります。家事動線を重視する場合は平屋の方が有利ですし、土地が狭く部屋数を確保できない場合は二階建ての方が部屋数の確保はとりやすいです。
また、高い建物に囲まれている土地の場合は採光がとれない可能性がありますので、このような土地に平屋を建てるのは適切とは言えません。いろいろな条件を照らし合わせて、二階建てか平屋のどちらの建物が適しているかよく検討して選びましょう。
まとめ
二階建てと平屋では生活スタイルが変わってきますので、どちらの方が暮らしやすいかよく検討して選びましょう。家を購入する際は、実際に住んでいるイメージを持つことが大切です。自分にとって二階建ての方が適しているのか、平屋の方が適しているのか、家族構成やライフスタイル、予算などを照らし合わせて後悔のない家を建てましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-

ハウスメーカーと工務店はどっちがいい?【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
現在、山陽小野田・宇部・防府・山口・周南で、家づくりを検討されているみなさん!今回のテーマは、「ハウスメーカーと工務店はどっちがいい?」です。ハウスメーカーと工務店のどちらにされるかのお悩みを抱えている方にぜひ読んでいただきたいです!新築住宅を建てたいと考えた時、ほとんどの方は、まず会社選びから始めますよね。しかし、総務省の統計によると全国には住宅会社は12万社もあり、どの住宅会社が最適なのか見つけ出すのも大変困難です。住宅会社を選ぶ中で最初に行き詰まるのが、ハウスメーカーと工務店のどちらにするのか?という選択です。・どれがハウスメーカーで、どれが工務店?・どちらに選ぶべきなの?・新築住宅は絶対に失敗したくない!ほとんどの方がそう思うはずです。なんと!ハウスメーカーと工務店にはさまざまな違いがあり、建てたい理想の家によって選ぶ住宅会社は変わってきます。新築住宅は一生に一度のとても大きな買い物です。住宅会社を選び間違えて「こんなはずじゃなかった・・・」と後悔する前に、しっかりと情報収集をしてから始めていきましょう!今回は、ハウスメーカーと工務店の違いについてお伝えをしていきます。 ハウスメーカーとはハウスメーカーという言葉に正式な定義はありません。例として、積水ハウス・セキスイハイム・大和ハウス・パナホーム・ヘーベルハウス・ミサワホーム・住友林業・三井ホームが大手住宅メーカー8社と言われております。しかし、大手8社の他にも、一条工務店やタマホームなどの住宅メーカーもハウスメーカーと呼ばれることもあり、どの県に行っても住宅会社があるところがハウスメーカーなのです。つまり・・・ ハウスメーカー=全国展開している住宅会社ということです。 工務店とは工務店もハウスメーカーと同様に言葉に正式な定義はありません。主に地元に根付いている建設業者で、伝統的に工務店と呼んでいる場合が多いです。複数の営業所があっても、建設エリアは県内や市内、近隣の県にとどまるなど、全国規模ではなく地域密着型が工務店です。工務店は、個人やメーカーから建設を請け負って、様々な分野の専門職人を集めて、工事全体を監督します。同じ工務店でも、業務体制に違いがあり、その体制は工務店によって多種多様です。つまり・・・ 工務店=地域密着型の地元に特化した住宅会社ということです。 しかし、一条工務店のように、○○工務店という名前で全国展開をしている住宅会社も増えてきており、線引きは難しいところでもあります。ちなみに当社は、山口県内の新築住宅を請け負う地域密着型なので、工務店となります! 業務体制の違いハウスメーカーは全国規模で展開しているために、新築住宅は規格住宅が多く、家を商品として売っているので、家を選んで買うと考えるとイメージしやすいです。反対に工務店は、多少の規格はありますが、間取りや外観などお客様と一緒に決めて、家をつくっていく形態が多いというイメージです。ここまではハウスメーカーと工務店の違いについてご説明をしてきました。新築住宅を建てられる方で、ハウスメーカーを選ぶべきか、工務店を選ぶべきか迷われるお客様が大変多いです。新築住宅を建てるにあたって、どちらにどのようなメリットがあり、そしてデメリットがあるのかをさらに深堀をしてお伝えしていきます。ハウスメーカーと工務店のメリットとデメリットをまとめてみました!ご家族の理想の新築住宅を建てるのにぜひ参考にしてみてください。 ハウスメーカーのメリットデメリット 【ハウスメーカーのメリット】・住宅会社が全国規模なので、大きくブランド力がある。・モデルハウスなどの展示場やカタログなどで、イメージがしやすい。・資金計画の相談から、引越し・仮住まい探し(賃貸)などにも対応している。・アフターメンテナンスなど、サービスが充実している。・デザイン力が優れている・品質が安定していて、施工もしっかりしている。 【ハウスメーカーのデメリット】・商品ラインナップ、仕様などがあまり自由でないことがあり、金額が割高。・仕様設備にはオプションの追加設定があり、標準設備に追加した方がいいと勧められて、金額が増えることがある。・住宅会社によっては利益第一で、営業担当は歩合制のため強引な営業をされるケースがある。・契約はハウスメーカーをしたけれど、実際に家を建てるのは下請けの工務店の場合が多く、技術の差に心配がある。 【どういう人に向いてるか?】◎経済力に余裕のある方◎仕事や家事が忙しく、時間をあまりかけたくない方◎資金計画の相談から入居後のアフターメンテナンスまで、幅広くサービスを受けたい方 ハウスメーカーもたくさん増えてきました。TVCMでもよくみますね。太陽光発電の設置住宅や、新商品のプランなどにも力を入れているため、最新の商品もあるのも魅力のひとつですね。長所と短所を比べながら決めていきましょう。 工務店のメリットとデメリット 【工務店のメリット】・信頼関係が大切なので、施工、完成、引渡し後もアフターメンテナンスも地場の業者なので早期対応してもられる。・ハウスメーカーと比較するとコストを抑えることができる。・担当者が同一なことが多く信頼関係を築きやすく、コミュニケーションがとりやすい。・こだわりを細かく聞いてもられて、希望がかないやすい。・標準設定がないので、後からオプションで追加がかかることが少ない。・契約時の見積もりがほぼ最終価格になり、金額の交渉もしやすい。・地元の業者なので安心感がある。 【工務店のデメリット】・一般的に会社規模が小さく不安に感じることが多い。・施工図がメインの設計士が多く、デザイン力、内装設備など提案力が弱い。・モデルハウスを建てていないことが多く、イメージがつかみづらい。・住宅ローンなど資金計画に対する、支援体制が弱い。・各建材や水まわりの商品を細かく決めていくので、決めたりするので時間と手間がかかる。・人数が少ないので、プラン、見積もりに時間がかかる場合がある。 【どういう人に向いてるか?】◎明確なイメージがあり、積極的に新築住宅作りを楽しめる人方◎住宅ローンのコストを抑えて、趣味や旅行などを楽しみたい方◎時間に余裕がある方◎大きい家ではなく、住みやすいコンパクな家に住みたい方 工務店での新築住宅は決める方も多く、それを楽しみながら決められる人向きかもしれません。豊かな生活を送るため、納得のいく後悔しないための家づくりができたら良いですね。地元でずっとやっている工務店さんなどは、安心して新築住宅をまかせられるのではないでしょうか? 自分たちの希望をかなえてくれるかも含めて、新築住宅のお話をすすめていきましょう。 それぞれのメリットとデメリットを比較し、あなたの要望を叶えられる方を選んでください。例えば、ブランドに価値を感じる方はハウスメーカーがいいと思います。反対に、ブランドにはまったく興味が無く、安くて良い家を建てたいと思うのであれば工務店です。 家づくりにおいて、会社選びはとても大切です。住宅会社選びを間違えると、どんなにあなたに知識があっても、どんなにあなたがしっかりと計画を立てても、家づくりは失敗してしまうでしょう。この記事を参考にメリットとデメリットをしっかりと把握し、あなたに合った住宅会社を見つけて頂ければ幸いです。 10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会
-

家づくりの流れ【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の下村です。本日は宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅をお考えの方に、「家づくりの流れ」についてお伝えします。今回は、新築住宅を建てる際の「家づくりの流れ」についてお伝えをしていければと思います。 家づくりの流れを知る 「山口で新築住宅を建てたい!」「マイホームが欲しい!」 とお考えの方、いざ新築住宅を建てようと思っても、いつ何をして、どうすればいいのかわからないことだらけですよね。そこで、まずは新築住宅を建てる際の「家づくりの流れ」を知ることが大切です。 以下より、どのタイミングでどのようなことを行うのかについてお話させていただきます。少しでもみなさんの家づくりの参考になると幸いです。 家づくりに必要な3つのSTEP 家づくりに必要なことについて大きく3つのSTEPに分けてお話させていただきます。 STEP1ヒアリング~土地決め 〇お家づくりヒアリング営業担当者が、家づくりについてのご説明、ヒアリングをさせていただきます。みなさんが思い描いている新築住宅、住まいのプランについてのご要望を出来るだけ詳しくお聞きさせていただきます。 まずは、どこに住みたい、どのような暮らしをしたいのかという理想の暮らしについて家族全員で話し合いましょう。 〇概算資金計画現在お支払いされている家賃や、年収に応じて、無理なくローン返済が出来る、住宅・土地の予算の目安をご提案させていただきます。 山口で新築住宅を建てると決めたら、まずは、家づくりに必要なお金のことを考えましょう! 資金計画で大事なポイント☟将来をイメージして「いくらまでなら返せるか」という返済計画を立てること。 借りられる金額ギリギリまで借りると、突然の大きな出費に慌ててしまう可能性があります。 お子さんの誕上や、結婚、進学などこれからの将来のイメージをふくらませ、家計状況の変化に対応できるよう、無理のない返済計画を立てておきましょう。 〇住宅ローン事前審査説明事前審査の必要性や内容、提出時の持参物などをご説明いたします。 住宅ローンを組むためには、金融機関の審査を通過しなければなりません。審査で考慮されている項目としては、完済時年齢、健康状態、担保評価、借入時年齢、勤続年数などがあげられます。 住宅ローンの審査の基準は、銀行によって様々違いがあります。年収や借入金額・返済期間が同じであっても、審査に通る銀行と、通らない銀行もありますのでご注意ください。 〇住宅ローン事前審査申込事前審査申し込みで必要なものとしては以下のものがあげられます。・事前審査申込書・運転免許証・健康保険証・借入残高のわかるもの・源泉徴収票・個人経営の方は3期分の決算書一式 〇土地見極め希望地域で売りに出ている土地をご紹介し、建物を建てるプロとしてアドバイスをさせていただきます。 理想の家づくりには、土地探しが重要となります。しかし、土地探しには難しい面がたくさんあります。土地には2つの面積があること、自由に住宅を建てられない土地がある、土地の契約と建物の契約は別であることなど、様々な法律で定められたルールがあります。難しい部分は、ぜひ相談できるプロの方に相談し、疑問や不安をなくしていきましょう! 〇住宅ローン事前審査 結果ご連絡書類提出後1週間後で結果がでます。結果が出たらご連絡させていただいております。 〇資金計画提示お客様の要望に応じて間取りプランを提案し、それに合わせ、概算金額、資金計画も提示させていただきます。ここで、もう一度、返済計画に無理がないかご確認いただいております。 〇土地 現地確認土地を絞り込み、現地を確認します。 土地周辺に何があるか、日当たりや風通しはいいのか、また、隣地との境界線もしっかりと確認しておき、後で後悔をしないようにしっかりと敷地選びをしましょう。 STEP2色決め~土地決済 〇内・外装の色決め思い描かれている、理想の住まいを実現するお時間です。お好みの色を選んであなただけのお家に仕上げます。 〇Panasonicショールームへカタログを見ながら考えてもなかなか決められませんよね。スタッフがショールームをご案内しながらお風呂やキッチンを決めていきます。実際に見て決めることができるのはうれしいですよね。 〇土地契約土地所有者と不動産屋と日程を合わせ、土地契約をします。土地契約には、手付金と契約印紙代が必要となります。 〇請負契約請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。 見積書・設計図書に基づきご契約を締結させていただきます。お支払い条件としては、以下の通りです。着工時30%上棟時30%完了時40% 〇住宅ローン 融資本申込銀行またはフラットへ融資本申し込みをします。 事前審査は銀行などの金融機関が行い、本審査は信用保証会社が行います。事前審査を無事に通過した場合でも、本審査で落ちてしまう場合もあるので、注意が必要となります。 〇住宅ローン 融資結果ご連絡1週間~10日程で結果が出ます。結果が出た後、ご連絡させていただいております。 〇内・外装の色決め内容確認 〇見積・資本計画書提示詳しい打ち合わせ後の資金計画、見積書の確認をし、変更契約をします。 〇工務引き継ぎ現場担当へ引き継ぎをし、図面やプランボードの最終確認をします。 〇土地決済(土地代金支払い)土地の売主と司法書士の立会いにて、代金の授受と所有権の移転を行います。 当日行うこと ・売主から買主に土地の名義を移転するために必要な書類の確認 ・売主の住宅ローンなどの抵当権がないかどうかの確認 ・買主が利用する住宅ローンの関係の書類確認 ・抵当権設定登記申請) ・買主から売主への土地代金の残りの支払い ・各種料金の支払い 土地決済の日に何をするのか、事前に知っておくと、どの書類にどんなサインをしているのかが明確になります。 〇確認申請提出役所に必要書類を提出し、建築確認を申請します。 〇地盤調査地盤調査をします。結果次第で工程が変わります。 家づくりで難しいことの1つに地盤があげられます。環境のいい場所を求めた場合でも、・不同沈下・液状化・盛土に遭遇してしまうと、建物を使用することは難しくなってしまいます。 地盤に関しては専門性が必要とされますので、一級建築士などの頼れる方に相談した方が安心です。 STEP3着工~引渡し 〇地鎮祭工事中の安全、工事後の家内安全を祈願します。 そもそも地鎮祭とは?地鎮祭とは、新築住宅工事の前に行う神様へのご挨拶の儀式といえます。地鎮祭で土地を利用する許可を得ることによって、崇りを防いで工事の安全を祈ります。建築工事を着工する前に大安の日を選んで、地鎮祭は行われます。ただ神様のために行う行事としてではなく、家づくりを依頼する施主様や施工業者、職人などが一堂に集まる機会ともとらえることができます。人生に何度もできる経験ではないと思われますので、ぜひ家づくりの記念として行われるといいでしょう。 〇着工地盤調査の結果次第で地盤補強工事着工し、その後、基礎工事着工します。 〇上棟(餅まき)建物の棟が上がり、上棟の段階になります。 家を建てる際に、骨組みが出来上がり、最後にその上の棟木を上げることを棟上げと言いますが、その棟上げの際に餅まきを行います。餅まきは、棟上げが行われる上棟式の際に散餅の儀として、厄災を祓うとともに、地域の方々への感謝と、皆さんに福を分けるという意味があると言われております。ここでご近所さんとのつながりを築いておくこともできるので、家づくりの思い出にもなり、いい行事であると思います。 〇社内検査お客様に立ち会っていただく前に社内で入念な検査を行い、キズや不具合を確認しています。 以上のステップにより新築住宅の家づくりが行われております。 今回は「家づくりの流れ」についてお話いたしましたが、新築住宅が完成するまでの流れが少しでも理解できましたでしょうか。 宇部・山陽小野田・防府・山口・周南で新築住宅をお考えの方、家づくりに関してお悩み事などございましたら、お気軽にご相談ください。いえとち本舗ならあなたに丁度いい新築住宅をご提供できます。是非一度ご来店ください。9月14日(土)~9月16日(月)イベント↓アパート脱出大作戦&わくわくイベント同時開催!
-

設計事務所・工務店・ハウスメーカーの違いを比較・会社の選び方解説
注文住宅を建てる会社は設計事務所や工務店、ハウスメーカーなどがあります。各会社の違いについてなんとなくわかっていても具体的なことは知らないという方がほとんどではないでしょうか。そこでこの記事では設計事務所や工務店、ハウスメーカーの特徴や違い、会社の選び方をご紹介していきます。 会社の種類注文住宅を建てる会社は複数あり、大きく分けると下記の会社になります。 設計事務所工務店ハウスメーカー住宅会社選びのポイントは各会社の特徴を押さえて自分の要望に合っている会社を選ぶことです。それでは、設計事務所と工務店、ハウスメーカーの特徴や違いについて解説していきます。 設計事務所の特徴設計事務所は建築士が事務所をかまえ、建物の設計および現場施工管理を行う住宅会社です。設計を主な業務として、お客様の要望を柔軟に応える住宅設計が特徴です。家の施工は工務店や施工業者に依頼し、設計事務所が現場管理をする体制となっています。ハウスメーカーのようにあらかじめプランが用意されていませんので、家が完成するまである程度の期間が必要です。 工務店の特徴工務店は具体的な定義で分けられているわけではありませんが、一般的に地元密着型で営業を行う住宅会社を工務店と呼んでいます。地元密着型というように工務店の特徴は、営業範囲が地域に根差しているため、こまやかで迅速な対応をしてくれる特徴があります。アフターメンテナンスや応急処置など、すぐに現場に迎える体制をとっているため家を建てた後も安心して任せることができます。工務店によって強みとしているところが異なり、品質などばらつきがあります。 ハウスメーカーの特徴ハウスメーカーは営業を全国展開し、自社のサービスを広い範囲で提供する住宅会社です。ハウスメーカーは自社工場による建材の生産や会社独自の施工システムなど、マニュアル化をして安定した品質の注文住宅をお客様に提供しています。豊富な住宅プランから好みのものを選ぶことができる自由設計やプランを土台に設備などの仕様を変更していく企画型と設計方法が各ハウスメーカーによって違います。 設計事務所・工務店・ハウスメーカーの違い設計事務所・工務店・ハウスメーカーの特徴を押さえつつ、次は各住宅会社の違いをご紹介していきます。家を建てる上で重要な「費用の違い」と「設計の違い」「施工の違い」を比較していきましょう。 費用の違い【設計事務所】設計事務所は自由設計の特徴から、予算に応じた設計が可能です。ハウスメーカーや工務店とは違って建築コストの基準が決められていません。1,000万円以内で家を建てたいという希望がある場合、ハウスメーカーや工務店だと選択できる会社が限られてきます。しかし、設計事務所はお客様の希望する予算内に納まるように提案をしてくれるため、予算調整しながら家を建てることができます。ただし、施工は工務店などに依頼するため設計費と施工費は明確に分けられており、設計料だけ見ると工務店やハウスメーカーよりも高く感じるかもしれません。【工務店】工務店の会社体制はハウスメーカと似ていますが、決定的に違うのは人件費や広告費の違いです。ハウスメーカーほど経費を掛けていないため費用は抑えられる傾向にあります。工務店によって大工など職人を抱える自社施工であるか、外注業者に依頼して施工を行うかによって費用の違いはでてきます。【ハウスメーカー】ハウスメーカーは坪単価など注文住宅の販売価格がある程度定められています。多少の値引きは期待できますが、予算の範囲内で建ててくれるハウスメーカーを選ばなければなりませんので、家の費用の幅はあまり融通が効きません。ハウスメーカーの建てる家は土台となる住宅モデルを複数用意しており、価格設定も決められています。このことから予算に合わせた商品選択が決めやすく、建てられていく家のイメージもわかりやすい特徴があります。 設計の違い【設計事務所】設計の自由度は工務店やハウスメーカーと比べて圧倒的に広いのが特徴です。基本的にできない設計はありません。工務店やハウスメーカーの場合、採用している構造に合わせて会社を選ぶ必要がありますが、設計事務所は木造や鉄筋コンクリート、鉄骨造など選択可能です。デザイン性の高い家を建てることができるのも設計事務所の強みで、住む人が魅力を感じる空間を提案してくれます。【工務店】 設計は社内にいる設計士が設計する場合と外注による設計を委託する場合とで分けられます。フランチャイズ制をとる工務店は構造などが既に決められていることもあります。前述したように工務店の強みは各会社によって異なるため、どこに力を入れているかによって建てる家が変わってきます。自然素材を重視していたり、耐震性など強度を重視していたりと、工務店の強みが異なるため、自分の要望が工務店の強みと合っていることが大切です。【ハウスメーカー】ハウスメーカーは会社に所属する設計士がプランを立てて、営業マンが打ち合わせを行う体制をとっています。設計はあらかじめプランを数種類用意して、選択したプランから好みに合わせて設計変更できます。設計変更の自由度は各ハウスメーカーによって異なり、完全自由設計を採用する場合と部分的な変更ができる企画型があります。すでに土台となるプランがあるため、打ち合わせ時間が短縮できるメリットがあります。 施工の違い【設計事務所】設計事務所の施工は工務店や施工店などに委託する体制をとっています。設計事務所が家そのものをつくるのではありませんが、現場施工管理を行って第三者の立場で図面通りの施工がされているかチェックしてくれます。設計事務所と施工店が別々の立場にあるため、手抜き工事などを抑止する効果があります。【工務店】工務店は自社施工をとる会社と施工を委託する会社で分かれます。また、施工をマニュアル化している場合としていない場合もあるため、工務店によってばらつきがあります。品質を確認するためにも現場見学会に参加してどんな工事をしているか見ておくことが重要です。【ハウスメーカー】ハウスメーカーは提携する施工店に施工を委託し、ハウスメーカーが現場管理をする体制が一般的です。外壁や床組みなど自社内工場で大枠をつくり、残りは現場で組み立てる仕組みをとっているハウスメーカーもあります。施工のマニュアル化や自社内工場の生産により品質のばらつきが少なく安定した住宅施工を提供してくれます。 まとめ各会社で特徴が異なるため、どの会社が最適かというとどんな家を建てたいかで決まります。会社選びで大切なことは、自分の希望に応えてくれる会社を選ぶことです。そのためにも、まずはどんな家を建てたいかイメージをつくることが大事になります。家のイメージをつくっていくにはたくさんの情報も必要ですので、住宅会社の資料を請求してみるのもいいでしょう。いえとち本舗は無料で家づくりの資料をご提供していますので、もし良ければご参考ください。資料請求はこちらのページからご覧にいただけます。









