ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
坪単価とは?新築・注文住宅を考える人が把握すべきこと

住宅を購入するときには、ほぼかならず「坪単価」という言葉が目に入ります。
坪単価は、住宅購入においてはとても重要な数字です。
これを理解せずして、理想的な住まいは手に入れられません。
とはいえ、「坪単価」は少々専門的な概念です。
住宅購入の段階に至るまで、坪単価をなんて知らなかった人も多いでしょう。
だからこそ住宅を建てる上で、坪単価に関する疑問は次々と出てくるものです。
今回では、坪単価の基本や相場について解説します。
本記事を読めば、坪単価に関する疑問はほとんど解消されるでしょう。
また坪単価に関する正しい向き合い方やポイントについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
坪単価の基本

まずは、坪単価の基本的な定義からおさらいしましょう。
坪単価は、「一坪あたりにかかる建築費」のことを指し示すものです。
ちなみに一坪は、およそ3.3㎡に相当します。
3.3㎡というと、だいたい畳2枚分ですね。
坪単価は、
<住宅本体価格÷述床面積>
というシンプルな計算式で割り出されます。
たとえば、本体価格2,000万円、述床面積50坪の物件があったとしましょう。
となると、2,000万÷50坪という計算なので、坪単価は40万円となるわけです。
坪単価の計算で注意しなければいけないのが、「延床面積」について、全国共通な規格が存在しないこと。
つまり住宅メーカーそれぞれで、延床面積の定義は異なり、同時に坪単価も異なってくるわけです。
要するに坪単価の概念を参考しつつ、住宅メーカーを観察する、選ぶことも重要となります。
ちなみに坪単価は、別途工事費や地盤改良費などは、(あくまで一般的な中では)反映されていないケースが大半です。
あくまでも、本来的には建物そのものの価格を坪数で割った数字でしかない点には注意しましょう。
大手メーカーの坪単価は?
全国的に名前が知られている大手メーカーの坪単価は、おおむね80万円から90万円程度とされています。
少なくともTVCMなどで見かけるメーカーは、こういった坪単価が相場であると考えて問題ありません。
高ければ、坪単価100万円近を超えているケースもあります。
こういった場合では、特に内装の設備がきわめて充実しているケースが大半です。
大手メーカーの場合は、人件費や維持管理費、あるいは広告費が多分にかけられています。
CM広告や展示場展開など、大手メーカーの商業活動にはお金がかかるわけですね。
また大手メーカーは日々の技術開発、研究にも、多額の予算を投じています。
よって大手メーカーの場合は、そうでないメーカーと比較すれば、坪単価はやや割高な傾向です。
ローコストなメーカーにおける坪単価相場
ローコストなメーカーからは、相当に低価格な住宅が流通しており、坪単価は安くおさえらる傾向です。
この場合、坪単価相場は30万円から60万円程度になると考えておきましょう。
ただし室内設備のグレードは、大手メーカー比較すると少し劣る部分があります。
住宅工務店の坪単価は高い?
住宅工務店の場合、坪単価の相場は50万円から60万円程度とされています。
ただし住宅工務店の坪単価は、会社や地域性の影響を受けやすく、変動しやすい部分もあります。
ちなみに住宅工務店のメリットは、地域に密着している傾向が強いところ。
建築中の情報共有や、建築してからのアフターフォローなどにおいて、同地域内であることを活かしたきめ細かい対応が期待できます。
坪単価を抑える方法

やはり住宅を建てる中では、できるだけ費用はおさえなければいけません。
もちろん、坪単価についても例外ではなく、できるだけ低くしておく必要があります。
下記では、坪単価をおさえる方法について解説しているので、参考にしてください。
1階と2階の床面積を同一に近づける
まず、1階と2階の床面積できるだけ同一に近づける方法が考えられます。
1階と2階の床面積が同一であれば、建物そのものには凹凸が付きづらくなるはずです。
つまり、複雑な構造ではなく正方形や長方形に近いほうが、坪単価は安くなります。
”切り妻”よりも”片流れ”
住宅の屋根は、
-
左右両方に傾斜している”切り妻”
-
左右一方にだけ傾斜している”片流れ”
の2種類に大別されます。
うち、片流れのほうが屋根面積が小さくなるので、坪単価は少しだけおさえることが可能です。
複数のメーカーに対して見積もりを取る
もちろん、複数のメーカーに対して見積もりを取ることも重要です。
なぜなら複数のメーカーから出された見積もりがないと、坪単価の高い安いが判断できないから。
しかし複数の見積書があれば、坪単価をわかりやすく比較できます。
比較することを忘れていると、建ててから「坪単価が高すぎた」と後悔するかもしれません。
必ず、複数メーカーから見積もりを出してもらいましょう。
坪単価をみるときのポイントは

続いて、坪単価を見るときのポイントについて解説します。
やはり坪単価は少し専門的なもので、初めて家を建てる人にはピンとこない部分も多いはずです。
下記のポイントは理解したうえで、坪単価を参照するようにしましょう。
坪単価に反映されているもの、そうではないものを確認する
先ほども触れましたが、坪単価には全国共通の定義は存在しません。
だからこそ、坪単価には何が反映されているのか、きちんと確認することが重要です。
基本的には坪単価は、建物価格しか含まれていないと考えましょう。
つまり、
-
手数料
-
外構工事費
-
地盤改良費
-
調査費
といった費用については、坪単価に関係しておらず、後々で別途必要となることが大半です。
特にメーカーは、「できるだけ値段を安く見せたい」といった理由で、こういった費用はほとんど外したりします。
よって、坪単価には何が反映されているのか、きちんと確認しておかなければいけません。
間違っても、坪単価だけがすべての費用であるとは考えないようにしましょう。
施工床面積と延床面積は、同じではないことを知る
よく勘違いされることですが、先ほども触れた延床面積は、「施工床面積」とは同一ではありません。
しかし一部メーカーは、坪単価について施工床面積を基準として計算したりします。
延床面積は、ベランダや玄関ポーチなどが含まれていません。
しかし、施工床面積には組み込まれています。
つまり施工床面積を基準として算出すると、あたかも坪単価が安く見えてしまうわけです。
よって、坪単価が何を面積として計算しているのか、逐一確認する必要があります。
まとめ
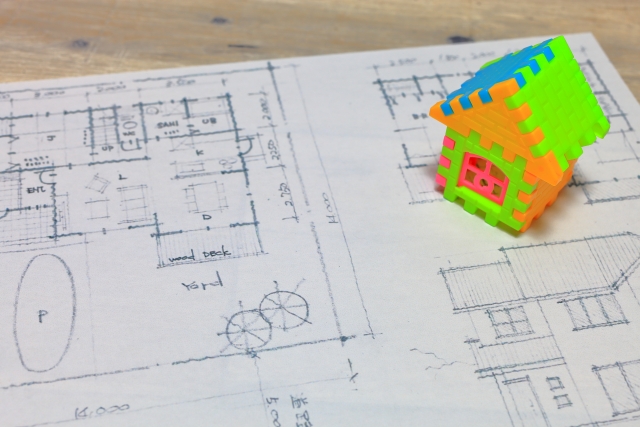
普段はかかわることのない坪単価は、初めて見る人には少し難しいことのように感じるかもしれません。
しかし実際のところは簡単な割り算で求められるもので、決して難しいものではないのです。
ただし、坪単価の概念と同時に、相場についてもよく知っておきましょう。
その相場を知ったうえで、提示されている坪単価が適切なものなのか、きちんと判断する必要があります。
いえとち本舗では、上記のような坪単価をはじめ、住まいや家づくりで知っておくべき知識について紹介しています。
今後、坪単価のようにちょっと難しい問題が出てきても、いえとち本舗なら疑問を解決できるはずです。
ぜひ一度、資料請求、および会員登録をしてみてください。
関連記事
-

夫に新築住宅へ興味をもってもらうコツ
新築住宅に興味を示さない夫は、決して少なくありません。 そういうタイプの夫は、「雨風さえしのげればなんでもいい」「家にお金をかけたくない」というような考えを持っており、新築住宅には興味を示しません。それに対して、妻が「いや、将来どうするのよ!」と感じているのは、珍しいことではないはずです。 そして本記事を読んでいる人の多くは、今まさに、「夫が新築住宅に興味を示してくれない」「どうしたら興味を持ってくれるのだろう?」 と考えているでしょう。本記事では、かつて心理カウンセラーとして働いていた筆者が、「夫に新築住宅への興味を持ってもらうコツ」について解説します。 本記事を参考にすれば、夫の新築住宅への興味関心を高められるはずです。むしろ、積極的に新築住宅を建てたいと考えるようになるかもしれません。新築住宅を建てることのメリットについて伝えるもっともオーソドックスなのは、新築住宅のメリットを伝えるということです。「家を立てたい! 新築が欲しい!」と感情をあらわにするよりも、よりよい効果が期待できます。新築住宅があれば、 「子供によい環境が与えられる」「もっと広いお風呂に入れる」「さらに美味しい料理が作れる」 というように伝えましょう。メリットを実感してもらえれば、少しずつ興味は湧いてくるはずです。データを用いるまた、データを用いて論理的に説明するのもよい方法でしょう。なぜなら男性という生き物は、「データ」というものに弱いからです。 よく「女性は感情、男性は論理の生き物」というようなことが言われます。この言葉はつまり、「ものごとを判断するとき、感情と論理、どちらを重視するか」ということです。 もしも夫が新築住宅に興味を持っていないなら、建てるべきだと判断するだけのデータを知らないのです。しかし建てるべき理由をデータで示せば、夫にも興味が湧いてくるはず。 たとえば、「新築住宅を建てた場合、将来的には○○円得をする」「現状は金利が下がっており、今のうちにローンを組めば○%得をする」というような形です。 客観的なデータを示して、「なるほど、それは合理的だ」と思ってもらいましょう。より深く納得してもらえ、積極的に新築住宅の話し合いへ参加してくれるようになるかもしれません。危機感を持たせる危機感を持たせるという方法も、かなり役立ちます。具体的には、「新築住宅を持っていないことは、危機的なことである」と思わせるわけです。 「周りはみんな新築住宅を建てている」ということを意識させるようなコメントを、日常で残していきます。すると夫からしてみれば、「新築住宅を持っていないのは、ウチだけか!?」と思うわけです。 というように「周囲と同じではないことに違和感が湧く現象」は、「認知的不協和」と呼ばれます。認知的不協和が起こると、違和感を取り除くための行動へ移ります。今回の場合は、「新築住宅を建てる」ということですね。 心配性、弱気、寂しがりやな夫ほど、認知的不協和を用いたテクニックは有効です。うまく活用しましょう。建てる建てないではなく、どんな家を建てるかまた、「どんな家を建てるか」という部分に焦点を当てるのもよい方法です。 「新築住宅を建てたいんだけど、あなたはどう思う?」と、尋ねた場合を考えましょう。だとすると話の焦点は、「新築住宅を建てるのと建てないのでは、どちらがよいか」というところにあります。 夫も「どちらが合理的か」ことを考えて、建てるか建てないか答えるはずです。そして今現在、興味を持っていない以上、「建てるべきではないな」という趣旨の回答が返ってくるでしょう。 しかし「どんな家を建てたい? おしゃれな家? それとも暮らしやすい家?」と聞いたとしましょう。だとすると話の焦点は、「おしゃれな家を建てるか、それとも暮らしやすい家にするか」というところになります。 つまり、本来あるはずの「家を建てるか建てないか」という選択を飛ばして、「どんな家を建てるか」という部分について考えるようになるというわけです。このように本来あるべき選択を飛ばして、一歩先のことについて考えさせることは、「誤前提暗示」と呼ばれます。誤前提暗示は、心理学的にも効果が高いと立証されているテクニック。うまく活用しましょう。恥ずかしくても褒めてあげるとはいえ、感情に訴えかける方法が役に立たないというわけではありません。少し恥ずかしいかもしれませんが、褒めてあげる、つまり自尊心を刺激するのも効果的です。 人間は、 自尊心をくすぐられると、相手の意見を尊重して行動するしかし、強制されると反発する という特性を持っています。これを「民間人の原理」といいます。 つまり「早く新築住宅を建てよう!」と言い続けるのは「強制」であり、反発されるというわけです。原理にしたがって、 あなたを頼りにしている今の暮らしがあるのはあなたのおかげあなたなら、もっと素敵な家を作れる というように褒めて、自尊心を刺激してあげましょう。ものすごく簡単に言うと、日常から夫を立ててあげるということですね。いざ新築住宅の話を進めるとき、意見が受け入れられやすくなります。ロマンを叶えられると思わせるまた、「新築住宅を建てれば、ロマンが叶う」ということを押すのもよいでしょう。たいていの男性は、多かれ少なかれ、「ロマン」のようなものを持っています。それを意識させられれば、「新築住宅っていいな」と思ってくれるかもしれません。 何にロマンを感じるかは、人それぞれです。夫に合ったロマンを刺激してあげましょう。たとえば、 本が好き→自分だけの書斎を持てるバイクが好き→ピットガレージでバイクをいじれる洋服が好き→ウォークインクローゼットでコレクションを並べられるフィギュアが好き→ショーケースをいくつも並べて、美しく並べられる というような形です。男はこの手のロマンに対して、かなり強い魅力を感じます。ぜひ夫のロマンを刺激し、新築住宅へのモチベーションを高めてあげましょう。まとめ夫が新築住宅に興味がない状態は、たいへんフラストレーションのたまる状態です。「いい加減、新築住宅建てようよ!」と感情的になるのは、ある意味で自然なことでしょう。 しかし感情的なままでは、なかなか話は進まないでしょう。感情論に対して夫が折れてくれたとしても、そこから満足できる新築住宅を建てるのは、難しい部分もあります。 いったん冷静になり、論理や話術を使って、少しずつ誘導していきましょう。すぐに「よし、じゃあ新築住宅を建てよう!」とはならないでしょうが、時間をかければ着実に心境は変化していきます。 また、夫が乗り気な状態で新築住宅の話を進めていけば、より理想的なマイホームが建てられるようになるはずです。ぜひ、参考にしてください。 いえとち本舗では、夫婦、子供ともに安心して過ごせる住宅を低価格で提供しています。新築住宅の建築を考えている方は、ぜひ一度、資料をご覧ください。資料請求はこちら また会員サイトでは、不動産や土地に関する、重要な情報を発信しています。こちらもあわせてご覧ください。会員登録はこちら
-

快適に過ごせる、バリアフリー住宅【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・防府・山陽小野田】
みなさんこんにちは!いえとち本舗山口中央店です♪ 山口・防府・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅の購入をご検討中のみなさま、お家のバリアフリーについて、お考えになったことはありますか? 最近では、公共施設等も、バリアフリー化が進んでおり、スロープ手すり、多目的トイレなど、車いすの方や障がいのある方だけでなく、妊婦さんや子連れなど、様々な方が利用しやすい施設が増えてきていますね(o^―^o) しかし、家を購入するとなると、どのくらいバリアフリー化ができるのか、費用面はどのくらいかかるのか等の不安を感じている方も多いのではないでしょうか? そのようなお悩みがある方に向け、今回の投稿では「快適に過ごせる、バリアフリー住宅」についてお伝えします! <そもそも、バリアフリー(住宅)とは?>バリアフリーという言葉を聞くと、高齢者や障がい者だけのことだと捉えられがちですが、バリアフリー住宅とは、小さな子どもから高齢者までが快適に安心・安全に過ごせる住まいのことを指します! もしも、突然のケガや病気になってしまった時、普段なら軽々に通ることができた家の中の段差でも躓いてしまい、さらに大けがをしてしまう危険性が出てきてしまいます。 しかし、バリアフリー住宅は一般的な住宅に比べ、段差等の危険因子となるものが少ないため、より暮らしやすい住宅にもなります!(^^)! <なぜ、バリアフリーがいいのか>これは、バリアフリー住宅に限らず、一般的な新築住宅を決める際にも同じことが言えちゃうのですが… バリアフリーは、人によって必要とされる部分がかなり異なってきます。例えば、座って作業することはできるが足腰が悪いため、立って移動することが難しい方や、病気によって手が震えてしまうけれど歩行はスムーズな方など、一人ひとりでニーズが異なってしまうことや、変容してきてしまこともあるんですね…(*_*;このように、直近の未来のことも大切ですが、先々の将来を考えたバリアフリー住宅をオススメします! 例えば、足腰が悪くなり歩行が難しくなってしまった場合、手すりを付けるだけでなく、車いすで移動できるよう玄関にスロープが置けるスペースを作ることや、外溝から玄関までのスロープを作っておくなど、何か起きても対応できる住まいづくりをすることはとても大切です♬ <さいごに>新築住宅を購入するとなると、その直後の住まいのことを考えるだけでなく将来性を考えることや、老後の住宅ローンのことだけでなく、老後も過ごしやすい住まいを作ることを意識して、新築住宅を選ぶことをオススメします( *´艸`) 山口・防府・宇部・山陽小野田・周南で新築の購入をご検討中のみなさまへいえとち本舗山口中央店・宇部店では、新築住宅を選ぶポイントや、買う時に気を付けることなど、お家に関する相談会等のイベントも実施しております♪ 住まいに関して、気になる事がございましたら、ぜひお問い合わせください(^◇^) 12月14日(土)~12月22日(日)開催イベント↓【山口市下市町】リビング21.3帖平屋3LDK完成見学会
-

子どもが安心できる家【いえとち本舗の新築・山口・防府・宇部・周南・山陽小野田】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の永井です。本日は山陽小野田・防府・宇部・山口・周南で新築住宅をお考えの方に、「子どもが安心できる家」についてお伝えします。今から、山口・防府・周南・山陽小野田・宇部で新築住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。宇部・山口・周南・山陽小野田・防府で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。周南・防府・山陽小野田・宇部・山口で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。周南・山口・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅を考えるきっかけの一つに、「子どもが生まれたから」というのがあります。 子どもが生まれると、生活リズムやお家の中・精神状態までもがガラッと変わってきます。特に小さいお子様がいらっしゃるご家庭では、賃貸アパートでの暮らしに苦労されているのではないでしょうか?なので本日は、「子どもが安心して暮らせる家」をテーマにしていきたいと思います。 「子どもが安心して生活できる家」とは?具体的に、「子どもが安心して過ごせる家」とはどんなものでしょうか?「子どもが安心できる環境」=「大人が安心して、子どもを育てられる環境」と考えられます。子どもの目線に立ってみると、普段の生活の中にも実は危険がいっぱいです。特にわんぱく盛りの小さなお子様がおられる方は些細な行動でもヒヤヒヤされることが多いのではないでしょうか?「安心して暮らす」ということは意外にも難しいものです。しかし「安心して暮らすためのポイント」を押さえておくことで未然にお家での事故・トラブルを防ぐ事ができ、安心して暮らす事ができます。以下では「安心して過ごせるお家~キッチン編~」についてお伝えします。 安心して料理のできるキッチンキッチンは水や電気を多く消費するスペースであり危険が沢山潜んでいます。特に小さいお子様がいらっしゃるご家庭では集中して料理をすることは難しくなってきます。赤ちゃんならば泣いたらすぐミルクをあげ、オムツを変えてあげなければなりません。少し大きくなって一人遊びをするようになっても、急にキッチンに入ってきたり目を離したすきに危険なことをしていないか心配になりますよね。そこで、山口・防府・宇部・周南・山陽小野田で新築を考えられている子育て世代の方にオススメのキッチンは、「対面式キッチン」です。 対面式キッチンって?対面式キッチンとは、リビングやダイニングに対面する形で設置されたキッチンの事です。家族や来客と話をしながら料理をしたり片付けができ、開放的な空間を演出してくれるため人気です。なので、リビング・ダイニングの様子を見ながら料理や片付けをする事ができます。キッチンから見える場所にお子様の遊びスペースを設けることで、お子様の様子を見ながら料理が出来るのでとても安心ですね。しかし、一般的な対面キッチンのマイナスイメージとして「収納スペースが少ない」ということが挙げられるかと思います。そこで私たちいえとち本舗では、キッチンを対面式キッチンに変更することが可能になっております。住宅機器は全てPanasonicをご提供させていただいています。Panasonicのキッチンは機能性に優れており、収納スペースも広~く確保されています。対面キッチンにプラン変更をした際も多くの収納スペースがありますのでキッチンをすっきりと見せる事ができ、開放的で魅力的な空間を作り出す事ができます。お子様の安全を見守りつつも効率の良い料理が出来る「対面式キッチン」は、子育て世代の方々以外にも開放的な空間を好まれる方にオススメしております。対面式のキッチンの入り口の部分にゲートなどを付ければ簡単にお子様の侵入を防ぐことが出来るので、集中して作業をする事ができますので安心ですね。散らかったおもちゃなどを急な来客時にサッと隠せるような仕切り等についていると尚更便利だと思います。また、シンクのカラーやキッチン空間を自分らしくコーディネートする事ができます。様々な種類の色からお選びいただけます。オプションでキッチンの天板を人工大理石にプラン変更することもできます。自分の好きな色や形に囲まれながら料理をするって、とても楽しいですよね。生活の質がグッと上がると思われます。お子様の安全を確保しながら、ご自身も過ごしやすい環境をご提供できれば感無量でございます。続きまして、キッチンの次は寝室の話をしたいと思います。 子どもが安心して過ごせる家~寝室編~日本では昔から、子どもがある程度大きくなるまで両親と一緒のベットや布団で寝るといった習慣があります。寝る瞬間まで家族とのコミュニケーションを深めることで家族の絆も深まるのではないでしょうか。お子様が寝るまで、そばで見守る事ができたら安心して寝る事ができますよね。なので、山口・宇部・周南・山陽小野田・防府で新築住宅を検討される時は、主寝室を広めにとっておくことをオススメ致します。ベット派の夫婦様だけならダブルベットでも十分かもしれませんが、お子様がある程度大きくなられるまで一緒に寝るとなればもっと大きめのベットに変えるかシングルベットをくっつけないと狭くなってしまいますよね。そうなれば少なくとも7帖以上は必要になってきます。お子様が2人以上おられるとなれば、もっと広い部屋が求められてきます。主寝室のシュミレーション家が完成してからいざ主寝室を見てみると意外と小さかった、、、なんてことがあると悲しいですよね。それを防ぐためにあらかじめベットや布団の寸法を測っておき、主寝室でのシュミレーションを行うことが大切だと思います。お子様が1人であれば布団の敷き方等で工夫すれば6帖でも親子3人で並んで十分に寝ることが可能です。寸法だけをチェックするのではなく、ベットや布団の置き方や向きをシュミレーションすることも必要になってきます。実際の寝室のイメージがつきやすいのはやはりモデルハウスです。出来るだけ正確にイメージができるようにするために、様々な場所のモデルハウスを見学されてみてはいかがでしょうか? イエテラスの新築モデルハウスについてはこの記事の一番下にURLを張り付けております♪続きまして、「住宅と寿命は密接に関係している」という話をしていきます。 住宅が寿命と密接に関係しているワケ幸せな暮らしに一番大切なものは、家族みんなが健康であることだといえとち本舗は考えます。しかしながら住む家の性能の違いで病気や死亡リスクが大きく変わってきます。 住宅における健康被害リスクとは??住宅における健康被害はアレルギーや急な温度差による事故死などが挙げられます。アレルギーの原因の約80%はダニです。外気と内気の温度差により結露が発生するとダニやカビの発生現場になります。また、冷えは人の免疫力を下げ、様々な症状を引き起こします。そのため、結露を防ぐことは健康を守り、家の長寿命化につながることになります。免疫力が低い子どもにとってはアレルギーは命とりです。すなわち、アレルギーの原因を防ぐことは子どもの命を守ることに直結しています。また、寒くなればなるほどヒートショックになる可能性が高まります。2011年の交通事故死亡者にくらべ、入浴中の死亡者はなんと3.7倍という結果が出ています。室内だからと安心せずに出来るだけ温度差をなくすことが室内での事故死から身を守る最大の予防策です。いえとち本舗がご提供させていただいているイエテラスでは、健康被害リスクを最小限にするための高断熱・高気密を標準装備をしています!なので寒い日でも低めの温度でも暖かく快適な空間が生まれます。お子様だけでなく、高齢の方の命を守るためにも健康被害リスクを最小限にする必要があります。起こってはいけない被害が起こる前に、一度イエテラスのモデルハウスで高断熱・高気密を体感されてみてはいかがでしょうか??7月13日~16日、19日は夏祭!家祭り開催!【山口・防府・宇部・山陽小野田・周南】で【月3万円から高性能なスマートハウス イエテラスの新築】









