ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
これからの住宅取得にコロナウイルスが与える影響とは?

新型コロナという未曾有なことが発生し、働き方などさまざまな場面で社会の変化が起きています。
リモートワークやソーシャルディスタンスなど、これまでとは違う生活になりつつある中、住宅も同じように変化し、ハウスメーカーなども安心してお客様が家づくりできるような対策がされています。
今回の記事ではこれからの住宅取得にあたり、コロナウイルスが与える影響についてお伝えしていきます。
コロナウイルスで新築住宅事情はどう変わるのか

コロナの影響により働き方などさまざまな面で社会が変化しています。
住宅会社もコロナの流れが影響して家づくりにも変化があり、今までなかった間取りが採用されています。
コロナウイルスの影響で家の間取りに変化

会社勤めの方はコロナウイルスが流行したことにより、リモートワークなど働き方の変化に対応しなければいけなくなりました。
コロナの感染を防ぐために通勤を減らし、自宅で仕事ができるリモートワークへと変遷していきましたが、実際のところは問題も多かったようです。
リモートワークになることにより通勤する手間は省けますが、現在の住宅では自宅で仕事を行うことが考えられていなく、仕事する環境が整っていませんでした。
今回のコロナウイルスの影響により、自宅で仕事をするということに関心が寄せられ、リモートワークに対応できる住宅づくりがでてきています。
コロナウイルスの影響によって関心が寄せられる衛生的な家づくり

コロナの流行によって現在はより衛生面に気を配る時代となりました。
マスクの着用や手洗い、うがいなど多くの方が心がけています。
コロナ感染の心配の一つに家族内感染が囁かれています。
現在の家は帰宅後すぐに手洗いやうがいなどをできる間取りにはなっていません。
玄関から廊下を通り洗面所へアクセスする動線となっているため、接触感染などのリスクはどうしても拭うことができていません。
そこで玄関に手洗器を設けて、帰宅後他の部屋にアクセスすることなく手洗いやうがいができる間取りが注目されています。
また、玄関にコートなど外出時に着用した服を収納するスペースを設けることで、さらに衛生面に気を配った間取りづくりが考えられています。
住宅会社はコロナウイルスの感染対策をして安心できる家づくりを実施

コロナウイルス感染対策のために、住宅会社はお客様が安心して家づくりができるようにしています。
ここでは、住宅会社がとっているサービスや対応についてお伝えします。
オンライン見学会やVR動画内覧会などを実施

外出の自粛やソーシャルディスタンスなど人との距離を気にかけなければいけない中で、住宅会社はお客様が不便のない家づくりができるようにいろいろな対策をしています。
お客様が自宅にいながらでも物件を内覧できる「オンライン見学会」はスタッフの方が現場に赴き、中継してくれるサービスです。
その他にもVR動画によるバーチャル動画をお客様に提供するなど新しい営業活動もされています。
オンラインで打ち合わせや相談に対応

家づくりは打ち合わせを積み重ねてようやく完成していきます。
大事な家だからこそ手抜きはできません。
しかし、コロナウイルスの感染もやはり心配なところ。
この時期は家づくりを諦めなければいけないのかと感じるかもしれませんが、住宅会社はこの状況で理想的な家づくりができるようにオンラインで対応するなど対策をしております。
対面して行う打ち合わせをオンラインにすることでお客様は自宅にいながらも、これから建てる家の話を進めることができます。
また、対面する回数を減らすためオンライン上で契約できるクラウドサインを採用している会社もあります。
注文住宅の打ち合わせだけでなく、新規のご相談もオンラインで対応していますので、コロ ナウイルスの感染を心配せずに安心して家づくりの計画を立てることができます。
ただし、土地を持っていない方の場合は対面で重要事項説明が必要になりますので、この時は店舗まで来店が必要になります。
三密を避ける・換気・消毒・マスク着用・健康管理の対策
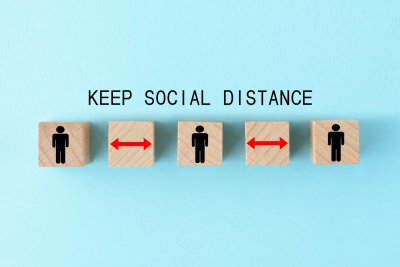
住宅展示場はお客様が安心して見学できるようにコロナウイルス感染対策を実施しています。
感染予防のために出展メーカー統一のガイドラインを設けていたり、ドアを解放して換気をとったりしています。
また、手に触れる場所は随時除菌消毒をし、スタッフの方もマスクを着用して対応するのが基本となっています。
ただし、住宅展示場によって対策が異なる場合もありますので、住宅展示場へ見学に行く時はコロナウイルス感染予防対策がちゃんとされているか事前に確認してから行くようにしましょう。
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置

コロナウイルスの感染症およびまん延防止のための特例措置が取られています。
コロナウイルスの影響により入居期限(令和2年12月31日)が遅れた場合は要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
【住宅ローン減税の特例措置適用条件】
1:一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合:令和2年11月末
・増改築等をする場合:令和2年11月末
2:新型コロナウイルス感染症およびまん延防止の影響により入居が遅れたこと
住宅ローン減税の特例措置は上記両方の要件満たしていることが必要です。
また、契約時期の確認や入居が遅れたことを証明する書類なども必要になりますので、詳しくは国道交通省の「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」をご覧ください。
国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅取得支援策について」
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは住宅取得のためのローンの金利負担の軽減を図る制度です。毎年末のローン残高または住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間にわたり所得税から控除される仕組みとなっています。(所得税から控除しきれない場合は住民税から一部控除)
消費税率10%が適用される住宅を取得した場合は、入居から(令和元年10月1日から令和2年12月31日まで)3年間控除期間が延長されます。
まとめ
住宅会社はコロナの影響を考え、家づくりを楽しみにしているお客様が安心して家が建てられるように、いろいろな対策を立てています。本来対面する必要があった打ち合わせや相談もオンラインにすることで改善することができています。
また、家の間取りも変化し、 変わっていく生活スタイルに合わせた設計をしています。
ステイホームと叫ばれながらも、家づくりでできることはたくさんあります。
通常家が建つまで半年から一年はかかります。
このタイミングを機に住宅会社の情報を集めたり、資料請求をしてみたりするのはどうでしょうか。
いえとち本舗は無料で資料を提供しておりますので、ぜひご利用いただければと思います。
資料請求の申し込みはこちらのページになります。
関連記事
-

お家を建て替える前に知っておきたい7つのこと
この記事では、建て替えを検討している方に向けて、費用や手続き、補助金、注意点まで、知っておきたいポイントを7つに整理して解説します。 1. 建て替えとは?1-1. 建て替えの定義とリフォームとの違い1-2. 建て替えが選ばれる代表的なケース1-3. 建て替えのタイミングを判断する基準2. 建て替えにかかる費用と内訳2-1. 建物解体費用の相場と注意点2-2. 建築費用の内訳(本体工事・付帯工事)2-3. 仮住まい・引っ越しなどの諸費用2-4. 見積もりの比較とコスト削減のコツ3. 建て替えの流れと必要な手続き3-1. 建て替えのスケジュール全体像3-2. 必要な手続きと書類の準備3-3. 解体から着工までの段取り3-4. 建て替えに関する近隣への配慮4. 建て替えにおける土地条件と制限4-1. 建築基準法における制限事項4-2. 再建築不可の土地と接道義務4-3. 容積率・建ぺい率・斜線制限の影響4-4. 境界トラブルと測量の重要性5. 建て替えに関する補助金・優遇制度5-1. 建て替えで利用できる補助金の種類5-2. 住宅ローン控除とその他の減税制度5-3. 省エネ・耐震性能向上による支援策5-4. 補助制度を活用する際の注意点6. 建て替えのメリットとデメリット6-1. 建て替えの主なメリット(最新設備、間取り自由など)6-2. 建て替えの主なデメリット(費用、手続き、期間)6-3. 建て替えとリフォームの比較検討6-4. ライフステージと建て替えの相性7. 建て替えを成功させるためのポイント7-1. 信頼できる業者選びのポイント7-2. プランニング段階での工夫と将来性7-3. 資金計画と無理のない予算設定7-4. 家族の希望を反映させるコミュニケーション 1. 建て替えとは? 1-1. 建て替えの定義とリフォームとの違い建て替えとは、既存の住宅をすべて解体し、新たにゼロから住宅を建築することを指します。対してリフォームは、建物の骨組みや構造を残したまま、内装や設備の修繕・改修を行うものです。たとえば、キッチンや浴室の交換、壁紙の張り替えなどがリフォームに該当します。建て替えは建物の寿命を迎えた場合や構造上の不安がある場合に選ばれることが多く、最新の耐震基準や省エネ基準を満たした住宅に一新することができます。自由な設計や最新設備の導入が可能で、暮らしの質を大きく向上させる手段でもあります。 1-2. 建て替えが選ばれる代表的なケース建て替えが選ばれる主なケースは、建物の老朽化が進行している場合です。たとえば、築30年以上が経過し、雨漏りやひび割れ、床の傾きなどが見られる住宅では、リフォームでは根本的な改善が難しく、建て替えが現実的な選択肢となります。また、1981年以前に建てられた旧耐震基準の住宅も、地震対策として建て替えが推奨されることがあります。さらに、二世帯住宅への切り替えや、子どもの独立後に生活導線をシンプルにしたい場合など、家族構成の変化をきっかけに建て替えが検討されることも少なくありません。生活スタイルの大幅な見直しを図りたいときには有効な手段です。 1-3. 建て替えのタイミングを判断する基準建て替えを検討するタイミングは、建物の劣化度合いや将来の暮らし方によって左右されます。一般的には築30〜40年が一つの目安とされ、特に1981年の耐震基準改正前の住宅は、現行の耐震性能を満たしていない可能性が高く、専門家による耐震診断を踏まえて判断するのが望ましいです。加えて、住宅設備の老朽化や断熱性能の低さが目立つようになった場合も、建て替えによって最新の快適性を得られるメリットがあります。また、将来的な相続や家族構成の変化を見据えて、住宅資産としての価値を維持・向上させたいという観点から建て替えを選択するケースもあります。単なる修繕ではなく、暮らし全体のリセットとしての意味合いも含む選択肢と言えるでしょう。 2. 建て替えにかかる費用と内訳 2-1. 建物解体費用の相場と注意点建て替えの第一歩は、既存の建物を取り壊す「解体工事」です。解体費用は構造や広さによって異なりますが、木造住宅であれば1坪あたり3~5万円程度が相場とされ、延べ床面積30坪の住宅ではおよそ100万〜150万円が目安となります。ただし、鉄骨造やRC造(鉄筋コンクリート)の場合は費用が倍近くかかることもあります。さらに、アスベストなど有害物質の処理や、狭小地での重機搬入が困難な場合にも追加費用が発生する可能性があります。解体時には、ライフライン(電気・ガス・水道)の停止手続きや、近隣への騒音・粉塵対策の配慮も不可欠です。業者の実績や見積もり内容をしっかり確認し、トラブル回避に努めましょう。 2-2. 建築費用の内訳(本体工事・付帯工事)建て替えの中心となるのが、新しい住宅の「建築費用」です。これは大きく「本体工事費」と「付帯工事費」に分かれます。本体工事費には、基礎、柱、屋根、内装といった主要構造部分の工事が含まれ、坪単価で言えばおおよそ60〜90万円が一般的です。一方で付帯工事費とは、外構(庭・塀など)、仮設工事(足場・養生)、給排水・電気工事など、建物そのもの以外に必要な工事を指し、全体費用の1〜2割を占めることが多いです。また、断熱性能や耐震性、スマートホーム設備などグレードを上げると費用も上乗せされます。事前に総予算を明確にし、必要な設備とそうでないものを取捨選択することが費用コントロールのカギになります。 2-3. 仮住まい・引っ越しなどの諸費用建て替えの期間中は、仮住まいが必要になるため、その賃料や引っ越し費用も予算に含める必要があります。一般的に建て替えには約6ヶ月〜1年かかるため、仮住まいの家賃が月8万円と仮定すると、それだけで50万円以上の出費になります。また、引っ越しも解体前・完成後の2回必要となるため、運搬費や荷物の一時保管費もかかります。特に荷物が多い家庭では、トランクルームの契約が必要になるケースもあります。さらに、郵便物の転送手続きやインターネット回線の再契約など、見落としがちな費用も発生します。建物以外の生活費用も想定しておくことで、予算超過を防ぎ、安心して建て替え期間を過ごせます。 2-4. 見積もりの比較とコスト削減のコツ建て替えにかかる費用は、工務店やハウスメーカーによって差があります。1社だけの見積もりに頼るのではなく、複数社から見積もりを取り寄せ、内容や単価の違いを比較することが大切です。特に本体工事と付帯工事、諸経費の区分が明確でない業者には注意が必要です。見積書の記載が詳細であるか、価格に含まれる内容が具体的かをチェックすることで、後々のトラブルを避けられます。また、使わない設備や過剰なグレードを削減する、外構工事を後回しにするなど、コストダウンの工夫も有効です。必要に応じて住宅診断士や建築士に相談し、費用対効果の高いプランを選びましょう。資金計画を立てる段階で「総額でいくらかかるか」を把握しておくことが成功の第一歩です。 3. 建て替えの流れと必要な手続き 3-1. 建て替えのスケジュール全体像建て替えは、計画から竣工までに通常6ヶ月〜1年程度を要します。まず初めに、現在の住まいの調査とライフスタイルの見直しを行い、どのような家にしたいかを家族で話し合います。次に業者選びと建築プランの検討を進め、設計・見積もりが確定した段階で契約を結びます。その後、解体工事の準備と仮住まいへの引っ越しが行われ、解体、着工、上棟、内装工事といった工程が続きます。建物完成後には登記や引き渡しが行われ、再び引っ越しという流れです。この間に必要な手続きや打ち合わせも多く発生するため、余裕のあるスケジュール管理と、家族全体での協力体制が重要となります。 3-2. 必要な手続きと書類の準備建て替えにはさまざまな法的手続きが必要で、書類の準備も欠かせません。まず、建築確認申請書の提出が必須で、建物の構造や用途が法律に適合しているかを審査されます。また、古い建物の滅失登記を行い、新たに建築する家の建物表題登記や保存登記を行う必要があります。固定資産税評価の変更や、住宅ローン控除などを受ける際にも、建築確認済証や登記事項証明書などの書類が必要です。加えて、都市計画区域内では開発許可や景観条例の届け出が必要となる場合もあります。行政や登記所とのやり取りが煩雑なため、多くの方は住宅会社や司法書士と連携して手続きを進めています。 3-3. 解体から着工までの段取り解体から新築の着工までの間にも多くの工程があります。まず、建物の解体には近隣への事前挨拶が重要です。騒音や振動、粉塵などのトラブルを避けるためにも、誠意ある対応が信頼につながります。解体業者との契約後は、電気・ガス・水道などのライフライン停止手続きを行い、必要に応じてアスベスト調査も実施されます。解体後は土地の整地と地盤調査が行われ、地盤改良の必要があれば追加工事が発生する場合もあります。その後、建築確認が下りればいよいよ着工です。これらの段階では、天候や手続きの進行状況によってスケジュールが変動することもあるため、ある程度の余裕をもって計画を立てることが求められます。 3-4. 建て替えに関する近隣への配慮建て替え工事では、周辺住民への配慮がとても重要です。解体や工事期間中は、騒音・振動・ほこり・大型車両の出入りなどで、近隣に一定の負担をかけることになります。そのため、工事開始前にはあらかじめ挨拶回りを行い、工期や作業時間、連絡先などを丁寧に説明しておくことが基本的なマナーです。業者によっては、工事前に近隣向けの案内文を配布するなど、対策を徹底してくれるところもあります。また、仮設トイレや足場の設置位置、資材置き場の確保なども近隣の生活に影響を及ぼすため、事前の確認と説明が不可欠です。トラブルを未然に防ぐことで、建て替え後も安心して暮らせる地域環境を守ることにつながります。 4. 建て替えにおける土地条件と制限 4-1. 建築基準法における制限事項建て替えを行う際は、建築基準法に基づくさまざまな制限に注意する必要があります。たとえば、住宅を建てられる土地は都市計画区域内の「用途地域」によって建物の種類や規模が制限されており、住宅が建てられない地域も存在します。また、建ぺい率や容積率によって建物の大きさや高さに制限がかかります。さらに、防火地域や準防火地域では耐火構造や外壁の仕様に厳しい基準が適用される場合もあり、設計に制限が出る可能性もあります。建て替え前には、自身の土地がどのような法的規制を受けているかを役所や専門家に確認し、想定通りの家が建てられるかを事前に把握しておくことが重要です。 4-2. 再建築不可の土地と接道義務建て替えができない土地として代表的なのが、「再建築不可」の土地です。代表的なものとして、建築基準法上で認められている「幅4メートル以上の道路」に2メートル以上接していない土地があります。建て替えには「接道義務」を満たすことが必要で、この条件をクリアしていないと新しい住宅を建てることができません。このような土地は、かつて建物が合法的に建てられていたとしても、現行の法制度では建て替えが制限されるため注意が必要です。解決策としては、隣地を買い取る、私道に持分を得るなどして再建築可能な状態にする交渉をするといった方法があります。建て替えを検討する際には、自身の土地が法的に「建築可能」かどうかを必ず確認しましょう。 4-3. 容積率・建ぺい率・斜線制限の影響建て替えでは、建ぺい率・容積率・斜線制限といったルールが建物の設計を大きく左右します。建ぺい率とは、敷地面積に対してどれだけの面積を建物が占められるかを示す数値で、容積率は延べ床面積の割合を示します。これらは用途地域や道路幅により上限が決められており、土地が広くても建てられる建物の規模には制限があります。斜線制限とは、日照や風通しを確保するために建物の高さや形状に制限を設けるルールで、隣接地や道路側から一定の角度で建物を切り取るような設計が求められます。これらの制限に適合させるために、希望する間取りや階数を調整しなければならないこともあるため、土地の条件に応じた柔軟な設計が求められます。 4-4. 境界トラブルと測量の重要性建て替え工事を進めるにあたっては、土地の境界を明確にしておくことが非常に重要です。境界線が曖昧なまま工事を進めると、隣地とのトラブルに発展するリスクがあります。特に古い住宅では、境界杭が見つからなかったり、測量図が残っていなかったりするケースも多いため、建て替え前に土地家屋調査士による正確な測量を行うのが望ましいです。測量によって敷地面積が再確認されることで、建ぺい率や容積率の再計算にも役立ちますし、後々の不動産取引や相続時にも安心材料となります。隣地との境界確認書を交わすことで、境界を巡るトラブルを未然に防ぎ、工事を円滑に進めるための信頼関係づくりにもつながります。 5. 建て替えに関する補助金・優遇制度 5-1. 建て替えで利用できる補助金の種類建て替えを検討する際には、国や自治体が用意している各種補助金制度の活用を視野に入れると、コストを抑えることができます。代表的なものに、一定の省エネ性能や耐震性能を満たした住宅に対する「子育てグリーン住宅支援事業」があります。また、バリアフリー化や高齢者対応住宅への建て替えを行う場合、介護保険や自治体独自の補助金が活用できる場合もあります。補助金の対象となるには、仕様や工事内容に一定の条件があるため、設計段階から制度の要件を確認し、申請のタイミングも含めてスケジュールを組むことが重要です。自治体によっては募集期間や上限金額も異なるため、事前の情報収集がカギになります。 5-2. 住宅ローン控除とその他の減税制度新築住宅として建て替えを行った場合、住宅ローンを利用することで「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の対象になります。この制度では、年末時点でのローン残高に応じて一定割合(最大13年間)を所得税や住民税から控除できるため、大きな節税効果が期待できます。さらに、長期優良住宅やZEH住宅といった高性能住宅に対しては、控除額の上限が引き上げられる制度もあります。また、新築住宅にかかる登録免許税や不動産取得税にも軽減措置が適用される場合があり、建て替えの際にはこれらの優遇制度も漏れなくチェックすることが大切です。申告には住宅ローンの年末残高証明書や登記簿謄本などの提出が必要なので、あらかじめ必要書類を整理しておきましょう。 5-3. 省エネ・耐震性能向上による支援策建て替えを通じて住宅の省エネ性能や耐震性を向上させる場合、さまざまな支援策が用意されています。省エネ面では、断熱性の高い断熱材や高性能窓の導入、太陽光発電や蓄電池の設置などが対象になることが多く、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援制度を活用することで数十万円〜百万円単位の補助が得られることもあります。また、耐震性を高めるために耐震等級を2以上に設定するなどの設計を採用することで、地方自治体からの補助金や融資支援を受けられるケースがあります。これらの制度は、居住者の安全性と環境性能の両立を目指す国の方針に基づいており、申請条件や施工業者の登録有無など細かな要件もあるため、事前確認が重要です。 5-4. 補助制度を活用する際の注意点補助金や優遇制度を活用するうえで注意すべき点は、申請タイミングと条件の厳格さです。多くの制度は「着工前」の申請が必須で、工事が始まってしまうと対象外となることがあります。また、予算枠が限られているため、応募多数の場合は早期締切や抽選となる可能性もあり、タイミングを逃すと受け取れないリスクもあります。さらに、補助の対象となる仕様や工事の詳細が決まっている場合が多く、設計の自由度が制限されることもあるため、制度利用を前提とする場合は設計段階から業者と密に連携することが求められます。書類の不備や手続きの遅れで不支給となるケースもあるため、行政書士や建築士などの専門家のサポートを受けながら慎重に進めるのが安心です。 6. 建て替えのメリットとデメリット 6-1. 建て替えの主なメリット(最新設備、間取り自由など)建て替えの最大の魅力は、最新の住宅性能と自由な間取り設計を実現できる点にあります。築年数の経った住宅は、耐震性・断熱性・設備の面で現在の基準に大きく劣る場合がありますが、建て替えを行うことでこれらをすべて刷新でき、より快適で安全な住環境が得られます。また、間取りを家族構成やライフスタイルに合わせて自由に設計できるため、子育て世代には家事動線を重視した設計、高齢者にはバリアフリー仕様など、個々のニーズに合った住まいが実現できます。さらに、省エネ性能の高い家は光熱費の削減にもつながり、長期的には経済的メリットもあります。住み慣れた土地で理想の住まいを一からつくり直せる点は、建て替えならではの大きな利点です。 6-2. 建て替えの主なデメリット(費用、手続き、期間)一方で、建て替えには大きなコストと労力が伴います。まず、解体費用・建築費・仮住まい費用などを含めると、総額で1,500万〜3,000万円ほどの出費となることが一般的です。これに加え、各種申請手続きや設計打ち合わせ、登記や補助金申請といった多岐にわたる作業が発生し、精神的・時間的な負担も大きくなります。また、工期も半年から1年程度と長期にわたるため、その間の生活設計や近隣対応にも配慮が必要です。さらに、思い入れのある旧家を取り壊すことに抵抗を感じる人も多く、精神的な負担となることもあります。こうした負担を軽減するには、信頼できるパートナー選びと、計画段階での入念な準備が欠かせません。 6-3. 建て替えとリフォームの比較検討建て替えとリフォームは、いずれも住環境を改善する手段ですが、その目的やコスト、自由度には大きな違いがあります。リフォームは部分的な改修を行うため、費用を抑えつつ短期間で工事を終えることができ、住みながらの施工も可能な点がメリットです。しかし、構造に問題がある場合や間取りを大きく変えたい場合には、リフォームでは対応が難しく、制約が多くなります。一方、建て替えは初期費用は高額になるものの、将来的なメンテナンスコストの削減や資産価値の向上につながる場合もあります。両者の違いを踏まえ、現在の建物の状態や今後のライフプランを総合的に判断して、最適な選択をすることが重要です。 6-4. ライフステージと建て替えの相性建て替えのタイミングは、ライフステージとの相性も深く関係します。たとえば、子どもが独立したタイミングで夫婦二人の生活に最適化したコンパクトな住まいに建て替える人もいれば、出産や子育てを見据えて、家事動線や収納を重視した間取りに一新する家庭もあります。また、高齢期を見据えたバリアフリー住宅や、二世帯同居を実現するための建て替えも増えています。今後の生活をどう設計したいかを明確にすることで、無駄のない間取りや設備選定が可能になります。ライフステージの変化は住宅のあり方を見直す絶好の機会でもあり、建て替えによってその変化に柔軟に対応できる住宅を手に入れることができます。 7. 建て替えを成功させるためのポイント 7-1. 信頼できる業者選びのポイント建て替えを成功させるうえで最も重要なのが、パートナーとなる建築業者の選定です。建て替えは多額の資金と長い期間を要するため、信頼関係のある業者とタッグを組むことが安心への第一歩となります。選ぶ際は、実績の有無や口コミ、施工事例をよく確認しましょう。地元での施工経験が豊富な業者は、地域の法規制や土地の特性を熟知しており、スムーズな対応が期待できます。また、見積書の内容が明確であるか、担当者が誠実に対応してくれるかも判断基準になります。複数社から相見積もりを取り、価格だけでなく、提案力やアフターサービスも含めて比較検討することが、後悔のない業者選びにつながります。 7-2. プランニング段階での工夫と将来性建て替えは、人生で数少ない「家をゼロから設計できる機会」です。そのため、プランニング段階でどれだけ将来を見据えた設計ができるかが、住み心地に大きな差を生みます。現在の家族構成や生活動線だけでなく、将来的な家族の変化、例えば子どもの独立や親との同居、高齢化による身体の変化にも配慮した設計が理想です。また、収納の配置や光の取り入れ方、風通しといった細かな部分も暮らしやすさに直結します。将来的にリフォームや増築を想定している場合は、その余地を持たせた設計を考慮するのも一案です。家族全員の希望を共有しながら、柔軟性と快適性を兼ね備えたプランニングを心がけましょう。 7-3. 資金計画と無理のない予算設定建て替えには解体費、建築費、仮住まい費など多くの費用がかかるため、無理のない資金計画が欠かせません。最初に「総額でいくらまで出せるのか」という予算上限を明確にし、そこから逆算してプランを練ることが大切です。住宅ローンを利用する場合は、金利や返済期間だけでなく、将来の収入や支出の変化も考慮したシミュレーションを行いましょう。見積もりには予想外の追加費用が含まれることも多いため、少なくとも10〜15%程度の余裕資金を見込んでおくと安心です。補助金や減税制度の活用も含め、計画的に情報収集を行い、過度なローン負担や資金ショートを避けるよう注意しましょう。 7-4. 家族の希望を反映させるコミュニケーション建て替えは家族全員にとって大きなライフイベントであり、全員の希望をしっかり反映させることが満足度の高い家づくりにつながります。たとえば、子どもは自室の広さや収納、夫婦は家事動線やプライバシー、祖父母はバリアフリーなど、それぞれに異なる希望があります。プランニング段階で家族間での意見交換をしっかり行い、設計士や施工業者にも具体的に要望を伝えることが重要です。また、完成後に「言ったのに反映されていない」といったトラブルを避けるためにも、要望は文書化しておくと安心です。家族の思いをひとつにまとめ、全員が納得できる家づくりを目指すことが、建て替え成功への大きな一歩となります。
-

平屋住宅の魅力【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店の杉田です。本日は山陽小野田・宇部・防府・山口・周南で新築住宅をお考えの方に、「平屋住宅の魅力」についてお伝えします。今から、山口・防府・宇部・周南・山陽小野田で新築住宅を建てようと思うと、たくさんの不安が出てくるかと思います。山陽小野田・防府・宇部・山口・周南で新築住宅を建てるのに、「何がわからないのかがわからない!」という状態になってしまいますよね。山口・周南・防府・宇部・山陽小野田で新築住宅を建てることは、 ほとんどの方が一生で一番の大きな買い物になると思いますので、絶対に失敗はしたくないものです。今回は、平屋住宅の魅力を中心的にお伝えをしていければと思います。山口で新築住宅をご検討する際に、平屋と二階建てとどちらにしようか?どちらの方が安く建てられるの?という疑問を持つお客様が増えています。平屋と二階建てどちらにもメリット・デメリットはあります。その話を少しお伝えできればと思います。平屋と二階建てとでどう違うのか?お話していきます。山口で新築住宅をご検討する際に一番よくでる新築住宅の大きさが、30~34坪くらいの坪数の住宅が多いです。30坪で平屋と二階建てを建てた場合で比べてみましょう。 平屋と二階建てとでどう変わるか?平屋はすべての部屋が1階部分になる為、1階の床面積が大きくなります。それに伴い、新築住宅で一番大切な基礎部分が大きくなります。二階建てになると平屋と比べて1階の床面積が半分になる為、新築住宅の基礎部分が平屋よりも小さくなりますので、基礎工事費用の削減ができます。しかし、平屋は階段がない為、家事が楽になり、老後が安心できる作りができる。一方、二階建てはどうでしょうか?というと二階建ての新築住宅の方を選ばれる方が多いです。なぜかというと、二階建ての方が南向きの部屋を増やすことが出来るからです。 新築住宅をご検討する際、日当たりは皆様のこだわりポイントの上位です!私たち住宅会社もできるだけ住んでから後悔してほしくない為、間取りを考える際も南面にできるだけリビングやお部屋を作ったりと工夫しています。平屋では叶わないような間取りが二階建てでは叶える事ができる場合があります!その為、二階建て新築住宅を選ばれるお客様が多いです。平屋では、10年~15年後にある外回りのメンテナンス費用が二階建てよりはかからないです。なぜかというと、メンテナンスする際に家の周りに足場をかけて工事を行います。その足場費用の節約ができるためです!平屋の方が二階建てよりも大きい敷地じゃないと新築住宅を建てる事ができない為、平屋の方が土地の大きさ、取得する費用も大きくなります。 ざっくりと書きましたけども、二階建てと平屋どっちがいいの??というのは、山口で新築住宅をご検討中の皆様、誰もが持つお悩みです。平屋がいいのか?二階建てがいいのか?各担当者、それぞれの考え方で変わってきます。ですから一度悩まれた時はインターネットで調べてみるのもいいですが、一度プロの住宅会社にご相談してみることをオススメします!いえとち本舗でも平屋住宅の魅力についてわかりやすくご説明をしています。 プロの目から見て、お客様にはどんな家があっているのか?どういうお家が欲しいのか?どういうステップでお家づくりを進めていけば失敗しないのか? などアドバイスいたします。 中でも今回は、平屋住宅のメリット・デメリットを簡単まとめてみました。 平屋住宅のメリット①家族の顔が見えやすいリビングが核になる間取りが多く、自然とコミュニケーションがとれる構造になっています。また、新築住宅の隅々まで目が届きやすいのも特徴のひとつです。 ②広々とした雰囲気が手に入る平屋は二階がない分、天井を高くしたり、大きく広い窓を複数設けたりすることが可能です。ワンフロアという機能性はマンションでも実現可能ですが、採光面でいうと平屋はより自由度を高められます。大きい窓を増やせば、自然光がたっぷりと降り注ぐ明るい家庭に!さらに、マンションでは難しい縁側やウッドデッキで庭とのアプローチを強めれば、山口で新築住宅も開放感がぐんとアップします(^^) ③移動が楽平屋住宅にした場合、もちろん階段がないので段差そのものが少なく移動がスムーズです。段差の少なさはケガや事故の予防にも繋がりますし、子育て中はもちろん、高齢になり健康に不安を感じるようになっても安心です。ただし、移動がスムーズな分、子どもがお風呂場や玄関にも行きやすい構造ともいえます。小さい子どもがいる場合は、お風呂場での水の事故や、玄関の段差による転倒に注意しましょう。 ④台風や地震に強い地震の揺れは高層ほど大きくなります。平屋住宅は2階・3階がない分、揺れに強いです。また、台風や強風などの影響も高さがある方が受けやすくなるので、概ね災害に強い造りといえるでしょう。 ⑤光熱費が抑えられるリビングを主とした生活になる為、冷暖房費用や電気代を抑えやすくなります。具体的には、各部屋でエアコンを使用したとしても、1階部分に部屋が集中しているので冷暖房効率がよく、各部屋の温度差が少ないということです! 平屋住宅のデメリット①都市部や住宅街などでは日当たりが悪くなりやすい住宅の密集している地域だと、1階に日が当たりづらいため、2階建にし、2階リビングを選択される方が多いです。②建築費が多くなりやすい同じ延べ床面積(1階と2階の床面積の合計)で比べると、2階建てよりも平屋の方が高くなりがちです。理由は、基礎や屋根の面積が多くなるため。同じ延床面積だと、2階建てにすれば基礎も屋根も半分の面積です。とはいえ、やはり平屋住宅は魅力的です♪土地の面積や付近の環境、予算などによって2階建てを選択せざる負えないこともありますが、土地に余裕があったり、建物面積や部屋数が少なくても構わないようであれば、平屋をご検討してみてはいかがでしょうか^^また補足ではございますが、間取りの失敗例についてお話します。 ①収納計画の失敗「収納が足りなかった」「収納が使いづらい」などがあります。服や靴、本やCDなどの趣味のもの、日用品の買い置き、掃除機やベビーカーなど、今一度、自分たちの持ち物を思い出してみましょう。その量はどのくらいですか?どこに置いてあると出し入れに便利ですか?また最近はご家族共通の「ファミリークローゼット」という間取りも増えてきています。洗濯物をしまうときは一か所で済んでしまった方がラクですし、家族構成が変わった時に個室にすることもできますが、着替えるときを考えると各個室にあった方が便利かもでしれません。ライフスタイルに合った収納計画を検討していきましょう! ②音の伝わり方の失敗洗濯機の音や子供の騒ぐ音がリビングに響いてしまったり、外の車の騒音が寝室に響いてしまうなどがあります。また、ご家族同士でもトイレの音は気になります。音の発生源と、リビング・寝室の位置関係を考慮しましょう。「建売を買って、すぐにリフォーム」という新築リフォームをされる方もいらっしゃいますが、使う前の新品を壊してしまうのはなんだかもったいないですよね。いえとち本舗では、ご提案・お選びいただいたプランからお客様のライフスタイルに合わせた間取り変更を行います。 「建売の間取りがしっくりこない」という方は、ぜひいえとち本舗にご来場ください^^マイホームは経験値のない買い物を実物を見ることなく契約することもありますので、信頼できるプロ(住宅会社・工務店)の手を借りて、様々な疑問や不安を解決しながら進めていきましょう!信頼できるプロを見付けることが出来ない間は、自身で疑問や不安を解決しなければいけません。しかし、どんなに資料を集めて検討しても、不安が付きまといます。「本当にこれでいいの?」「間違っていないよね?」そうして、検討すれば検討する程、答えが出ないのです。当然だと思います。経験値が無い買い物なので、自問自答しても答えを出すことが難しいのです。だからこそ、いえとち本舗は、お客様のその気持ちに寄り添い信頼による安心感をお届けします。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。8月17日(土)~8月18日(日)の最新イベント情報↓30分聞くだけで400万円得する相談会
-

ガレージハウスのメリット・デメリットは?税金の有無や施工事例を紹介
新築住宅を建てるとき、「ガレージのあり方」はひとつのポイントとなります。将来的な使用方法も踏まえて、ガレージをどのように設置するか考えている人も多いでしょう。 そしてガレージ(住宅)の一形態として、「ガレージハウス」というものがあります。特に男性から人気が高い構造であり、ある種の「憧れ」を抱いている人も多いでしょう。本記事ではガレージハウスの定義やメリット・デメリットについて、詳しく解説します。ガレージハウスとはガレージハウスのメリット 風雨を避けられる 土地が狭くても建てられる ガレージ以外の用途が考えられるガレージハウスのデメリット 居住空間が狭くなる 通常よりも費用がかかる ガレージハウスを検討する上でのポイントガレージハウスには税金はかかるの?ガレージハウスの施工事例まとめガレージハウスとはガレージハウスとは、「ガレージ(車庫)と建物自体が一体化している住宅・建物」のことを指します。一部ではガレージハウスではなく、「ビルトイン・ガレージ(”内部建築されたガレージの意”)と呼ばれることも。 1階部分はガレージ、2階部分が居住空間となっているわけですね。ガレージハウスは娯楽性や趣味性が高く、先ほども触れたように男性から人気の高い構造です。自動車やバイクを整備する「基地」的な部分に惹かれている人も、多いのではないでしょうか? ガレージハウスのメリットもちろんガレージハウスのメリットは、趣味性や娯楽性が高いことだけではありません。実用面でも、非常にメリットの大きい建築構造だと言えます。ガレージハウスのメリットとしては、以下のような点が挙げられるでしょう。風雨を避けられる第一に、風雨をほとんど完全に避けられるというメリットがあります。 通常、自動車は屋外に駐車されるものです。たいてい、上部の屋根のみの駐車スペースに駐車されているでしょう。もしかしたら何も囲うものがない駐車場かもしれません。 しかしガレージハウスでは、少なくとも前方以外の三方向は住宅そのもので覆われています。よって、風雨の影響をほぼ完全に避けられるわけです。 シャッター付きのガレージハウスであれば、風雨の影響は一切あり得ません。よって、自動車やバイクなどについては、天候の影響が及ばない場所で、安心して保管できるわけです。 また、風雨だけではなく、砂塵や紫外線なども回避できます。外装の劣化や汚染を避ける上では、とても重要なポイントだと言えるでしょう。土地が狭くても建てられる土地利用の観点から考えると、「土地が狭くても住宅を建てられる」のが重要なポイントとなります。 本来、ガレージは住宅とは別な部分に広がる場所です。しかしそれが住宅そのものに組み込まれるため、必要になる土地も小さくなるのは当然のこと。 これにより、土地取得費用などが大きく低減されます。また、購入候補として挙げられる土地の範囲も大きく広がるでしょう。 土地というものは、左右へ広がる限りは取得費用がかさむものです。しかし上下の方向に対しては、少なくとも居宅レベルでは取得費用が余計にかかるわけではありません。ガレージハウスは、経済的に考えても合理性の高い選択肢だと言えるでしょう。ガレージ以外の用途が考えられる「ガレージハウス」という名称があるとはいえ、何も絶対に車庫として使わなければいけないわけでもありません。半ば屋外であることを活かして、さまざまな用途で利用できます。 たとえば自動車やバイクといった、車両以外の物を保管する場所としても活用できるでしょう。あるいはバーベキューの会場、子供の遊び場としても活用できます。変わったところでは、一部分をトレーニング・ルームに改造するようなケースも。ガレージハウスのデメリット一方で、ガレージハウスを作ることにはデメリットもあります。特に以下のようなデメリットは、必ずおさえておきましょう。居住空間が狭くなる最大のデメリットは、居住空間が狭くなること。1階の大部分がガレージになるので、これは当然のことですね。具体的には、最低でも5坪ほどが、ガレージハウスで占有されるでしょう。居住空間を確保するためには、3階建てにするなど、何かしらの大掛かりな工夫を求められます。通常よりも費用がかかるガレージハウスは、そうでない場合と比較して費用がかかります。 ガレージハウスは、その構造上、設計においてあらゆる制限がかかるものです。もちろん設計においても、より幅広い配慮が求められます。 また木造建築において、一般的にはガレージハウスを設置できません。よって、より高額な鉄筋コンクリート造をチョイスする必要があります。 さらには、ガレージハウスは難易度の高い構造です。よって工法も、高度なものが採用されます。 こういった背景があり、ガレージハウスを設置にするには費用がかかるわけです。ガレージハウスを検討する上でのポイントガレージハウスの導入するならば、第一に「ガレージの幅と奥行き」について、長い目線で考えましょう。将来的には、ガレージハウスの利用方法は多様に変化する可能性があります。 たとえば、自動車を2台か3台駐車することになるかもしれません。また、バイクや自転車、その他保管物を置くこともあるでしょう。となると、やはりガレージの幅と奥行きも、それに合わせておく必要があります。 そして、「ガレージの高さ」も重要となります。自動車の種類によっては、ガレージの高さが足りなくなる可能性もあるから。ミニバンなどを購入する予定があれば、それなりの高さは必要になります。 細かいところで言えば、耐震性にも注意したいところ。一階部分にある柱や梁が少なくなるため、ガレージハウスは地震に弱くなりがち。もしガレージハウスを採用するなら、別な部分で耐震性が確保されるように工夫したほうがよいでしょう。ガレージハウスには税金はかかるの?ガレージハウスには、当然ながら固定資産税がかかります。そして、ガレージハウスの場合は固定資産税が高額になるのではないか、と不安に思っている人も多い様子。しかし、ガレージハウスであることが、極端で税制面で不遇なわけではありません。 むしろガレージハウスだからこそ、固定資産税が安くなったりします。具体的には、ガレージ総床面積の1/5以下であった場合、その部分は固定資産税の課税対象から外されるしくみです。つまり固定資産税に懸念があるなら、課税対象から外れるような形でまとめるのがよいわけですね。 ただし、仮にガレージ部分が総床面積の1/5以上であったとしても、通常の部屋と比較して固定資産税が安くなる傾向にあります。これは、多くのガレージハウスは床や天井が簡素な造りであることに由来しています。とはいえ、できることなら固定資産税の課税対象から外れるようにはしておきたいところです。ガレージハウスの施工事例(引用:Instagram)広々としたスペースと、居住空間にも劣らないほど作り込まれたインテリアが魅力的なガレージハウスの施工例。奥には、所有者の自室へ直通している螺旋階段があります。 (引用:Instagram)最大で4台ほどの自動車を格納できる、大きなガレージスペース。通用口を設けることで、動線がきれいに確保されています。まとめガレージハウスは、自動車やバイクの愛好家からしてみれば、非常に魅力的な住宅構造です。ガレージハウスがあれば、日々のカーライフは非常に充実したものとなるでしょう。 もちろん、実用性といった面でも、非常に優れています。本記事で紹介したように風雨が避けられるといった点は、大きなメリットと言えるでしょう。さらに細かいところで言えば、乗り降りの際に雨を避けられるとった利便性もあります。 もちろん居住空間の問題などもありますが、それでもガレージハウスが魅力的であることは間違いありません。ぜひ一度、ガレージハウスを採用する方針で検討してみてください。 いえとち本舗では、今回お話ししたガレージハウス のように、家づくりにおいて少し専門的な内容もわかりやすく解説しています。いえとち本舗の資料とコンテンツなら、ガレージハウスのビジョンがより強く湧いてくるはずです。ぜひ一度、資料請求、および会員登録をしてみてください。 資料請求する 会員登録する









