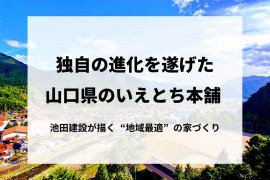ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
理想のスタイルから選ぶインテリア◎【いえとち本舗の新築・山口・防府・山陽小野田・周南・宇部】
みなさまこんにちは!いえとち本舗山口中央店です♪
山口・防府・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅の購入をお考えのみなさまは、理想のお部屋のインテリアなどはありますか?(*^-^*)

インテリアのスタイルを統一するとぐっとおしゃれなお部屋になり、生活するのが楽しくなりますよね。
逆にインテリアのスタイルにこだわらずにコーディネートしてしまうと、なんだかお部屋がごちゃごちゃして見えます・・・
インテリアのスタイルと言っても様々なスタイルがあります。
なので今回は
「理想のスタイルから選ぶインテリア◎」
についてお伝えしていきます♪
山口・宇部・防府・山陽小野田・周南で新築住宅の購入をお考えの方で
「お部屋のインテリアにはこだわりたいけどまだスタイルは決めていない・・・」という方に少しでも参考になれば幸いです(^^)
今回は北欧ナチュラル・アンティーク・シンプルモダン・ヴィンテージのスタイルに分けてお伝えしていきます♪

★北欧ナチュラル

北欧ナチュラルは木を基調としたナチュラルなスタイルです♪
特徴としては木の雰囲気や匂いでリラックスできるようなスタイルで、インテリアが部屋に溶け込みやすいです。
素材の色を変えるだけでナチュラルになったり上品になったり・・・と様々なテイストに変化します。
木材の暖かさや匂いを好まれる方にオススメです♪
★アンティーク

アンティークインテリアは他に類を見ない上品でエレガントな雰囲気。まるでお城のような空間を味わうことができます(^^)
アンティークインテリアの特徴は、熟練職人の手作業のような装飾や塗装が施されていることです。
実際に全て熟練職人の手作業で施されているインテリアも多く見られ、優雅な雰囲気でとても魅力的です。
白を基調としたインテリアは清潔感のある女性らしい空間を作りだし、茶を基調とすれば大人なクラシカルな空間になります。
レトロで美しい雰囲気がお好みの方にオススメです♪
★シンプルモダン

シンプルモダンのインテリアはその名の通りシンプル。
でもシンプルなだけではなく他のインテリアの邪魔をしない上品さをあわせ持っています。
クロスや照明を派手なものにしたい場合はシンプルモダンのインテリアがピッタリです(*^-^*)
また、シンプルモダンは生活感を感じさせないモデルルームのような雰囲気を作り出します。
いつでもスッキリとした空間で生活されたい方にオススメです♪
★ヴィンテージ

ヴィンテージのインテリアは落ち着きのある雰囲気で生活に程よくなじんできます。
ヴィンテージのインテリアの特徴は、長年使いこんだような味わい深い風合いの塗装や装飾です。
テイストを変えれば上品にもクラシックにもなるのが見どころです。
使い古されたインテリアのような雰囲気がお好みの方にオススメです♪
★さいごに

4つのインテリアのタイプをお伝えしましたが、インテリアはもっと多くのスタイルがあり奥が深いものです。
多くの時間を過ごすお家のインテリアは自分が一番落ち着くことができるスタイルがいいですよね。
好みのスタイルを見つけてから、インテリアを統一すると良いと思われます♪
インテリアのスタイルについて少しでも皆様の参考になれば幸いです(^^♪
【山口市下市町】圧倒的リビング!平屋3LDK GRAND OPEN!
関連記事
-

ZEH住宅で健康被害を防ごう!冬の換気不足による体への悪影響【いえとち本舗の新築・山口・宇部・周南・山陽小野田・防府】
みなさんこんにちは! (●ゝω・)ノいえとち本舗山口中央店です! 1月も下旬にはいりましたが、まだまだ寒い日が続いています。そんな寒い日は、みなさん暖房やヒーターなどで室内を暖かくしますよね。 冬はできるだけ冷たい空気を入れたくないものですが、みなさんは換気をされていますか?? (o゜ー゜o) 換気をしなければ、室内の空気はだんだんと汚れてしまい、体へあらゆる悪影響を及ぼしてしまいます。 従来の一般住宅ですと、窓を開けて換気するなど、冷たい空気も取り入れなければいけませんでしたが、ZEH住宅なら、室内を暖かく保ったまま、キレイな空気を室内に取り入れることが可能です。 では、一般住宅での換気不足による体への悪影響には、どのようなものがあるのでしょうか。 実は…外の空気より、室内の空気の方が汚い 室内の空気は、外の空気のように循環しないので、ほとんどの場合は室内の方が外の空気より汚れています。EPA(アメリカ合衆国環境保護庁)によりますと、最悪の場合、室内の空気は、外気よりも100倍も汚れることもあるようです。(゜ロ゜ノ)ノ そんな見えない空気を私たちは24時間吸い続けております。大量の空気を体に取り入れていると考えると、当然、キレイな空気を吸いたいですよね。 部屋の空気がどのように汚れ、その汚れによってどのような健康被害があるのか見てみましょう。 空気の汚れによる健康被害 換気を行わない室内では、あらゆる物質が飛び交っております。空気中に舞っているホコリやダニ、その他有害物質などを吸っていますと ・免疫力が低下する・呼吸器系の病気にかかりやすくなる・アレルギー症状が悪化する・冷暖房設備の効率が悪くなる・生活の質・仕事の質が落ちる などの身体への悪影響があります。 ■空気中を舞うホコリ・ダニ・有害物質 室内の空気には多くの微細なホコリや細菌、ウイルスが含まれています。 空気中のカビやウイルスが粘膜を攻撃することによって、呼吸器系の病気にかかりやすくなります。また、体内に入り込んだ細菌やウイルスを撃退するために免疫が機能した結果、アレルギー症状が悪化することがあります。 ■二酸化炭素の増加 私達が室内で、料理をしたり、作業を行うと、その人間の活動により、二酸化炭素が増加していきます。そして、空気中の酸素の濃度が低下してしまい、集中力や記憶力が低下していくという悪影響が起こります。また、空気が汚染されている室内にずっととどまっていると、免疫力が低下していき、免疫のバランスが崩れて、風邪を引きやすくなったりします。 ZEH住宅は冷たい空気を入れずに換気を行うことができる いかがでしたか?私達が想像していたよりたくさんの身体への被害がありましたよね。 以上のような換気不足による身体への悪影響を防ぐことができるのがZEH住宅です。 ZEHに関わらず、全ての建築物に常時換気ができる設備の設置が義務付けられております。 “室内に冷たい空気を入れたくないけど、クリーンな空気の中で生活したい” そんな理想の暮らしを叶えるのがZEH住宅です。 山口で新たな生活をお考えの方は、ぜひ、ZEH住宅で住居内の空気をキレイにして、健康な生活を送ってみてはいかがでしょうか。 山口・周南・山陽小野田・宇部・防府で新築住宅をお考えの方は是非一度、いえとち本舗までお気軽にお問合せください!家族全員が楽しく過ごせるお家づくりを一緒に考えていきましょう。ヾ(・∀・*) 1月25日(土)~2月2日(日)開催イベント↓【防府市田島】地域最大級!超絶怒涛の3棟同時見比べ見学会
-

【2020年6月版】新築住宅の固定資産税とは? 安くおさえる方法はある?
新築住宅を建てた場合、やはり「固定資産税」のことは気になるでしょう。固定資産税がいくらかかるかによって、将来設計も大きく変わってくるはずです。 とはいえ、 「固定資産税はどれくらいかかるのか?」「どうすれば安くできるのか?」 という疑問を抱えている人も、たいへん多いはずです。本記事では固定資産税の概要、および安くおさえる方法について解説します。新築住宅を建てようと考えている、あるいはすでに建てている人は、ぜひ参考としてください。新築住宅の固定資産税の概要固定資産税とは、土地や住宅を持っている人に課せられる税金です。不動産を所有している限りは、支払い続ける必要があります。 支払いは、1月1日時点で新築住宅を持っている人に対して要求されます。実際に支払いを始めるのは、その年の4月から6月あたりです。このタイミングで固定資産税が支出として発生することは、念頭に入れておきましょう。 固定資産税は、どうやって計算される?固定資産税を求める計算式は、【課税標準額×税金率】となっています。 課税標準額と税金率はどのように決まるか、下記で詳しく解説します。課税標準額の算出方法課税標準額は、「家屋調査」によって計算される「評価額」に基づきます。新築住宅に入居してからおおむね3ヶ月後に、自治体が家屋調査を実施します。 家屋調査を拒否することは可能ですが、おすすめはできません。なぜなら家屋調査を拒否すると、正確に評価額が計算できず、課税標準額も高くなってしまうかもしれないから。 基本的に課税標準額は、評価額と同額です。ただし何らかの特例などが適応される場合は、その限りではありません。 ちなみに評価額の見直しは、3年に一度行われます。よほどのことがない限り、評価額が前年より上がるということは起こりません。つまり3年ごとに安くなっていくというわけです。固定資産税がどのように安くなっていくのか、事前に確認しておきましょう。ライフプランも立てやすくなるはずです。 税金率はどうやって決められている?標準税率は、たいていの場合、「1.4%」に定められています。ただし一部の市町村では、これよりも高い割合を設定していることも。心配であれば、市町村に問い合わせるとよいでしょう。新築住宅の固定資産税における減額冒頭でも述べたとおり、固定資産税は減額することが可能です。まず新築住宅を建ててから3年の間、固定資産税は半額になります。減額時の固定資産税は、以下のような式で求められます。 【課税標準額(評価額)×0.14x0.5】 4年目からは、先ほど述べた【課税標準額(評価額)×0.14】という式が適用されます。4年目から固定資産税の支払い総額は高くなるので、家計もそれに合わせておきましょう。固定資産税の減額を受けるための条件 ただし新築住宅にかかる固定資産税の減額を受けるには条件があります。具体的には新築住宅が、以下のようなものでなければいけません。 新築住宅が、令和4年3月31日までに建てられている床面積が50m2から280m2の範囲内である 特に重要なのは、「1」の条件です。新築住宅を建てる場合、令和4年3月31日までに完成されるよう、スケジューリングする必要があります。 土地減税についてちなみに新築住宅のみならず、土地にも減税が存在します。以下の条件を満たしていれば、固定資産税全体の1/6が減税させることさせられます。 面積が200m2以内である令和4年3月31日までに取得した土地である小規模住宅用地に該当する なお、小規模住宅用地以外であれば、全体の1/3が減税されるようになっています。その後に受けられる減税新築住宅を建てたあとも、さまざまな減税措置が存在します。いますぐに受けられるものではありませんが、以下のような減税措置の存在は、頭には入れておきましょう。なお、すべての減税は、令和4年3月31日までが適用期限となっています。 省エネ改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税バリアフリー改修に関する減税:翌年の固定資産税の1/3を減税 他にもさまざまな減税がありますが、少なくとも新築住宅を建ててしばらくは条件が満たせられないでしょう。現実的に関わってくるのは上記ふたつでしょう。固定資産税を安くおさえる、そのほかの方法とは?基本的に固定資産税を安くおさえる方法としては、減税してもらうのが現実的です。しかし、以下のような方法によっても、多少は固定資産税を安くおさえられる可能性があります。家屋調査の実施時、伝えるべきことを伝える 先ほども述べたとおり、評価額(=課税標準額)は、家屋調査にて決定されます。つまり家屋調査にて、査定が不利にならないように、伝えるべきことを伝えることが重要です。 これをやっていたからといって、かならずしも評価額が安くなる、というわけではありません。しかし、いい加減な、あるいは間違った査定を受けることは防がられるはずです。仮に評価額が変動しなかったとしても、その結果には納得できる、という部分もあります。 できれば事前に、評価額の相場や、査定で重要となるポイントなどをおさえておくとよいでしょう。何かを伝えるとき、論理的に主張できるようになります。クレジットカードで支払うまた、クレジットカードで固定資産税を支払うというのも、よい方法です。なぜなら固定資産税をクレジットカードで支払えば、ポイントの還元を受けられるから。 厳密に言えば固定資産税が安くなっているわけではありません。ただしポイントを得られるということは、実質的に安くなっているとも表現できるでしょう。 当然のことながらポイントの還元率は、クレジットカードによって異なります。還元率については、事前の確認が重要です。また、できるだけ還元率の高いクレジットカードを利用するのも、大切なポイントと言えます。 固定資産税は金額が高く、ポイント数も多くなりやすいです。固定資産税は、できる限りクレジットカードで支払いましょう。ただし自治体によっては、クレジットカードでも支払いに対応していないケースがあります。まとめ新築住宅と、およびその土地を有している限り、固定資産税はかならず支払うこととなります。今後の生活においてずっと関わり続ける、たいへん重要な要素です。 できるだけ安くおさえられるように努めましょう。その努力をしているか否かで、新築住宅にまつわる税額は変わってきます。 また、ほぼすべての減税は、令和4年3月31日までと定められています。減税を狙うのであれば、タイムリミットには注意しておきましょう。 いえとち本舗では、快適かつ暮らしやすく住宅を、低価格で提供しています。新築住宅の建築を考えている方は、ぜひ資料をご覧ください。資料請求はこちら また会員サイトでは、住宅と土地に関する重要な情報を発信しています。興味のある方は、ぜひ会員登録してご覧ください。会員登録はこちら
-

独自の進化を遂げた山口県のいえとち本舗 ― 池田建設が描く“地域最適”の家づくり
コラム目次1. 「いえとち本舗」とは?全国ブランドの理念と強み1-1. 全国ブランドとして培ってきた“土地×建物×価格”の仕組み1-2. 全国モデルから発展した山口オリジナルの家づくり2. 山口で深化した「池田建設のいえとち本舗」2-1. 地域の暮らしを知る池田建設のものづくり2-2. 全棟G2仕様という高性能化へのこだわり2-3. 独自ブランド「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」3. 全国モデルとの違いが生む“地域最適化”の価値3-1. 性能の底上げと暮らしの最適化3-2. 「取り扱う商品を選ぶ」という品質思想3-3. デザイン・価格・サポートの三位一体提案4. 山口のいえとち本舗が選ばれる理由4-1. 気候・地形・習慣に合わせた住宅設計4-2. 県内全域をカバーする店舗ネットワーク4-3. 建てた後も寄り添う地域密着サポート5. まとめ ― 全国ブランドの枠を超えた、山口発の住宅ブランドへ5-1. 全国ブランドの枠を超える“地域版アップグレード”5-2. 山口の暮らしに寄り添う、これからの家づくりへ6. FAQQ1. 山口県のいえとち本舗と全国の違いQ2. 高性能でも価格を抑えられる理由Q3. G2仕様とは?Q4. 平屋への対応Q5. 見学・相談の場所1. 「いえとち本舗」とは?全国ブランドの理念と強み1-1. 全国ブランドとして培ってきた“土地×建物×価格”の仕組みいえとち本舗は、「土地と建物をまとめて提案する」という独自の仕組みで全国に広がった住宅ブランドです。家を建てたいと思っても、土地探しと建物計画を別々に進めるのは時間も手間もかかります。いえとち本舗はその課題を解決するため、ワンストップで“理想の土地に、理想の家を”実現できる体制を整えました。さらに、仕入れ・設計・施工の各工程を効率化することで、“わかりやすい価格設定”と“安定した品質”を両立。全国の加盟企業が共通の基準をもとに運営するため、どの地域でも一定のクオリティを保ちながら、マイホームを手の届く価格で提供できる点が支持されています。このように、全国ブランドとして培ってきたノウハウは、いえとち本舗の根幹をなす強みとなっています。1-2. 全国モデルから発展した山口オリジナルの家づくり全国のいえとち本舗では、どの地域でも安定した品質を提供できるよう、共通仕様のベーシックモデルが展開されています。たとえば「シンプリエ」シリーズのように、コストパフォーマンスを重視した合理的な住宅がその代表です。一方、株式会社池田建設が展開する山口のいえとち本舗は、そうした全国モデルの仕組みを土台としながらも、地域の気候・土地事情・平屋志向に合わせて独自に発展したスタイルを確立しています。 全国共通の設計をそのまま採用するのではなく、山口の暮らしに最適化したオリジナルモデル(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を自社で開発。これにより、「同じいえとち本舗でありながら、より地域に根ざした家づくり」を実現しています。これは単に商品を変えたというよりも、「山口の暮らしに最適な住宅を自社で設計し、責任を持って提供する」という考え方の表れです。つまり、同じ“いえとち本舗”であっても、池田建設では地域性を軸にした独自の発展を遂げているのです。 2. 山口で深化した「池田建設のいえとち本舗」2-1. 地域の暮らしを知る池田建設のものづくり山口県はいえとち本舗の中でも、新築住宅の需要が非常に高い地域です。一方で、理想の住まいを建てたくても「土地が見つからない」「希望のエリアに空きがない」という悩みを抱える人も少なくありません。そうした背景から、土地探しと家づくりを一体で考える提案力が、山口での家づくりには欠かせない要素となっています。また、山口県では全国的に見ても平屋住宅の人気が際立っており、若い世代からシニア層まで“ワンフロアで完結する暮らし”を求める声が多くあります。株式会社池田建設が展開する山口のいえとち本舗は、この地域特性を的確に捉え、限られた土地を最大限に活かす平屋設計のノウハウを磨いてきました。創業以来70年以上にわたり地元の土地・気候・生活習慣を熟知してきた同社だからこそ、「土地の選び方」「建物の配置」「光と風の通し方」まで、“暮らしやすさ”を中心に据えた提案ができます。単に家を建てるのではなく、“土地から暮らしをデザインする”――それが、株式会社池田建設が手がける山口のいえとち本舗の家づくりです。2-2. 全棟G2仕様という高性能化へのこだわり池田建設のいえとち本舗が評価される最大の理由のひとつが、「全棟G2仕様+耐震等級3」という確かな性能です。G2仕様とは、国の省エネ基準を大きく上回る断熱性能(断熱等級6相当)を意味し、冬でも室内の温度差が少なく、年間を通じて快適に暮らせる水準です。冷暖房効率が高く、光熱費を抑えながら快適さを維持できるため、実際の生活コストにも直結します。さらに、すべての建物で許容応力度計算による耐震等級3を標準採用。これは建築基準法で定める耐震性能の最高ランクであり、災害時でも家族の安全を守るための基準です。多くの住宅会社が“等級3相当”と表現する中で、池田建設は全棟で構造計算を実施し、確実に等級3を取得している点が大きな違いです。また、Kダンパー(制震ダンパー)を採用することで、地震の揺れを吸収・分散し、建物へのダメージを軽減。繰り返しの揺れにも強く、長期にわたって構造体の耐久性を維持します。断熱には現場発泡ウレタン吹付断熱を採用し、細部まで気密性を高めることで、G2仕様の性能を最大限に発揮。これにより、「高断熱×高気密×高耐震+制震」という4要素がすべて標準で備わる仕様となっています。“性能はオプションではなく標準であるべき”――。この考えを貫く姿勢こそが、池田建設のいえとち本舗が多くの施主から信頼される理由といえるでしょう。2-3. 独自ブランド「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」池田建設のいえとち本舗では、山口の暮らしに合わせて開発した3つのオリジナルブランドを展開しています。すべてのシリーズでG2仕様(断熱等級6)を標準採用し、性能の高さを前提に“暮らし方の違い”に合わせた提案を行っているのが特徴です。まず「イエスタ」は、間取りを考える手間を省きたい方や、設計をプロに任せて効率よく家づくりを進めたい方におすすめのシリーズです。設計士が生活動線や収納、採光バランスを考え抜いた完成度の高いプランで、コストを抑えて建てられるため、初めての家づくりをする若い世帯や、予算を重視する方にも適しています。特に平屋需要の高い山口では、シンプルかつ洗練されたプランが幅広い層に支持されています。次に「イエミライ」は、太陽光発電+蓄電池+HEMS(エネルギー管理システム)を標準搭載したスマート住宅。G2仕様の断熱性能を活かしながら、創る・蓄える・賢く使うエネルギーの自給循環を実現。停電時にも安心して暮らせる、次世代型の省エネ住宅として高く評価されています。「エネルギーを自給自足したい」「将来の電気代上昇や災害に備えたい」と考える未来志向の顧客層に支持されています。そして「イエテラス」は、G2仕様を基盤としながらも、デザイン性と価格のバランスを重視する方に最適なシリーズ。屋内外をつなぐテラス空間や、自然光を取り込み、性能とデザインの両立を楽しむ設計が特徴です。「性能にもこだわりたいけれど、デザインも妥協したくない」というバランス志向の層から選ばれています。これらの3シリーズはすべて、池田建設が自社で開発・管理する地域専用ブランドとしてそれぞれ明確なコンセプトとターゲットを持ち、どんな世代・ライフスタイルにも応えられる構成となっています。全国モデルの“量産”ではなく、山口の土地・気候・ライフスタイルに最適化された“質の提案”として展開されています。3. 全国モデルとの違いが生む“地域最適化”の価値3-1. 性能の底上げと暮らしの最適化全国のいえとち本舗が“コストパフォーマンスの高さ”を軸に展開しているのに対し、池田建設のいえとち本舗はコストパフォーマンスに加えて「性能を起点にした家づくり」を徹底しています。全棟でG2仕様・耐震等級3を標準採用することで、単に“建てやすい価格”ではなく、“住み心地の質”を標準化した家づくりを実現しています。これにより、冬場の室温ムラや夏場の熱こもりが少なく、日々の冷暖房費を抑えながら快適に暮らせる住宅が当たり前になります。また、山口特有の“平屋志向”や“限られた土地条件”にも柔軟に対応。断熱・耐震・換気といった基本性能の底上げを前提に、敷地条件や家族構成に合わせた最適な間取りを提案できる点は、全国モデルにはない大きな強みです。性能値を高めるだけでなく、その性能を地域の暮らしにどう活かすかまで設計に落とし込む――この姿勢こそが、池田建設が選ばれる理由です。3-2. 「取り扱う商品を選ぶ」という品質思想Point.池田建設はいえとち本舗の理念を共有しながらも、すべての商品を扱うわけではありません。例えば全国的に展開されている「シンプリエ」シリーズは、コスト面で魅力がある一方で、山口の気候や居住ニーズとは異なる設計思想を持つため、同社ではあえて採用していません。これは“取り扱わない”のではなく、“地域に最も適した品質だけを提供する”という判断です。代わりに、独自開発のG2仕様シリーズ(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を中心に展開。「選択と集中」によって、性能・コスト・デザインのバランスを地域基準で最適化しています。全国統一ではなく、山口基準での“ベストクオリティ”を追求する姿勢が、同社の品質哲学として根付いています。3-3. デザイン・価格・サポートの三位一体提案池田建設のいえとち本舗は、デザイン性・価格・サポートを三位一体で提案する体制を整えています。デザイン面では、間取りや外観だけでなく、採光計画や通風シミュレーションまでを考慮した「体感的な快適さ」を重視。価格面では、性能を高めつつも月々3万円台から実現できるよう、施工効率とエネルギーコスト削減の両面でコストバランスを追求しています。さらに、過度なメディア露出や外注に依存せず、資料・チラシ・Webなど多くの広告物を自社で企画・制作。その分のコストを住宅の性能・設備・アフターサポートに再投資することで、価格を抑えながら品質を維持しています。「見せ方より中身を磨く」――この地に足のついたブランド戦略が、長期の満足度につながっています。また、地域密着の強みを活かし、建てた後の暮らしを支えるサポート体制も充実。定期点検やメンテナンス、蓄電池の追加・改修提案など、住まいを“長く良い状態に保つ”ための伴走を行います。建てる前も、建てた後も、安心して任せられる――総合的な安心感が“地域最適化ブランド”としての価値を高めています。4. 山口のいえとち本舗が選ばれる理由4-1. 気候・地形・習慣に合わせた住宅設計山口県は、瀬戸内海と日本海の両側に面し、エリアごとに日射・風向・湿度の条件が大きく異なる地域です。沿岸部は潮風や湿気、内陸部では冬の冷え込みが強く、地域によって理想的な家の形が違います。池田建設のいえとち本舗では、こうした地域特性を丁寧に読み取り、地形・方角・風の通り方を考慮した設計を一邸ごとに行っています。また、山口では昔から「家族が集まる広いリビング」「来客を気にせず過ごせる平屋」へのニーズが高く、同社はその生活文化を反映した現代的な平屋デザインを数多く手がけています。性能値やデザインを“全国共通の基準”で押し付けるのではなく、山口で暮らすための最適解を導き出す設計力――それが、池田建設のいえとち本舗が信頼される理由です。4-2. 県内全域をカバーする店舗ネットワーク池田建設のいえとち本舗は、山口県内6拠点(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)を中心に展開しています。それぞれの店舗が地域密着で運営され、土地情報・施工事例・お客様の声を常に共有。「家を建てたいけれど、どのエリアが暮らしやすいか分からない」といった初期段階の相談から、建築・アフターまでをワンストップで支援できる体制が整っています。また、各店舗には経験豊富なスタッフが常駐しており、家づくりが初めての方にも分かりやすく丁寧な対応を徹底。こうした“地域の顔が見える運営”が、全国モデルにはない安心感を生み出しています。4-3. 建てた後も寄り添う地域密着サポート池田建設のいえとち本舗が特に重視しているのが、「建てた後の安心」です。完成引き渡し後も、定期点検やアフターメンテナンスを自社で実施し、施工からアフターまでを一貫して責任を持つ体制を維持しています。時代の変化に合わせて太陽光や蓄電池の増設、断熱性能の見直しなど、“住まいのアップデート”を提案できる地域パートナーとしても機能しています。地元企業だからこそ、住まいの状態や家族のライフステージの変化を継続的に見守ることができる――。この“地域で完結する家づくり”の安心感が、多くのOB施主から高い信頼を得ている理由です。5. まとめ ― 全国ブランドの枠を超えた、山口発の住宅ブランドへ5-1. 全国ブランドの枠を超える“地域版アップグレード”いえとち本舗は、全国で“土地と建物をセットで提案する”という画期的な仕組みを築き上げ、多くの人に「マイホームをより身近にする」きっかけを与えてきました。その理念を受け継ぎながら、池田建設のいえとち本舗は独自の進化を遂げています。土地不足が課題となる山口県で、最適な土地を提案し、平屋を中心に暮らしやすさを追求した設計とG2仕様・耐震等級3を標準化。さらに、地域の気候・文化・生活リズムに合った自社開発ブランド(イエスタ・イエミライ・イエテラス)を展開することで、全国モデルにはない“山口版アップグレード”を実現しています。全国ブランドの安心感と、地域企業の柔軟な対応力を両立させた存在――それが池田建設のいえとち本舗です。5-2. 山口の暮らしに寄り添う、これからの家づくりへ家づくりは、単に建物をつくることではなく、その土地でどう暮らしていくかをデザインする行為です。池田建設のいえとち本舗は、山口という地域で暮らす人々の価値観や生活スタイルを丁寧に汲み取り、性能・価格・デザインのすべてを“ちょうどいい”バランスで提案してきました。全国のいえとち本舗が築いてきた信頼を背景にしながらも、地域に合わせて進化し続ける――その姿勢こそが、池田建設の強みです。これからも同社は、山口の人々が“無理なく、永く、快適に”暮らせる住まいを提供し続けていくでしょう。「山口で建てるなら、山口を知る会社へ。」その言葉を体現する存在として、池田建設のいえとち本舗はこれからも地域の未来をつくり続けます。6. FAQ Q1. 山口県のいえとち本舗と全国の違いは? 全国のいえとち本舗は共通仕様の商品ラインを展開していますが、株式会社池田建設が運営する山口のいえとち本舗では、それらの本部商品は取り扱っていません。代わりに、山口の気候・土地事情・平屋需要に合わせて独自に開発した「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」という3ブランドを展開。全棟G2仕様・耐震等級3を標準化し、地域に最適化された“山口版のいえとち本舗”として進化しています。 Q2. 高性能なのに価格を抑えられる理由は? 広告や外注を最小限にし、資料やチラシ、Web制作まで自社で行うことでコストを削減。その分を性能やアフター体制に還元しています。過度な宣伝よりも、品質とお客様満足に投資する方針です。 Q3. G2仕様とはどのような性能ですか? G2仕様は、国の省エネ基準を上回る断熱等級6相当の性能です。冷暖房効率が高く、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちます。池田建設のいえとち本舗では全シリーズで標準採用しています。 Q4. 平屋を希望していますが、対応できますか? はい。山口県は平屋人気が特に高く、池田建設では限られた土地を有効活用できる平屋設計を多数ご用意しています。間取り・採光・収納計画までワンフロアで完結する快適な住まいをご提案します。 Q5. 見学や相談はどこでできますか? 山口県内の6店舗(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)で随時ご相談を承っています。ご予約は公式サイト(https://smarthouse-yamaguchi.jp/)からお気軽にお申し込みください。 (function() { var id = location.hash ? location.hash.slice(1) : ""; if (!id) return; var el = document.getElementById(id); if (el && el.tagName.toLowerCase() === "details") { el.setAttribute("open",""); } })();{ "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "LocalBusiness", "@id": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/#localbusiness", "name": "いえとち本舗 山口(株式会社池田建設)", "image": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/assets/img/logo.png", "url": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/", "telephone": "083-941-5963", "priceRange": "¥¥¥", "address": { "@type": "PostalAddress", "streetAddress": "山口県山口市大内千坊6丁目9-1", "addressLocality": "山口市", "addressRegion": "山口県", "postalCode": "753-0221", "addressCountry": "JP" }, "geo": { "@type": "GeoCoordinates", "latitude": 34.1623, "longitude": 131.4737 }, "openingHours": "Mo-Su 10:00-18:00", "sameAs": [ "https://www.instagram.com/ietochi_yamaguchi/", "https://www.facebook.com/smarthouseyamaguchi/" ] }, { "@type": "FAQPage", "@id": "https://smarthouse-yamaguchi.jp/#faq", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "山口県のいえとち本舗と全国の違いは?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "全国のいえとち本舗は共通仕様の商品ラインを展開していますが、株式会社池田建設が運営する山口のいえとち本舗ではそれらの本部商品を取り扱っていません。代わりに、山口の気候・土地事情・平屋需要に合わせて独自に開発した「イエスタ」「イエミライ」「イエテラス」という3ブランドを展開。全棟G2仕様・耐震等級3を標準化し、地域に最適化された“山口版のいえとち本舗”として進化しています。" } }, { "@type": "Question", "name": "高性能なのに価格を抑えられる理由は?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "広告や外注を最小限にし、資料やチラシ、Web制作まで自社で行うことでコストを削減。その分を性能やアフター体制に還元しています。過度な宣伝よりも、品質とお客様満足に投資する方針です。" } }, { "@type": "Question", "name": "G2仕様とはどのような性能ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "G2仕様は国の省エネ基準を上回る断熱等級6相当の性能で、冷暖房効率が高く、夏は涼しく冬は暖かい快適な室内環境を保ちます。池田建設のいえとち本舗では全シリーズで標準採用しています。" } }, { "@type": "Question", "name": "平屋を希望していますが、対応できますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "はい。山口県は平屋人気が特に高く、池田建設では限られた土地を有効活用できる平屋設計を多数ご用意しています。間取り・採光・収納計画までワンフロアで完結する快適な住まいをご提案します。" } }, { "@type": "Question", "name": "見学や相談はどこでできますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "山口県内の6店舗(山口中央・宇部・周南・下関・岩国・長門)で随時ご相談を承っています。ご予約は公式サイト(https://smarthouse-yamaguchi.jp/)からお気軽にお申し込みください。" } } ] } ]}