ブログ/コラム
Blog/Column
土地
準防火地域とは?制限や費用はどのくらいになるのかを解説
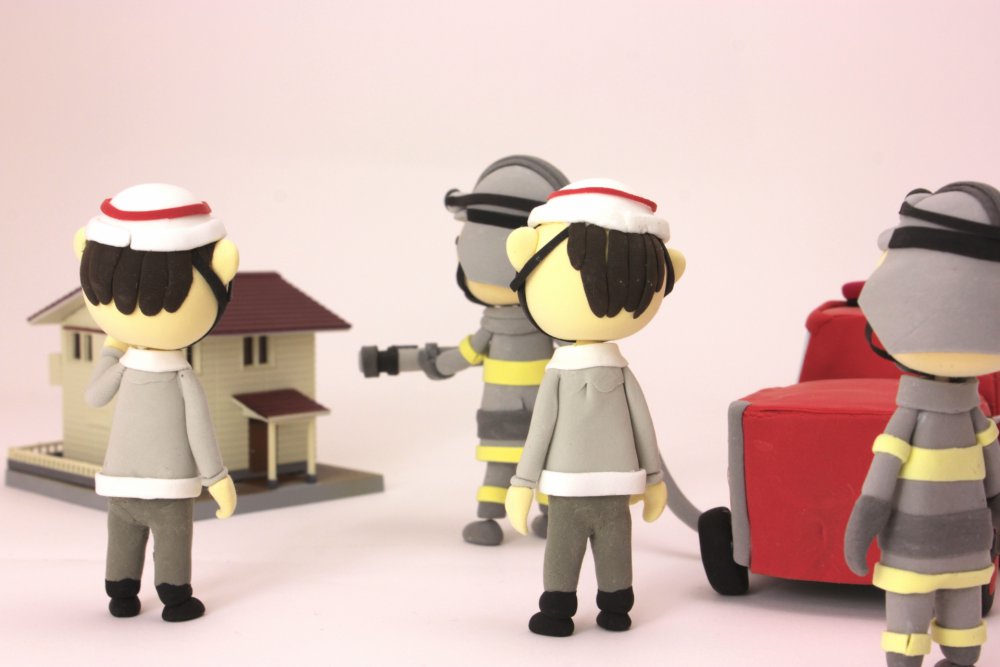
建物が並ぶ都市は火災が発生した時にそのまま燃え広がらないように規制を定め建築できる建物を制限しています。制限される建物は地域ごとに区分けし、防火地域や準防火地域などがあります。
この地域内にある建物は火災で簡単に倒れてしまっては被害も広がってしまうため、倒壊しにくい構造や材料でつくらなければいけません。この記事では都市計画の一つ、準防火地域についてとその地域で家を建てる際にかかる費用、火災保険料などをご紹介します。
準防火地域とは

建築基準法62条により火災を防ぐ目的で建築できる建物を制限する地域が準防火地域です。この地域に指定されるのは市街地や住宅密集地に多く、防火地域よりも外側に指定される区域となり、建築制限が防火地域と比べて緩くなっています。準防火地域は階数や延床面積の広さで耐火建築物か準耐火建築物にするように指示されていて、地階は階数に含まれません。
準防火地域内の建築制限
以下には階数や延床面積数で分類する建築物を記しましたのでご覧ください。- 階数≧4:耐火建築物
- 延床面積>1500㎡:耐火建築物
- 階数≦3かつ500㎡<延床面積≦1500㎡:耐火建築物、準耐火建築物
- 階数=3かつ延床面積≦500㎡:耐火建築物、準耐火建築物、防火上の技術的基準をクリアする木造住宅
- 階数≦2かつ延床面積≦500㎡:木造建築物
【階数による区別】
1・2・3階建て、延床面積>1500㎡:耐火建築物
1・2階建て、500㎡<延床面積≦1500㎡:耐火建築物、準耐火建築物
1・2階建て、500㎡以下:規制なし
3階建て、500㎡<延床面積≦1500㎡:耐火建築物、準耐火建築物
3階建て、500㎡以下:耐火建築物、準耐火建築物、防火上の技術的基準をクリアする木造住宅
4階建て:耐火建築物
防火地域はどんなところが指定される?
防火地域は駅前や繁華街、主要幹線道などに沿った一定の幅で指定される地域です。準防火地域よりも規制は厳しく階数に地階が入り、原則木造建築を禁止しています。防火地域内の建築制限は以下の通りです。
- 階数≧3:耐火建築物
- 延床面積>100㎡:耐火建築物
- 階数≦2かつ延床面積≦100㎡:耐火建築物、準耐火建築物
その他にも法22条指定区域というものもあり、木造建築は可能ですが屋根は不燃材料で葺き、外壁の延焼のおそれのある部分は準防火構造とする規定があります。法22条指定区域は防火地域と準防火地域の外側に指定される地域で屋根不燃化地域とも呼ばれています。
準防火地域などに家を建てる方法

以下に耐火建築物と準耐火建築物がどんな建物か記載しましたのでご覧ください。
耐火建築物
- 主要構造部が耐火構造であること
- 主要構造部が火災終了まで耐える構造であること
- 外壁開口部で延焼のおそれのある部分は防火戸などの防火設備を設ける
建築基準法施工令108条の3に定める技術的基準をクリアするものとして火災が終わるまで耐える構造については耐火性能検証法・防火区画検証法により確かめられたものになります。
政令で定める技術的基準に適合する構造は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの構造が該当し、耐火建築物は非損傷性、遮熱性、遮炎性のそれぞれに耐火基準の時間が定められています。
準耐火建築物
準耐火構造は政令で定める技術的基準に適合する準耐火性能を持つ建築物で外壁の延焼のおそれのある部分には防火設備を設けることとなっています。準耐火構造は「建築基準法2条1項九号の三イ」と「建築基準法2条1項九号の三ロ」にのいずれかにあてはまる建築物で、建築基準法2条1項九号の三イを「イ準耐」、建築基準法2条1項九号の三ロを「ロ準耐」と略称して呼ばれています。
簡単ではありますが以下に「イ準耐」と「ロ準耐」の構造を記載します。
【イ準耐】
- 45分準耐火
- 1時間準耐火
※1時間準耐火:木造3階建てまたは高さ13mか軒高9mを超える木造建築物に適用
非損傷性、遮熱性、遮炎性のそれぞれに耐火基準の時間があり、耐火時間は45〜60分の間で部位ごとに規定しています。
【ロ準耐】
- 外壁耐火構造
- 軸組不燃構造
※外壁耐火構造:外壁が鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、ALCなど
※軸組不燃構造:柱や梁が鉄骨など
家を建てる方法
準防火地域で家を建てるには建築制限がされており、通常の住宅よりもコストは高くなります。これから家を建てる方は、まずは建築する土地がどの地域に入っているかを確認することです。防火地域または準防火地域に該当する土地なのかは不動産会社や住宅会社、施工店などで確認することができます。また、役所に行って自分でどこの地域に入るか調べることもできます。その他にもインターネットで都市計画図の確認ができますので、土地のある地域を探し、防火地域なのか準防火地域なのかを閲覧することが可能です。
準防火地域に建てる場合の費用は高くなるの?

準防火地域では1〜2階建て500㎡以下の建築物を除いて耐火建築物または準耐火建築物にしなければいけません。耐火建築物や準耐火建築物は通常使う建築資材とは違い不燃材料や準不燃材料、防火設備など一定基準の防火性能をクリアした建築資材を使うように指定されています。
不燃材料は加熱開始後20分間燃焼しないことなど不燃性能を満たす材料であること。準不燃材料は加熱開始後10分間燃焼しないことなど不燃性能を満たす材料であること、となっています。
これらは通常使う建築資材よりも価格が高いため建物の価格も高くなります。建物のデザイン性にも関わってくるため、どの建築資材を使うかというところが悩みどころだと思います。
窓は網入りガラスの他にデザイン性を崩さない防火窓が出てきましたが、やはり価格が高いのがネックです。防火窓を取り付けるよりも通常の窓に防火シャッターを取り付けた方が安くなりますので、住宅ではこちらを採用することが多いです。
耐火建築物・準耐火建築物であれば火災保険が安くなる?
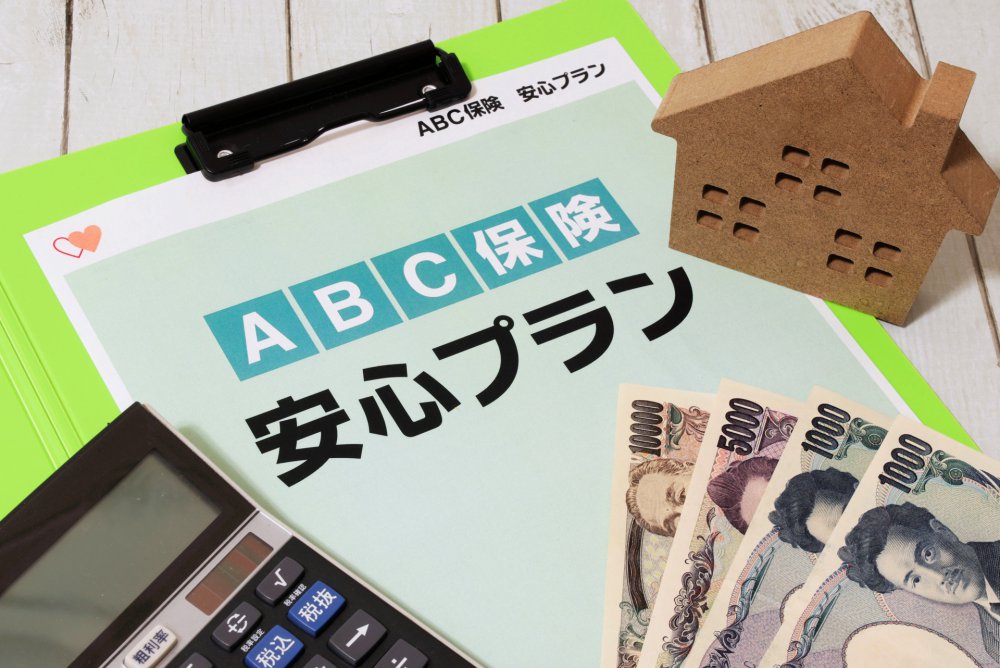
耐火建築物や準耐火建築物は火災保険の割引を受けることができます。通常の木造住宅の火災保険料は約30万円(保険期間10年)ですが、耐火構造にすることで10万円ほど安くなります。
注意するところは割引が効くのはあくまでも基準とされる構造であるため、防火地域や準防火地域内に家が建っているから火災保険料が安くなるというわけではありません。割引を受けるには耐火建築物や準耐火建築物、省令準耐火建築物のいずれかの構造を有していることです。
省令準耐火構造は住宅金融支援機構の定める基準に適合する構造で耐火構造や準耐火構造に準じる耐火性能を持つ構造です。在来木造住宅は省令準耐火構造に適合することが可能であり、内装の一定の防火被覆やファイヤーストップなどの施工が必要になります。2×4(ツーバイフォー)工法も住宅金融支援機構の仕様で建てることで省令準耐火構造に適合することが可能です。
【建築物の耐火性能の確認方法】
建物がどんな耐火性能を持った建築物とされているか確認するには建築確認申請に記載されています。建物の概要が載っている書面があり、その書面の項目には「用途」や「工事種別」「構造」などがあり、「耐火建築物等」のところに耐火建築物なのか準耐火建築物なのかが記されています。書類を見てもわからないという方は、家を建ててもらった会社や不動産業者に問い合わせをしてみるのもいいでしょう。
まとめ
私たちが安全に生活できるように都市は火災での延焼を防ぐために防火地域や準防火地域など建物を区分けしています。準防火地域内の建物は規制があり建てられる建物は制限されますが、安全かつ快適に暮らしていくためには守らなければいけない大切なルールです。これから家の購入を考えている方は、今回ご紹介した地域内に建物を建てるとなると制限により建築費が高くなる可能性がありますので、土地を選ぶ時はどの地域に入るかよく確認してから選びましょう。
家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-

セットバックとは?メリットや固定資産税はどうなるのかを解説
1 セットバックの基礎知識2 セットバックのメリット・デメリット3 固定資産税は払わないといけないの?4 セットバックの注意点5 まとめ土地探しや家づくりの際にでてくる「セットバック」という言葉はどんな意味かご存知でしょうか。たまに敷地よりも後ろに後退して建物が建っているのを見て、もっと建物を前に持ってくれば広く建てられたり、庭を広くとれたりするのでは、と思うはずです。しかし、このような建物はもしかするとセットバックが関係しているかもしれません。セットバックについて知らないでいると理想としているマイホームを建てることができなくなってしまう可能性がありますので、この記事でお伝えするポイントをチェックしておきましょう。セットバックの基礎知識引用:国土交通省 建築基準法制度概要集「セットバック」とは敷地に接する道路や隣地から定められた距離を確保するために建物を後ろに後退させることです。セットバックは建築面積の大きさにも関わってくるのでしっかりと理解しておきましょう。では、なぜ道路から建物を離さなければならないのか、その理由を具体的に解説していきます。道路の定義と接道義務 道路は建築基準法第42条で幅員4m以上のものと定義しています。(特定行政庁が指定する区域では6m)また、建築基準法第43条の「接道義務」により「建築の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されており、道路の幅と道路に接する距離が定められています。つまり敷地に接する道路は4m以上の幅員と道路に2m以上接していることが必要であり、それを満たさない場合はセットバックや道路の拡張、行政との相談などの対応が必要になってきます。道路の幅員が4m以上を満たしていない道路 道路の中には幅員が4m以上に満たさないものもあります。こういった道路(第42条2項道路)は中心から2m以上確保することが定められています。この規制はたとえ敷地に入り込むことがあっても道路中心線から2m以内に建築物を設けることはできません。また、敷地が池や川、線路などと対面している場合は、対面する敷地側の道路境界線から4m以上確保するように定められています。セットバックの目的 1. 災害時など緊急車両の通行経路と避難経路の確保2. 幅員を満たさない道路(第42条2項道路)に接する敷地での建築の解消 3. 建物の高さ制限1〜2の場合は道路幅の確保がメインですが、3の場合は建物の高さに関わることで、建物には高さ制限がかけられています。日当たりや風通しを確保するために道路斜線制限や北側斜線制限というものがあり、地面から斜め上に伸ばした線にかかる建物は建てることができません。こういった高さ制限に関わる斜線を避けるために建物を後退させて対応させます。セットバックのメリット・デメリット セットバックは自分の土地をめいっぱい使うことができないためデメリットではないかと思うかもしれませんが、メリットとなるところもあります。ここではセットバックのメリット、デメリットについて解説していきたいと思います。セットバックの有利な点車や人の通行が円滑になる見通しが良くなり防犯になる防災になる価格が安価セットバックにより道路幅が広がることで、通行の利便性や視認性が良くなります。通行のしやすさや視認性は普段生活する上での安全性と防犯性に関わります。視認性が悪く狭い道路の場合は車の事故が懸念され、暗い道だと女性や子供への危険が潜んでおり防犯性に不安があります。防災に関しては緊急車両の通行や駐停車が容易になり、隣地する建物への延焼や地震の倒壊による被害を防ぐことにも繋がります。また、セットバックが必要な土地は建築設計の不利になるという点から人気は下がるものの土地代は安くなるため、費用を抑えたいという方には有利に働きます。セットバックの不利な点建物の大きさが制限されるセットバックのところは公共の道路とみなされて使うことができないセットバックされた範囲は公共の道路とみなされるため私用に使うことができず、その範囲を駐車スペースにしたり、門塀やフェンスなどの外構を設けたりすることができません。また、敷地面積も狭くなるため予定していたよりも建物を小さくしなければいけなくなってしまう恐れもあります。こういったことを避けるために土地を選ぶ時はどんな制約がかかるか調べ、敷地に対してどれくらいの建築面積をとることができるか確認しましょう。固定資産税は払わないといけないの? 土地や建物には固定資産税がかかりますが、セットバックされた部分にも課税の対象となるのか疑問に思うところです。セットバックした部分は所有者以外の不特定多数の方が使うことになるため、所有者としての資産価値がなくなり、固定資産税の非課税対象となる場合が多いです。ただし、申告せずにいると免除されませんので注意しましょう。固定資産税の非課税の適用は市役所や区役所に申告する必要があります。非課税の適用を受けるためには、謄本や地積測量図、その他に役所が指定する書類などを用意して申告する必要がありますので、事前に調べてから手続きしましょう。また、セットバックをする敷地は調査費用や舗装費用がかかりますが、自治体によっては補助金を出してくれる制度がありますので、不動産会社や建築会社に調べてもらうことをおすすめします。そのまま高い費用を支払い続けないように早めに役所へ相談することが大切です。セットバックの注意点 これからマイホームを建てる方は事前に不便な点を把握していれば後々困るようなことを避けることができます。ここでお伝えする注意点を踏まえて土地を探し、マイホームを設計しましょう。建築可能な面積がどれくらいとれるか確認する セットバックした範囲は道路とみなされるため、その範囲に門塀やフェンスなどの建築物を設けることができません。また利用自体が道路となるため、駐車スペースとしても活用することができませんので注意しましょう。建ぺい率や容積率の計算はセットバックされたところを除いた敷地面積が適用されます。土地の購入の際もセットバック分の費用も支払っているということになり、セットバックが大きければ大きいほど、建築できない敷地に多く費用を払っているということになるため、土地を購入する前にちゃんとセットバックがどれくらい必要になるか確認しておくことが大切です。建て替えの時はセットバックが必要な敷地か 中古住宅の購入または昔から持っていた土地で建て替えをする際はセットバックが必要なのか確認することをおすすめします。セットバックしなければいけない土地は、建て替えだと現状より狭い敷地面積で建物を建てなければいけなくなってしまいます。建て替え前の建築面積の確保ができなくなるほど敷地面積が狭くなってしまっては、建て替えする建物も小さくなってしまうということになりますので注意しましょう。まとめ セットバックとは道路幅や高さ制限の影響で敷地境界線から建物を後退させることです。セットバックされた範囲は敷地面積として除外され、建物の設計に制限がかかり有効的に敷地の利用ができないため注意が必要です。何も知らずに土地や中古物件を購入してしまうと希望する建物を建てることができなくなってしまう恐れがありますので、どんな制限がかかるか事前に確認しましょう。いえとち本舗は会員登録をするとお得な最新情報や限定間取りの見放題、施工事例、限定土地情報など家づくりに役立つ情報を会員様にお届けしています。会員登録は完全無料ですので、これからマイホームを計画している方はぜひご利用ください。いえとち本舗プレミアムVIP会員登録はこちらから資料請求はこちらから
-

土地の方位は間取りに影響する!方位別にみる土地の探し方
土地の方角はこれから建てる家の間取りに大きく影響します。一般的に日当たりの良い南向きの土地が人気ありますが、一概に土地は南向きが良いというわけではありません。大切なことは希望している間取りに合っている方角の土地を選ぶことです。土地方角の特性上、イメージしている間取りにすることができない可能性もあるので、各方角の特徴とメリット・デメリットをチェックしておきましょう。 方角の影響まず、注文住宅を建てる前に必要なのが土地選びです。土地には方角があり、前面道路(土地に接する道路のこと)の方位によって価値が違います。人気のある南向きは他の方角の土地よりも価値が高く、日当たりに問題のある北向きは不人気で価値が低くなっています。また、角地は利便性も良いため北向きでも価値は高い傾向です。土地の方位は家の間取りに大きく影響し、採光が欲しい部屋は日が良く差す方角に部屋を配置する必要があります。この条件を考えると南向きに配置した方がいいという判断ができます。部屋の配置は土地の前面道路の方位が大きく影響しますので、土地を選ぶときは方角を気にしておきましょう。 土地は南向きがいいと聞くけど本当にいいの?土地の方位で南向きは人気があります。南向きのメリット・デメリットとは何か、下記にまとめましたのでチェックしてみましょう。【メリット】一日中日当たりが良い冬でも暖かい洗濯物が乾きやすい土地の価値が高い【デメリット】玄関配置の工夫が必要外構や駐車スペースの配置に工夫が必要土地価格が高い夏は日が高いため直射日光が入りにくく、冬は日が低くなるため日が入りやすくなっていることから室内環境がつくりやすい方角となっています。南向きの土地は玄関や駐車スペース、外構の配置に気を付ける必要があります。玄関が南側に配置されるため採光が取れる南側のスペースが少なくなります。もし南向きに玄関を配置しないとした場合、前面道路から玄関までの距離が遠くなり動線もあまり効率的にはなりません。これは駐車スペースにも同様なことが言えます。南向きに玄関を配置する場合は、採光が入ることを活かして玄関に吹き抜けを設けるなどするといいでしょう。 他の方角はどうなの?南向きの土地は人気がありますが、決してメリットばかりではないということを前述しました。それでは、他の方角の土地はどうなのか、気になるところだと思います。ここでは各方角の特徴とメリット・デメリットをご紹介していきます。 東側の特徴とメリット・デメリット【メリット】日当たりが良い暖かい洗濯物が乾きやすい南側の空間を広くとれる【デメリット】夏場は暑い朝から日差しが強い午後は日が陰るのが早い東側も日の入りやすい方角です。朝から日差しが入るため洗濯物が乾きやすく、冬でも部屋は暖まりやすい環境になります。東側に前面道路がくるため、玄関や駐車スペースの配置がとりやすく、動線も良くなります。ただし、一般的な間取り配置として南側にリビング、北側に水回りがくるため、各部屋までの動線が長くなります。このことから廊下の面積を多くとらなければいけない問題がでてきます。朝から日が入る東向きの土地は洗濯物が早い時間から干せて乾きやすいメリットがありますが、日が陰るのも早いため洗濯する時間は注意が必要です。夜型の生活スタイルの人は朝から日が入ることで睡眠の妨げになるためデメリットと感じてしまう可能性もあります。 西側の特徴とメリット・デメリット【メリット】長い時間日が当たる布団が干しやすい南側の空間を広くとれる【デメリット】朝は日が入りにくい夕方の西日で眩しい夏は暑くなりやすい西側の玄関は西日により劣化が早い西側の土地は長い時間日が当たる土地です。日の当たる時間が長いため布団などの干している時間が長いものが干しやすいです。東側の土地と同様に玄関配置もとりやすいため、リビングなど南側に持っていきたい部屋のスペースの確保がしやすい方角です。問題は西日です。夕方になると強い日差しが入るので眩しさを感じます。夕方の時間帯に日が強く入るため、夏場は暑くなるのもデメリットの一つでしょう。西日による紫外線は建物を劣化させますので、西側に玄関を配置してしまうと他の場所よりも早く劣化する可能性があり、庇を設けるなどの対策が必要です。 北側の特徴とメリット・デメリット【メリット】夏は涼しい土地の価値が低く安い南側の空間を広くとれるプライバシーの確保がとりやすい高さ制限の影響を受けにくい【デメリット】冬は寒い暗くなりやすいため照明が必要梅雨時は湿気やカビの対策が必要室内温度が下がり暖房設備による光熱費がかかる温度差が生じる北側の土地は日当たりは期待できませんが、玄関や水回りなど採光を必要としない部屋を集約できるため、採光のとれる南側や東側のスペースを広くとれるメリットがあります。また、建築基準法で義務付けられている高さ制限の「北側斜線制限」の影響が少ないです。ただし、日が入りにくいというデメリットは否めないもので、家の中が暖まりにくく、部屋間で温度差が生じます。梅雨時は湿気が溜まりカビが発生する可能性もあるため、換気をとるなどの対策が必要です。北側の土地は人気がないため価値は低いですが、その分土地価格も安くなっています。方角に合わせた間取りの工夫をすれば費用を抑えて家を建てることができるので、一概に北側の土地は悪いとは言い切れません。温度差や寒くなりやすいというデメリットは、断熱性と気密性を高めることで解消ができます。 作りたい間取りに方角を合わせる前述した通り南側の土地だけが家にとって条件がいいというわけではありません。方角によって良し悪しがあり、方角で得られるメリットを最大限に活かした間取りづくりが大切であり、デメリットとなるところは設備や断熱性能を向上させるなどでカバーして解消すれば大丈夫です。土地を選ぶときは、ますどんな間取りにしたいかをイメージできていることが大切になります。間取りのイメージができていないと、購入した土地の方角に合わせて設計することになります。先に間取りのイメージをつけておけば、間取りに合う方角の土地を選べばいいだけなので、どの方角にすればいいか迷う心配もありません。土地を選ぶときは先にどんな間取りにしたいかイメージをつくってから土地を選びましょう。 まとめ土地の方角は家の間取りに大きく影響します。人気のある南向きは一日中日が当たるためリビングの配置に適しています。しかし、南側に玄関を配置すると南側のスペースが損なわれ、それを避けるとなると道路から玄関までの距離が長くなります。南向きとは間反対の北側の土地は、人気はありませんが、南側のスペースを広くとれるメリットがあります。このように土地の方角によってメリット・デメリットがありますので、どんな間取りにしたいか決めてから最適な方角の土地を選びましょう。いえとち本舗は家づくりの資料を無料で提供しております。家づくりの参考にぜひご覧ください。資料請求のページはこちらからになります。
-

位置指定道路とは?固定資産税の支払や注意点を解説
1 位置指定道路とは?2 位置指定道路の仕組みとは? 3 位置指定道路は廃止することは可能? 4 位置指定道路にまつわる注意ポイントは? 5 まとめ 道路は建築基準法で定義が定められており、さまざまな道路が規定されています。しかし、見ただけでは道路がどの分類なのか、誰が所有しているかなどはわかりません。知らないまま土地を購入してしまうと、維持管理の費用が発生したり、利用するのに使用料や承諾が必要になったりするケースもあります。この記事では「位置指定道路」とはなにか、仕組みと固定資産税についてお伝えしていきます。位置指定道路とは? 「位置指定道路」は、私道の一つであり、特定行政庁から認定を受けた道路になります。建築基準法第42条により道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m)のものと定義されており、建物を建てるには接道義務という規定に則した敷地であることが必要です。接道義務とは、建築基準法第43条により定められており、「建築の敷地は道路に2m以上接しなければならない」と規定されています。例えば土地をいくつかの区画に分割して建物を建てる時、道路に接しないところは接道義務が果たされないため建物を建てることができません。そのため建物を建てるために道路を敷地まで新設し、これを道路として認めてもらえるように特定行政庁から許可をもらった道路が「位置指定道路」となります。位置指定道路の仕組みとは? 引用:横浜市道路位置指定申請のしおりなぜ「位置指定道路」として認定を受ける必要があるのか疑問に思われるかもしれません。また、所有者も「位置指定道路」は一人とは限らないため、この道路が誰のものかというのも少々複雑なところ。ここでは「位置指定道路」の仕組みについてお伝えしていきます。位置指定道路が作られる理由引用:国土交通省 建築基準法制度概要集新たに「位置指定道路」に認定しなければいけないケースとは接道義務によるものが大半です。一つの土地を分譲する場合、道路に接しているところは接道義務が果たされるので問題ありませんが、奥のところは道路がないため建物を建てることができません。このような問題を解消するために、奥の分譲した土地まで新たに道路を設けて特定行政庁に「位置指定道路」として認定を受け、建物が建てられる敷地にするのです。位置指定道路の所有者と固定資産税 公道なら国が管理するため所有のことは考慮する必要はありませんが、私道となるとメンテナンスや固定資産税においては所有者が負担することになります。また、所有者は一人とは限らず複数人が所有していたり、道路に接する敷地が分割して所有していたりします。つまり道路の所有者は管理やメンテナンスの義務、固定資産税の負担を担うことになりますが、国税庁により公共用に使う道路(通り抜けができる道路など不特定多数の人が通行用で使える)場合は課税対象から外れ非課税になることがあります。こういった負担を考慮すると、私道が引かれた土地の場合は誰が道路を所有しているか確認しておくことが大切です。また、一見私道に思われる道路でも自治体により公道に変更されていることがあるので、道路がどの種類になっているか知りたい場合は各自治体の役所で道路の形態を調べることができます。トラブルに注意!私道通行・掘削に関する承諾書とは?引用:東京都水道局 私道に接する敷地に建物を建てる場合、ガスや水道管が引き込まれているか、ということはとても重要です。もし、水道やガスが引き込まれていない場合、新たに配管を敷地にまで引き込ませる必要があります。配管を敷地まで引き込ませるには道路を掘削して配管類を埋設する工事が必要となるため、私道の場合は所有者の承諾がないと工事ができません。もし、所有者が複数人いる場合は、全員から承諾が必要となるため、承諾を受けるために交渉し、相手に理解を求める必要があります。「私道通行・掘削に関する承諾書」とは、この水道管やガス配管の埋設工事、それに付随する工事を行うことを私道の所有者が承諾したと証明する書類になります。この書類があることで私道での配管の埋設工事を行うことが可能になります。そのため、所有者から承諾が得られない場合はライフライン工事を進めることができないため注意しなければなりません。私道に接する土地を購入する際は所有権を持っているかが重要で、もし所有の持ち分がない場合は後々トラブルに発展する可能性があります。私道の持ち分がない物件を購入する場合は売買契約を交わす前に売主や不動産会社に「私道通行・掘削に関する承諾書」を現在の私道の所有者からもらうことをおすすめします。 位置指定道路は廃止することは可能?位置指定道路を廃止、または公道にするということは可能ではあります。しかし、かなりハードルが高いとされています。位置指定道路は所有者がいるため私道ではありますが、その用途は公共の責任を負いますので、通行できることも容認しなければいけません。ですから、いくら所有者であっても自由に位置指定道路を廃止するということはできません。また、建築基準法により接道義務が定められていますので、位置指定道路を廃止してしまったら、そこに接する建物はみんな接道義務違反になってしまいます。 位置指定道路を寄付する条件も厳しい 廃止の他に位置指定道路を国や地方公共団体に寄付するということも一つの方法ですが、これもハードルが高いです。条件には以下のことが挙げられます。 幅員が4m(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域では6m)以上であること 公道に接続していること側溝があること 公道として管理する必要があること公費を投入するのに見合う道路であることなどさらに上記の条件が満たされていたとしても公道として認められないケースもあります。公道として認めるということは、これから国や地方自治体が管理していくということになりますので、そのための維持費がかかり、予算に組み込んでいかなければいけません。公費(税金)として投入するのに見合う道路なのかというのが判断され、税収の少ない自治体の場合はさらに認められにくい可能性があります。位置指定道路の廃止、または公道として認められるケースとしては、接道義務などの違反に影響してこないこと、その道路の関係者全員が同意、協力を得ていること、がありますが、それもなかなかレアなケースと言えるでしょう。 位置指定道路にまつわる注意ポイントは? ここでは「位置指定道路」に接する土地を購入する際に注意しておかなければならないポイントをお伝えしていきます。ここでお伝えすることを知らずに購入してしまうと、後々トラブルに発展する可能性もありますので、ちゃんとポイントを押さえておきましょう。誰が所有者しているか必ず確認すること 前述したように水道管やガス配管などのライフラインに関わる工事が必要な場合は所有者から許可をもらわなければ工事を行うことができません。また、複数人が所有している場合は全員から許可をもらわなければいけないため、工事までかなりの労力と時間が必要になります。私道での工事は近隣トラブルになり、交渉がもつれてしまうと訴訟問題にまで発展することもありますので、もし所有の持ち分がない道路に接した土地を購入する場合は、将来的に起こるかもしれないトラブルを想定しておき、それを理解した上で土地を購入することです。土地の売買契約は重要事項説明があり、道路が位置指定道路であることや所有者について説明をする義務がありますので、誰が所有しているのかを必ず確認しておきましょう。 位置指定道路とその所有者を調べるには公図や登記記録を法務局で取り寄せて調べることができます。また、位置指定道路であるか役所の建築指導課でも確認を取ることができます。 自由に通行できるかどうか確認すること 位置指定道路はあくまで私道となるため、道路を利用するのに所有者が介入してくる可能性も否めません。位置指定道路の土地を購入する場合は、公道までの移動に障害が出ないように、購入前に通行の妨害がなかったか、通行料の請求がなかったか、など過去に問題が起きていないか確認しておきましょう。なるべく購入する際は売主から無償で通行できる承諾書を所有者全員からもらっておくことをおすすめします。また、道路や上下水道の修繕費の分担が決まっていないことが多いですので、こちらも確認しておくことです。最初は関係が良好であっても、なにかしらのきっかけで関係が悪化してしまう可能性だってあります。安心して通行できることや修繕費用の負担などの線引きはあらかじめ決めておかないと、トラブルになった時に妨害を受けて生活に支障をきたす恐れがありますので、リスクを避けるためにも自由に通行できるかなどの確認はしておきましょう。 埋設配管の維持管理費用が発生する場合もある 埋設されている配管に私設のものがある場合は、「位置指定道路」を所有するものが話し合って、その費用を捻出し負担することになります。そのため位置指定道路に埋設する配管が公設か私設か事前に確認しておくことが大事です。また、すでに老朽化していて購入してすぐに補修が必要になる可能性もあるため、どの程度古くなっているかも確認しておくことです。配管がどちらなのか確認するには、公設の場合は役所、私設の場合は売主に確認することができます。また、直接売主とやり取りしていない場合は不動産会社に仲介してもらい配管がどちらなのか確認してもらいます。これまで補修をどれくらいしてきたかについては水道局など各事業所の台帳で確認することができますが、私設の場合は土地購入前だと所有者しか確認できないため売主(直接ではない場合は仲介を通して)に委任状をもらってから役所で確認となります。まとめ 「位置指定道路」とは私道の一つで、特定行政庁から認定を受けた道路になります。私道に接する土地を購入する際は、所有者が誰なのかが重要なため、後々トラブルとならないように必ず確認をとることです。もしライフラインの工事が必要な場合は、道路を掘削し配管類の埋設工事を行わなければいけませんので、こういった事情も踏まえて道路の所有権を持っているか土地を購入する前にちゃんと確認をしておきましょう。家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。資料請求はこちらからさらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。会員登録はこちらから









