ブログ/コラム
Blog/Column
建物・家づくり
勾配天井とは?メリット・デメリットは?照明を選ぶ際のコツも紹介

勾配天井と聞くと名前がすでに物語っているように、なんとなくどんな天井かイメージがつくかと思います。しかし、具体的にはどんな特徴やメリットがあるのか知らない方も多いかもしれません。この記事では勾配天井とはどんな天井か、メリットやデメリット、空間づくりに必要な照明器具の選び方をご紹介します。
勾配天井とは?

勾配天井とは屋根の傾斜を活かして仕上げた天井のことをいいます。名前のとおり天井に傾斜があるため、低いところから高く上がっていく天井は奥行きの広がりと開放感を生み出してくれます。通常の天井は梁の下に野縁という骨組みを組みボードを張って仕上げているので、天井はフラットに仕上がり屋根の構造もボードで塞がってしまいますが、勾配天井の場合は屋根構造の梁を見せる仕上げ方も可能です。
天井に動きが生まれ、天井高の違いを活かして間取りをゾーニングすればメリハリのある立体的な空間も演出することができます。勾配天井は屋根の形状で仕上がり方が左右され、切妻屋根や片流れ屋根などどんな屋根を採用するかで勾配天井の形も変わってきます。また、北側斜線制限のかかる屋根を活かして勾配天井にするというケースもあります。
勾配天井のメリット

勾配天井の大きなメリットは空間に開放感を与えてくれるということです。一般的な天井高は2.4mですが、勾配天井にすることでさらに天井を高くすることができ、低いところから高く上がっていくことで視線が縦に抜けて広がりを感じさせてくれます。
勾配天井は吹き抜けの組み合わせと相性が良く、高窓を設置することで光が部屋に差し込み明るく開放的な部屋になります。また、採光の他に暖かい空気を外に出すのにも役立ちますので空気の循環も良くなります。内装の見せ方としても勾配天井は優れており、屋根構造である梁を空間のデザインとしておしゃれに見せることも可能です。
勾配天井は空間の一部として使えますので、リビングなどの居住スペースの他にロフトなどの収納としても有効活用することができますので、収納スペースの確保ができないという方にもおすすめです。北側斜線制限のかかる家の場合は、制限のかかる屋根を有効活用して勾配天井にするのも一つの方法です。
天井が低いところは落ち着きが生まれ、窓も低くなるためプライバシーを確保することもできます。
勾配天井のデメリット
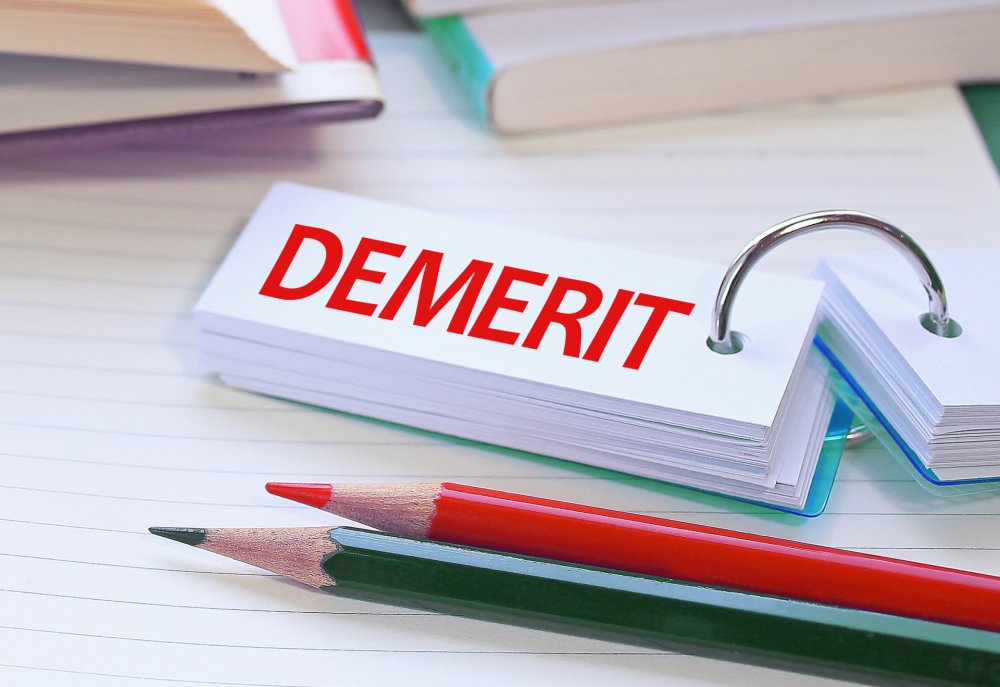
勾配天井を取り入れる際に注意すべきことはコストが掛かるということです。天井の面積が増えますので、通常のフラットに仕上げる天井よりも施工手間や材料費は高くなり、どのくらいの予算を掛けていくかかがポイントになります。
また、新築時の予算だけを考えるのではなく、後々必要になるメンテナンスの費用も事前に計画しておくことが大切です。数十年後にはクロスや塗装、塗壁などメンテナンスが必要になり工事のお金が掛かります。勾配天井の場合は高さもあるため脚立では作業ができず、室内に足場を設置するケースもあり、通常の部屋と比べて工事代が高くなるかもしれません。
また、断熱性能が低いと冷暖房効率が悪くなり部屋の快適性が損なうばかりか光熱費も掛かってしまいます。勾配天井を取り入れる時は快適な室温を維持できる断熱性を持たせることが重要です。また、日頃のお掃除のことも忘れてはいけません。
梁やシーリングファンには埃が溜まり定期的に掃除をしなければいけませんが、高い場所にあるため掃除は手軽とは言えません。脚立に登ったり、伸縮できるモップを使ったりと掃除の負担を感じることもありますので、勾配天井を取り入れる時は毎日のお手入れのことも対策しておきましょう。
勾配天井に取り付ける照明の選び方

快適な空間づくりはどんな照明を取り付けるかも重要なポイントです。各照明器具は特徴が異なり、光の照らし方も変わるため、イメージしている部屋に合った照明選びが大切です。また、単に部屋を明るくする目的で照明を設置するのではなく、光を見せるというのも大切です。
レストランやカフェのようにインテリアとして照明を見せ、絵画や雑貨などに明かりを照らして存在感を与える演出もできます。ここでは勾配天井に取り付ける照明の種類や選び方をお伝えしていきます。
シーリングライト

シーリングライトは天井にある電源ソケットに接続して固定する照明で、価格も安価なため住宅に多く普及している照明器具です。通常のフラットの天井なら部屋全体を照らすことができ有効なのですが、勾配天井の場合は光を照らす方向が傾くため部屋を明るくするにはあまり向いていません。
また、照明器具が傾斜に合わせて固定されるため、器具自体が重力に逆らいソケット部分に負荷がかかり取り付け強度に問題が生じてしまいます。もし、勾配天井にシーリングライトを取り付ける場合は器具の傾きがないようにパッキンなどを当てて水平に固定する必要があります。
勾配天井での照明器具としては光の届け方に工夫が必要ですし、見栄えとしてもあまり良くはありませんので、シーリングライトは避けた方が無難かもしれません。
ペンダントライト

天井から吊り下げるタイプの照明がペンダントライトです。天井から下がる位置に照明器具がくるため、光が手元に届きダイニングテーブルやカウンターのところの設置に適しています。ペンダントライトは光の範囲が狭くなりがちですが、複数のペンダントライトを連続して設置することで明かりの確保とおしゃれな空間を演出することができます。
吊るすタイプの照明ですので、地震などの揺れには注意が必要です。ガラスなど割れる素材が使われているペンダントライトだと落下した時に怪我をしてしまう恐れがありますので、割れにくい素材の器具を選ぶといいでしょう。
ダウンライト

天井に埋め込むタイプの照明がダウンライトです。ダウンライトは一つのみで部屋を照らすのではなく、複数のダウンライトを天井に埋め込んで部屋に光を届けます。デザイン的にも勾配天井の邪魔にならずおしゃれな空間を演出してくれます。
ダウンライトを採用する際は傾斜天井に対応したものを選びましょう。天井の傾斜角度に合わせて壁面や床面を照らすことができます。また、間接照明としてもダウンライトは有効です。テレビや絵画、ニッチにあるオブジェ、ベッドの枕元、などピンポイントに光を照らすことで特別な空間を作り出してくれます。
シーリングファン

照明とファンを組み合わせたタイプがシーリングファンです。ファンのプロペラが回ることで空気が循環し、冷暖房で整えた空気が部屋に広がり快適な室内環境にしてくれます。空気が流れるため冷暖房効率が向上することにより節電の効果も期待でき、室温が整えにくい勾配天井にシーリングファンは適しています。
器具のサイズも大きいため存在感があり、空間をデザインするアクセントにもなります。温かみを感じさせる木材を使用したプロペラやモダンな薄型デザインのシーリングファンもあります。また、設置方法も天井に直付けするタイプと天井から吊るすタイプがありますので、空間のテイストに合わせて照明を選ぶことができます。
まとめ
勾配天井は傾斜を持たせた天井で、空間に開放感を与えることができます。光を取り入れ明るい部屋にすることができますので、家族が集まるリビングにもぴったりです。天井高の低いところと高いところで部屋を用途別に分けてあげれば、立体的な空間となりメリハリが生まれます。動きのある空間となりますので通常のフラット天井よりも視野が広がり、開放性を感じさせてくれるでしょう。
家づくりは情報収集することが大切です。いえとち本舗は無料で家づくりに役立つ資料を提供しておりますので、これから家を購入しようと考えている方はぜひご利用ください。
資料請求はこちらから
さらに会員登録をするとVIP会員様限定の間取り集や施工事例、最新の土地情報をお届けいたします。当社は一切押し売りを致しませんので安心してご登録ください。
会員登録はこちらから
関連記事
-

知らないと損をする。新築住宅の人気オプションランキング7選とは?
どんなに素敵な家でも、最初からすべてが揃っていることはありません。もしも、より便利な生活を希望するのであれば、ハウスメーカーが用意するオプションを利用するという方法があります。しかし、いざオプションを決めようと思っても、たくさんありすぎて、どれを選んでいいのか迷ってしまうことってありませんか? でも大丈夫です。 今回は「いえとち本舗」が、人気のオプションを7つご紹介します。どのオプションも生活が豊かに変わるものばかり。気になるオプションがあったら、ぜひ検討してみてくださいね。 いえとち本舗がおすすめする「人気オプションランキング7選」 1.省エネで環境にもやさしい「エコキュート」 参考:三菱 エコキュート ・取付け費用目安:370Lタイプ60万円〜 エコキュートは、電気とヒートポンプユニットを動力としてお湯を沸かす給湯器です。まずヒートポンプユニット(熱交換器)で、空気中から熱を取り込み、その熱を圧縮しさらに高温にして、水をお湯に変えていくわけです。電気はあくまでもきっかけとして少量だけ使用し、他の給湯器のようにガスや灯油を使わないため、環境にやさしい給湯器として近年人気が高まっています。熱を伝える冷媒も、自然な二酸化炭素を利用しているため、環境を汚しません。 またエコキュートなら、電気料金の安い夜間料金を利用するため、ランニングコストも月額平均2,700円(1日87円)と抜群。エコキュートの設置には200Vの電源が必要なため、あとから工事するよりも、新築時に説明するのが断然有利です。※参考:中国電力 エコキュートの特徴http://www.energia-support.com/denka/ecocute/tokucho.html 2.まとめて洗えば、家族団らんの時間が増えます「ビルトイン食器洗浄乾燥機」参考:とっても節水・節約 | 食洗機のメリット | はじめてガイド | ビルトイン食器洗い乾燥機・取付け費用目安:45cmタイプ18〜25万円 食器洗いは意外と重労働。夫婦共働きが増えている昨今では、夜帰宅してからまとめて洗ったほうが効率的ですよね。かといって、シンクの中に汚れた食器を置きっぱなしにしておくのも、気分的にイヤなものです。 食器洗浄乾燥機があれば、食器を中に入れておくだけ。あとはスイッチひとつで、キレイに洗って、乾燥までしてくれます。家族が多い、ママ友や両親がしょっちゅう家に集まって一緒に食事を楽しむ、といった場合でも、洗い物を気にせずにゆっくりとした時間を楽しめます。 ちなみにパナソニックのサイトによると、手洗いに比べて、食洗機で使う水の量は約1/9で済むそうです。その節水効果により、なんと年間2万円以上も節約できるというのですから、驚きですね。 時間的にも、お財布的にも、働くママにおすすめのオプションです。3.雨の日も安心して洗濯ができる「浴室乾燥機」 参考:浴室乾燥機 | 浴室 | 次世代住宅ポイント制度・取付け費用目安:10〜15万円 オプションの中でも抜群の人気度を誇る「浴室乾燥機」乾燥換気機能があるため、雨の日でも浴室に洗濯物を干せますし、浴室にありがちな黒カビやヌメリを防止してくれます。 また最近では、乾燥機能だけでなく、暖房や涼しい風が出るタイプが人気です。リビングとお風呂場の寒暖差による体へのダメージを「ヒートショック」といいますが、高齢者や高血圧の人にとっては、心筋梗塞などの原因にもなりかねません。しかし、浴室換気暖房乾燥機を設置すれば、ヒートショックの影響は最小限で済みます。 高齢者や病気をお持ちのご家族がいる場合は、検討の価値はあると思いますよ。 4.荷物が多くても大丈夫「スマートキー」参考:商品特長 ポケットKey | スマートコントロールキー | YKK AP株式会社 ・取付け費用目安:〜10万円 鍵を使わずにリモコンでドアの開閉ができる「スマートキー」。開け方によって、大きく下記の2種類に分類されます。リモコンタイプカードタイプ リモコン・カードどちらにしても、直接ドアに触れることなく、簡単に施解錠が可能。大きな荷物を持っていたり、子供がいて手が離せなかったりするときには、本当に重宝します。また表面に鍵穴が露出していないので、空き巣にピッキングされる危険性が激減。 この便利さと安全性を知ったら、もう普通の鍵には戻れないかもしれませんよ。 5.物騒な時代だからこそ「人感センサーライト」参考:人感センサについて|屋外用人感センサのタイプ|コイズミ照明株式会社 ・取付け費用目安:〜3万円 動きを感知して自動でライトがつく「人感センサーライト」を玄関や外回りに設置すれば、不審者による犯罪を未然に防ぐことができます。明るくて人物が識別できる場所には、不審者は寄ってきません。そういった意味では、子供部屋になることが多い2階のベランダに設置するのも、とても効果的です。 また外出時には玄関周りを照らしてくれますから、つまずきによるケガの防止にも役立ちます。もちろん一定の時間が経てば自動で消灯するため、ムダな電気代もかかりません。 帰宅が遅くなる働くママや、部活動や塾に通う子供がいる家庭には特におすすめです。 6.足元からポカポカ「床暖房」参考:空気熱ヒートポンプ式システム コロナエコ暖シリーズ|製品情報|コロナ ・取付け費用目安:温水ヒートポンプ式21〜24畳の場合 / 60〜120万円 もともと比較的暖かい山口県。さらにわがイエテラスは、断熱に優れた「ZEH(ゼッチ)」が標準仕様ですから、夏涼しくて冬暖かい、そんな住宅になっています。 とはいえ、どうしても暖かい空気は上昇してしまい、足元は若干ひんやりするものです。また人間は手足の先から冷えを感じます。床暖房を設置すれば、足元からじわじわと暖めてくれますし、部屋中どこにいっても暖かいのがうれしいところです。 唯一ネックとなるのは、比較的高額な設置費用でしょうか。 ただ、エコキュート設置と同時に工事すれば、床暖房はあとから工事するよりも、圧倒的に安上がりです。いえとち本舗にご相談いただければ、毎月のランニングコストなども考慮しながら、最適なプランをご用意します。ぜひご相談ください。 7.停電になっても慌てない「家庭用蓄電池」参考:蓄電システム | 太陽光発電・蓄電システム ・取付け費用目安:80〜200万円(本体価格) 毎年大きな災害に見舞われる日本では、太陽光発電の普及とともに「家庭用蓄電池」の人気も高まっています。 その理由は大きく2つ。ひとつは蓄電池の価格が下がり、一般の家庭でも購入しやすくなったこと。もうひとつは、2019年からはじまった売電価格の下落だと考えられます。 つまりこれまでのように、太陽光発電の電気をすべて売却するのではなく、自己消費して、電気代を抑える人が増えたということです。もちろん、停電時でも電気が使えますから、そういった意味でも安心といえますよね。 いずれにしても、蓄電池は太陽光発電との相性がバツグンです。太陽光発電が標準装備のイエテラスだからこそ、蓄電池導入を検討されてみてはいかがでしょうか。 まとめ今回はいえとち本舗が、おすすめの人気オプションをご紹介しました。オール電化、24時間換気システムなど、驚くほどのシステムを標準装備している「イエテラス」しかしそれでも、お客様一人ひとりに、もっとこうしたいというご希望があるはずです。 私たちは、お客様の望むライフプランに少しでも近づけるように、さまざまなオプションをご用意しています。時期的にむずかしい場合もあるかもしれませんが、ぜひ一度イエテラスのモデルハウスか、店舗にお越しください。事前にご予約いただければ、混雑を気にすることなく、すぐにご相談いただけます。 来場予約はこちらからどうぞまた、いえとち本舗の公式サイトより「プレミアムVIP会員」に登録していただくと「VIP会員限定施工事例集」など、会員限定資料が見放題になります。もちろん会員登録は無料!しつこい営業なども一切ありません。 無料VIP会員登録はこちらからどうぞ
-

騒音対策で快適なお家づくり【いえとち本舗の新築・山口・宇部・防府・山陽小野田・周南・下松】
こんにちは!いえとち本舗山口中央店の永井と申します(^^)/本日は防府・山口・山陽小野田・宇部・周南で新築住宅の購入をお考えの皆様に「騒音対策で快適なお家づくり」についてお話します!突然ですが皆様、今住まわれているお家で他人の音について困ったことはありませんか?例えばアパートなどでは、上の階の人の足音がうるさいだとか話し声が響いてくるとか、、、一軒家でも、隣のお家との間隔が狭かったら生活音はかなり聞こえてきますよね。新築を建てるときに大切にしたいポイントとして、「静か」であることが挙げられます。日中は気にならない程度の音も、深夜や早朝では聞こえ方が変わってきます。騒音が気になってしまうお家では気が休まらず、知らないうちにストレスが溜まってしまうことも、、、( ;∀;)それが原因でご近所トラブルになってしまったニュースもありました。反対に、自分から発せられる生活音が近隣住民のストレスになっていないかの配慮も必要です。静かな家は落ち着きがあり、趣味や仕事に没頭できる空間であると同時に大切な家族とのコミュニケーションの場です。そこで山口・周南・防府・宇部・山陽小野田で新築住宅の購入をお考えの皆様に、静かなお家を実現させるために知っておきたい騒音対策についてのポイントと具体的な対策方法をご紹介していきます。 ★騒音対策のポイント〇騒音の特性をまず理解する音には様々な種類がありますが、騒音対策として知っておきたいのが・空気伝搬音・個体伝搬音です。空気伝搬音とは、空気を媒体として伝わる音のことで、電車や車の音がこれにあたります。個体伝搬音とは、壁や床などの物体を媒体として伝わる音のことで、2階の足音や床に物を落とした時の音がこれにあたります。このように、同じような騒音でも伝わり方で特徴がことなるので、対策も異なってきます。家を建てる前に土地の立地や騒音の特性をよく検証し、それに合わせて必要な対策を練ることが大切になってきます。 〇防音性能を高める方法①主な生活スペースは音源から距離を置く外からの騒音対策として、家族と過ごす時間が長い寝室やリビングは、道路や川などの音源からできるだけ離れたところに作るプランニングが必要です。プランニングの時に部屋の開口部をできるだけ小さくすることをお忘れなく。防音効果が高まります(^_-)-☆音源から離すことが難しい場合は窓に防音カーテンを取り付けることで窓から入ってくる音を減衰させましょう。防音カーテンは防音だけでなく断熱や遮光の効果もあります。防音カーテンは厚手の記事を複重層に折り重ねた構造になっており、布の間には遮音材が挟み込まれています。一般のカーテンだと上部や最下部にすき間ができやすいですが、防音カーテンは密閉性を確保するためにカーテンの上部と底部はカーテンレールや窓に密着するような構造になっています。最近の防音カーテンは複数カラーが用意されていることが多いので部屋の雰囲気に合わせて好きな色を選ぶことができます♪通常では、防音カーテンは重い方が効果を発揮するので、大幅な騒音カット効果を実感したいのなら、重量のある物を選びましょう。(^^♪また、道路側の壁を防音壁や防音パネルを使用するなどの対策もあります。防音壁は割と価格が安価で屋外のどんな過酷な環境でも使用できることからパーキングの付近の壁などに多く使われています。防音パネルはお家の外側の壁だけでなく内側にも取り付けることができる上に簡単で設置に時間がかかりません。 ②遮音効果の高い窓やサッシを使用する なるべく気密性の高い窓やサッシは外の騒音を大幅に軽減させることができます。気密性の高い窓やサッシは音の遮断の他にも、室外の空気の流入を防ぐのでエアコンなどの冷暖房費を抑えることができるので省エネにもなります♪気密性の高い窓やサッシが付けられない場合は窓と窓枠のすき間にシールテープを貼ることにより外気の風や音を遮断します!気密性が高いと、外からの騒音だけでなく自分のお家からでる生活音を軽減させることができますので、ピアノや楽器を室内で使用する方はできるだけ気密性の高いお家に住まれた方がトラブルを未然に防ぐことができます。 ③小さな工夫で遮音・吸音性能を高める 音は平らで固いものにぶつかると反射しやすく、デコボコして柔らかいものにぶつかると吸収されやすくなります。この特性を利用し、お家の壁紙を凹凸のあるものにしたり、床をフローリングではなくカーペット素材にすることで遮音・吸音効果を高めることができます。 具体的な対策としては、まず壁に遮音シートを貼ることが挙げられます。遮音シートは壁に貼るだけで壁から伝わってくる音を減衰させることができ、簡単に取り外しができる優れものです。 シートはできるだけ質量のある物を選んだ方が壁の防振効果が高く、防音に優れているので、ピアノや楽器を室内で使用される方は質量のあるものを選ぶ方がよさそうです(^^)/ 床材は防音マットを敷くことが適していますが、お子様が小さい場合は柔らかいコルクマットの方がよいでしょう。万が一お子様が転んだ時も緩衝材となるためタンコブやアザができたりといった怪我をする可能性が低くなります。 また、コルクマットは夏は涼しく、冬は暖かく過ごす事ができるためとても快適です。保温効果もあるのでエアコンの冷暖房代を削減する効果も期待できます! コルクマットを購入するときはそのコルクの粒の大きさも確認するようにしましょう。大粒タイプのコルクは通気性や弾力性に優れています。一方、小粒タイプのコルクは遮音性に優れています。 防音マットやコルクマットの上に防音カーペットを敷くとさらに遮音効果が高まります。また、カーペットは肌触りが良いので生活空間を快適にします♪ 防音カーペットにも種類があり、「タイル式」、「ラグ式」、「オーダーメイド」、「不織布」があります。 タイル式は、汚れたり傷ついた部分を簡単に交換できるのでメンテナンスに優れています。ラグ式はデザイン性に優れているものが多いです。不織布はフエルト素材でできており、安価といった特徴があります。 家族それぞれのライフスタイルに合わせてカーペットを選べるので適応しやすいですね (^^)/ 家具家電の振動や騒音を防ぐための防振ゴムというものもあります。防振ゴムは一般的にはゴムもしくはジェルでできています。 エアコンや冷蔵庫、プリンターなど振動して音を発生させている機械の下に防振ゴムを置き、振動をゴムの弾性により吸収します。 また、スベリ止め効果もあるので机やテーブルに設置した機械が地震などで落ちてくるのを防止する効果も期待できます。 ゴム製品は一般的に時間経過とともに劣化をします。(*_*) ですので新築を建てたときの購入当時より硬くなったりヒビが入ってしまっているものは買い替えをする必要があります。 防振ゴムの他に家具家電に取り付けられる騒音対策として防音材というものもあります。防音材は発砲素材で作られていることが多く、ハサミなどで簡単に思ったカタチに加工することができます! 素材が柔らかいので、曲面やパソコンの角への貼り付けも簡単にできます。 防音材は耳障りな高周波音を遮断してくれるので、パソコンの静音対策やドアのすき間から入ってくる外部の音を防ぐのに適しています。また、防音材は音にこだわる人のスピーカーやピアノ用吸音材としても効果があり、反射音を吸収することで音がクリアになる効果もあります♪ ★最後に 上記の騒音対策を実施することで、騒音によるストレスが軽減するのではないでしょうか。 「静か」なお家づくりには家を建てる前のプランニングがとても大切になってきます。壁材や床材に加えて小さな工夫を施すことで快適な住まいづくりができると思います。 防府・山口・宇部・山陽小野田・周南で新築住宅を建てられる際は、静かで快適で居心地の良い空間を実現するために参考にしてみてください。気になることがあれば、イエテラスの新築、いえとち本舗山口中央店までお問い合わせ下さい(^^)/ 10月19日(土)~20日(日) 開催イベント↓【山口市大内問田】将来の住まいを考えた平屋3LDK完成見学会
-

新築の注文住宅を建てる方必見!2階建てと平屋の選ぶ基準を解説
新築を建てる時はいろいろな情報を収集しますが、触れれば触れるほど魅力的な家を見つけてしまい、あれもこれもと取り入れたくなってしまいますよね。2階建てと平屋も迷うことの多いケースの一つです。一生に一度の買い物だからこそやり直しはきかないので、納得したものを建てたいですよね。この記事では2階建てと平屋のどちらを選ぶべきか迷われている方に向けて、選ぶ基準やそれぞれの建物のメリット・デメリットをご紹介していきます。 新築は2階建てと平屋どっちがいい?選ぶ基準をチェック2階建てか平屋のどちらの方がいいか選ぶ際に押さえておくのが下記のポイントです。【2階建てか平屋か選ぶ時の基準】 土地の広さ家族構成と人数予算メンテナンス上記の要素のどれを重視するかで、どの建物が適しているか決まります。このポイントを押さえながら各建物の特徴やメリット・デメリットをチェックしていきましょう。 2階建てと平屋の違い新築住宅は2階建てと平屋の2種類があります。2つの住宅の違いは以下のようになります。【2階建て住宅の特徴】階層が2層ある住宅です。階の移動があるため階段を設けます。部屋の数や広さの確保がしやすく、一般的に多く建てられているのは2階建て住宅です。【平屋住宅の特徴】階層のない1階建ての住宅です。階段や廊下を設けない設計ができるため、空間の有効活用ができ、高齢者にも優しい住宅です。最近は平屋の流行により採用している方も多くいます。 平屋と比較:2階建ての良いところ2階建ての住宅の良いところは下記のポイントです。 敷地に対して効率的に延床面積が広くできる部屋数を確保できる収納部屋を確保しやすい家族構成に捉われず2世帯住宅にも向いているプライバシー・防犯の確保がしやすい階層が2層ある2階建て住宅は、部屋の数と広さ(延床面積)を効率的に活用することができます。そのため家族構成に縛られず、必要な部屋を設けることが可能です。このことから住宅の失敗に多い収納部屋の確保もでき、家の広さが敷地の広さに左右される平屋と比べると、2階建ては二世帯住宅も建てやすいつくりとなっています。プライバシーや防犯の面も一般的に寝室が2階に来るので確保がしやすいです。 平屋と比較:2階建ての悪いところ続いて2階建ての悪いところについて下記のポイントをチェックしましょう。 地震対策をした構造設計が必要効率的な家事動線の設計が必要階段の上り下りの負担建物の総額は2階建ての方が高い2階建ては階層があるため建物に重さがあり、地震に対して平屋よりも不利なつくりとなっています。地震大国である日本は耐震性を有した設計であることが重要なため、2階建て住宅を新築するときは耐震性能に注意して建てましょう。また、部屋つなぎとなる平屋と比べて、2階建ては廊下や階段があり移動して家事を行う必要があります。効率的に家事を行うには動線に気を配る必要がありますので、間取り設計の時は実際に家事をしているイメージを持って行うことが大切です。建物の費用も総額では2階建ての方が高くなります。 2階建てと比較:平屋の良いところ次に平屋の良いところをチェックしていきましょう。 お年寄りが生活しやすい掃除・洗濯など家事がしやすい地震に対して構造的に有利階段・廊下がないので空間を効率的に使えるコミュニケーションがとりやすいメンテナンス費用を抑えられる平屋の良いところは階段や廊下を設ける必要がありません。段差をなくしてバリアフリー設計にすることで、移動による身体への負担が軽減できて高齢の方にも優しく安心して暮らすことができます。平屋は部屋と部屋を繋ぐような間取りとなっているため、家族とコミュニケーションがとりやすく、家事の動線も効率的にしやすい特徴があります。また数年後のメンテナンスも建物高さがないため足場をかける必要がなく、外壁面積の量も少ないためメンテナンス費用を抑えることができます。 2階建てと比較:平屋の悪いところ平屋の悪いところは下記のポイントになります。 周辺の建物で環境は変わる間取り設計は敷地の広さで左右されるプライバシー・防犯の対策が必要水害の心配建築コストは割高になる同じ延べ床面積の場合は税金が高くなる二世帯住宅は不向き平屋は建物の高さが低いため周辺に建つ建物によって生活環境がガラッと変わります。周りの建物が3階建てやマンションなど比較的高い建物がある場合は、圧迫感を感じる可能性があります。また、防犯やプライバシーの面も対策が必要です。人の目線にある平屋は塀やフェンスなどの目隠しや防犯カメラ、人感センサー付きのスポットライト、ピッキングされにくい玄関ドアなどで対策することが大切です。最近ではゲリラ豪雨などの水害にも注意しなければいけません。万が一洪水が起きてしまうと、2階がない平屋は床下浸水してしまうと逃げ場がなくなります。メンテナンス費用は抑えられる傾向にありますが、新築の時にかかる建築費用は2階建よりも割高、2階建てと同じ延床面積の場合は、必然的に敷地も広くなるため固定資産税などの税金が上がります。 2階建てと平屋の向き不向きを比較2階建てと平屋の良いところと悪いところ見てきましたが、どちらの建物がいいか向き不向きを比較しましたので下記にてお伝えしていきます。 2階建ての向き不向き【2階建てが向いている方】延床面積を効率的に確保したい方部屋の数や広さを確保したい方3人家族以上の家族構成の方2世帯住宅を建てたい方【2階建てが不向きの方】少数世帯で部屋数を必要としていない方階段の移動など身体の負担を感じる方 平屋の向き不向き【平屋が向いている方】ある程度の敷地広さを確保できる方部屋の数や広さにそこまでこだわらない方2人家族など少数の家族構成の方家の移動で身体の負担を減らしたい方バリアフリー住宅を希望している方家事のしやすさや家族とのコミュニケーションを大事にしたい方【平屋が不向きの方】ある程度の部屋の広さや数の確保が必要な方家族人数が多い方防犯やプライバシーが心配な方近隣に3階建てやマンションがある まとめ2階建ては延床面積を効率的に使えるため、限られた土地でも十分な部屋の広さと数を確保できる建物です。平屋の場合は、階段や廊下を設けないで建てることができるので、バリアフリー住宅に適していてお年寄りの方にもぴったりなつくりとなっています。2階建てと平屋はどちらも良いところと悪いところがあり、一概にこの建物がいいとは言い切れません。それぞれの特徴を押さえて、家族構成や生活スタイルに合っている建物を選びましょう。いえとち本舗は家づくりに役立つ資料を無料で提供しています。厳選した間取り集や施工事例を見ることができますので、良ければご参考にしてください。資料請求の申し込みはこちらからになります。









